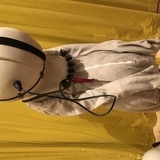クワイエット・プレイスのレビュー・感想・評価
全480件中、1~20件目を表示
言いたいことも言えないこんな世の中じゃ♪
うーん、久々。
「孤狼の血」から5か月ですか。
相変わらず姫が生活の中心で、おっさんの映画鑑賞はすっかり激減してしまった。鑑賞だけならまだしも、レビューなんて書こうものなら、蹴り倒されるそんな日々のすきを見ての、
「クワイエット・プレイス」
・
・
・
オープニングから末っ子をブチ殺すように、次は誰が殺られるか、の緊張が走る。ただし、設定はしょせん出オチモノなので、緊張感の持続には限界がある。どうしてもダレる。
そこでどうしたかというと、セリフはもちろん少ないが、のどかな風景に、でもBGMはガンガン、という。そこは、ほれ、BGMも極力減らし、というのが定石なのだが、楽曲が結構よく、ついつい使ってしまった、というのが実情なのかもしれない。
これが、「退屈」と「味わい深い」と「やかましく興を削がれた」の観る側のリテラシーに頼る結果に。
クリーチャーについては、突っ込む人も分からないではないが、いや、分からないか、クリーチャーの設定はそんなに重要ではない。
この映画のクリーチャーは、慎ましく生きる家族に対し、理不尽な外敵、テロ攻撃、庶民の味方にならない政治政策、不況経済、ネットで気に入らないことがあったらすぐ食いつくお前らの圧力そのもの。
庶民はじっと我慢し、言いたいことも言えないのだ。
そんな世の中に耐えながら、小さな喜びを求め、生きがいを感じ、希望を未来につなぐ家族の物語だ。
だから、赤ちゃんを産むのは、当然の欲求であり、義務なのだ。ちゃんと見てれば、用意周到に準備していることも分かる。
ブサイクで、聴覚障害で、性格もめんどくさい長女がイイ。昨今のマイノリティヨイショの臭いにおいが少々鼻につくが、そこは抜かりない、と観るべきか。
というより、父親は、そんな長女でも、それでも、それでも、愛する。そして命を呈して、子を守る。父親はいつだって、そういう役割なのだ。というメッセージが、子を持つおっさんにはとても響く。
追記
劇中、もうろくジジイに、家族の命の危険にさらされる、なんて、ホントこの映画は家族の映画なんだなと、笑った。
追記2
ニール・ヤングの「Harvest Moon」。
20年前に聴いたときはさっぱりだったが、この年になり、こういうシーンで使われると、染みるなあ。
劇場が静まり返る愉しさ
これは現実のデフォルメかも知れない
音を立てたら殺される!何に?それは(意外に)どうでもいい。要は、終末世界でそんな"音無生活"を強いられる1組の家族が、どうやって音を押し殺して生きているか?そこが強烈にリアルなのだ。エミリー・ブラント扮する母親が歯を食いしばって音の封印しようとするシークエンスなど、こっちまで奥歯を噛みしめてしまう。これほど皮膚感覚で共感できる映画は、近未来、サスペンス、ホラー等々に関わらず近年珍しい。そして、得たいの知れない何かに周囲を包囲されているという設定が、音のない屋内をさらに孤立させて、身が軋むような孤独感を味合わせてもくれる。もしかして、これは現実のデフォルメかも知れない。そんなことまで想像させるジョン・クラシンスキーのしたたかな演出力に技アリを!
設定を巧みに機能させ、異色の家族ドラマにまで高めた傑作
ホラー映画で「〜してはいけない」というNG事項が突きつけられることはよくあるもの。本作の「音を立ててはいけない」という設定もまさにそれだろうと舐めてかかっていたら、とんでもない返り討ちをくらった。この物語はその一つの視点を覗き窓として、人生や社会、そして我々が生きる世界そのものを炙り出していく。突飛なアイディアを見事に具現化して見せた大胆な筆致とスピリットに、ただただ恐れ入るばかりだ。
音を立てると絶望的なことが起こる世界。だがその宿命に負けじと、必死に生きる家族がいる。親は今伝えられることを子供に精一杯伝えようとし、その思いが痛いほどわかりながらも、反発してしまう子供達の姿がある。まさにこれは、誰もがたどる”人生の縮図”。普遍的とも言えるテーマが、言葉を廃していればこそ、従来とは違う角度、感覚にて鋭く突き刺さってやまない。ホラーに見えながら、これは家族の肖像を描いた秀逸なドラマなのだ。
「ドント・ブリーズ」の着想の発展形
圧倒的な敵は盲目だが異常に鋭い聴覚を持つ。音を立てると瞬殺されてしまう。これは2016年の傑作ホラー「ドント・ブリーズ」のアイデアを発展させたような設定だ(製作時期が近いので偶然似たのかもしれないが)。ただし本作の正体不明の敵は大勢いて、すでに全世界を制圧しそうな勢い。かつての文明は壊滅し、わずかな人々が息を殺して生き延びている。
主人公一家のお父さん役ジョン・クラシンスキーが監督・脚本で、これが3作目の長編監督作。2作目「最高の家族の見つけかた」は温和なルックスを裏切らないハートフルな家族ドラマだったが、こんな奇抜なホラーも撮れるとは。感情移入させる演出が巧みで、登場人物たちとつい一緒に息を詰めて見入ってしまうので結構疲れる。敵キャラだけに頼らない様々な恐怖描写と、家族間の感情の繊細な表現。アメリカでの大ヒットを受け続編製作も決定。クラシンスキーの監督作、もっと観てみたい。
クワイエット・プレイス
自分の呼吸音さえ気になった
超シンプルでわかりやすい内容だったのですぐに楽しめました。
「静かにしなきゃいけない」という一点のみを意識させるので、足音を気にするのはもちろん、瓶を棚に置くシーンでさえも緊張感が走って、ドキドキする作品でした。
最初の犠牲者となったのが、1番幼い子どもというショッキングな始まりで、印象深いです。しかもその犠牲を生み出した大きな原因の一つもまた子ども、というのも精神的に蝕まれる要素になっていて、良かったと思います。
最後の撃退方法が判明して、登場人物たちの勝ち誇った顔が爽快感あって、ホラー映画なのに割とスッキリとした気持ちで見終わることができました。
音を出すことができない怖さ
発想が面白かった
アボット家族は3人姉弟がいるごく普通
の家族。ただ姉は聴覚障害者。
それゆえ両親は手話で話す。
ただその生活が尋常じやない。
それは音を出すとエイリアンみたいなのがやって来て人間を襲うから。
歩く時はスニーカーを履いた方が音出ないんとちゃう?素足で歩く方が何か踏んだ時 無意識に声出るやんと思ったのは私だけ?
食料を調達する為家族で移動した
帰り飛行機のおもちゃを嬉しそうに
持っていた下の弟。それがいきなりおもちゃが光り音が鳴った!
さあ大変!父親は離れた息子を助けようと必死で走るが間に合わず…
何とか息を潜めて生活する中、
母親は妊娠。こんな中でよくつくるよね。子供を食べさせていけるのかサバイバル状態なのに赤ちゃんは泣くのが仕事。しかも息子を亡くしてるのに。出産も声を潜めて自力で産んじゃう頼もしい母!子供達もたくましく育つよね。
突っ込み所もありましたが
これは家族の絆のドラマでした。
全く怖くないB級ホラー映画
タイトル通りなんだけどまっっったく怖くないねこれ。
最初の末っ子が犠牲になるシーンでは音を一切だしてはいけない緊迫した世界観にうまく惹き込まれた。でもそこからはツッコミどころの連続でだんだん怖くなくなるというか。
こんな知能低いアホエイリアンに人類滅亡なんかありえんやろとか、もっと防音効果高い家住めやとか、走るのはセーフなんやなとか、身重の妻おいてどこ行くんやとか、技師なら音のトラップ仕掛けとけやとか、ツッコミどころが山のように湧いてくる。
それにSFオタの自分としては、エイリアンのアホさ貧弱さ音への反応性などディテールが気になりだして、これはB級映画なんだなと冷めちゃった。
エイリアンを映画に使うんならただのホラー舞台装置としてではなくもっとしっかり作り込んでほしい。
でも最後の父親がエイリアンに向かって吠えるシーンはかなりかっこよかった
ファミリードラマとして見れば面白いのかもしれない。
エイリアンもの
面白いか面白くないか以前の問題
この映画を面白いと思っている人は、きっとこの映画に登場する親子くらいの知能しかないのだと思う。と、評するのはもちろん根拠あってのことだ。
理由はタイトルにある通り、面白いか面白くないか以前の問題で、そもそもおかしいのだ。
沢山ある中で一つだけ抜粋するなら、それは赤ちゃんだ。ご存知の通りこの作品は音を出してはならない。なぜなら化け物に殺されるから。作中では砂利道に砂のようなものを巻いてその上を歩き、極力音が出ないようにし、会話は基本囁き声。この徹底ぶりの中で、果たして子供を作るだろうか? 家族というテーマ対して、赤ちゃんを持ってくるのはいいだろう。しかし世界が世界だ。赤ちゃんなんて1番声を出すに決まっている。産声という言葉があるくらいだ。まして、主人公たち家族は、1度怪物によって幼い子供を失っている。それなのに、2人の子供を危険に晒してまで新たな子供を作るだろうか? これを家族愛だと呼ぶのなら、実に面白いZ級コメディ映画だな。まだしも、赤ちゃんが泣いても化け物に襲われない準備をしていたならば良い。しかしもちろんそんなことはなく。作中登場した滝の裏では普通に会話し、あるいは大声で叫んでも化け物に襲われなかったというのになぜそこに行かない。バカなのか。
上述したようなおかしな要素は他にもある。しかし全てをあげようとなると、それはレビューというより悪口大会になってしまいかねないのでやめておこう。
悪い点ばかりをあげるとレビューにならないので、いい点をあげよう。それは“この世には面白いか面白くないか以前に、破綻した内容の映画もある”ということを教えてくれることだ。ここまで分かりやすくおかしいのは、もはや教科書といって過言ではない。成功はアート、失敗はサイエンスという言葉がある通り、失敗には法則性がちゃんとある。作品を作る人は、これを反面教師にして素晴らしい作品を作っていただきたい。なおこうして酷評をするのは、別に悪口が好きという訳ではなく。残念なことにこのようなことでしか評価すべきポイントがないのだ。むしろ反面教師としての役割を見いだせたことに、一種の誇らしさを覚えるほどである。
シーッ!
怖そうが先行して中々観る気になれなかったが、等々鑑賞してしまった。始めから終盤までほぼクワイエットな為、なるべく外野の音が入らないようにヘッドフォンで鑑賞。物語的には平凡だが、ある意味シュールで新しい描写だった。声を出さない演技は、キャストの力が試されるからね。元々エミリーが好きで気になってた作品だったが、クラシンスキー圧巻の演技だった。子供達も十分恐怖が伝わる演技で今後が楽しみだね。
この映画、続編はまだ観てないが、何か連続ドラマのオープニングみたいな内容だった。ここから家族の巻き返しと世界を取り戻す戦いが始まるんだなって思えた。そして、今公開してるDAY 1で恐怖の始まりを描いているのかな?上手い手法だし、人気出たら幾らでも過去や未来での物語映画化出来るしね。しかしそれにしても、流石に上映時間短過ぎない?グズグズするよりよっぽど良いんだが、ビール半分飲んだ所で終わってしまい少し拍子抜けたわ笑
あの終わり方が最高
ジョン・クラシンスキーという人を、それまでは『13時間 ベンガジの秘密の兵士』でしか知らなかったが、エミリー・ブラントのパートナーだったのか!と、本作の映画情報で知った。
夫婦で主演かつ低予算(ハリウッドでの低予算だけど……)のホラーという、まるでインディーズのノリのようなこの映画には特に興味はそそられなかったのだけど、本国で公開されるやいなや高評価&No.1大ヒットということで無視するわけにはいかなくなった(笑)
劇場で鑑賞した本作は、ある家族に焦点をしぼり、音をたてたら“奴ら”が襲ってくる状況で、この世界での新たなルールや習慣(この家族ならではのもの)が新鮮で、緊張感を保ったままスリリングな90分を楽しめた。
エミリー・ブラントは監督(夫であるジョン・クラシンスキー)から、あの結末を知らされた時に「イェェーース!」とぶちあがったという(笑)
たしかにあの終わり方は最高だった!
沈黙の世界‼️
視覚がなく、聴覚だけが異常に発達したエイリアンの恐怖を描くシリーズの第一弾‼️エミリー・ブラント扮する妻を中心とする家族の物語で、妻が妊娠中、子供が聴覚障害という設定が素晴らしく、サスペンスの構築に一役買ってます‼️音を立てずに生活する姿や情報源はラジオ、遠く離れた家と灯りを目印に連絡を取り合うアイデアも見事ですね‼️そしてホラーやSFでは子供や動物を殺さないというハリウッドの鉄則が簡単に覆されたオープニングも戦慄すぎる‼️
全480件中、1~20件目を表示