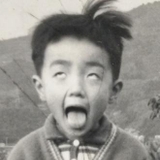日日是好日のレビュー・感想・評価
全311件中、241~260件目を表示
ほっとする
落胆も大きいが日日是好日
心に沁み入るような作品でした
主人公・典子が母親の勧めで何気なく始めた茶道を通じて、感じ、そして学んだ様々な人生訓を、20数年に亘る武田先生との子弟関係を絡めて描いた作品。原作未読。所作の「形」を学んだその先に、自然と人の世の移り変わりにさり気なく寄り添う茶道の深遠な世界を垣間見たような気がしました。毎年毎年、同じように繰り返されるお茶事には何か悠久の営みのようなものを感じます。その前では、人の苦しみや悲しみも季節の移ろいのようなもので、毎日を迎えられたことこそが僥倖であり、それが作品のタイトルである「毎日が好日(よきひ)」に通ずるのでしょう。主人公の20数年を一人で演じた黒木華さんが見せる多彩な表情は、多感な主人公の心情を映し実に見事でした。そしてその主人公の人生の困難な時も優しく包み込む先生役の樹木希林のたおやかさが何とも心地良く、観る者の心まで慰さめてくれるようでした。「続けられることが幸せ」、武田先生の最後のこの言葉は、生涯役者を貫いた樹木希林さんの人生とも重なって心に染みました。合掌。
女優と日本伝統にうっとり
何気なく観たのですが、実に良い映画だったと思います。
茶道を通じて若い女性が人生を学んでゆく姿が、清涼な空気感の中で語られていて心地よい。日本の伝統的所作の美しさ、特に茶道における手先の美しさにうっとりとしました。静かだけど、決して退屈することはありません。
女優陣が皆さん素晴らしい演技をする中で、やはり樹木希林の存在感と緩急付けた芝居が作品に面白さと深味を与えてます。
新年の茶席で希林さん演じる先生の挨拶は、この映画のタイトルにも、女優樹木希林の生き様にも通じるもので感動的でした。
がん告知から数年の希林さんの演技はどれも素晴らしく、リアリティー溢れる人間像でした。
共演の黒木華、多部未華子等、若い女優に彼女の魂が受け継がれる事を信じ、冥福を祈りたいと思います。
雨音がこれほど心洗わる気分にさせてくれる映画はなかなかない
「頭で考えずに手を信じなさい。」
なるほど、その言葉の意味するところがすとんと腑に落ちてきた。現代人はなにかと、それは何故か、その意味はどこにあるのか、と納得ができないと気が済まない質である。それは、ググればたいていのことが明らかになる世の中になってしまったからであろう。400年以上も続いてきた茶道には堅苦しそうな様々な形があり、初心者には不可解な決め事が多いと映る。だけど、その形にはそれなり理由がある。何度も何度も繰り返すことで、いつしか自然とその無駄のない動きとなっていく。その時に「頭で考えないうちに手が動く」所作となっている。その言葉の意味を、この映画は押し付けがましくもなく教えてくれる。
「世の中には直ぐにわかることと、直ぐにはわからないものがある。」と言う言葉もそうだ。「気づき」を知った人は、日々これまで気にも留めなかったことに気づきだす。すると、自分に関わる全ての人、もの、感情、季節、気象、日々変わっていくもの、変わらないもの。そんな諸々の物事が愛おしくなる。本当に大切なことは、あとからゆっくりと気付くのだ。そしてそれに気付いたからこそ、とめどなくじんわりと流れる典子の涙が清らかなのだ。
この映画は雨のシーンが多い。あるシーンで典子が床の間に掛けられた言葉に気付く。そして何かを思い出しながら、優しい笑顔をしたまま目に涙を溜めた。とても心優しいシーンだった。僕も、先生が雨模様の天気に合わせて選んだ掛け軸だと気付いていた。典子も、そう感じたのだ。先生のその気持ちに気付いて、今の自分の境遇と重ね合わせて、自然と潤んできたのだ。そんな典子の感情を共有するかのように、微笑みとともに僕の目にも涙があふれた。
難しい事は時間をかけてゆっくりと「道」を紐解いていく自然に即した世界観が素晴らしいですね!
私は残念な事に森田典子氏の原作を未読の為、原作の素晴らしさや、面白さ、人気の秘密を知らない。
本作の物語は至ってシンプル。主人公の典子は大学時代に将来に対する展望が見出せずに、モンモンとしていた矢先に、両親の薦めで全く正反対のキャラの従妹の美智子と一緒に茶道を習い始める事になる。そのお稽古の日々を追いながら、学生から大人へと成長していく一人の女性の姿が描き出される物語。シンプルな物語だが、実に典子の成長する様が清々しく、心が洗われる作品だった。
私は、茶道も書道も習った経験は無く、武道の類も習った経験がゼロの為に、日本古来の伝統文化の神髄を全く何も知らないでこれまで過ごして来た事はとても残念だと、本作を観て思った。
映画の中心には、常に茶道のお稽古のシーンが描かれていて、四季折々の時の変化の流れの中で少しずつ大人へと成長していく、典子の姿を詠い挙げて行くのが実に晴れ晴れとして、映画を観ている私達にも、典子の気持ちの変化が自然と伝わって来る、素敵な作品だった。
茶道等の日本の伝統文化とは、一つ一つのお作法を重んじ、その一つ一つの手順を忠実になぞり、真似る事で日常の忙しさの中では決して観えてくる事の無い世界へと、自らを誘い、その様式美を追及する事で、自己の内感を深めていくと言う誠に深い世界感を持っている文化で有る事をお恥ずかしながら、この歳で本作を観る事で知りました。
この作品では、お軸の大切な意味も出て来ましたが、茶室でお茶を本来頂く時は床の間に飾るお花まで御亭主の心遣いが現れ、茶室全体の空間その物を、お客様に提供する訳ですから奥深い、おもてなしの心の総てが詰っている世界なんですね。
最近では時代劇が映画化される機会も激減し、日本人の護ってきた伝統美、様式美、そしてその中心に息付く、自然の流れと共に有る日本人の心、魂をみつめる「道」の世界の素晴らしさを描いた作品が少ない現在、こうした心のぶれない生き方を示してくれる本作に出会えた事は実に素晴らしく意義深い事だと思います。
戦後の日本、占領政策の中で一番に阻止された事が武道や書道、華道。これらの伝統文化は日本人の根幹で有る精神性の向上を育む大切な習い事である為に、「道」と名の付く伝統文化が余り一般的に普及されないように西洋式重視の文化へとシフトされた事は残念な側面でもある。
2020年オリンピック開催を目前に控えた私達の国、日本で、日本人の心を表現出来るような本作が制作された事は非常に嬉しい事だ。
映画本来の話から脱線しているが、どうかお許し頂きたい。
黒木華は最近公開作品で「散り椿」「億男」等沢山お目見得する機会の多い女優さんだけれども、
彼女の女優としての成長する姿が本作の典子と自然と重なり合い、そしてお茶の師範を演じた樹木希林も、本作で描かれる「一期一会」の心の総てを、武田先生を演じながら、俳優人生の力の総てを懇親の芝居でご披露して下さって逝った事に、心より感謝を申し上げたい。
私は子供時代「寺内貫太郎」のドラマを観て育った世代なので、立派な名脇役と言うより、もっと身近なお茶の間、お婆ちゃん俳優と言う気持ちが強いのだが、本作程彼女の遺作として相応しい作品は他にはないだろう。希林さんのご冥福を心よりお祈りすると共に、本作の更なるヒットをお祈りしたい!
様式を愛で、二度と同じ日のない日日を祝福する
なんとも心地よい映画だった。毎日この映画を見ながら眠りたいと思えるほど。そして日本の文化の美しさに改めて気づかされた。お茶を立てる、という行為が持つ深く大きな意味を、私はこの映画で初めて知った。
私は茶道の経験がないので、冒頭の若い娘たちと同じ感覚でこの映画を見始める。
「お茶って変なの」と言ってくすっと笑う気持ちが少しわかるような気もする。決まりごとが多く、様式に則った動きをしてお茶を立てる。そのことに何の意味があるのか?と尋ねても、樹木希林さん演じる武田先生も口ごもって「そういうものなのよ」なんて答えたりする。しかしこの映画を最後まで見ると、様式に則りお茶を立てると言う行為の真髄が確かに見えて実感できるから素晴らしい。
私たちは、毎日似たような一日を繰り返している、ように感じている。今日一日を振り返れば、まるで昨日と同じ一日のようだったと思うし、明日のことを考えれば、まぁ今日と同じような一日だろうと思う。しかし、同じ日などは本当にまったく存在せず、一日一日少しずつ違う日が訪れている。春夏秋冬4つの季節より更に細かい二十四節季よりももっと細かい、言葉さえ存在しない単位で季節は365日移り変わっているし、その都度お茶菓子も変わるし、掛け軸の文字も変わる。茶器も変わる。装いも変わる。天気も変わるし、気がつかないだけで自分自身も変わっている。そういった変化に気づくためには、変わらない「何か」が必要だ。そしてそれが「お茶を立てる」という動作だと私は思った。お茶を立てるという動作は様式が決まっていて、毎回同じ所作をする。様式を愛でることで、日々の変化に気づき、また一日として同じ日のない今日という日を慈しみ祝福する。12年に一度巡って来る干支の茶器を見て過ぎた12年という歳月を想い今日という日を祝福する。仮に、辛い失恋や永訣の日でもその日を祝福する。辛い日もあるからこそ何事もない日の好さに気づきそれを祝福する。それがお茶を立てるという様式の美学なのだと、私はこの映画を見て初めて知った。
するとこの映画のタイトルを思い出す。
日日是好日。
二度と同じ日のない一日一日すべてが素晴らしき日である。
茶道。なんて美しい道だろう。
日本人であるというだけで、少し胸を張りたくなるような、そんな気分にさせてくれる映画だった。
映画の後の帰り道。私は無意識に背筋が伸びて、歩き方もいつになく上品になりました。
「茶道」の奥深さ
二十四節気☆
何事も取り組む時は、自分の心の持ち方次第。 素直に、目の前の事に誠...
そのころ百歳
タイトルなし
主人公の20歳からの二十年間を茶道の習い事を通して淡々と描いている。
茶道の稽古で感じたことを綴ったエッセイを原作に、
よく一本の映画に仕立てあげたものだ。
映画のほとんどは稽古場の茶室が舞台で、
四季の移ろい、時の経過を庭の風景や茶菓子、掛軸などのカットで現す。
それらのカットは、黒木華の静かな語りによって説明される出来事による主人公の心情に重なる。
大森立嗣作品としては新境地と言えるのではないだろうか。
樹木希林の演技はいつものとおり、独特の間合いで微かな笑いを誘いながらも、説得力がある。
あの人が演じると、小豆を煮る様子も、茶道の所作も、本物のように感じる。
地味な顔立ちの黒木華に対して、多部未華子はくっきりとした顔で対比が明確だ。
フェリーニの「道」が例えに使われているが、悶々とする黒木華演じる典子に、典子にとっての茶道は「道」みたいなのもじゃないかと多部未華子演じる美智子が言う。
冒頭、典子と美智子は仲良くないのかと思ったけれど、美智子は物事がよく見えていて、時に典子の迷いを晴らす役割だった。
そして、典子はそんな美智子を認めている関係。
鶴見辰吾が、静かに暖かく娘を見まもっている父親を好演している。
聴く映画
全311件中、241~260件目を表示