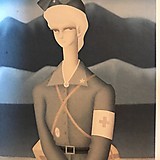日日是好日のレビュー・感想・評価
全311件中、201~220件目を表示
上手く行ってる時も、悲しみにくれてる時もそっと寄り添っていてくれた...
上手く行ってる時も、悲しみにくれてる時もそっと寄り添っていてくれたり、方向を示してくれたり。
習い事ってそんな存在だよなー、そう頷きながら観た。
レディースデーの銀座、同じタイミングで泣いている気配に、女性同士愛おしい気持ちになった。
奥深くないけど味わいのある映画
物語はドラマチックではないけれど、それがリアルで共感が持てた。
茶道を通してみる日本の四季、和菓子、道具、掛け軸、花、着物等々、美しかった。
水音が印象的で意味深かった。
若い二人の主人公は、樹木希林の存在感には太刀打ちできず、それが先生と生徒の関係なのかもしれない!?
観終わった後は「ふ~ん」という感じだったけど、記憶の隅に残り続ける映画かな。
茶道の映画と言えば千利休が主人公で、彼の美意識と生き様が強調されるけど、それは現代の茶道とは違う、と感じてきた。
この映画は等身大で、これが「現代の日本の茶道」だと世界の人々に知って欲しいと思う。
タイトル通り
まるで茶道のPRのようでもあるが 自分も含め この説明がないと 現代の日本人には伝わらない そこから 茶道の正に「道」の部分を感覚的に表現しようとしている。 「道」とは 日本文化そのものではないか みち どう タオ…神にさえ道が付く 道とは全てであり 源であり 時間とともにあり 今とここであり 花であり 鳥であり 風であり 月であり 森羅万象であり 喜びであり 哀しみであり 憎しみであり 怒りでもあり…道は全てを含み それは日日是好日である。
それは今ここに全てがある そんな事が映画から伝わってきた
樹木希林は勿論だが 黒木華の演技への迸る情熱も⭐
見終わって 少し背筋伸び 立ち居振舞い
という言葉を思った
もう一度見たい。フェリーニの「道」も
いい空気
日日是好日、素晴らしい言葉
三月ウサギの庭園で催されていたお茶会を覚えていますか
ディズニー映画『不思議の国のアリス』のお茶会
あの場面で歌う歌が好きでそれで子供の頃から何でもない日が大切で好きな日になりました
誕生日や元旦やクリスマスなど特別な日もいいものですが
何でもない日がどれだけ大切で意味があるか
結局は毎日がとても愛おしく無駄な日などないのだな〜と
日本も外国も関係ない、晴れの日も雨の日も熱い灼熱や極寒の凍てつく日も楽しい日も辛い日も
続けることに意味があるのではなく続けられたことに感謝できる今がいい
「日日是好日」
追記
涙が出るほどに愛おしくなる作品
一度見た時に「よしよし俺はこの映画分かったぞ」と思ったけど録画されていたので二度目の鑑賞
かったるいかな〜と思いつつ見ていたらズンズン引き込まれて没頭してしまいました
典子の心が激しく忙しく動いて行く、庭にやって来る季節が心地いい
四季のある日本に産まれた幸せを感じます
『今ここで』を感じること
とんでもなく濃密な映画だと感じました。凄い観応えだった!
静謐な映画だからこそ、目を離すことができない。いや、この映画を隅々まで味わいたい!と思わせるモノがありました。
目の前の音を感じ、観て感じ、触感や温度を感じるお茶の世界が描かれていたからこそ、そう感じたのかしれません。
意識を集中し、その瞬間瞬間を丁寧に感じることは、なんと豊かなことなのだろうか。素晴らしかったです。
黒木華演じる典子の24年を描いた映画でした。そのほとんどを茶室の描写に当てているにも関わらず、彼女の成長や変化がバッチリ描かれていました。
また、黒木華がすごい。その時その時の心の状態がちゃんと外に現れていて、これもビックリしました。所謂達者な役者とはちょっと次元が違う印象です。
典子はお茶が好きなのかは不明ですが、典子はお茶を必要としているのですよね。支えと言えるかもしれませんが、もっと的確な言葉がありそう。典子はお茶とともに人生を歩むことが運命づけられているような印象です。
典子のエピソードは基本サラっと描かれてますが、父との物語はさすがに胸に刺さりました。お父さんを演じた鶴見辰吾も素敵でした。あと、『セクシーは気品に宿る(ただしラテン系セクシーは除く)』を持論としている私にとって、本作の鶴田真由はド真ん中でした。めちゃ艶っぽかったです。
しかし、お茶は豊かですね!普通ならば通り過ぎるモノをキャッチして、味わう。茶室の造りや謎の儀式性はそのためにあるんじゃないか、なんて感じてます。
そんな風に理屈っぽく考えると武田先生に怒られそうですが、水とお湯の音は聞き分けられましたぜ!私の耳には、水はキーンでお湯はトロッ、でした。
武田先生は樹木希林意外はあり得ないですね。彼女の訃報を聞いた時は、「あんな妖怪みたいなバーさんも死んじまうんだなぁ」くらいにしか思わなかったのですが、本作を観て、もうこの世に彼女がいないと思うととてつもなく悲しくなりました。鑑賞後に、特に実感してます。
ただ、本作には間に合ってくださり、とてもありがたいとも感じてます。本作で改めて樹木希林のバーさんに出会え、何かを感じることができ、嬉しい気持ちになっています。
樹木希林さんは凄い!
主人公の小学生時代、親からフェデリコフェリー二監督の「道」と言う映画(私はこの映画が大好きです)に連れて行かれ「全然わからりませんでした。」からの始まり。彼女がふとした事で茶道と出逢い、お師匠さん(樹木希林)と出逢う。それからはお茶の道と人生の道を淡々と歩いていく主人公。わからなかった映画「道」の捉え方が変わり、心の中の茶道の位置が変わりながら、人生は淡々と過ぎて行く…。樹木希林の表情や所作を見ているだけで、私のほほをあついものが伝い、黒木華の変化に女性の人生を感じました。ストーリーには、大きなドラマも、大自然の壮大な描写もないのに、それ以上大きな人生と自然が感じられた、不思議に心が洗われる、清烈な映画でした。私は感動しました。泣きました。
日本文化って良いなあ〜〜
原作は未読です。
なので映画だけの感想です。
平日午後に観に行ったので
おそらく茶道をされているのであろう雰囲気の方が多く
前半部分に出てくる「茶道あるある」的なエピソードに
楽しそうに笑っておられて
茶道なんかわかんない!と思ってる方でも
すんなりに話しに入っていけます。
特に大きな事件がある訳ではなく
黒木華が演じる一人の女性が
25年程の間に起きる出来事
失恋したり、就職試験に落ちたり
そんなことを経験しながら茶道を続けることで
より茶道を深く理解してゆく過程を丁寧に映像化しています。
そして四季折々の掛け軸や器の選び方
和菓子の美しさ、そして全てを統合する茶室の豊かさ。
茶道の精神とも言える一期一会の美しさと
何でもない日々が続くことの有り難さ〜〜
日本文化って良いなあ〜〜
と私は、涙が出ました。
星五つは、こんな素敵な映画を
作ってくれた全てのスタッフへの感謝の数です。
よく行く映画バーのマスターと話した時、
こんな映画こそ、
海外の映画祭に出せば良いのにと意見が一致しました。
これこそ、ザ、日本映画〜〜。
で、月に8回ほど映画館に通う中途半端な映画好きとしては
とにかく、映画の全てが上手い!!
先ほども書いた通り、入り易い笑える話から
だんだんと精神的な高みに内容が深くなってゆく過程が
無理がなくて、上手い!!
「瀧」と書かれた掛け軸から
飛沫がほとばしる瀑布を想像する
日本文化のイマジネーションの豊かさ!
唸らされました!
普段あまりパンフレットは買わない方ですが
この映画では、映画の中で使われた掛け軸や
器やお菓子がパンフレットで解説されているので
映画の余韻を楽しむ意味で買ってみても良いと思います。
一番目立っている3人はもちろんですが
黒木華の父親役の鶴見辰吾!
娘を思う父をさり気なく演じてして、ほんと、泣けました!
改めて、重厚な役からコミカルな役まで軽々とこなす
樹木希林さんがもういないことに涙、そして、合掌。
@もう一度観るなら?
「近いうちに映画館でもう一度観ます!」
心に沁みる美しい映画
物足りん
心よりご冥福を申し上げます。
遺作として、樹木さんの「武田先生」は適役でした。
典子が大学を卒業し社会に出て一人を暮らしを、茶道を通して人生の
一片を描いた作品であり、そこに「師」と仰ぐ武田先生が寄り添っているいう感じの作品で、樹木希林さんの遺作としては、気持ちの良い作品であったように思える。私自身も茶道の作法の難しさを分かって良かった。「茶法」というのは、
練習を積めば自然に手が覚えるという。「茶道」の奥深さを感じ取れた気がした。気持ちを「無」の状態で一連の作業を行う。
映画の中に、フェリーニの「道」のエピソードが描かれている。それも作品に何らかのアクセントをつけていて、今の私の年齢だと理解できるだろうかと思った。一度、ゆっくり見てみてみたい。そんな上品な作品でした。
私としては、樹木さんのハチャメチャな作品を最後観たかったような気もする。
丁寧な良作
祖母が表千家の地方講師だったのですが、樹木希林の指導の言葉が、昔祖母から聞いた言葉と重なって、まずそれにしみじみしました。
お茶の世界は意外とローカルルールがないもんだな、という点に感心しました。
原作は未読ですが、茶道の心と、日々の生活にそれを活かすことというテーマを、よく消化していると思います。
?と思ったところ3点。
黒木華と多部未華子のカラオケシーンが無駄に長い(一瞬でよかった)。
時々挟まれる主人公の心象風景らしきものが、黒木華の演技力をもってしても浮いて見える時がある(海辺でずぶ濡れになって、亡き父に呼びかけるシーンとか)。
瀧のお軸から瀑布を感知するシーンは無音で映像だけ流す方が、観客も、無音だけど聴こえる、を共有できるし、没入感が出てよかったのでは。
庭木の若葉をズームインして細胞にまで入り込んでミトコンドリア?を大写しにするくだり(理化学研究所が協力でクレジットに入っていた)は、自然と生命の直結、悠久の時の流れと人の一生の儚さとか、禅的なものの含意だったのかなと思いますが…なんか唐突で押し付けがましかった。
ごめんなさい。
いい俳優さんを使って、丁寧に作られていたと思います。
傑作
全311件中、201~220件目を表示