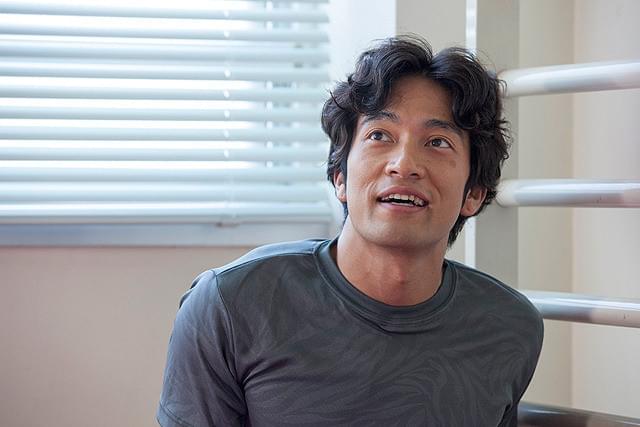ネタバレ! クリックして本文を読む
患者に肩入れしすぎる雅哉。純粋に「いい奴なんだろうな」とは思うが、チラリと突っ走ってしまう危うさも見え隠れして、不穏な空気が漂う。
対して、同僚の永田はちゃらんぽらんだがスマート。患者との距離感を保ち、失敗にもへこたれない。
永田は、折に触れて雅哉に「肩入れしすぎ」とからかい、一線を画しているように見える。けれど「雅哉、タバコ行こうぜ」という声がけは欠かさない。周囲が見えなくなるほど没入してしまう雅哉の身を、本気で案じているのだ。
やがて、雅哉の受け持ち2人が相次いでこの世を去る。1人は病気によってどうしようもなく。もう1人は、脅威的な努力によって取り戻した力を使って自らの意志で。
理学療法士として、もっと手を差し伸べたかったと思う相手と、自らのプライベートタイムまでかけ充分に回復させたと思う相手、どちらにも自分は届かなかったという雅哉の虚しさは、観ている我々の心にも重く響いてくる。
そんな雅哉を救ったのは、海音の母の言葉。
そして、雅哉の肩入れを案じていた永田の言葉。
「いや、お前1人だけ患者に肩入れしててもさ、こういうのは限界あるだろ。こういうのはみんなでやってかないと。まあ、それでもこんな狭い病院の中の俺たちだけじゃ限界あるけどさ。でも、仕方ないとか言ってちゃダメだよな。少しずつ出来ること増やしてかないとさ。」
自分にとっては、ここがこの映画でのベストシーン。
ラストで、見も知らぬ誰かに、確かな希望を与えた雅哉は、かつて危うさを感じさせた雅哉ではなく、少しずつ出来ることを増やそうとしている地に足をつけた雅哉だった。
1人の青年の成長の物語としてだけでなく、生と死、抗えない運命と人間の尊厳など、様々なテーマが提示されるが、出ている役者たち、全てが映画の中でしっかりと存在しているので、説得力がある。
主役の三浦貴大はもとより、阿部進之介の気迫には圧倒される。上半身と下半身のアンバランスな筋肉量とか、どうやって作ったのか。
父親役の鶴見辰吾も、みるみるうちにやつれていくように見えた。
役者たちの力量の高さが、この映画を一段と高いものにしていると感じた。










 デイアンドナイト
デイアンドナイト リトル・フォレスト 夏・秋
リトル・フォレスト 夏・秋 繕い裁つ人
繕い裁つ人 リトル・フォレスト 冬・春
リトル・フォレスト 冬・春 四月の永い夢
四月の永い夢 大コメ騒動
大コメ騒動 シサム
シサム ゴーストマスター
ゴーストマスター サムライフ
サムライフ ローリング
ローリング