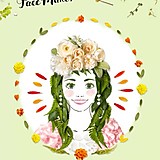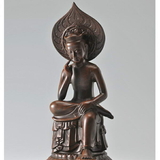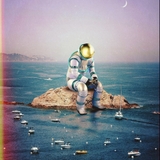映画 聲の形のレビュー・感想・評価
全459件中、41~60件目を表示
私は私が嫌いです
『ショーシャンクの空に』を星4とし評価しています。
ストーリー ★★
演出 ★★★
映像 ★★★★★
音楽 ★★
総合 ★3.5
漫画既読。
8巻の漫画を1本の映画にまとめようと思うとある程度のシーンを省略するのは致し方ない。
しかし映画製作編がないことでしょーやと竹内先生との関係や佐原さんと植野さんの関係が深掘りされなかったのは残念であった。
更に真柴くんの印象も薄く映画しか見ていない人からすれば「あいつは必要なのか」と思われても仕方ない。
映像はさすが京アニと言ったところで教室の質感などは大変クオリティが高いと感じた。
映画で物足りなかった人には漫画をおすすめする。ただ序盤のイジメのシーンが1.2割り増し位で胸糞なので注意すること
ひどいことばかり言って…
分かりあうことを諦めない
序盤は学生生活特有の息苦しさが臨場感ありすぎて、胸が痛すぎる!
私も小学校にはあまりいい思い出はないので、本当に嫌な気分になりました。
昨日まで仲良くしてた人たちが急に手のひらを返す。
いつも地雷の上を歩いているような感覚。
そんなイメージが小学校生活にはあります。
まだ子どもだから、嫌なもの、未知なものにストレートで純粋な反応をしめす。
だからこその残酷。
主人公の石田くん。序盤でやったことは酷いけど、彼だけが悪いのではない。
一番酷いのは担任の先生に見えた。
あいつマジ最悪。
出てくる子どもたちはみんな、お互いに分かりあうことを諦めなかった。だからこそのあの結末なのだと思う。
どんな時も、分かりあう努力をしたなら、苦手な人も受け入れられるようになるのだろうか。
この作品は、大丈夫。どんな人とも諦めなければ分かり合えるし、受け入れられるよ。
と教えてくれている気がした。
あとね、永束くん。
彼がこの作品のヒーローです。
間違いない。
ジェットコースター
イジメの描写が痛々しかった。子供時代のエピソードは観ていて苦しくなる。
背景がやけに美しい。
美しい世界に生きている。
BGMがピアノで♪ポロン、ポロン。と、悲しげなメロディ。この先、とてつもない悲劇になるような予感が漂う。
主人公の父親が登場しないことが氣になった。
他の子の父親も同様。
なぜか母親は頻繁に登場。
思春期の話は家族構成が謎の作品が多い。
本作は家族ぐるみで登場するから、なおさら氣になった。
美しくて繊細で真面目で暗くて残酷な儚い世界。
癒やされるような、落ちていくような、楽しみなような、怖いような、そんな不安な氣分の状態から、ジェットコースターのように一気にゴールにたどり着いたような映画だった。
絵のクオリティが高い。
単焦点レンズで撮影したような味わい深さがある。
ジェットコースターのシーンも迫力満点だった。
ラストは色々報われて良かった。
爽やかな氣持ちで終われて満足だったが、やはり氣になるポイントがある。
引っかかるポイントは、主人公がイジメる動機。納得出来るエピソードが欲しかった。
それと、ケータイのメッセージのシーンが短いために、読みきれず一時停止した。
話がダーク過ぎて集中力が続かず、二日に分け更に細かく小分けにして視聴した。
私はつくづくピンク色の髪の女性キャラに目がない。ツンデレの植野も悪くないが西宮硝子さんを応援してた。
本作は好みの絵だった。エンドクレジットで山田尚子監督作品と知って納得した。
肌に合わなかった
【”ディスコミュニケーションから、届けコミュニケーションへ・・。”聾唖者への悪戯により疎外された少年の聾唖者への理解の過程を切ない描写を含めて描いた作品。作中の斬新な心理描写が素晴しき作品。】
ー 今作を鑑賞したのは、2018年頃であったかと思う。
作品が発信するメッセージ”友達って何だ”が強く心に響いた。
その後、京都アニメーションを襲った忌まわしき出来事に呆然とし、京都に行った際には自分なりに出来る事をした事を思い出す・・。ー
◆感想
ー 多くの方がレビューを挙げられているので、久方振りに鑑賞した感想のみをシンプルに記す。ー
・主人公の石田が、小学生時代に、引っ越して来た聴覚障碍者の西宮に対する悪戯。だが、彼のみがやっている訳ではないのに、いつの間にか、彼が一人で責任を負う姿。
だが、彼はその罪を一人被る。
ー これは、今でも年代を問わず行われている事ではないか・・。だが、石田は西宮を苛めているようであるが、彼女を大切に思っているシーンが随所で描かれている。濡れたノート・・。-
・中学時代の石田は暗黒の生活を送る。一人も友達が居ない日々の生活・・。
西宮を苛めた故の自身の境遇を甘受する姿は、初見時にはやや苛立ったモノである。
苛めに加担していた生徒達の言い逃れする姿。
ー これは、現代でもあるのではないか・・。-
■この作品の価値を高めているのは、石田とディスコミュニケーション状態にある生徒たちの顔に”×”が付いている描写であろう。
そんな中、ナガツカが彼の友となり、”×”が消え去る描写。
そして、高校に進学した石田の境遇は余り変わらないが、徐々に”×”の数が少なくなっていく。
石田は、自らが過去に犯した(と言っても、小学生である。)過ちを悔い、西宮とコミュニケーションを取るために手話を密やかに学ぶ姿。
彼が、人としてキチンとした人物になっている事が、容易に伺える。
・高校になって、久しぶりに出会った石田と西宮。彼らはぎこちないながらも再び関係性を築いていく。だが、自分の存在が石田を傷つけていると勘違いした西宮の哀しき行動。
ー 美しい花火大会を、石田と一緒に観た西宮は”自分の想いが聾唖者故、伝わらなかった事で・・。
”好きと月・・。”
命を断とうと思ったのであろう。
だが、それをいち早く察した石田の身を呈して、西宮を助けようとした崇高な姿。ー
・そして、学校に復帰した石田の学友たちの顔から、”×”が次々に落ちて行くシーンは、可なり沁みる。
<初見時に、”こんなにすごいアニメーション映画を作る集団って、どんな人たちなんだ!”と思い、その後「リズと青い鳥」「ヴァイオレット・エヴァ―ガーデン」を見て、その感を強くした。
哀しすぎる出来事の後、京都に行った際に陰ながらお参りをした。
だが、この素晴らしき映画製作会社は、亡き人たちの想いを込めて、素晴らしき映画を届けてくれる筈、と信じている遅れてきた京都アニメーションの作品に魅了された男の一人ごとである。>
人が人である限り、健常者、障がい者問わず他者を理解するのは難しい
オープニングがとてもカッコよく
一気に引き込まれました
そして
エンディングのaikoさんの歌まで
あっという間に時間が過ぎました
本作品
西宮さん以外の健常者がたくさん出てきますが
皆それぞれが衝突し合います
健常者同士でもコミュニケーションが難しいのに
ましてや障がい者となると
接し方が難しいのは必然…
実生活でも
障がい者だから優しくしてあげるべきなのか
障がい者だけど健常者と同等に接してあげるべきなのか
考えさせられる場面たくさんあります
やはり
その人の障がいの有無は関係なく
人が人である限り個性は十人十色であり
その人に合わせた対応の仕方が求められるのではないか…
この映画はその感覚を見事に映画化してくれてる作品と感じました
心を抉る。とにかく「生々しい」
公開からしばらく、強烈に賛否両論があったと記憶しています。
特に「(いじめ)加害者を美化してる」といったマイナス批評が多く目に付きましたが、トラウマを喚起されてしまった当事者でないならば、表層的でもったいない見方だと思います。
物語の軸は、完全に硝子と将也の関係性に置かれています。
一見主題にも思える「いじめ問題」や「聴覚障害」は全く主題ではなく、大きめの舞台装置に過ぎません。
この作品が描く主題は、「人間の不完全さ」「コミュニケーションの難しさ」だと思います。
登場人物が全て見事に欠点を晒していて、通常のドラマ作品には必要ないまでに「脚色され尽くした生々しさ」があります。
虚勢から手痛い失敗をする繊細な小心者。
真っ直ぐ過ぎる故、不器用に周囲を傷つける者。
強烈な自己愛と、自覚すらない歪んだ邪悪。
未熟で無責任な教職者…
遠慮なく言ってしまえば、「○○性人格障害」のテンプレートのような登場人物の群像劇に仕上がっている。
そういった不快感が漂う世界観と相関関係の中で、硝子と将也の関係性が絶妙に付いては離れてはで転がる。
不完全な人たちの不完全なコミュニケーションは少しずつ噛み合い、最後には小さな希望を感じさせながら、深い余韻が残る。
「重苦しい恋愛映画」のようでもあって、やはりそうではない。
「こんな関係もある」という、そんな一例を描いた作品だと思います。
心理をゲームや記号などの独特の映像で表現したり、硝子視点での聾唖者の音のこもる表現など、京都アニメーションが放つ圧倒的なクオリティも最大のポイントです。
最高のアニメーション映画
全459件中、41~60件目を表示