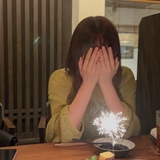映画 聲の形のレビュー・感想・評価
全580件中、41~60件目を表示
見たはずなのにすっかり忘れてた
水の美しい町大垣の水饅頭はとても美味い
遠くに見えるのは養老山地、最高峰は笙ヶ岳908mでさほどけわしくはないです
養老鉄道にはまだ乗ったことがないな
花火は桑名の水濠花火大会、ついこないだ見てきましたよ
安田顕さんの『愛しのアイリーン』のここら辺がロケ地でしたね
聖地とかってほどではないにしても知っている場所を映画で見るとそれだけで嬉しいものです
私もかつてはイジメあっていたことがありました
表情を殺し余計なことは言わずただ逆らわずに黙って耐えるだけ
それが精一杯の自己防衛だった
悪いことばかりじゃない、イジメる人がいない時は大いに明るく大いに笑いとても楽しい思い出ばかりが蘇ります
作品にするとしてもエピソードが地味すぎるしこの作品ほどキャストが揃わない
現実とはそういうものです、イジメる人とイジメられる人の二人がいただけ
私にとってラッキーだったのはイジメる人がイジメを悪いことだと知っていたこと、だから度を越すことは無かったと思います
ちなみに今はその事を許していますよ、悪かったと謝ってくれたので
『聲の形』は見ていて羨ましい、しっかりと適材適所に人がいて美味い具合に助け舟が出てくる、二人は幸せに向かって進めると思う
人の痛みがわかるからね
何度観ても泣いてしまう
映画館で観た事は無くて、地上波で3度目の鑑賞です。きっとこの作品は、辛い事があっても勇気を出して変わる大切さを教えてくれているのだと思います。
入野自由さんの演技がとても自然で、石田がヒロインの名前を叫ぶシーンでは涙が止まりませんでした。ヒロインを演じた早見沙織さんの演技もとても良かったです。
京都アニメーションは作画がとても繊細で柔らかく優しい雰囲気で、「ツルネ」を初めて観た時から大好きです。いろいろ大変な事もありましたが、これからもずっと京アニを応援しています。辛い事に直面した時は、また「聲の形」を観て頑張ろうと思います。
心の再生
このマンガがすごい!で、この漫画の事を知った。
でも、読まなかった。
イジメの話と聞いて、よくあるやつだろう、と高を括っていたから。
映画になって評判が良かったので興味が沸き、
アマプラにて配信が始まったので観てみた。
まいった。心を打たれた!感動した!
特にラストは号泣してしまった・・・(T_T)
原作8巻分を1本の映画にまとめているので、
周りの登場人物達の描写が少ない事は否めないが、
映画としてちゃんとまとまっていると思います。
原作との違いを比べたくて、ネットでちょっと比べてみたら、
(石田と島田がたこ焼き屋で再会するシーン)
これが結構演出が全くと言っていい程違っていて、
映画はかなり監督の作家性を強く出して変えている。
このシーンは映画演出の方がかなり好きです個人的には。
植野は凄い悪者みたいに見えるけど、
あれは嫉妬上の行動だと見ていれば分かる。
だけど川井と小学生の時の連れ島田だけは
最後まで好きになれなかった!
特に島田は悪い奴のまんまじゃん!映画ではね。
原作では知らんけど・・・
学校はいかなくてもいい
問題作の劇場アニメ化を考える
友人が鼻息荒くマ王の所にやってきて「凄いマンガがあるぞ」と捲し立てた。
大今良時の原作「聲の形」だった。
何が凄いのか解らず渡された全7巻をマ王は読んでみた。
成る程、可愛らしい絵なのに容赦の無い無垢な残酷をココまで描き切るとは。
更に驚いたのが「聲の形」は少年誌での連載だった事だ。
よくもまぁ世間が許したもんだ(調べたら実際に大問題になってたらしい)
全7巻の中身がイジメ、自殺、障害者、挫折など、子供が見てはダメ、と教育委員会やPTAが目を吊り上げる内容だからだ。
ただし全てを否定するではなく、ちゃんと作者の考えを溶かし込んでるトコは見事なストーリーテーラーぶりだと感嘆した。
悪い話ではない、でも知識の無い子供が見たらどういう反応を示すだろう。
大人が読んで老婆心を抱くくらい「聲の形」は良薬と劇薬の狭間に居座る名作である。
マ王自身、子供の頃はイジメもしたしイジメられもした。ここは正直に告白しておく。
だから、どちらの気持ちも代弁出来ます。
いい大人になって理解したのは、イジメ根絶は不可能なのとそれでも、イジメる側が絶対アカンくらいで積極的な行動には出ていない。
何処の世界にも未だにイジメという行為は存在し多くの人々を傷付けてる、更にはイジメは高度化しフィジカルよりもメンタルへのダメージを狙うという悪質な形態に成長している。
マ王のイジメ問題も随分と過去の話だが、加害者被害者どちらの感情も黒く残って洗い流せない。
マ王の唯一のアドバイスとして被害を受けてる方は誰に相談しても構わないので、イジメから逃げる、しか無いと思う。
何も日本の生活に拘る事も無い。
貴方の個性は日本サイズではないだけで、世界に目を向ければ受け入れて成長を助けてくれるトコなんて山のようにあるぞ。
それでも日本から離れたくないなら最悪の選択だけはしてはいけない。
要は自殺である。
貴方にとっては復讐のつもりかもしれないが、死とは加害者に想像以上のダメージを残す。
その後の人生が大きく狂ってしまうワケだ。
でも自殺って貴方がされた事と同じ行為の最強ヴァージョンなワケで、貴方はイジメの加害者として死を迎えるのさ。
ソレは貴方の最終評価として人生が終わる意味なんよ。
「それでも構わない」という短絡思考が一番ダメ。
相手と同じ土俵にワザワザ登ってはアカンのよ。
恨みは残るかもだけど、それだって何時かは赦してやらなくてはいけない。
何故なら貴方の人生なのだから他人の事で時間を消費するなんて勿体無いのよ。
さっさと忘れて(赦さなくては忘れられない)自分の人生を取り戻さないとね。
放火で多くの犠牲者を出した京都アニメーション制作の劇場版「聲の形」はいい形でバイブルになっている。
別にハッピーエンドを狙えという話ではない。
進行形でイジメの加害者も被害者もそれ以外の何もしてこなかった傍観者も、多くの人間に観てもらい多く語り合ってほしい映画でした。
映画館での鑑賞オススメ度★★★☆☆
でも多くの人に観てほしい度★★★★★★★★★★
イジメはアカンけど早いトコ謝れ度★★★★★
私自身が虐められる側だった
前を向く為の物語
鑑賞時間を感じさせない深~い映画
今から数十年前ですが、小学校6年の時代に、一般のクラスを体験させたいとの親御さんの願いで担任先生が受け入れ、わがクラスに1ケ月だったかな?来た聴覚障害の娘さんがいました。軽い陰口をすることはあっても、映画のようなイジメもなく、仲良くしていたように記憶していますが、そのことを思い出しました。さて、映画は3度〇マ〇ンプ〇イムで鑑賞、見ていて理不尽な扱いにつらい場面がいくつかあったけど、最後に各キャラクターともども救いがあり、見て良かった鑑賞時間を感じさせない深~い内容の映画でした。感動!
聴覚障害を扱った名作では「名もなく貧しく美しく」という古い映画がありましたが、こちらはアニメながら、それを超える名作だと思います。
私は私が嫌いです
『ショーシャンクの空に』を星4とし評価しています。
ストーリー ★★
演出 ★★★
映像 ★★★★★
音楽 ★★
総合 ★3.5
漫画既読。
8巻の漫画を1本の映画にまとめようと思うとある程度のシーンを省略するのは致し方ない。
しかし映画製作編がないことでしょーやと竹内先生との関係や佐原さんと植野さんの関係が深掘りされなかったのは残念であった。
更に真柴くんの印象も薄く映画しか見ていない人からすれば「あいつは必要なのか」と思われても仕方ない。
映像はさすが京アニと言ったところで教室の質感などは大変クオリティが高いと感じた。
映画で物足りなかった人には漫画をおすすめする。ただ序盤のイジメのシーンが1.2割り増し位で胸糞なので注意すること
期待の京アニ映画だったが、好みからは外れ、自分には不思議な物語展開
山田尚子監督による2016年製作(129分/G)日本映画。配給:松竹、劇場公開日:2016年9月17日。
面白くて全部を見てしまったテレビアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」の京都アニメーションの有名作品ということで、大きな期待を持って視聴。聴覚障害を題材として丁寧に作られた映画には思えたが、あまり自分の好みのものでは無かった。
小学校時のいじめっ子がいじめれっ子になってしまうという展開は、身近に実例も覚えており、悪く無いアイデアとは思った。しかし自分は、因果応報と思ってしまい主人公石田将也(声は松岡茉優→入野自由)に共感することはできなかった。まあ主人公のデザインが、好みから大きく外れていたこともあるかもしれない。何より、過去いじめられてた主人公を異性として好きになってしまうというストーリー展開に、説得力を感じなかった。何時から何故なのか、明示する様なエピソードが欲しかったとも。
聴覚障害というハンディの存在には同情でき、可愛いいとも思えたが、ヒロイン西宮硝子(声早見沙織)の謝ってばかりの性格設定も好みでは無かった。周りの女子のイライラに、すっかり共感を覚えてしまった。
一方、障害者のお姉ちゃんを守ろうと健気に男の子の様に振る舞うヒロインの妹、西宮結弦(声悠木碧)のキャラクター設定には好感を覚えた。主人公と家族の様な関係性を構築していく展開も、ナカナカに良かった。主人公の中学での唯一の友人永束友宏(声小野賢章)には、どこまでもいい奴すぎて、違和感とつまらなさを覚えてしまった。どこかで激しく争う様なとこが欲しかった。
結局主人公は何故硝子をいじめていたのか?好きで関心が欲しくてとも思えなく、その過去のことに直接的に向き合っていない様にも思えなかった。それなのにハッピーエンドで終わってしまい、障害者へのいじめを扱った映画として、本当にそれで良いのか?と思ってしまった。
監督山田尚子、原作大今良時、脚本吉田玲子、製作八田英明、吉村隆 、沖中進 、加藤雅己 、高橋敏弘 、吉羽治、企画八田陽子、古川陽子 、西出将之、 中嶋嘉美、 黒田康太、 松下卓也、プロデューサー大橋永晴 、中村伸一、 植月幹夫 、飯塚寿雄、 立石謙介、アシスタントプロデューサー瀬波里梨、鎗水善史、長谷川百合、 高橋祥 、奥長祥正、 伊藤洋平、キャラクターデザイン西屋太志、総作画監督西屋太志、絵コンテ山田尚子、 三好一郎 、山村卓也、演出小川太一、 河浪栄作 、山村卓也、 北之原孝將 、石立太一、設定秋竹斉一、作画監督
門脇未来 、丸木宣明 、明見裕子 、植野千世子 、角田有希 、岡村公平 、池田和美 、西屋太志、原画チーフ北之原孝將 、石立太一 、佐藤達也、色彩設計石田奈央美、色指定石田奈央美 、宮田佳奈、特殊効果、三浦理奈、美術監督篠原睦雄、3D美術鵜ノ口穣二、撮影監督高尾一也、3D監督冨板紀宏、音響監督鶴岡陽太、録音名倉靖、音響効果倉橋裕宗、音楽プロデューサー中村伸一、音楽牛尾憲輔、主題歌aiko、編集重村健吾、アニメーション制作京都アニメーション、制作協力アニメーションDo。
声優
石田将也入野自由、西宮硝子早見沙織、西宮結弦悠木碧、永束友宏小野賢章、植野直花金子有希、佐原みよこ石川由依、川井みき潘めぐみ、真柴智豊永利行、石田将也(小学生)松岡茉優、島田一旗(小学生)小島幸子、広瀬啓祐(小学生)武田華、竹内先生小松史法、西宮いと谷育子、マリア鎌田英怜奈、将也の姉濱口綾乃、ペドロ綿貫竜之介、島田一旗西谷亮、
広瀬啓祐増元拓也、石田美也子ゆきのさつき、西宮八重子平松晶子。
ひどいことばかり言って…
Netflixで2回目鑑賞
いじめの問題から、聾の少女に対する差別。
劇場で観た時は手話に興味なかったけど
手話講習会終了した後の鑑賞はまた違う。ウジウジとするシーンはイライラしたが、なかなかすんなりは、いかないやろな。京都アニメーションなんだね。
オタクぽい映像は少し恥ずかしい。
2度目となるとまた違う。
目と耳が聞こえていても聴いていない、見ていないのが全て。ラストは、皆んなのバッテンが外れて良かったな。
分かりあうことを諦めない
序盤は学生生活特有の息苦しさが臨場感ありすぎて、胸が痛すぎる!
私も小学校にはあまりいい思い出はないので、本当に嫌な気分になりました。
昨日まで仲良くしてた人たちが急に手のひらを返す。
いつも地雷の上を歩いているような感覚。
そんなイメージが小学校生活にはあります。
まだ子どもだから、嫌なもの、未知なものにストレートで純粋な反応をしめす。
だからこその残酷。
主人公の石田くん。序盤でやったことは酷いけど、彼だけが悪いのではない。
一番酷いのは担任の先生に見えた。
あいつマジ最悪。
出てくる子どもたちはみんな、お互いに分かりあうことを諦めなかった。だからこそのあの結末なのだと思う。
どんな時も、分かりあう努力をしたなら、苦手な人も受け入れられるようになるのだろうか。
この作品は、大丈夫。どんな人とも諦めなければ分かり合えるし、受け入れられるよ。
と教えてくれている気がした。
あとね、永束くん。
彼がこの作品のヒーローです。
間違いない。
まあいい話
................................................................................................
小学生の時に耳の聞こえないショウコが転校して来た。
しかし主人公とその女友達から虐められることになりまた転校。
主人公も女友達もその件でモメて友人との仲に亀裂が入った。
因果応報というか主人公は中学で虐めにあい、高校でも孤立。
自殺しようと思い、その前に心残りであったショウコを訪ねる。
それをきっかけに、上記のメンバー達に改めて交流が生まれる。
孤立する中で学校に友人が2人出来て、彼らも含めて交流する。
しかし主人公の女友達はショウコのことを今もどこか嫌ってた。
ショウコのせいでみんなが築いてきた人間関係が崩れたから。
そういうのを知ってかショウコは自殺を図り、主人公が助ける。
身代わりとなった形で主人公は意識不明となる。
ある夜ショウコは悪夢を見て、主人公が急に心配になり思い出の場所へ。
同じように夢を見た主人公も目を覚まし、病院を抜け出てそこへ。
こうしてお互いの大切さを知ることが出来た。
それを機に主人公らのコミュニティは復活する。
そして長年人の顔を見られなかった主人公は、それを克服する。
................................................................................................
劇場で見ようと思ってて見られなかった作品。
当時からものすごく高い評価だった。
ジーンと来るシーンはあったが、TVやとやっぱり感動が減ってしまうなあ。
最後の偶然2人が再会するシーンとかはやり過ぎな気もする・・・。
障碍者を扱う現実的な映画にしては、安っぽい恋愛映画チックかなと。
ジェットコースター
イジメの描写が痛々しかった。子供時代のエピソードは観ていて苦しくなる。
背景がやけに美しい。
美しい世界に生きている。
BGMがピアノで♪ポロン、ポロン。と、悲しげなメロディ。この先、とてつもない悲劇になるような予感が漂う。
主人公の父親が登場しないことが氣になった。
他の子の父親も同様。
なぜか母親は頻繁に登場。
思春期の話は家族構成が謎の作品が多い。
本作は家族ぐるみで登場するから、なおさら氣になった。
美しくて繊細で真面目で暗くて残酷な儚い世界。
癒やされるような、落ちていくような、楽しみなような、怖いような、そんな不安な氣分の状態から、ジェットコースターのように一気にゴールにたどり着いたような映画だった。
絵のクオリティが高い。
単焦点レンズで撮影したような味わい深さがある。
ジェットコースターのシーンも迫力満点だった。
ラストは色々報われて良かった。
爽やかな氣持ちで終われて満足だったが、やはり氣になるポイントがある。
引っかかるポイントは、主人公がイジメる動機。納得出来るエピソードが欲しかった。
それと、ケータイのメッセージのシーンが短いために、読みきれず一時停止した。
話がダーク過ぎて集中力が続かず、二日に分け更に細かく小分けにして視聴した。
私はつくづくピンク色の髪の女性キャラに目がない。ツンデレの植野も悪くないが西宮硝子さんを応援してた。
本作は好みの絵だった。エンドクレジットで山田尚子監督作品と知って納得した。
全580件中、41~60件目を表示