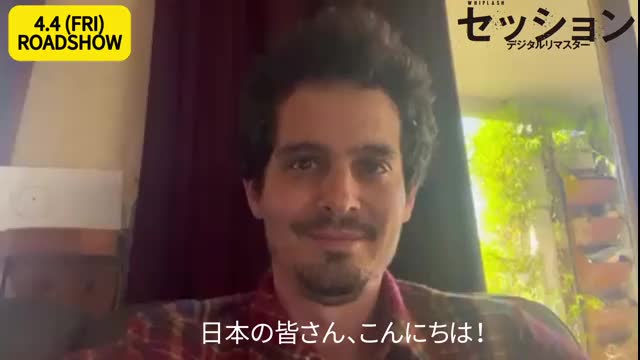セッションのレビュー・感想・評価
全931件中、41~60件目を表示
ニコルがかわいい。 普通片親系は母!な所、父親なのがなんかいい。 ...
ニコルがかわいい。
普通片親系は母!な所、父親なのがなんかいい。
単純に正義対悪!か共闘!みたいな関係じゃないのがいい。何か拗らせまくった二人でSelfishの極みとぶち切れた極みで引き込まれてしまった。
自分の中で、その余韻で寄り道したくなったり、自己嫌悪になったりした時はいい映画を見たという自分の体の正直な反応なのだが今回は後者だ。
大学デビュー前のニコルがかわいいです。
叩け、叩け、叩け! 血が騒ぐ!
4月9日(水)
またしても、極私的公開時見逃して再公開劇場初見シリーズ?「セッション 4Kデジタルリマスター版」をTOHOシネマズ日比谷の4KDolby-Atmosで。
いつも言ってる事だけど、映画は映画館で観るのを基本としているので、殆ど配信では観ない。円盤持っているのも基本は映画館で観た作品である。
と言う訳で、もはや伝説にもなっているJKシモンズの鬼教師フレッチャーの怪演をやっと映画館で観る事が出来た。
今なら絶対ハラスメントで駄目なやり方でフレッチャー(J・K・シモンズ)は罵詈雑言を浴びせ、追い込んで行く。
本作を観た日に、趣味でオーケストラやっている娘が家に帰って来たので聞いてみた(彼女は公開時にセッションを観ている)。
「101小節目頭から、なんてあんな風に練習するの?」「コンサート前の練習なんてあんなもんだよ。先生も必死で(フレッチャーと)変わらないよ」
へぇ〜そうなんだ。趣味でやっててもそうなら、プロを目指すプレイヤーは必死だろう。
フレッチャーは色々な手を使ってニーマン(マイルズ・テラー)にプレッシャーをかける。ニーマンの友人のドラマーを主奏者に呼んでライバル心をあおったりもする。
あの指導の仕方で天才や伝説のプレイヤーが生まれるとは思わないけれど、ニーマンはフレッチャーに必死に食らいついて行く。しかし、演奏会への途上のアクシデントでスティックを忘れて取りに戻り事故る。それでも血だらけでプレイするがアウト、ニーマンはドラムを辞めるのだが…。
ラストの約9分にわたるプレイは圧巻だった。そこに至るまでの二人の駆け引き、教師の座を追われたフレッチャーの怒りの報復、復帰したニーマンの意地、全てが混ざりあった"セッション"の中でニーマンは叩く。
叩け、叩け、叩け!プレイ中に緩んだシンバルを締めなおして継続させるフレッチャー。
ニーマンは叩き抜く。
不満は、恋人ニコルの扱い(よりを戻そうするのを含めて)と復帰する時に仕舞ってあったドラムセットを引っ張り出すだけで練習するシーンが無かった事。
助演男優賞、録音賞、編集賞(音楽(音)とシンクロする編集が見事)3部門のアカデミー賞受賞も納得だった。
見終わった時に心地よい映画ではないが、凄い映画だった。
「WHIPLASH」と並ぶ演目が「キャラバン」だった。知っている曲で良かった。
まぁ、私が聞いていたのはベンチャーズだけどね。
おまけ
ニコルがバイトしている映画館へ父親と映画を観に行って知り合うが、上映しているのがジュールス・ダッシンの「男の争い」。ここは名画座か?
期待度◎鑑賞後の満足度◎ 性格悪~いツルッパゲのオヤジ(でもジャズ愛は熱~い)と、確かに友達少なそうな頑固で自己チューな若者(でも負けん気と努力は人一倍)との音楽バトル。アメリカ映画近来の力作。
Not my fxxxin’ tempo!!
何度か観ている作品ですが、スクリーンで観たことがなかった事と4K&Dolby atmosで再上映ということで鑑賞しました。
スパイシーなフレッチャーの指導がニーマンを追い詰め、彼の焦りと苛立ちがヒシヒシと伝わる前半。フレッチャーも丸くなったか…と思わせてそんなことある訳なかった後半。教え子だった時はもちろんフレッチャーのペースだったのが、最後はニーマンがフレッチャーを飲み込んでいく…!
何よりも好きなシーンはラストでドラムソロを叩く息子を隙間から見つめる父。あの表情が本当に堪らんのです。
自分にとっては実にリズムもテンポも良い作品です。
再上映に感謝🙌✨
圧倒的な没入感に大興奮 でもシンバル投げ伝説を持ち出されてもね……
ご存知デイミアン•チャゼル監督の出世作。私は最初に見たとき、これはすごい、大傑作だと大いに興奮したものですが、鑑賞直後の興奮から醒めると、結局は暴力礼賛じゃないの、いろいろとやり過ぎてるし、といった、内容に対する嫌悪感がふつふつと湧いてきて、あれはいったい何だったのだろうかと思うようになっていました。私のこの作品に対する評価は大きく揺らいで今を迎えております。
再鑑賞を前にして、私のこの作品に対するスタンスをQ&A形式で示すと下記になります。
-傑作と思うか?: イエス。傑作には違いない
-ひとに薦められるか?: イエス。薦めて鑑賞仲間を増やして、この作品についていろいろと語り合いたい。ただし、薦めるひとは選ぶかもしれない。
-好きか?: ノー。同じ監督の作品なら『ラ•ラ•ランド』のほうがはるかに好き。
-自分の生涯お気に入り映画のリストに入るか: ノー。絶対に入れたくない。今回がこの作品の生涯最後の鑑賞になるかも。
ということで、見てまいりました、公開10周年記念デジタル•リマスター版の上映。どうだったかというと、まあ、なんというか、つまり、そのぉ……いいっ!! いきなり首根っこを押さえつけられてスクリーンの中に引きずり込まれたような没入感を味わい、クライマックスまで息つく間もなく一気に駆け抜けました。やはりタダモノではないですね。体感時間が非常に短い、極上の映画体験でした。
やはり初回鑑賞時の記憶があやしくなっていたようで、今回、少し認識を新たにした部分もあります。最初に見たときには、主要登場人物のふたり、フレッチャー(J.K.シモンズ)とアンドリュー•ニーマン(マイルズ•テラー)の行動の原動力となっているのは、完璧なジャズを目指しての、もっと芸術至上主義的な側面寄りの何かだと思っていたのですが、今回見た感じでは実際にはそういった面もあるにせよ、エゴやプライドといった、もっと人間臭いどろどろとした何かではないかと考えるようになりました。まあ、ふたりともエゴが強くてプライドが高いですからね。ということで、初回鑑賞時はより良い芸術を生み出すためにちょっと違ったゾーンに入ってしまった人たちの物語みたいな受け取め方をしていたのですが、今回はニーマンの上昇志向やふたりの間の私怨、そのもととなっているエゴやプライドに目が行って、思ってたより人間臭い話だったんだなと思うようになりました。二回の鑑賞で共通しているのは圧倒的な没入感と鑑賞直後の大興奮です。
今回の鑑賞で気づいたことは他にもあって、私がこの作品のことを好きになりきれないのは、この作品がファシズムとか反知性主義とかいった、いかがわしくて怪しげな何かを持ち合わせている感じがするからだと思いました。チャーリー•パーカーはシンバルを投げつけられなくとも偉大なサックス•プレーヤーになっていたと信じたいです。まあでも面白かったし、これが生涯最後とか言わず、また見たくなるかも。
ありがとう再上映
今回初めて鑑賞。DOLBY ATMOSで音よろし。
ジャズはフリーに楽しむものという印象があったが、
このような軍隊みたいな世界もあるのかと恐れ慄く。
フレッチャーは終始鬼だが、最後の最後にアンドリューと音で魂通わせるシーンは言葉では表せないほど最高だった。
アンドリュー、おとなしそうで対人関係も苦手、フレッチャーに何度も痛めつけられるのに最後これでもかと実力見せつけてくれた。最高のカタルシス!
作品を観ている間、ずっと心がたかぶっていたが
ラストは音楽の力で感情を最高の最高レベルまで高め上げてくれた。
エンドロール後、あーっと叫びたくなるほど余韻が素晴らしい映画だった。
Jack the JAM
ずっと気になっていた作品を、リバイバルにて。
オープニングからもう音が格好いい。
そして初登場時からハッキリと分かるパワハラモラハラ教師フレッチャーのヤバさ。笑
彼が本当に曲者で、最後まで一筋縄ではいかない。
ショーンの死に涙を流しながらも死因を偽り、丸くなったかと思えば強かに復讐を仕掛ける。
対するニーマンは、最初はナヨナヨした雰囲気。
しかしフレッチャーの熱気と狂気にあてられてどんどんと“そちら側”へ踏み込んでゆく。
中盤以降、特に演奏中は輪郭すらシャープに見えるほど。
普通なら終盤にフレッチャーの真意が明かされて感動的な共闘関係になりそうなものだ。
いや、実際言葉に偽りはないだろうし共闘もする。
しかしそれは殴り合いながらの共闘だ。
「本当は良い人でした」なんて優しい真相は用意されておらず、それでも音楽やプレイヤーへの愛は本物。
最後のセッションで否応なく熱くなるあの姿から、それは疑いようもない。
彼におもねることなく挑みかかるニーマンも、もう同じ所まで行ってしまったのだろう。
睨み合いながらも楽しそうな2人が印象的。
口元の演技が魅力的だったニコルをあの扱いにするのは勿体ないが、本作には必要な措置だった。
その分、本番直前に復縁を狙おうとしたのは余計かも。
半年以上のブランクから最後の演奏の説得力を出すには、「実は練習続けてました」くらいは欲しかった。
あの後の2人の関係を描かないのは賛否が割れそう。
個人的にはフレッチャーの年齢になったニーマンの様子とかで何かしら臭わせて締めてほしかったかな。
とはいえ、ジャズにはまったく詳しくない自分が前のめりになるくらいには、素晴らしい作品でした。
天才アーティストの心理
評価が高いので、その理由が知りたくて観ました。
完璧を求める指揮者ってこんな人なんだなー。ドラムのタイミングで速いか遅いかが素人には全くわからない。しかし、作品として完成をイメージしてる人には、僅かな違いが許せないんだろう。
変人、奇人と言われる所以はこんな部分に表れるんだろうな。
ラストシーンまでモヤモヤ感が抜けず、こんな大舞台でも引きずり落とそうとする変人に付き合ってられるかー。はめやがってー。って主人公の気持ちになって観てました。しかし、与えられる側だと、相手の思うつぼになることを逆手に取って、主導権を握る辺りからの大逆転劇。
ドラム主導で、周りはプロの演奏家。観客のために合わせざるをえず、痛快な10分間。きっと、指揮者もこの大どんでん返しに驚きながらも、こんなやり方で仕返してくる主人公に嬉しさが出てきたんだろう。
しかし、この指揮者の怪演を演じることのできる演技力は圧巻。名作と言われるのが分かりますね。
最初から最後までずっと緊張感
やっぱ凄ぇよ…(4Kリマスターを観て)
ムビチケカード回遊をしていたら、不意に本作が再上映との事で、早速観てきました!
結論。歳を重ね、更に面白さupです!
実は、要所のお父やん重要っぽい(完璧に理解は出来ていない)、ニコルこんなキュートだったっけ?、コノリーのピエロっぷり、その他etc...と新たな&思い出しの気付きがあり非常に楽しめました。
J・K・シモンズのフルメタルジャケットよろしくのセリフ回しも、相変わらず狂気で最高でした。
以前は、終盤のシーンは“上出来(good job)”と言ってると思っていましたが、改めて観ると違うっぽいような…笑
また、本作のエンドロールの入り方は、個人的にTOPです!!(あのドラムは踊るかのようで狂気です!!)
是非、観た事がない方&見て時間が空いた方、絶対気付きがあります。
是非、映画館でご観賞ください!!!
真剣勝負に人格は要らない
真剣勝負に於いては、パフォーマンスへのリスペクトは人格とは関係ない。
真剣勝負!というほど大げさでなくても、ゴルフとか麻雀とかトランプゲームの大富豪でもいいのですが、真面目に勝負に向き合ったことがある人なら誰でも心当たりがあると思います。普段は〝嫌な奴だなぁ〟と避けてるような人がメンバーにいても、その人の良いパフォーマンスに対しては、人格とは関係なく率直に「上手い」とか「いい手だな」というふうにプレー自体に自然な気持ちでリスペクトの気持ちが湧いてきます。
アンドリューはひとことでは言えない複雑な気持ちを〝自分の土俵〟ですべてプレーとして発揮しました。
始めは土俵の外で、陰湿に仕掛けていたフレッチャーも最高のプレーを見ているうちにプロとしての魂に火がついて、気が付けば同じ土俵に立っていました。
不器用で人間関係に気を使うのが苦手な人でも、何かひとつ自分の土俵といえるものがあると少し違った世界が見えてくるような気がします。
映画館で観るべき映画
昔WOWOW契約していた頃家のTVで観て色々衝撃受けて最後度肝抜かれて「この映画は絶対映画館で観るべき映画だ!!」と思ったのを覚えてる。時が流れリバイバル上映で映画館で観られて嬉しい。私は音楽は小中高の音楽の授業で習っただけだから音の良さや主人公の技量もわからないけど本当最後は圧巻なのでぜひたくさんの人に映画館で観て欲しいと思った。J・K・シモンズだからあのトラウマ級の鬼教授が演じられるんだろうね。一昔前はこんな怖い教授本当にいたのかな〜?お互い最後復讐し合ったけど結局音楽で繋がった感じだよね。主人公のマイルズ・テラーはトップ・ガン マーヴェリックのルースター役の俳優さんなんだけど困り顔が何とも可愛い。マーヴェリック映画観た時セッションに出てた俳優ってことに全く気付かなかったよ。マーヴェリックでも軽快にピアノ弾いてたね♪
殴り合い
音の戦争
「目玉をくり抜いてやる」
音楽院を舞台にしたスパルタ教師とドラマー志望の学生による音の戦争。ミュージカルを製作したかったデイミアン・チャゼルが資金集めとアピールのために製作したのが本作にあたる(ご存知の通り、その後チャゼル監督のミュージカル構想はは「ラ・ラ・ランド」として結実する)。
やるじゃねえかチャゼル、というかどうした?こんなに素晴らしい作品を製作したのにその後は一体何だ?「ラ・ラ・ランド」はまあまあ面白かったが「バビロン」はまるで離乳食だ。
魂を揺さぶられた。また私事になるが、僕は奇しくもアンドリュー(演:マイルズ・テラー)とフレッチャー(演:J.K.シモンズ)両方の立場を自分の中で経験した。そしておこがましいことを言えばチャーリー・パーカーも。
僕は10歳の頃同級生からいじめにあった。中学は受験したので中高一貫校に進んだが、小学校時代の同級生を見返したい一心で(「自分はあいつらとは違う」という差別意識もあった)勉強も部活も取り組むようになった。ここまでは聞こえが良いが段々と方向がおかしくなり、気付けば「叩く側」と「叩かれる側」の二面が自分の中に。謂わば「セルフパワハラ」である。「猿でも解ける問題で何故満点が取れないのか?お前の存在は人類第8の大罪だ」といったことを並べたて、ピーク時には真冬に窓全開でシャツ一枚で勉強、試験の成績が思わしくないとズボンのベルトで自分のことを殴りつけるといった始末だった。しかしそうこうしているうちに今度はメンタルがおかしくなり、17歳の頃学校内の試験で失敗したことで完全にグレた。ライブ中にシンバルを投げつけられたチャーリー・パーカーのように、周囲から笑われて完全にやる気をなくした。「お前は無能だ」と吐き棄てて自分を見限ったのである。残念ながら現在でも自己嫌悪の感情はある。
気持ち、僕はフレッチャー寄りだ。僕からすれば「努力」「立派」というワードは人を破滅させる危険なワードだ。英語で言うと"Good Job"といったニュアンスだろうか。だが同時に「一線というものがあるでしょう」とも思う。17歳の自分は、やってもやっても認められない虚しさにやってられなくなって全てを投げた。数年前、電車が遅延した際に「社内会議に遅れる」という理由で勝手に線路を歩き出した会社員が社会問題となった。やはり行き過ぎるとこういうことが起こるし、ここまでくると容認も看過もできない。
でもね、「努力」は結局偽物でしかなく、本物にはなり得ないと個人的には感じる。ここまで来るともう価値観の問題で、要は「天然だろうが養殖だろうがウナギは美味しい」と考えるか、「いや、やっぱりウナギは天然に限る」と考えるかの問題である。別に世の中妥協しても死にやしない、というか、チャーリー・パーカー自体が結局ドラッグに溺れて寿命を縮めたことを考えると、陽キャとして生きたければそこそこのラインで妥協することが必須だ。だから皆「努力が大事」などと不揃いな薄っぺらいことを言う。僕は陽キャにはなれない、故に「努力」とは生涯相容れない。となれば「イカれる」しかなさそうだ。伝えるべきは、狂気。
恐怖体験ココにあり
最高に飛ぶ映画
勢いとパワーで押し切られない様にしないと負けそうになる映画
アメリカ版「嵐を呼ぶ男」(嘘です)
腕を怪我したら自分で歌えばいい・・・わけないw
数年前に配信で鑑賞したが、公開10周年を記念した4K&Dolby Atmosのデジタルリマスターでリバイバル公開という事で劇場にて再鑑賞した。
公開当時は自分も小中学生向けにとあるスポーツの現役コーチをしており、クラブ自体も厳しい事で知られていたこともあって、フレッチャーの指導方法に対し少なからず共感する部分もあったが、時代が変わり10年経った今改めて観るとただのイジメにしか見えなかったw。
名門音楽学院の指導者フレッチャーは自分でジャズの名演奏者を育てるという崇高な目的を掲げ軍隊の様な厳しい指導をするが、教え子達のメンタルをことごとく壊し、中には自死した者もおり、最後は行き過ぎた指導により学院を辞めさせられるが、その復讐として大衆の前でニーマンに恥をかかせようと(ここがなかったらホントに良かったのに)という反省どころかとんでもなくセコイ暴挙に出るなど、本来の目的はどこ吹く風状態で生徒への愛情なんていっさい無いイジメ体質のただのパワハラ指導者だということがわかる。
追い込まれていく生徒のニーマン自身も必死に食らいつこうとするが、交通事故など不運(とというより単なる自分のミスなんだけど)もあり大事な演奏に遅刻し、最後はフレッチャーへ掴み掛かり退学になる。
ニーマンが最後はあくまでもミュージシャンとして、そしてジャズドラマーとしての戦い方で応戦するが、フレッチャーも戸惑いながらも中断させなかったのは本来自身もジャズを心から愛する者としてずっとこのままでいたい、ずっと演奏させたいという気持ちが勝ったからだと思う。
色々とツッコミどころは多いが、とにかく演奏シーンは圧巻で見応えが半端なく、実際ジャズドラマーを目指していたというデイミアン・チェゼル自身の経験からならではの臨場感を演出し、特にラストのニーマンの血と汗が飛び散るドラミングは観ていて鳥肌が収まらないほど強烈で、画面に呑まれないよう必死になってしまうほどだった。
まさに音響設備の良い劇場で観るべき映画である。
天才と狂人は紙一重
狂気と狂気のセッション
ラスト9分19秒は、何度見たことか。多分100回ではおさまらない。それだけ思い入れのある『セッション』が、デジタルリマスター&DollbyAtmosで再上映だから見逃すわけにはいかない。
パワハラの代名詞ともなったフレッチャー教授。『フルメタルジャケット』のハートマン軍曹も恐いが、精神的なダメージの与え方で言えば、フレッチャーの方が上回る。全人種平等に悪態をつくその徹底ぶりに、奇妙な“公平さ”を感じてしまう。
教え子が、現場に満足することを恐れて常にプレッシャーを与え、意図的にライバルを作って競わせる。フレッチャーのしていることは、星一徹メソッドの究極バージョンとも言える。
星一徹メソッドの欠点は、勝ち残った人間はとてつもなく強靭な能力を得るが、数多くの落伍者は、悲惨な末路をたどる。
フレッチャー的な父親に育てられ、フレッチャー的な教師にどつかれながら教育を受けた身としては、強圧メソッドには嫌悪感を感じるし、肯定できない。結果的に打たれ強くなっただけで、真の強さとは程遠い。
……でも、あの狂気の先に何かがあるんじゃないかって思ってしまう。それを信じさせるのが、デミアン・チャゼル監督の巧さなんだよね。狂気と狂気がぶつかって、何かが生まれる。そう感じてしまう自分がいる。
それにしても、DolbyATMOSの効果はすごい。全方位からフレッチャーに罵倒されている気分になり、タマタマが縮む上がる。拳銃を突きつけられるよりも恐い。
見た人も見てない人も見逃す選択肢はございません。
全931件中、41~60件目を表示