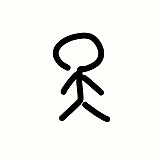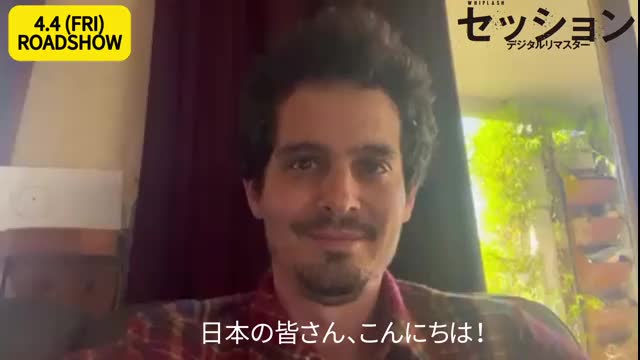セッションのレビュー・感想・評価
全931件中、201~220件目を表示
究極を追求した先の景色とは…人生の選択を問う作品
犠牲を伴っても徹底的に理想を追求した先の成功を選ぶか、現実的な幸せを選ぶのか。
ラストふたりのセッションが完成した後のニーマンの人生は描かれていない。どちらを是とするかは観た人の価値観に委ねられている。
原題は「Whiplash」でそれが愛の鞭なのか理不尽ないじめなのかをテーマにしているが、日本では「セッション」としてラストの高揚感をエンタメとして中心に据えた表現となっていると感じた。
フレッチャーは夢を持っているが不器用な人で寂しそうにも見えた。
挫折禁止の先に見える景色はどんなものなのか。ただ従うだけではなく、自分で考え悩み気づくことが大切だと伝えようとする究極の優しさではないだろうか。
アカデミー助演男優賞を受賞したJ・K・シモンズの圧倒的な存在感は見応えがある。
この映画はデイミアン・チャゼル監督の実体験をもとに描かれているとのこと。どういう想いでつくったのか。
結果本人はジャズを挫折しているが、次作『ラ・ラ・ランド』でジャズピアニストのミュージカルを製作し見事アカデミー賞を受賞している。
60点
映画評価:60点
この作品は凄い。
何が凄いかって、
最後まで和解していないのが凄い。
この手のストーリーはありがち
そして最終的に和解するか、
悪が手痛い思いをするというのがお約束。
でも、この作品は違う。
ジャズのドラマーとして
大成を志す主人公と、
自身の美学の頂点を目指す講師との
自尊心のぶつかり合い。
その本質は《セッション》にある。
観た方に勘違いしてほしくないのは、
このセッションというタイトル。
これはジャズ音楽のセッションではない。
主人公と講師の《魂》のセッションだという事。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下、解説です
当初、漠然と有名なドラマーになりたいと
日々ドラムと向き合ってきた主人公は、
周りの人よりドラムが上手かった。
そこに鬼講師が現れた。
最初の出会いの段階では、
講師の言われるがまま萎縮していた。
講師からの要望を体現する中で、
漠然さが鮮明化していく。
自身の弱点や、音楽性、そして意識をしながらの練習の大切さ。
そのうち接点が増えていくうち、
主人公もまた執着の鬼となっていった。
いつの間にかチームの中で、
唯一講師に楯突く存在へと変貌していく
それほどの執着と希望を胸に。
普通、ここまでくると和解する。
でも講師は認めない。
彼は指導者ではなかったのだ。
講師は美の追求者。
講師の美学とは違う音が許せなかった。
互いの執着は激突し主人公は退学となる。
その後、色々あり講師と出会い
またチームを組む。
そこでも主人公はヒドイ扱いを受ける事になるのだが、貧弱な彼はもういない。
魂と魂
意地と意地
執着と執着のぶつかり合い。
この音楽はまさに
セッションなのだ。
上手く合わせた形じゃない、
殴り合いの統合。
だから特にジャズは関係ない。
【2021.7.26鑑賞】
ただのドジ映画では…笑
主人公はまず、ちゃんと約束の時間を守れるように、時間に余裕をもって行動していれば、普通に上手くいってたと思う。
バスではちゃんと降りる駅を確認して、もし乗り過ごしても対処できるように、集合時間の1時間前に着くように予定を立てるなどした方が良かったと思う。
天才かなにか知らんけど、音楽とかドラムする以前に集合時間を守れないのは人間としてどうかと思う。
あと、天才か知らんけど、本番中の舞台であんな出たり入ったりして許されるんか、と疑問。
あと、天才か知らんけど、あんな好き勝手ドラムソロしてええんかと疑問。
でも、吹奏楽部でドラムやってた身としては、指揮者の制止も振り切ってあんぐらい好き勝手ドラム叩いてくれて痛快だった笑
厳しい指導者のもと、コンクールメンバー争いをしたことがある吹奏楽部経験者なら、この映画見て、青春を思い出せるんじゃないかと思う。
凄すぎる
趣味でクラシックギターかじってますが、狂気と言えるフレッチャーの指導、フレッチャーの厳しすぎる指導を受けながらも、事故で血まみれになりながらこのバンドのメインドラマーは自分しかいないと主張するニーマン。
音楽に対する情熱をぶつけ合う2人の熱いやりとりを手に汗にぎりながら見て、自分はもう音楽をやめよう…一瞬そんなふうに思った作品でした。
熱いわ〜
めちゃめちゃ熱かった。
ニューマンの自分の追い込む姿がなんとも言えないくらい熱かったな。
フレッチャーの前時代的な恐怖で追い込むやり方に最初は泣いたりするのに
段々戦う姿勢になっていき全てをドラムに捧げる姿が昨今の
ゆるふわな青春ストーリーと違い迫力満点だった。
いわゆるスポ根ものではない。
二人の音楽狂が音楽のためならどうなってもいいという
狂った世界を凡人が垣間見る世界を楽しむ映画。
正しいとか間違いとか関係ない。
極めることが全ての二人が見ていて楽しいって話だよね。
ちょっとこんなに熱い青春はないかもしれない。
最後のライブシーンの意地悪な仕掛けを逆手に取ってやり返すあたり
めちゃめちゃかっこよかったけど、やり返されたフレッチャーが
忌々しく思いつつもそのドラムの熱に取り込まれてしまう。
まさに音楽に取り憑かれた二人の男の物語だった。
天才にあこがれる凡人たち
主人公の、特に彼女との会話で明白になるが、
「僕はドラムに夢中で君を蔑ろにするはずだから、その前に別れよう」などと
もしも本物の天才なら言わない。
彼は自分が妄想する天才の道を、意図的に歩もうとしているだけだ。
これは教授も同じで、天才を発掘できるという妄想を根拠にパワハラを続けているだけで、
それが身を結んだことは一度もなく、人ひとりを死に追いやっている。
告発されればそのまま解雇され、奏者としては小さなバーでピアノを弾く男だ。
天才にあこがれてその狂気を模倣する。そんな勘違い男ふたりが、幸か不幸か噛み合う。
最後にふたりは高みへと上り詰め、圧巻のエンディングを迎えるが、
作中で彼らの音楽を客観的に評価してくる人間は存在しない。
満足げなふたりを見せ、聴衆が拍手したかどうかすらわからないまま映画は終わる。
スポ根映画かと思いきや
ラストのための映画
様々な感情が浮かんだ。
まず途中までは、この教育法はどうなのか、でも強さとか自分の意思とかが無いと厳しいだろうし。でもあまりにひどいよな。見てるだけでも気分が悪いし。難しいなぁ。って考えてた。
教授の思いを聞くと、それぞれの価値観として理解できなくもない。素晴らしいものを生むための苦しみも良いのか、いやでもエゴだろ、でも教育なんてエゴか・・・とか考えた。ここまででも、並の映画として楽しめた。
そしてラスト・・・このための映画だった。音楽を通した全力の殴り合い。ぶつかり合い。善悪でも良し悪しでもない。和解も勝利も、過去も未来もない。成功でも失敗でもない。この瞬間、二人だけのための。
こんな教育法でも、素晴らしい奏者を生み出したんだというのは、違うだろう。何の評価も無い。二人だけが、あの瞬間だけ通じた。それだけの事であり、それこそがこの映画や、音楽の本質だと感じた。
音楽という狂気
言わずと知れた名作を今更ながら鑑賞。
とにかく狂気!狂気!少し置いてまた狂気!
みたいな映画でした。
J・K・シモンズの鬼教師っぷりとマイルズ・テラーの陶酔っぷりが何ともいえないノージャンルな映画(まあ、音楽映画ではありますが)。
『ラ・ラ・ランド』の監督と聞いてなるほどと思った。
いわゆる、〈良い映画〉だけで終わらせないところが似てる。
彼女と別れようが、椅子が飛んでこようが、血が出ようが、交通事故で血まみれになろうが、音楽が大事、音楽が全て。
頭の中でずっと鳴り続けるドラムロール。
鑑賞側さえも鑑賞中はドラムのことで頭いっぱいになる。
ドラムのテンポはダメでも、この映画のテンポは非常に良くて、1秒たりとも目が離せない。
普通、音楽映画って楽しくなるはずですが、こんなキツい音楽映画があっていいのか?
いや、それこそが音楽の本質。
良くも悪くも、のめり込むと自分を見失い、人生が狂っていく麻薬みたいなものなんじゃないかと。
こんなの観たら、新しいことにチャレンジする気が失せますね笑
ただ、予告などのキャッチコピーが悪い。
「映画史が塗り替えられる」とかいうから、どんな事件が起きるのかと思ってしまった。
ある意味事件だけど、想像しているものとは違った。
普通に観ていたら、あのラストは違うものになっていたような気がして、ちょっと悔しいような…悲しいような…
シンバルの上の汗、ドラムの上の血、ムワッとした空気を感じる個室。
自分が追体験しているようで苦しくなるのに、あのクソ鬼教師をイマイチ嫌いになれないのは、J・K・シモンズが可愛いからか?それとも、それこそ我々の秘めたる狂気なのか?
夢を抱いたら思い出したい、夢を持つ人に教えてあげたい、激ヤバ映画でした。
うーん。。。
最後のシーンはプロの音楽家としてどうなの?って思いました。
お金を払ってこの日を楽しみにしてきたお客さんが目の前でいるのに、あれはひどい。
自分があの会場にいて、舞台上でドラマーがワタワタしてるのを指揮者は何も助けない、指揮者から罵声を浴びせるドラマーを見せられたら、この日までに楽しみにしてきた気持ちとチケット代を返して欲しいと思った。
鬱で死んでしまった彼の話を交通事故と亡くなった。生徒に嘘を言うシーンも、首を吊って亡くなったと弁護士から聞いたときは驚きだった。人の死をなんだと思ってるんだ、あの教授は!
現実と物語は違うけど、こんな人が現実にいたらいくら才能があって素晴らしい音楽を作れても人間として見れないなぁ〜
ヤベエ奴
呆れた自己満足大会
公開当時から賛否両論激しかったので
今まで見ないようにしてた、想像つくから…
無料配信になったので真偽を確かめたく
なにか唸らせるものがあるか?と期待したが
まぁなんともイヤな気持ちにしかならない
進めども進めども…見てるのがイヤになる
はっきり言って「胸糞悪い」
こんな教え方、音楽はこんな教え方はしちゃいけない
この主役のふたりも、この映画の監督も
バカな自己満足大会だ
この映画は内容も作りも
何も知らない人たちの作品だ…残念ながらスポ根よりも悪質
あたしは10代の頃から音楽、特にジャズにハマって人生を共にしてきたけど
音楽からは感動しか与えられなかったよ?
音楽は神からの贈り物だよ?
自己満足の表現は一番しちゃいけないこと
強者と弱者の立場から本物はどっちだと主張しあう話
フレッチャーの言動がパワハラで胸糞悪いみたいな感想は持って当然だと思うけれど、
だからといって映画が最低だという評価は何か違う気がする。
戦隊モノのヒーローの敵として出てくる組織に対して、ウザイ、キモイと投げかけるようなもので、
悪の組織もフレッチャーも物語の為に用意された必要悪なのである。
この映画はそんな必要悪のフレッチャーとひたすらに名声を求める学生のニーマンによる意地の張り合いを最初から最後まで描いている。
フレッチャーのやり方は汚い。
教えてやってるんだという強者の立場から、
ひたすら自分が気持ちよくなるような罵詈雑言を吐きかける。
まさに狂人でしかないのだが、ただ正しい、音楽的にはただただ正しい。
でもこれって自力で空を飛ぼうとしている人に、
お前はただジャンプしているだけだって罵詈雑言と共に怒鳴ってるだけで、
正しいのは正しいけれど、怒鳴っている側も決して空が飛べるわけはないので、
本当に卑怯なパワハラ行為でしかない。
ニーマンは音楽的にも人間的にも成長し、ついにフレッチャーを突き落とす所まで来たが、
結局正義の味方は汚い手は使わずに実力での最終決戦に持ち込まれる。
最後は絶対悪であるフレッチャーを正義の力に目覚めたニーマンが叩きのめして終わりというのが王道ではあると思うが、
何故か見つめ合って共闘してしまっていた。
パワハラどうこうでこの映画に怒るよりはただの長いギャグ映画だったと怒るべきだと思う。
俺は、あまり、、、
狂気と天才
この指導も悪いとは言い切れない・・・のか?
幸せになれない男たちのお話
予告編では密室なスタジオでひたすら才能惚れ込まれた鬼コーチにしごかれるストーリーと思っていたが実際本作品を見たら、違う話だった。アメリカで1番と豪語する一流の音楽学院の教授であるフィッチャーは、自分のバンドを厳しく指導しバンドメンバーたちはバンドに入っていることを誇らしく思っているがフィッチャーがスタジオに入ってくると恐怖と緊張でみんな下を向いて萎縮してしまう。椅子を投げたり詰ったりしてこのような先生のもとでジャズと言う自由な音楽を楽しむ事はとてもできない。主人公のアンドリューは父子家庭に育ち友達もなく一流のドラマにあり親戚や彼女や周りの人に認められることをあまりに強く望んでいてそのストイックさはフィッチャーに負けず劣らず異常なレベル。
2人を見ているだけで気が滅入るしこんなバンドが素晴らしい演奏をしてコンテスト優勝できると言う所からして音楽アカデミズムの権威主義しか感じない。音を楽しむ音楽がそこにはなくかつて指導した生徒が精神を病み自殺したときのフィッチャーの涙もバンドメンバーへの話も保身のためのものだったし、一方のアンドリューもドラムを極めたい先生に認められたい一流になりたいと言う強い気持ちが純粋に音楽を愛する者と言うよりも周囲を見返したい、周囲に認められたいと言う意固地なものになっていく。サンクスギビングか何かで親戚一同が集まるテーブルを囲んでの会話どの国にも見られる自分の家庭自分の子供自慢、世間の物差しで見栄の張り合い。アンドリューと父親との関係は信頼と愛に溢れているが一度親子関係の外に出るとアンドリューは孤高を楽しむようなことを嘯きつつし満たされない承認欲求にや悩まされ彼女や周りの人にミーンな態度となっていく。社会的な賞賛や地位や承認でしか満たされない不幸な、幸せになれなそうな男たちが奏でる音楽には聴衆がほとんど出てこない。最後のアンドリウの圧巻の独断ドラムソロとジャズの精神に基づくかと思われたバンドへの合図呼びかけでのキャラバンの演奏も観客の拍手喝采からエンドロールとはならず。
師弟のかけひき、そこでごく稀に瞬間に生まれる音楽を通した理解疎通、ジャスクラブでの師のリラックスした演奏など救いは瞬間に訪れ魔法にかかったようにドラムに引き寄せられ血まみれになるまで練習、、、アメリカ的な家族の幸せごっこ見栄の張り合い、信田元教え子の件でヒアリングに来る弁護士弁護士に協力しようとする父親はいわゆるアカハラ問題を明るみにしようとしていてこれもアメリカや各国での現代的な問題提起。ジャズを聴いているとは思えない重苦しいシーンの連続だがCharlie Parkerの話をするフィッチャーやその話を自分流に理解し親戚との晩餐で披露するアンドリュー、などのちょっとした良い場面あり、また、入れ代わり立ち代わり3名のドラマーがらドラムセットにすわり罵倒を浴びがながらドラマーの座を得ようと何時間もバトルさせられるシーンなど素晴らしい場面あり、全く共感理解できないが凡庸な人間には理解できない異常な世界と、人間界の醜悪さを凝縮したような話を緊迫感あふれる映像で堪能した。
全931件中、201~220件目を表示