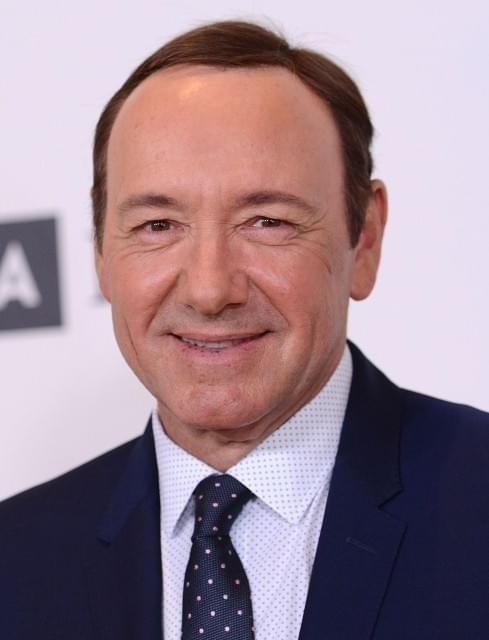ウォーム・ボディーズ : 映画評論・批評
2013年9月17日更新
2013年9月21日よりシネクイントほかにてロードショー
ジョン・ヒューズの青春映画を思わせる、愛すべきゾンビ映画

前作「50/50 フィフティ・フィフティ」で、生存率50%の青年の視点から生の営みをみつめたジョナサン・レビン監督。今回は、生ける死者(ゾンビ)になった青年の視点から恋を描いた。しかも一人称で!
ゾンビ映画に社会風刺を求める人は、この作品に物足りなさを感じるかもしれない。それもそのはず、この映画の本質は青春ラブストーリーだから。もっと言えば、誰からも恋愛対象とみなされず、自分でも恋愛不適格者だと思っている男が、いかにしてキュートなお嬢様のハートを射止めるかという、恋愛のハウトゥものとして作られているからだ。
まずはアプローチ。この段階で重要なのは、相手に関する情報収集だが、主人公のゾンビR(ニコラス・ホルト)は、お嬢様の彼氏の脳ミソを食べて記憶を追体験するという、えげつない方法でこれをクリア。さらに、懐メロを通じてコミュニケーションをとることに成功する。が、ときには「オレはノロマで猫背なゾンビだから」と落ち込むことも。
そんなRの心情をモノローグで語らせ、恋にオクテな若者の共感を誘う作劇は、1980年代のジョン・ヒューズ脚本の青春映画を思わせる。そういえば、劇中には「フェリスはある朝突然に」のオマージュらしきオープンカーのドライブ場面が登場するし、シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」をゆるく下敷きにしている点は「プリティ・イン・ピンク/恋人たちの街角」と共通している。何より、「胸キュン」の感覚が呼び覚まされるところにヒューズ映画の遺伝子を感じる。
「人間を人間たらしめているものは愛である」というテーマのつきぬけた楽観主義には少々着いていけない部分もあるが、それも笑って許せてしまう愛すべき映画だ。
(矢崎由紀子)