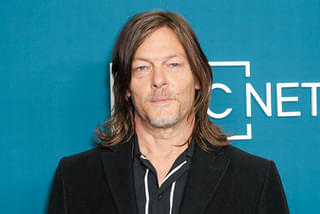ブラック・スワン : 映画評論・批評
2011年5月10日更新
2011年5月11日よりTOHOシネマズ日劇ほかにてロードショー
激痛と覚醒が観客に感染する。豪華な悪夢を思わせる映画だ

話の枠はバレエだ。ニナ(ナタリー・ポートマン)というダンサーが苦悩する映画だ。ただし彼女は、芸術を取るか人生を取るかという古典的命題をめぐって苦しむのではない。「赤い靴」とはそこがちがう。
私はむしろ、別の映画を連想した。「イヴの総て」と「何がジェーンに起ったか?」の2本。わけても近いのは後者だ。
「ジェーン」はサイコパスの映画だった。動けない姉と狂った妹の百年戦争。光と影の落差が激しい画面で、メロドラマとスリラーとゴシック・ホラーが入り混じる。おや、この構造は「ブラック・スワン」と似ていないか。
「ブラック・スワン」に姉妹は出てこない。が、ニナを取り巻く女たちは、彼女の天敵であるとともに彼女の分身だ。競争相手のリリー、過保護で過干渉の母親エリカ、もと花形のベス。そしてだれよりも、ニナはニナ自身に苦しめられる。白鳥は踊れても黒鳥を踊れないニナ。踊るためには、自身のデーモンを解き放ってやる必要がある。だが、そんなことが簡単にできるのか。そもそも、彼女にはデーモンが備わっているのだろうか。
監督のダーレン・アロノフスキーは、ここで一気に負荷をかける。オーバーロード、オーバードライブ、オーバー・ザ・トップ。似たような言葉が私の脳裡で一斉に明滅する。同時に映画のテンションも急激に高まる。現実と妄想の境界線は溶け合い、映画は強力な薬物のように観客の脳髄に侵入する。
ここが「ブラック・スワン」の勇敢なところだ。いや、勇敢というより無謀に近い大胆さか。「赤い靴」が追求した二元論はすでに吹き飛ばされている。ニナは、芸術と人生を串刺しにして……いや自分自身をも突き貫いて、世界の中心に迫っていく。その激痛、その覚醒は観客にも感染する。これは、映画が豪華な悪夢になりうることを証明した作品だ。
(芝山幹郎)