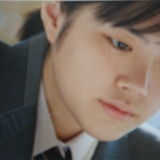マイ・バック・ページのレビュー・感想・評価
全34件中、1~20件目を表示
映画だからこそ成し得る奇跡
この本を、どうやって映画にするんだろう?
…大好きかつ信頼する監督・脚本家・プロデューサーによる、尊敬する文筆家の著作が映画化されると聞き、原作本をさっそく読んだ直後の感想だ。全体に流れる空気は同じでも、駆け出し記者であった著者の回想録(元々は雑誌連載)だけに内容多岐に及び、映画としてまとめ上げようとすれば、こぼれ落ちるものが多すぎる気がした。けれども、彼らならば、きっと。そんな気持ちで、映画公開に期待を膨らませていた。…そして、その期待は裏切られることなく、それ以上のものを見せてくれた。
なんといっても秀逸なのは、映画にふさわしい(映画にしかできない)幕切れだ。特ダネを追っていたはずの主人公・沢田は、抜き差しならない挫折を味わい、思想・政治活動であったはずの殺人は犯罪事件として泥沼に陥った。…それから数年。就職浪人するほど憧れていたジャーナリズムから沢田は遠ざかり、かつて否定した「泣く男」が登場する映画を生業とするようになっている。
そんな彼が果たした、思いがけない再会。かつて記者であることを隠して生活を共にした男は、今も彼を疑うことなく懐に招き入れる。偽り、欺く傍観者であった彼は、いつしか偽られ、欺かれていたのだが…。
ジャック・ニコルソンばりに泣きじゃくる主人公を、画面一杯の光が包み込むかのような唯一かつ一瞬のホワイトスクリーンは、映画だけがなし得る奇跡だ。暗転による場面展開と黒地に白い文字でのクレジットに統一された構成が醸し出す寡黙さと、煙草の煙で淀んだ空気(今では考えられないほど、皆揃って煙草を吸いまくる。とにかくふかさずにいられない、そんな脅迫的なものさえ感じる。)が、その瞬間、晴れた。
とめどなく溢れ、ただただ流れる彼の涙は、美しくもせつなくもなく、(少なくとも私には)センチメンタルさも感じられなかった。それでいて、沢田が全身で泣く姿はとにかく忘れ難く、映画ならではの感情を観る者に掻き立てる。
映画、原作。それぞれを存分に味わってほしい、深みある作品だ。
白いブリーフ履いてみるか
このテのヤツってエログロがデフォルトだと思い込んでいたのでちょっと反省。そのあと観た事にも反省したけどな。
まず内容。普段オレたちが経験していることを盛り上がりも何も無く映画にしてんじゃねえっての。経験豊かな諸先輩にやめとけ、って言ってくれてんのに、てめえがヤレるヤツだと勘違いして、のっかっちゃったら、やっぱ先輩の言うとおりでした、えーん。乗っかる対象が小物なのもあるある。
映画なんだからさ、小物っぷりをもっと面白おかしくみせてくれちゃっていいじゃん。冒頭で小物っぷりをちらっと見せてくれたんだから、やっぱ最後は彼女の所在をばらしたりしたことや取調室だけじゃモノ足らず、裁判はテロップでなく、描いてほしかったな。そこしか盛り上がるとこねえだろが。
キャスト。松山さんはその小物ぷりがイイ。だけど想定内の配役なので、妻夫木さんと逆にしたほうが面白えんだけどな。だけど小物ぶりは松山さんがやるほうがいいかもな。妻夫木さんがやると逆に小物じゃなくなりそうなんで。
あとな、みんな白いブリーフ世代じゃねえんだからさ、監督ぐらいはその世代のほうがよかったんじゃねえのか?
70年代初頭 全共闘時代のジャーナリストのお話です。 調べてみたら...
70年代初頭 全共闘時代のジャーナリストのお話です。
調べてみたら映画評論家の川本三郎さんという人の朝日ジャーナル時代の話らしい。
今では見ることがなくなったくわえタバコで仕事をする人、とにかく若者も何かっていうと、すぐタバコに火をつける。
妻夫木君と松ケン。
松ケンが好きだけど、この映画の妻夫木君はいいデス。オーラスの泣くシーンの長回しにはやられます。
そこからのエンドロール、奥田民生の主題歌も良かった。
なし
最近本作の存在を知り、DVDを借りようかと思案していた矢先、BS日テレでテレビ公開をされました。
原作者の自伝的小説をもとに、あの高度経済成長の爛熟期と同時に、
世界的な大学紛争の時代がどのように表現されているか興味がありました。
画面は室内や室外でも夜間シーンが多く、全体的に暗い色彩に彩られています。
映像もわざと16ミリで撮影したそうで、そのためかざらつき感があり、
私が子供時代に感じた、「あの時代」の
ザラザラして落ち着かなかった感覚を上手に表現しています。
ラスト近く、時系列の説明が無く、予備知識なしで観た人は混乱するのでは思います。
ラストシーンの「泣き」については賛否両論あるようですが、
私としては、「思い出して泣く」若き日々があったというのは羨ましいと思います。
タイトルにも使われているボブ・ディランの曲は、マスターが持っている
ベストアルバムに入っていたのでしょうか、聞いたことがあります。
長いし分かりにくいかな
................................................................................................
学生運動が盛んだった頃の新聞記者の妻夫木が主人公。
妻夫木自身も学生時代に運動には参加したが、中途半端だった。
いつも安全な位置にいたがる弱腰な性格だった。
そこで革命家を名乗る松山に合い、本物と信じて取材する。
松山は実は口先だけでポリシーなんてないハンパ者だったが、
彼らの行動で自衛官が死んで一大事になる。
妻夫木は社に記事掲載を要望するが、さすがに犯罪だと却下され、
警察に通報されて松山らは逮捕される。
妻夫木も自分のキャリアを棒に振った感じになる。
................................................................................................
何が何だかよう分からんかった。
長いのもあって、早く終わらんかなってずっと思ってた。
内容が分かればおもろいのかも知れんけど。
「あまりにも重すぎた」ということか。
1970年頃の日本と言えば、高度成長の絶頂期といったところでしょうか。
空前絶後の経済成長を背景に、日本中が「何でもできる」と過熱していた時期とも言えます。
そんな頃ですから、いわゆるセクトに加入していた大学生たちも、理論や暴力(武力)で階級闘争を勝ち抜き、自分たちの力で権力を倒して社会変革する(革命を起こす)ことも可能と考えていた時代と言えると思います。
そして、本作の梅山(松山ケンイチ)もご多分に漏れなかったと言うことでしょう。
他方の沢田(妻夫木聡)にしても、本紙編集部には入れなかったものの(否、本紙編集部どころか(社会問題に鋭く切り込んでいるという設定の)ジャーナル編集部にも入ることができず、不本意な週刊誌編集部に配属となってしまっただけに、それらの編集部員を見返すべく)、いっぱしのジャーナリスト気取りで、ますます意気軒昂だったのだろうと思います。
そこへ、この結末ですから、梅山も沢田も、自分の中では咀嚼し切れないほどの挫折感を味わったことは、想像に難くないと思います。
(最後の沢田の涙の理由も、そういう意味に、評論子は理解しました。)
結局、梅山も沢田も、自分の余白(バック・ページ)に押し込んでしまうには、その挫折が余りにも重すぎたということだったのではないでしょうか。
そう思いました。評論子は。
佳作であったと思います。
なんだろな…人間って愚かだ…
岸井ゆきの映画デビュー作
原作未読
約10年ぶり2回目の鑑賞
2011年の作品
2時間21分
ノンフィクションをフィクションとして映画化
時代は1970年頃
学生運動
活動家とジャーナリストの交流を描いていた作品
あの時代の雰囲気を味わえる
あの時代の音楽にあの時代の映画
あの時代の理屈
当時の若者の挫折
団塊の世代の思い出
監督は『リンダ リンダ リンダ』『天然コケッコー』『苦役列車』『もらとりあむタマ子』『味園ユニバース』『ぼくのおじさん』『ハード・コア』の山下敦弘
ベースが学生運動のドキュメンタリー
エンターテイメント性はない
娯楽映画ではない
プロパガンダ映画でもない
三島由紀夫のドキュメンタリー映画に出てくる学生に比べれば梅山の主張はそれほど難解ではないが本人真面目なのに頓珍漢で胡散臭くアホらしい
問い詰められ言葉に詰まれば「おまえ敵だろ」と言ったりする
共感はできないが凡人の域を脱していないならそれが当たり前だ
共感できないと楽しめないならこの映画はあまりにも冗長
妻夫木や松山のファンじゃないとキツい
『リンダリンダリンダ』『俺たちに明日はないッス』『色即ぜねれいしょん』『ふがいない僕は空を見た』『もらとりあむタマ子』『聖の青春』『愚行録』の向井康介
東都新聞の週刊誌記者・沢田雅巳に妻夫木聡
赤邦軍リーダー梅山こと片桐優に松山ケンイチ
週刊東都表紙モデル倉田眞子に忽那汐里
赤邦軍隊員・安宅重子に石橋杏奈
赤邦軍隊員・赤井七恵に韓英恵
赤邦軍隊員・柴山洋に中村蒼
東都ジャーナルのデスク飯島にあがた森魚
週刊東都のデスク徳山健三に山崎一
自衛官・清原に山本剛史
運動家・佐伯仁に山本浩司
活動家に岸井ゆきの
週刊東都記者・中平武弘に古舘寛治
週刊東都記者津川に中野英樹
京大全共闘議長・前園勇に山内圭哉
唐谷義朗東大全共闘議長・唐谷義朗に長塚圭史
兎売りタモツに松浦祐也
コンドームメーカーに面接に行く予定のキリストに青木崇高
東都新聞記者に近藤公園
刑事・高峰に康すおん
キネマ旬報編集者に早織
東都新聞社長山口に並樹史朗
東都ジャーナル編集長小林に菅原大吉
週刊東都編集長島木武夫に中村育二
東都新聞 社会部部長白石に三浦友和
岸井ゆきのはかなりわかりにくい
セリフはない
ほんの一瞬だ
おそらく全共闘の白いヘルメットを被り妻夫木聡の背後から走り抜けていく女が岸井ゆきのだろう
これじゃエキストラじゃないか
心なしか不貞腐れたような表情でいやいや走らされている感が否めない
悪い意味でプリプリしていたように見える
どんなコンセプトで臨んだのかわからないが芝居をしているようには見えなかった
彼女からすればあまりにも不本意だったのかもしれない
唐谷が刑事たちに逮捕されそうになっている様子を見つめ恐れおののく中核派のヘルメットを被った女学生を演じた二人組の方がよっぽど芝居をしていた
2人の役者名は知らないけど
この作品は岸井ゆきののマイ・バック・ページといえる
熱い部分と冷めた部分
“赤邦軍”という新左翼のリーダーである梅山=片桐優(松山)は全共闘に乗り遅れた感もあり、憧れの革命家たちをも踏みにじろうとしていたのか?焦る気持ちが自衛隊から銃を強奪しようとする計画を生みだし、マスコミを利用して自らのセクトを確立したかっただけにすぎないのだろう。彼の嘘や虚言に騙されながらも親近感を抱いた沢田(妻夫木)はスクープを得ようと躍起になるところで共通点があった。元は彼も左翼運動に加わっていたのに、どうしても暴力の中に入り込めなかったのも原因か?
69年から71年にかけての物語。熱く語っている部分と冷めた部分が共存し、結局は空しさしか残らない。松ケンがCCRの「雨を見たかい」を弾き語りするシーンも印象的だし、東都新聞のイメージガールとして選ばれた忽那汐里が男の涙について語っていたが、それを否定していた妻夫木が最後に涙を流すシーンとがいい伏線になっていた。『ファイブ・イージー・ピーセス』のジャック・ニコルソンの男泣きだなんて、ぜんぜん記憶に残っていない。
山下敦弘作品には必ず出演している山本浩司も登場するが、彼のエピソードなんかもイマイチ理解できなかったりする。やはり敦弘向きじゃない作品だったんだな・・・
屈折した正義感
70年安保の迸る情熱は薄れつつある時期。熱く新しい世界を求めた純粋さは、そこに参加できなかった男たちに負い目を与えたのか?
主人公は距離を置いていた負い目から、活動家もどきにのめりこんでいく。活動家は乗り遅れて追いつこうとするが、そこには培った理論や思想はなく、自分の言葉に酔い次第に活動家になっていく。
当時の学生運動、幼い頃のかすかな記憶はお茶の水の学生・デモ行進・ヘルメット、喧騒と情熱。その後の連合赤軍への怒りと恐怖。
これが入り交じったのもあり、思いのほか適当な活動家の行動に共感できず、むしろ怒りを覚えどうも好きになれなかった。
ノンフィクションを観る感覚でないとキツい
学生運動が盛んだった時代を舞台に、雑誌記者と活動家を描く物語。
ガロとかCCRとかアポロ11号の月面着陸とか、時代を感じさせる演出はよかった。でも、本筋は活動家と記者のお話。武力行使を企む活動家側と、それを取材する記者という形で物語が展開していく。同じ時代を舞台にした映画をいくつか観ていたので、当時の活動家の言っていることが無謀なのは知っている。でも、松山ケンイチ演じる梅山の言っていることがうわっ滑りしていることにガッカリした。何がしたいんだ?との問いに、さては敵だな?と議論を避ける手法。それだけで梅山に共感はできなくなる。それが当時の現実なんだろうけど。
一方、梅山を取材する側の沢田にも共感できない。モデルの女の子と映画館でデートするシーンも唐突だし、後に発展することもない。最終的には自分も逮捕されて有罪判決が下されましたという結論。でしょうねという感想しか抱けない。
なんだこの映画はと思ったが、原作があって、しかも自伝的な書籍だったとわかって納得。ノンフィクションのような気持ちで観るならありかもしれない。いや、それでも話の盛り上がりがなさすぎだろう。
誰にも共感はできない。 うさんくらい学生運動家・それを信じて取材を...
彼は何を成し得たのか
1970年代大学抗争・全共闘最盛期、新聞社の雑誌記者・沢田は、思想犯・梅山と出会う。
上司は梅山の浅い資質を見抜き、近づくなと忠告する。しかし、安田講堂の陥落を安全地帯で目撃し虚しさを抱えていた沢田は、梅山に惹かれ協力しつつ取材を重ねていった。
だが梅山の言動には矛盾があり、組織は実態のないものだった。マスコミを利用してのしあがろうとしていた梅山は、遂に行動に出る。
その計画は自衛隊駐屯地で武器を奪い、都心でテロを行うというものだった。
しかし、仲間が計画実行中に自衛官を殺めてしまう。武器も奪えず、別組織のリーダーや仲間に責任をなすりつける梅山。
やがて、社会部の告発により梅山は逮捕される。沢田は梅山の真実の姿を見て信じた己を悔やみ、新聞社を退社する。
数年後、映画評論家としてペンを持つ沢田。ふらりと立ち寄った居酒屋で、昔取材と称してつるんでいた仲間と出会う。そして一人カウンターで涙を流すのだった…。
ブッキーの演技はもう少し頑張りましょう。マツケンは良くできました。ブッキーは顔が綺麗なので役の職業によっては浮いて見える時がある。ミスキャスト多数。
オウム事件を思い出す
豊かで平和な社会では、このような独りよがりな若者たちが暴発する事件が、時折思い出したように起きるものである。この映画が題材にした事件から20年ほど経ったときに起きたのが「オウム真理教」による一連のテロ事件であった。映画の中の事件が川本三郎の実体験に基づくものだということを鑑賞後に知るまでは、作品のモチーフになったのはオウムの事件ではないかという確信に近い思いを抱いていた。
しかしこれは安保闘争が終わりに近づく頃の、事実を基にした新米記者の物語。
山下敦弘の作品を何本か観てきたが、この作品はその中でも重く暗いトーンとなっている。妻夫木聡や松山ケンイチといった当代の売れっ子俳優をメインに据えているが、このキャスティングを目当てに劇場へ足を運んだ観客の期待は裏切られたことだろう。
この裏切りは初めから意図されたものではないだろうか。
映画では学生運動を、やっている本人たちの「道楽」として描かれている。運動資金のために自分たちの計画のあることないことを自らマスコミにリークし、実際にやっていることは無責任なガキのやんちゃに過ぎないという突き放した眼差しでとらえている。特に、根拠のない自信満々の言動からうさん臭さを放出している松山が本当に不愉快な存在。このインチキ野郎の学生運動家が、妻夫木やほかの登場人物を裏切り、観客の期待を裏切っていくのである。
主人公が一人で映画館に入り観ているのは川島雄三の「洲崎パラダイス 赤信号」である。勝鬨橋の上で、三橋達也演ずるダメ男が新珠三千代に「こんな俺が嫌ならどこかへ行ってしまえ。」と開き直っている。おそらくこれまで何度も彼に失望させられてきた新珠は、今回もまた同じ結果になることを分かっていながら三橋とは離れられないのである。
いっぱしの革命家を目指していると大口をたたく松山に対して、うさん臭さを感じながらも、信じてみたいと思う妻夫木や、セクトの他のメンバーたち。ずさんな計画が結局は破たんすることが半ば分かっていながら、誰も彼を止めることができないこちら側の構図と、「洲崎」側の構図が重なる。
期待はずれ
今の若者たちはこの若者たちを何と見るか
「天然コケッコー」「苦役列車」の山下敦弘監督が、妻夫木聡と松山ケンイチの顔合わせで送る社会派青春ドラマ。
1960年代後半〜1970年代初頭の鮮烈な時代と若者像を活写する。
若手演技派と呼ばれる二人がその本領を発揮。
妻夫木が若きジャーナリストに、松山が学生活動家にそれぞれ扮し、理想と革命に葛藤し、不思議と共感し合う姿を体現。
初々しい忽那汐里も印象に残る。
アポロ11号月面着陸、ベトナム戦争、学生運動…。
人によって懐かしかったり、熱い青春時代を思い出したりするだろう。
この頃影も形も無かった者にとっては把握が難しいが。(ちなみに僕も)
しかし、この当時の若者像と今の若者像に、深く思い比べてしまった。
かつて、学生運動というのがあった。
若者たちが声高らかに社会への不満を訴え、社会を変えようとした。
時としてその運動は異常な熱を呼び、暴徒と化して社会問題になる事もあった。声を武器に変え、暴力で訴えた過激派も存在した。
過激派は論外だが、学生運動自体は、人それぞれ判断が分かれ難しいが、若者たちの社会へ対する疑問や熱心な考え、変えようとする行動力があった事は否定出来ない。
それに比べ、今の若者たちはどうか。
社会に対して関心も薄く、声を上げるとすればインターネット上に悪口を書き込むだけ。
何とも情けない。
別に当時の若者たち見習え!と言う訳ではないが、せめて熱い魂だけでも感じ取って欲しい。
お前に足りないのは、そういう覚悟だよ。
映画「マイ・バック・ページ」(山下敦弘監督)から。
1960年代後半の学生運動を舞台に、物語は進んでいく。
その混乱の中に入って、真っ正面から向き合うタイプの人間と
ちょっと距離を置いて、動向を眺めるタイプ。
そんな人間の2つのタイプを、当時の世界の出来事で表現して、
こんな会話で、妻夫木聡さん扮する、若手ジャーナリスト・沢田に
仕事に対する姿勢をアドバイスする先輩が眩しかった。
「月かベトナム、どっちかに行けるといったら、
俺は迷わずベトナムに行くな。
お前に足りないのは、そういう覚悟だよ。」と。
世界中の人々が注目し、誰もが憧れる宇宙の「月」よりも、
生きるか死ぬかもわからない「ベトナム戦争最前線」を選べ、
そんな感じなんだろうか。
取材とは、それだけ覚悟がいるんだ、と言い聞かせるように。
会社の上司も「俺たちは、社会の目なんだよ。大事なのは、具体。
そこで何が起こっているかが重要なんだよ」と叱咤する。
そういう覚悟を決めて立ち向かう経験をしないから、
お前が一番伝えたいのは何なのか、俺たちにはわからない、と。
実は、この選択はジャーナリストの話だけではない。
どんな職業でも通じる仕事に対する姿勢であるし、
「現場第一主義」を忘れがちな、私たち管理職には特に、
意識しておかなければならないことだな、とメモをした台詞。
「覚悟」という単語、胸に響くなぁ。
三丁目の夕日のそのあとの時代
松山ケンイチ演じる似非革命家
本当に頭にくる糞野郎をしっかり演じていてどんどん嫌悪感が、大きくなっていました。
妻夫木聡演じるジャーナリスト沢田
スクープの為に結果的に犯罪の片棒を担いでしまうことになりますが、マスコミの汚さと心が弱い沢田をしっかりと演じています。さすが悪人!
三丁目の夕日 のころに生まれたおじさんは この70年代を実体験しているはずですが、学生闘争のことはほとんど覚えていません。
トイレットペーパーが無くなったのは覚えているんですけど。
浅間山荘はテレビでやっていたのを覚えているな~
そういえば、中学の頃、国語の若い先生だったと思いますが、大学時代はちょうどこんな時期でまったく大学に行かないで卒業したって授業中に話をしたことがあり、羨ましかったのを覚えています。
そんな時代がありました。
ということを知ることができる映画です。
時代感はよい…俳優陣もよい
作品の背景になっている時代は、私の生まれたころの時代なので、当時の時代感は記憶にない。だが、とてもその時代の雰囲気が伝わってくる作品であった。服装も、街の様子も、けだるい甘えきった学生の感じも…。あざとくなくてよい。少なくとも『ノルウェイの森』、(あまりにもあざとすぎる)『コクリコ坂から』などよりはよい。
妻夫木聡、松山ケンイチの演技がよかった。
○妻夫木演じる沢田の、視野の狭い感じの演技はよし。のめりこみはしないのだが、いつの間にか泥沼にはまっている感じ。ただ、梅山率いる赤邦軍のことを何故信じたのかなど、内面をもう少し描いてほしかった。
○松山演じる梅山の、自意識過剰な、体制内で甘えきったうそつき新左翼な演技はよい。松山がよいというより、脚本と演出がよいのだろうけど。
○忽那汐里演じる倉田はとてもかわいく、美しかったが、70年代初期のモデル・女優というイメージじゃないな。そこだけ時代感がないかな。
全34件中、1~20件目を表示