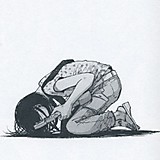インビクタス 負けざる者たちのレビュー・感想・評価
全139件中、61~80件目を表示
これが実話なんて泣くしかない。
マンデラ大統領の赦し。監獄での30年。大統領としての寛容さ。ラグビーの一体感。何度泣いたことか。今年一番泣いた映画なんじゃないかな。文句なし星5つ。クリントイーストウッド。モーガンフリーマン。マット・デイモン。いい仕事してます。スポーツは人種の壁を越える。歌は人種の壁を越える。いろんなところで、人種の壁を感じる機会が、残念ながら、今もある。日本には国籍にうるさい人たちもいるし。でも大切なのは許し。許しですよ。マンデラさん。過去の感情に支配されるのではなく、自分の魂の支配者。コントロールできるんです。いい映画でした。
タイトルなし(ネタバレ)
ウッドくんの映画にはやっぱりやられました。
黒人のマンデラが南アフリカの大統領になった直後~ラグビーのワールドカップ優勝までの話。
白人の象徴のチームだから黒人からしたら、憎むべきチームのはず。それを排除するのではなく、それを認めてもらおうとする態度。白人からも黒人からも認められる。
30年も刑務所にいたのに、それを赦すココロ。それは誰にでもできることではない。そのココロが、南アのラグビーチームを強くしていったと言っても過言ではない。
マットデイモンが窓に向って30年間の牢獄人生を思うシーン。
「動」が多い中で、「静」だけど力強さがあふれていて、それが試合につながっていく。
ただ練習して強くなっていくのが真の強さではない。チームとして、いや国の代表として1つにまとまっていく。肌の色とかが問題ではなく、お互いラグビーを愛する仲間としてまとまっていく。それこそチームが強くなる秘訣なのだろう。
試合終了間近で涙腺刺激されました。
凄くよかった!
語り継ぐべき話
マンデラとラグビー
ラグビー映画ではなかったが素晴らしい作品だった。
人種を越えて
人種を越えて国が1つになり、世界に誇れる国へ…。
スポーツを政治的に利用した例は過去にも多い。
最も痛ましい例は、1980年と1984年のモスクワとロス五輪だろう。
但し五輪に関して言えば、ヒットラーを始めとして、国威発揚・経済発展を筆頭に民族統一等。五輪の理念であるアマチュアリズムとはかけ離れた。開催国が世界に対して示す《思惑》が、先ず第一に目立つ大会として進化を遂げて来た。
1990年代に、《アパルトヘイト》により、国際的に孤立した南アフリカ共和国からは、毎日の様に国中で暴動が起きていたのを報道していた。
冒頭にて、代表選手がラグビーをしているが、道路を隔てて黒人の少年達はサッカーに興じている。その間を行くネルソン・マンデラ。
「この屈辱を忘れるな!」と語る男。
しばしばスポーツに於いては“奇跡”が起きる。
ちょっと場違いな例えかも知れないが、以前『元気が出るテレビ』で放送された、アイスホッケーのエピソードは良い例かも知れない。
一度も勝った事が無いライバル高校(相手はライバルと思っていない)に勝つ事を目標に番組で追い掛け、その結果奇跡的な勝利を収める。
まさにスポーツは“筋書きの無いドラマ”だと言う事を、実感した企画だった。
敢えて理由を考えれば、その場の異様な雰囲気に、相手が飲まれ込まれた結果と言える様な出来事だった。
テレビ放送によって人気となり、物凄い応援で個人のスキル以上の力が発揮されたとも言える。
その場の応援によるエネルギーのパワーとゆう奴は馬鹿に出来ない。
そんな例えとして、YOU TUBEでじっくりと見られるが、数年前の近鉄バッファローズが優勝した試合に於ける、近鉄北川のサヨナラ満塁ホームランが良い例だ。
始めは観客も諦めムードだったのだが、徐々にボルテージが上がり、最後の盛り上がりの物凄さたるや凄まじい。
おそらく、1995年のラグビーワールドカップに於ける決勝戦での盛り上がりも、この様な観客のパワーが後押しをしたからだと思う。
ネルソン・マンデラは、ラグビーとゆうスポーツを通して、人種を超え民族が1つになる事を願った。
決して“政治的”にスポーツを利用した訳では無い。
27年間投獄されながらも、人を赦す気持ち。
主将役のマット・ディモンが、マンデラが実際に投獄されていた房を自分の目で見て、その想いの凄さを実感する場面こそが、この映画に於ける一番重要な場面と言える。
その想いが、試合後に交わす2人の会話に表れる。
我々が、世界に誇れる民族で有る事を宣言する如くに…。
今、新国歌を白人と黒人が一緒に歌い、試合展開には一喜一憂する。
ラストシーンはファーストシーンとは違い、みんながボールを手を使いパスする。
代表選手の活躍が国民全員の意識を変え、やがては人種の壁も取り除かれるであろうとゆう希望に溢れている。
ところで、監督クリント・イーストウッドは、今回いつにも増して。《ちょちょい》と言った感じでこの映画を作ってしまっている。一体どうなっているんだ…。映画ってそんなに簡単に製作出来てしまうモノなのか…。
この作品の後で、既に2本作ってるって情報も有るし※1…。そのフットワークたるや、我々がどんなにタックルしたところで、いともたやすくスルリと交わされてしまう。
全く恐ろしい爺様だ!
※1 ご存知の様に『チェンジリング』と『グラントリノ』の超ド級傑作。
その後も製作意欲に全く衰えを見せない。
(2010年2月16日新宿ピカデリー/スクリーン6)
映画らしい映画
心が洗われる
良い指導者・リーダーの、あるべき姿とは。ネルソン・マンデラの、人を赦す心の広さ、自分の信念をブレずに周りに示せる強さに、心を打たれる。
そして、そんな彼に感化され、変わっていく人々が描かれる。
黒人と白人のボディガード達の壁がなくなっていく様子や、ピナールがチームを良くまとめていく様子に感動した。
観終わったとき、心が洗われる様な気分になる映画だ。
いまひとつ
南アフリカの歴史とか社会を知っていれば、この映画はもっとおもしろかっただろうと思いました。ネルソン・マンデラ氏のご冥福をお祈りしたいです。
いい映画だった。勉強になるし、面白い。内容は通常のイーストウッド作品と違い、明るくて希望に満ちていて、スクールウォーズの国家版といったところです。
特にモーガン・フリーマンの演技がよかった。実際のマンデラ氏はどうだったのか知らないけど、どう見ても迫力満点の大人物で、もしオバマとモーガン・フリーマンどっちを大統領にしたいか?と聞かれたら、モーガン・フリーマンに一票入れたくなりました。
でも、マンデラ氏が不屈の精神で人種差別と闘ってきたところが抜けていて、大統領になるところから始まっているのが難かな?
普通の日本人はネルソン・マンデラ氏という名前しか知らないし、南アフリカのことも知らない。
ラグビーが強いのも知らないし、アパルトヘイトや人種差別がどういうものかも知らない。
知らないから、いきなり大統領になるところから始めて、ワールドカップといかれると、負けざるものではなくて、勝ちまくっている者にしか見えない。
イーストウッド監督の見事な演出で、昔のひどい時代の雰囲気は伝わってくるんだけど、やはり苦しい。
アメリカ人は同じようなことやってきたから、わかるのかもしれないけど、日本人には説明不足です。
南アフリカの歴史とか社会を事前に知っていれば、この映画はもっと面白かっただろうと思いました。
日本にもネルソン・マンデラ氏みたいな指導者がほしいです。
関係ないけど、オールブラックスの強さを強調するために、日本代表が17対145で負けた(事実)と言っていたけど、これが気になった。
ラグビーはよく知らないけど、スクールウォーズでは0対108で負けた時、先生が泣きながら生徒を殴っていたような気がするんだけど、それくらいの情けないスコアということかな・・・?
日本人としては、日本にもいろんな意味で頑張ってほしいです。
全139件中、61~80件目を表示