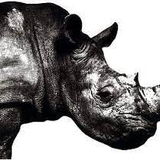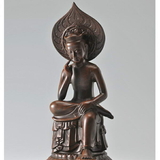チェンジリングのレビュー・感想・評価
全132件中、1~20件目を表示
チェンジリング
今年2009年には満79歳になるクリント・イーストウッドというこの映画作家の凄まじいまでのエネルギーは一体何処から来ているのだろうか?
一向にボルテージが下がる様子がなく、テンションが緩んだユッタリとした老境を感じさせるような作品にもなっておらず、 或いは小粒なスケールの佳作が増えてきたといったような傾向も今のところ皆無である。
映画史上において巨匠、名匠と呼ばれる偉大な映画監督であっても決して避けて通ることが出来なかった加齢から来る作品上に見られる上記のような衰えが全く見られない。
それどころか年齢を重ねる毎に、取り扱うテーマは重くなり(嘗ての様な軽い作品が姿を消してしまったのはちょっと残念だが)、だからと言って決して頭でっかちな映画になっている訳でもなく、また説教臭くなって来ている訳でもない。
老いて益々作品は重厚且つ緻密になり、構成にも隙が見られない。また映画自体もスケールアップしている為、イーストウッドの新作が封切られる度に多くの観客が口を揃えて「前作を上回る出来栄えである。」と意図も容易に言い切ってしまうこととなり、驚きの色が隠せない。
参考までに巨匠、名匠と呼ばれる映画監督で、老齢まで映画を撮り続けた人達の作品と製作時の年齢を以下に示す。
ジョン・フォード監督: シャイアン('64)=69歳、荒野の女たち('66)=71歳
ハワード・ホークス監督: エル・ドラド('66)=71歳、リオ・ロボ('70)=74歳
ジョン・ヒューストン監督: 勝利への脱出('80)=74歳、アニー('82)=76歳、女と男の名誉('85)=79歳、ザ・デッド/『ダブリン市民』('87)より=81歳
ビリー・ワイルダー監督: 悲愁('79)=73歳、バディ・バディ('81)=75歳
アルフレッド・ヒッチコック監督: フレンジー('72)=73歳、ファミリー・プロット('76)=77歳
黒澤明監督:乱('85)= 75歳、夢('90)=80歳、八月の狂詩曲('91)=81歳、まあだだよ('93)=83歳
そしてイーストウッドはと言うと以下に示すような状況だ。
クリント・イーストウッド監督: スペース・カウボーイ('00)-兼主演=70歳、ブラッド・ワーク('02)-兼主演=72歳、ミスティック・リバー('03)-兼音楽=73歳、ピアノ・ブルース('03)=73歳、ミリオンダラー・ベイビー('04)-兼主演=74歳、父親たちの星条旗('06)-兼音楽=76歳、硫黄島からの手紙('06)=76歳、さよなら。いつかわかること('08)-音楽=78歳、チェンジリング('08)-兼音楽=78歳、グラン・トリノ('08)-兼主演=78歳
短期間で撮影を終え、次々と作品を送り出す多作家であるところも未だ変わらず、その驚異的なペースも以前と変わらない。自らのプロダクション(マルパソ)を持つ製作者でもあり、作品によっては主演、音楽も兼ねるというこのエネルギーに対抗し得る映画作家は目下の所、古今東西を探してもちょっと見当たらない。
さて今回の作品はどうだったのかと言えば、一言で言ってその出来の良さに圧倒されてしまった。
イーストウッドの描く一連の犯罪を取り扱ったサスペンス・スリラーとしては珍しい時代物であり、丁度ユニヴァーサル・スタジオが設立され、映画がサイレントからトーキーへと移り変わる1920年代後半のロサンゼルス(ほぼハリウッド近辺である)を舞台にしており、この映画の冒頭に現れるユニヴァーサル映画のトレード・マークも怪奇映画の名作「フランケンシュタイン ('31)」、「魔人ドラキュラ ('31)」、「フランケンシュタインの花嫁 ('35)」、音楽映画の名作「オーケストラの少女 ('37)」やアメリカ時代のヒッチコックの初期傑作「逃走迷路 ('42)」で見られるあの懐かしのマークだ。
誘拐された一人息子を孤独に探し出そうとするシングル・マザーであるクリスティン・コリンズ(アンジェリーナ・ジョリー)の姿を描いた感動的な母物であり、同時に恐るべき史実に基づいた猟奇殺人を描いたかなり陰惨な犯罪劇でもある。これら二つが絡み合いながら進行する内に浮き彫りになって来るのは、当時の警察のずさんな捜査と警察組織自体のあるまじき行為の数々であり、猟奇殺人もさることながら、最も恐ろしいのはそんな捜査記録を組織ぐるみで隠蔽する為の暴力行為であり、警察組織の腐敗ぶりである。この女主人公が受ける数々の受難のシーンをリアルに見せられる内に、観ているこちら側も次第に生理的に耐えられなくなる程の痛み、苦しみ、恐怖を実感させられることとなる。
警察組織の腐敗と言えば、イーストウッドが四半世紀以上も前から「ダーティハリー・シリーズ ('71)~('88)」, 「ガントレット ('77)」等で繰返し描き続けて来たテーマであるが、当時のように法を無視した正義の暴力で悪を一掃すると言ったような勧善懲悪のヒーローも登場せず、アクション派女優として有名なアンジェリーナ・ジョリーも今回に限っては唯ひたすら精神的なタフネス振りを見せることに終始している。
やがて当時の警察組織に対し予てから疑問を抱いていた教会側が彼女に手を差し伸べ、無償で弁護士が付き、またこの猟奇殺人事件の捜査に疑問を抱いた正義感のある一捜査官が立ち上がる。そして最終的には市民運動にまで発展し、映画はクライマックスへと、殺人事件の真相究明と警察側が執った暴力行為が次々と明るみにされる法廷シーンへと進む。この法廷シーンにおける法に則った完全懲悪振りは、爽快さと力強さに満ち溢れており、そこに至るまでに共有体験させられた生理的な不快感が一掃されることとなる。
にも拘らず、どこか心が晴れず曖昧さが残るのは、捉われた20人近い子供たちの内、数人は逃げ出すことに成功したのが分かるのだが、彼女の一人息子は本当に殺害されたのか?或いは逃げ延びて何処かで生きているのか?がこの法廷シーンでは何も証明されないからである。
映画は刑務所に収監されている犯人を死刑前日に訪問し、涙ながらに真相告白を迫るクリスティンの姿を追う。更には死刑執行の模様までもが非常にリアルにこれまた生理的な痛みと不快感の極みを伴いながら厳しくも淡々とした口調で描かれていき、またも映画を観ている観客側に突きつけられる。この辺りは同じくイーストウッド監督作品の「トゥルー・クライム ('99)」を想起させるが、ここでの救いのない痛々しさは、それを遥かに凌駕しており、トルーマン・カポーティ原作、リチャード・ブルックス監督作品「冷血 ('67)」を思わせる程である。
それから数年が経ち、時は1934年の春となり、丁度アカデミー賞の受賞式の夜、フランク・キャプラ監督の名作「或る夜の出来事 ('34)」が「クレオパトラ ('34)」, 「影なき男
('34)」等をおさえて作品賞を受賞したその直後に、クリスティンはあの猟奇殺人事件で捉われた少年の内の一人が今尚生きており、無事に生還したと言う知らせを受ける。
映画の最後では、今や表面的には完全に社会復帰を果たしたクリスティンが、この僅かではあるが小さな希望を抱きつつ、一生涯を一人息子の捜索に費やしたという事実が字幕で知らされ、その深い母親の愛情を感じながらも、非常にやるせない思いと漠然とした不安感を伴いながら終わる。
クリント・イーストウッド程、社会における暴力とその恐怖を生理的な痛みを伴って表現出来る作家は居ない。またその暴力の結果として生じる様々な問題に関しては、漠然とした煮え切らない結末を示すことが多く、不安感を拭えないものが多い。時には明確に回答が示されたりすることもあるが, それは決して絶対的なものではなく、賛否両論を捲き起こし、最終的には観ているこちら側の一人一人の判断に委ねられることが大半である。これもこの作家ならではの特質であり、複雑な社会の問題点をリアルに浮き彫りにしていくといった点において、本質的に過去よりも寧ろ現代の映画製作に非常にマッチしているように思えてならない。
次回作が早くも控えている。4月25日(土)ロードショー公開予定の「グラン・トリノ」だ。
本作では久しぶりに主演も兼ねているから楽しみだ。噂にによると俳優としてはこれを最後にして、今後は監督業に専念する(?)とのことである。
「グラン・トリノ」とは1972年製のフォード車。BIG3全盛時代の象徴のような車である。この映画は朝鮮戦争を経験した後、フォードで自動車工として働き、定年後も日本車に押されて沈みゆくデトロイトに住み着いている頑固老人の最期を綴った古き良き時代のアメリカへの鎮魂歌のような作品らしい。
俳優イーストウッドとして、あのジョン・ウェインが映画の中で自らが演じて来た数々の役柄と共に自己を葬り伝説化させた名作「ラスト・シューティスト('77) (ダーティ・ハリーの)ドン・シーゲル監督」のような作品になるのではないか?と、過去にイーストウッドが好んで演じた役柄の集大成のような映画になっているのではないかと、今からとても楽しみなのである。
既に本国アメリカでは、全イーストウッド作品中過去最高の興行収入を得て上映中とのことである。
実話というのが衝撃的!!!! 警察が腐りすぎてて憎たらしくてしょうがなかった笑
実話というのが衝撃的!!!!
警察が腐りすぎてて憎たらしくてしょうがなかった笑
アンジェリーナ・ジョリーの演技がすごすぎて最後まで見入ってしまった!!
ある日突然息子がいなくなってしまった母親の心境なんて想像を絶する…
結局戻ってくるかと思ったら最後まで戻らなかったのか…辛すぎて言葉にならない…
そんな中希望を捨てずに探し続けてきたクリスティには、息子が戻ってきたと言ってあげてほしかった…
いい映画でした!!
クリント・イーストウッドの映画は間違いない!!
【90.1】チェンジリング 映画レビュー
作品の完成度
本作はクリント・イーストウッド監督の円熟期を象徴する、圧倒的な完成度を誇る傑作。物語の核となるのは、警察の腐敗という社会的な不正と、それに対し一人の母親が孤立無援で立ち向かう個人の闘いという二層のドラマだ。この重厚なテーマを、監督は上映時間142分に一切の無駄なく描ききっている。物語の展開は緻密で、観客は主人公の絶望と希望、怒りと悲しみを追体験していく。実話に基づいているからこその説得力が全編を貫き、観客はフィクションを超えたリアリティに引き込まれる。特に終盤、事件の真相が明らかになり、主人公の闘いが法廷闘争へと発展していく過程は、単なるサスペンスを超えた社会派ドラマとしての重みを持つ。そして何より、希望を失わずに息子を待ち続けるクリスティンの姿は、人間の尊厳と母性愛の強さを深く問いかける。物語、演出、演技、映像、音楽、そのすべてが高次元で融合し、観客に深い感動と問題提起をもたらす、映画史に残る完成度といえる。
監督・演出・編集
クリント・イーストウッド監督による抑制の効いた演出が光る。感情に訴えかけることを目的とした過度な演出を排し、淡々と、しかし力強く物語を紡いでいく。観客は主人公の感情を強制されることなく、自らの感情で物語に没入していくことができる。長回しを多用し、登場人物の葛藤や決意をじっくりと見せる一方で、裁判のシーンではテンポの良いカット割りが緊張感を高める。編集はジェームズ・J・ムラカミとゲイリー・D・ローチが担当。緩急をつけた絶妙なリズムが、長尺を感じさせない。特に、クリスティンが精神病院に強制収容されるシーンの不条理さと、その後の法廷闘争におけるカタルシスのコントラストは鮮やか。監督自身の作風である、静謐でメランコリックな雰囲気が、1920年代のロサンゼルスの街並みと見事に調和している。
キャスティング・役者の演技
主演、助演陣の演技が作品の重みを支えている。特に主演のアンジェリーナ・ジョリーは、キャリア史上最高の演技との評価も高く、アカデミー賞主演女優賞にノミネートされた。
* アンジェリーナ・ジョリー(クリスティン・コリンズ役)
息子を突然失い、警察の理不尽な対応に翻弄されるシングルマザーを熱演。息子が戻ってきたと聞かされ、喜びに満ちた表情から、それが別人だと悟った瞬間のわずかな表情の変化、そして絶望へと突き落とされる様子を繊細に演じ分ける。警察に反抗して精神病院に送られた後、尊厳を奪われながらも決して諦めない強い意志を眼差しで表現。終盤、犯人との面会で息子の消息を問い詰めるシーンでは、怒りや憎しみ、そしてわずかな希望を抱く複雑な感情を爆発させ、観客の心を揺さぶる。絶望の淵に立たされても、母としての信念を貫く力強い姿は、観る者に深い感動を与える。
* ジョン・マルコヴィッチ(グスタヴ・ブリーグレブ牧師役)
不正が横行する警察を告発する孤高の牧師を演じる。彼の演じる牧師は、クリスティンの唯一の理解者であり、希望の光。理知的で冷静でありながら、正義感に燃える情熱的な面を抑制の効いた演技で見せる。不正と闘うクリスティンに共感し、彼女を支える姿は、物語に大きな安心感と希望をもたらす。静かな語り口と眼差しに、揺るぎない信念を感じさせる演技はさすがの一言。
* ジェフリー・ドノヴァン(J・J・ジョーンズ警部役)
腐敗したロス市警の権力を象徴する冷酷な警部を怪演。自身の保身のために、クリスティンの主張を無視し、彼女を精神病院に送り込むなど、非道な行いを繰り返す。その悪役ぶりは徹底しており、観客の怒りを一身に引き受ける。権力を笠に着て尊大な態度を取る一方で、内心では自身の保身と恐怖に怯える人物像を巧みに表現。クリスティンとの対立は、この物語の大きな推進力となっている。
* エイミー・ライアン(キャロル・デクスター役)
クリスティンが強制入院させられた精神病院で出会う女性。理不尽な警察権力に屈した被害者の一人であり、クリスティンに現実の厳しさを突きつける。彼女の絶望的な表情は、クリスティンが置かれている状況の深刻さを観客に伝える。短い登場ながら、その存在感は強く、クリスティンが直面する闘いの過酷さを物語る重要な役割を果たしている。
* ジェイソン・バトラー・ハーナー(ゴードン・ノースコット役)
物語の後半、連続殺人事件の犯人として登場する人物。その残虐性を内包しながらも、どこか世俗的で神経質な青年という人物像を演じる。彼の登場により、クリスティンの闘いが単なる警察の不正告発だけでなく、息子を殺されたかもしれないという個人的な悲劇へと深まる。悪そのものを体現するような鬼気迫る演技は、物語に決定的な緊張感と恐怖をもたらす。
脚本・ストーリー
脚本はJ・マイケル・ストラジンスキーが担当。実話に基づいた重厚なストーリーを、サスペンスフルな展開とヒューマンドラマの要素を巧みに融合させて描き出す。警察の腐敗、女性差別の問題、そして精神医療における人権侵害といった、当時のアメリカが抱えていた社会問題を鋭く切り込む。主人公クリスティンの「息子を返してほしい」というシンプルな願いが、巨大な権力との闘いへと発展していく過程は、観客の感情を強く揺さぶる。物語はクリスティンの個人的な悲劇から始まり、やがて社会全体を揺るがす大きな事件へと広がっていく。結末は完全なハッピーエンドではないが、彼女の闘いが無駄ではなかったことを示唆し、観客に希望を残す。ストラジンスキーは、この脚本でアカデミー賞脚本賞にノミネートされている。
映像・美術衣装
トム・スターンによる撮影は、1920年代のロサンゼルスをモノトーン調の落ち着いた色調で表現。街の活気や人々の生活をリアルに捉えつつ、同時に事件の不穏な雰囲気を醸し出す。特に、クリスティンの自宅や精神病院の薄暗い映像は、彼女の孤独や絶望感を強調している。美術はジェームズ・J・ムラカミとゲイリー・D・ローチが担当。当時のロサンゼルスの街並み、電話交換局、精神病院の内部など、細部にまでこだわったセットが、時代背景に説得力を持たせている。衣装はデボラ・ホッパーが担当。クリスティンの着用するクラシカルなドレスや帽子、手袋は、当時の女性のファッションを忠実に再現。それらの衣装は、彼女の気品と、警察の理不尽な対応に抗う強さを象徴している。
音楽
クリント・イーストウッド監督自身が作曲を担当。ジャズを基調としたシンプルで抑制の効いたスコアが、映画全体に静謐でメランコリックな雰囲気を醸し出す。過剰な感情表現を避け、物語の陰影をさりげなく彩る。特に、ピアノの旋律が印象的で、クリスティンの孤独な心情や、わずかに残された希望を表現している。主題歌は特になし。
受賞・ノミネート
第81回アカデミー賞では、主演女優賞(アンジェリーナ・ジョリー)、脚本賞(J・マイケル・ストラジンスキー)、撮影賞(トム・スターン)の3部門にノミネートされた。カンヌ国際映画祭コンペティション部門にも出品され、高い評価を獲得。その他、主要な映画賞に多数ノミネートされている。
作品 Changeling
監督 クリント・イーストウッド 126×0.715 90.1
編集
主演 アンジェリーナ・ジョリーA9×3
助演 マイケル・ケリー A9
脚本・ストーリー J・マイケル・ストラジンスキー A9×7
撮影・映像 トム・スターン A9
美術・衣装 ジェームズ・J・ムラカミ
A9
音楽 クリント・イーストウッド A9
衝撃的な映画
日本では誘拐事件はあまり聞かないが、アメリカでは当たり前のように起きている。子どもを一人にしておくことはなく、通学もスクールバスが普通。親が子どもから少し目を話した隙に、男が誘拐を実行しようとして失敗した映像をみたことがある。『チェンジリング』は、そういった事件が日常的に起こるアメリカならではの映画だと感じた。
序盤で牧師がLA市警の腐敗について話していたが、想像以上に腐敗していた。クリスティンが強制入院させられた精神病院の患者が言うように、警察に刃向かう人間は強制的に精神病院に送られる。精神病院の環境も劣悪。クリスティンが入院当日に強烈な放水を浴びさせられるシーンは、人を人と思っていない残酷で野蛮な行為で、強烈な印象を残した。当時のアメリカは文明が発達しているように見えて、人権に関わる部分はまだまだ未開なのだと感じた。
クリスティンの息子と間違えられたアーサーが、自分が息子だと嘘をついた理由は、LAのスターに会えると思ったからだと述べている。この映画がフィクションならその設定は違和感があると言いたくなるが、実話なので驚く。事実は小説より奇なりとはまさにこの映画のことだ。
クリスティンと犯人のゴードンを演じた2人の熱演は特に素晴らしい。
クリスティンを演じたアンジェリーナ・ジョリーが、息子ではないアーサーに「おやすみママ」と言われて「それを言わないで」と激怒して皿を壁に投げつけ泣き崩れるシーンは、息子を失った母親の苦しみを十分に表現できていた。
犯人のゴードンを演じたジェイソン・バトラー・ハーナーは、法廷に表れたときのヘラヘラした態度や、死刑台に向かう際に喚き散らすところなど、人間の屑を全力で演じられていた。
犯罪実話にハズレなし
【”この子は息子ではない!”腐敗し切った1920年代のLA市警を相手に、真実を追求する信念を曲げない母の姿が切なくも心に沁みる作品。実話ベースである事も恐ろしさを増幅させている作品である。】
■1928年のロサンゼルス。シングルマザーのクリスティン(アンジェリーナ・ジョリー)は9歳の息子ウォルターと幸せな毎日を送っていたが、ある日、家で留守番をしていた息子が失踪する。
それから5カ月後に発見されたとの報が入るが、クリスティンの前に現れたのは、息子に似てはいるが身長も違う、見知らぬ少年だった。
ー ご存じの通り、今作は実際に在った20人もの子供を誘拐し殺害していた”ゴードン・ノースコット事件”を絡ませている。
そして、観る側はクリスティンが腐敗し切ったLA警察に果敢に迫る姿と、緊迫したサスペンスを並行で見ながら、物語に没入して行くのである。
◆感想<Caution! 内容に触れています。>
・捜査に当たった、ジョーンズ警部(ジェフリー・ドノヴァン)や警察本部長(コルム・フィオール)の警察の対面しか考えない愚かしき姿に、怒りを感じる。
ー ジョーンズ警部は、”この子は息子ではない!”と抗議に来るクリスティンを、精神病院にぶち込むのである。
そこには、警察に歯向かっただけで拘留されている”コード12”と呼ばれる女性達が多数収容されている。女性達の人権を無視した腐った司法の実態。-
・ブリーグレブ牧師(ジョン・マルコヴィッチ)の動きにより、病院を出たクリスティン。それでも、彼女は息子を探し続けるのである。
ー ブリーグレブ牧師が居なかったら、どうなっていたのか・・。-
■そんなある日、サンフォードという少年が警察にやって来る。レスター・ヤバラ刑事(マイケル・ケリー)が対応するが、少年が口にした驚愕の出来事。
ー レスター・ヤバラ刑事はノースコット牧場に駆け付ける。警察の中の数少ない良心を持った刑事である。
事態は、急転直下する。-
■更に、クリスティンは、ブリーグレブ牧師の紹介でハーン弁護士を雇い、精神病院に隔離されていた女性達を解放し、LA市警に訴訟を起こすのである。
ー 胸の好くシーンである。-
<そして、ゴードン・ノースコットの裁判と、LA市警に対する聴聞会が市民の批判を交わすため、市警の意向で同時に行われる。
が、ゴードン・ノースコットは当然、死刑。ジョーンズ警部は無期限の停職、警察本部長は解任されるのである。
だが、クリスティンはその後も”希望”を持ちながら、息子ウォルターを探す決意をするのである。
実話ベースの作風は、クリント・イーストウッド監督の自家薬籠中のモノであるが、今作程恐ろしく切ない作品は、少ない。
秀作であろう。>
この既視感は何なのか…
今まで見ないまま過ごしてきた、イーストウッド作品のいくつかのうちひとつ。
長さを感じさせないストーリーは、丁度いい展開にまとまっているからなのだろう。終わってみれば、深く考えさせられるいつもの余韻に浸る。やっぱり彼の映画は独特の間があり、「何か意味があるに違いない」と思わせる何かがある。
TRUE STORY
ということらしいが、信じられないほどの警察の怠慢と傲岸不遜。連続殺人鬼の不気味さ。行方不明だった息子の秘めたる勇気。それを伝え聞き魂の癒しを得る母親。息子に成りすました少年の謎の動機と、本気で地獄行きを心配する苦悩。
など、「これでもか」というくらい沢山の語るに難しい要素が詰まっている。
少なくとも、友人に「どんな映画?」と聞かれても、ひと言では言い現わすことが出来ない、多面的で、それでいてしっかりと太い幹のストーリーがある。
俳優たちの演技も見ごたえのあるものばかり。アンジェリーナ・ジョリーも、抑制の効いた演技で、苦難を乗り越えていく強い母親を演じている。
それにしても、「なんか見たことがある」気がするんだよなあ。
2020.9.4
母親の愛は永遠に!
2008年(アメリカ)監督:クリント・イーストウッド。主演:アンジェリーナ・ジョリー。
実話をベースにしたストーリーです。
1928年。
シングルマザーで電話会社に勤務するクリスティンの息子ウォルターが、
突然行方不明になります。
クリスティンはロサンゼルス市警に捜査を依頼。
そして5ヶ月後、ウォルターが見つかったとの報告を受けます。
駅まで迎えに行ったクリスティンは、驚愕します。
まったくの別人だったのです。
しかしジョーンズ警部は《人違い》と主張するクリスティンを強制的に精神科病院に
収容させて隔離してしまう。
この辺で、ロサンゼルス市警の異常さに見てる者は驚きます。
この頃のロサンゼルス市警は大変な腐敗の温床で不祥事が絶え間なく起こる状態だったそうです。
更に事件は発展して・・・
カナダからの不法移民の少年が、従兄弟のノースコットに脅されて少年たち20人近くを殺して養鶏所の敷地に埋めたと告白するのです。
この中の少年たちの写真の中に、ウォルター少年がいたのです。
敷地を掘り起こすと実際に多数の骨が見つかります。
本当にウォルター少年は殺されたのでしょうか?
(現在ならDNA鑑定がありますが、当時はありませんでしたね)
こどもが誘拐されて所在が掴めない。家族には地獄の日々です。
どこか見知らぬ場所で監禁されて生きているかもしれません。
母親の息子を思う感情をアンジェリーナ・ジョリーは涙ながらに、しかし力強く演じていました。
アカデミー賞主演女優賞に輝いたそうです。
実話だという。 警察とは何か、病院・医者とは何か。権力によって市民...
当たり前にあるはずの良心を尊く感じる
警察の不正に何故、認めなかったのか。
柱のきずはおととしの~♪
タイトルの“changeling”とは“取替え子”という意味だそうで、「さらった子供の代わりに妖精が置いていく醜い子」という伝説があるらしい。それを身をもって体験するシングルマザーのクリスティン・コリンズ(アンジェリーナ・ジョリー)。実際に起こった事件だというのだから、彼女の悲痛な思いが胸に突き刺さる。最近香川県で起こった、体外受精において受精卵を取り違えるという医療ミス事件も思い出してしまいます。
時は世界大恐慌前夜の1928年。再現された当時のロサンゼルスの風景が心地よく、クラシックカーをよく集めたもんだと感心するし、バスのシートが木でできていることにも驚かされる。小学校では土曜日が休みだとか、電話交換手がローラースケートを履いていることにも軽く驚いたのですが、子供の身長を柱に刻むという行為に親近感を抱きました。
息子のウォルターが失踪してから5ヶ月後に見つかったと連絡が入り、会いに行ったら別人だったという衝撃。しかも名誉挽回のチャンスだとばかりに、腐敗しきった当時のLAPDは「間違いない」とクリスティンを納得させようとするのだ。なんとも憎たらしいほどのジョーンズ警部(ジェフリー・ドノヴァン)。人違いを主張するクリスティンを黙らせようと精神病院送りにまでしてしまう。
ミステリー中心の映画だとばかり思っていたのに、さすがは御大クリント・イーストウッド。『ミスティック・リバー』以降に見られる、今まで正義とされていたものを疑問視する社会派要素たっぷりの作風は今作でも健在。善良なる市民が権力の前に泣き寝入りせぬよう勇気を与えてくれてるといっても過言ではない。それがジョン・マルコヴィッチ演ずるグリーブレブ牧師であったり、証言してくれる歯科医であったり、息子の学校の教師であったり、精神病院の患者キャロル・デクスター(エイミー・ライアン)であったりするのです。
中盤からは主軸であるはずの息子捜しは影をひそめ、横暴で無秩序な警察に対する闘争がメインとなり、同時に子供ばかりを狙う連続殺人鬼も登場する。警察内にもヤバラ(マイケル・ケリー)という良心的刑事が現れ、最後までクリスティンに付き添ってくれる姿が印象的。注目していたら、いつのまにか右頬に切り傷があったのが気にかかりました。そして、不正に立ち向かうためならと、無報酬で協力する弁護士の活躍も溜飲を下げてくれる。
ただ、法廷モノとして感動していると、その後にエピローグ的なストーリーがまだまだ続くので、涙も乾いてしまいました。決してハッピーエンディングとならない静かな展開はイーストウッド的手法なのかもしれない。余韻を残し、深く心に刻まれるような。
映画ファンとして興味深いことに1934年のアカデミー賞のネタがありました。もしかすると、本作品がオスカー候補となることを見込んでいたのだろうか?残念なことに作品賞にはノミネートされませんでした。そんな中、前半と後半では全く雰囲気が違って見えたアンジーの主演女優賞には期待したい。なにしろ助演女優賞を獲得したのが『17歳のカルテ』。奇しくも精神病院という共通項があるのだから・・・
【2009年2月映画館にて】
母親の強さ
息子が突然、いなくなる悲しみ
最初に思ったのは腹立たしい気持ちです
警察の怠慢そして一人の権力で
ここまで住人を苦しめる
何のために
女性が自分の言うことを聞かなかったから
気分の感情を逆撫でしたから
このような傲慢な警察官でなかったら
もしかしたら生きていた可能性もあった
ここでは母親の息子の想い(重い)悲しみなど
いなくなった息子は必ず戻ってくると
帰ってこないことなど一ミリも
疑がうことはなかった
最後まで探すことを止めなかった
息子は帰ってくる 必ずや我が家に
母の諦めない強い意思がすごく伝わってくる
彼女は誰も(警察も犯人も)傷づけていない
…ただ息子に会いたいだけ
ただそれだけ…… それが叶うことはなかった
彼女は今でも希望を持ち続けている
権力を盾にやりたい放題の警察
私欲まみれのあり方に警鐘をならす
じわじわと感情に訴えていく
描き方が(音楽を含め)とても上手いです
音楽の妙
嘘のような現実
全132件中、1~20件目を表示