劇場公開日:2005年7月9日
解説・あらすじ
独裁者アドルフ・ヒトラーの最期の12日間を克明に描いた実録ドラマ。ヨアヒム・フェストによる同名研究書、およびヒトラーの秘書を務めたトラウドゥル・ユンゲの証言と回想録「私はヒトラーの秘書だった」を基に、「es エス」のオリバー・ヒルシュビーゲル監督がメガホンをとった。1942年、ミュンヘン出身の若い女性トラウドゥルは、ナチス総統ヒトラーの個人秘書として働くことに。1945年4月20日、ベルリン。ヒトラーは迫りくるソ連軍の砲火から逃れるため、側近たちとともにドイツ首相官邸の地下要塞に避難する。その中にはトラウドゥルの姿もあった。誰もがドイツの敗戦を確信していたが、もはやヒトラーは客観的な判断能力を失いつつあった。「ベルリン・天使の詩」の名優ブルーノ・ガンツがヒトラー役を熱演。トラウドゥル役に「トンネル」のアレクサンドラ・マリア・ララ。
2004年製作/155分/ドイツ
原題または英題:Der Untergang
配給:ギャガ
劇場公開日:2005年7月9日
スタッフ・キャスト
- 監督
- オリバー・ヒルシュビーゲル
- 製作
- ベルント・アイヒンガー
- 原作
- ヨアヒム・フェスト
- トラウドゥル・ユンゲ
- メリッサ・ミュラー
- 脚本
- ベルント・アイヒンガー
- 撮影
- ライナー・クラウスマン
- 美術
- ベルナント・ルペル
- 音楽
- ステファン・ツァハリアス
受賞歴
第77回 アカデミー賞(2005年)
ノミネート
| 外国語映画賞 |
|---|

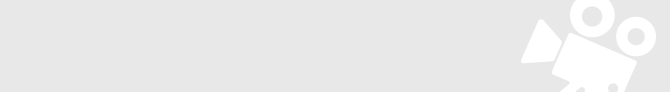






 ハウス・ジャック・ビルト
ハウス・ジャック・ビルト コリーニ事件
コリーニ事件 ベルリン、天使の詩
ベルリン、天使の詩 イマジン
イマジン アメリカの友人
アメリカの友人 左利きの女
左利きの女 バルトの楽園
バルトの楽園 ヒトラー暗殺、13分の誤算
ヒトラー暗殺、13分の誤算 ダイアナ
ダイアナ インベージョン
インベージョン
















