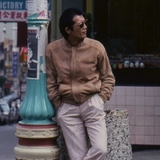招かれざる客のレビュー・感想・評価
全28件中、1~20件目を表示
人種問題を軽いタッチで作り上げた感動作
白人の女性と黒人の男性の結婚
差別は黒人を見た瞬間の表情に
徹底してNOの答えを出す時代
上手い俳優を揃えた映画
彼らの演技は見応えあり
傷つけ合う家族
親の失望と望み
娘と息子の幸せ
差別という暴力
台詞の応酬に舞台劇を感じ
顔の表情に驚きと愛を見た
ふたりの未来は偏見の世界
この時代の問題作でもある。
※
重い鞄を運んだのはそれが仕事だから…
名作。理性を超えた葛藤が胸を打つ。
黒人男性と白人女性。そんな二人が結婚することが異端とされていた時代の話。娘が突然結婚相手を連れて家に帰ってきました。相手は黒人の男性。黒人であることを除けば、非の打ちどころはありません。娘の両親は、リベラルであることの大切さを教育してきましたが、いざ自分の身に降りかかると、言うは易し横山やすしです。
愛する娘に平和で無難な道を歩ませたい。親であれば自然に思い抱く心情と、人としてこうあるべきと教えてきた価値観とのせめぎあいが繰り広げられます。言行一致、walk on the talkの難しさをよく描いています。今の日本に置き換えると、もし娘が韓国人の男性を連れてきて結婚すると言ってきたら、素直に喜べるのかしら、と考えてしまいます。二人は当事者ではないとはいえ、2国間に横たわる歴史的な不幸、家父長制度・儒教的思想が強い価値観など、いばらにも思える道が娘の未来に広がるように思わずにはいられません。相手が欧米の人であれば、そこまで深く考えないかもしれないので、私には少し偏見があるのかもしれません。
愛する二人なら厳しい困難も乗り越えられると信じて二人の門出を祝福するのか、それとも、不幸になるかもしれないから力ずくで押しとどめるのか。娘といえども、人格は別物。親の所有物ではないのですよね。そんな毒にも薬にもならないことは、だれもが百も承知です。それを超えたところにある葛藤だから、共感できるし、感情移入できるのでしょう。
愛については、女性の方が理解があるのか、双方の親も夫人側から子供たちに理解を示し始めます。娘の本気度を知って、人を愛することの大切さを思い出し夫に伝えるキャサリンヘップバーン。いい配役ですね。最初は反対だった人が少しずつ理解を示し始める様子は、テーマは全く違いますが、『12人の怒れる男』を彷彿させるものがあります。
本作品のクライマックスは、双方の家族、友人である神父、家政婦を前にして花嫁の父トレンサー・スペンシーが演説のようにスピーチをするシーンでしょう。非常に素晴らしいですね。あのシーンだけでも定期的に見返したいと思うくらいです。
花嫁の父の言葉でハッピーエンディングに終わる本作品ですが、この続編のようなストーリーを映画にしても面白いのではないかと思うのです。思い描いた将来と現実のギャップ。何度も挫けるけれども初心を思い返しそれらの困難を乗り越えて、気づけば金婚式のような話も良いかと思います。もしくは、現実に押しつぶされる話はありきたりかもしれませんが、そんな二人にも共感できるのではないでしょうか。
私が勝手に選ぶ22世紀に持っていきたい映画の一作品です。世代を問わず鑑賞できるので、未鑑賞の方はぜひご鑑賞ください。
50年以上前のシネマスターたち…
たまたまテレビでやっていた作品、こちらのサイトでレビューをチェックしたら、なかなかの高評価だったので、最後まで鑑賞しました。
ストーリーよりも、この作品にまつわるエピソードも色々興味深いのですが、まさか1967年公開の作品だったとは!とても美しいカラー作品だったので、古さを全く感じませんでした。
カナダに来てもうすぐ2年、今だに働くたびにチクチク感じる人種差別的、透明な存在だと感じる瞬間。
無視をされるくらいなら特にやり返したりしないのですが、どうせ日本人なら英語わかんないだろうと思われて、たまに嫌味を言われることもあるので、最近は黙ってないで "Why are you so mean?" と言い返すようになりましたw
黙って反論したい気持ちをグッと飲み込んでも、こちらでは大して美徳ではなく、「アジア人ナメんな!」というプライドは忘れずにいたいものです。
今だに人種差別は存在するのだから、50年以上前の白人と黒人の結婚だなんてどれだけ珍しいことだろうと思います。
割とシンプルな英語だし、最近の作品と違って役者さんの発音が美しくてセリフは聞き取りやすいのですが、日本語字幕がなかったので、お母さん同士の会話や、最後のお父さんの長いスピーチには、どんなニュアンスで翻訳されたか知りたかったです。
時代のせいか「ニグロ」という言葉を何回か使っていて、なんだかんだRacism の根深さは感じましたけどね。
家族会議ムービー
他人事と自分事。
めちゃめちゃ良かった。半日という限定された時間の中で、かつ、ほとんど家の中で個々の会話の中から、それぞれの心情、思い、迷いや憤りが浮き彫りになっていく、秀逸な群像劇。
表向き、他人事として論評する、表明する意見・綺麗事と、自分事となったときに感じ考える本当の気持ちと。倫理的には正しくても、受け入れられないと感じてしまうことや、自分の身に降りかかってきた場合は別だ、と意見を翻す。誰もが胸に手を当てると思い当たる出来事の一つや二つあるのではないか?
ゴミの分別が少し甘いかなと思いつつも出してしまうといったところから、2023年11月、自分がイスラエル人だったら、倫理的に正しかろうとも現時点での停戦は受け入れられないだろうといったところまで。
1967年の作品だが、ここに描かれている両親の苦悩・葛藤は、その対象が異なったとしても、普遍的で誰もが経験するところだろう。
この葛藤の中で、それぞれがどのような見解に到達し、他者にどのように伝えていくのか?ラストまで、どう転がるのか、自分だったらどういう選択をするのか、緊張感をもって見守ることのできる作品だった。
黒人の母の語りは沁みたし、お互いが必要としていることの大切さを改めて考えることができた。
鑑賞してほんと良かった。
もっと若い時に見たかった
タイトルなし(ネタバレ)
まあ、大体想像できる展開だったが、ハラハラしながらも毅然とした態度の娘の母役、キャサリンヘップバーンがよかった。シーンで言えば、結婚反対し続けた娘の親が許す最後、「息子の母の言葉で気が付いた、自分が妻に注ぐ半分の愛があれば大丈夫」というところに涙が出た。 それから、息子が黒人の父に反発しながら愛情を示すところが熱くなった。 家のテラスの外観とか車窓の合成ぶりがあまりにも。。。でテンション下がる。 鑑賞後調べたらキャサリンヘップバーンはアカデミーの主演女優賞取ってた。やっぱりね。
「何があってもあなたの味方よ」
期待せずに初鑑賞。
今の日本でも、娘が黒人男性連れてきたらぶったまげる時代なのに、
当時の衝撃は如何ばかりか。
超エリートの黒人とはいえ、将来を心配するジョアンナの父の気持ちもよくわかる。
でも、最後には、親は、子供の幸せをながっているんだね。
ジョアンナのお母さんが、何度も、「あたしは何があってもあなたの味方よ」
と言ったのは印象が強い。
ジョンの母との会話で、若く情熱ある頃を思い出したジョアンナの父がラストで、
2人を祝福する。泣いてしまった。みなさん演技が上手く、入り込めました。
世界がこの作品の登場人物のように、聡明で、思慮深い人々で構成されていたなら…
多分、4度目位だが、TV放映を機に再鑑賞。
私は、監督の演出力で映画を観る方で、
あまり俳優の演技力に注力して鑑賞する
タイプではないが、この作品に関しては、
スペンサー・トレーシー、
キャサリン・ヘップバーン、
シドニー・ポアチエ、
3人の演技力に心酔して鑑賞させて頂いた。
感情と理性の狭間で揺れ動く心情を
見事に演じきった出演陣と、
それを支えた脚本力と演出力が描く登場人物
の人間性に涙腺が緩みっぱなし。
これまでの中で一番感動した鑑賞になった
ような気がする。
世界中が、この作品の登場人物のように、
誠実で、聡明で、思慮深い人々で
構成されていたら、
こんな不安が高まる世界には
なっていなかったように
思わされるばかりだ。
スタンリー・クレイマー監督作品としては、
近年「渚にて」を観たが、
今後予定している
「手錠のままの脱獄」の初鑑賞と、
「ニュールンベルク裁判」の再鑑賞が
楽しみになってきた。
社会を変える人はいつの時代でも、一歩行動に出る!
この映画は1967年12月12日にリリースされたと。 異人種間の結婚が最高裁を可決したのが1967年6月だと読んだ。 キング牧師やロバート・ケネディが殺されたのが1968年、翌年である。 スタンリークレーマの亡き後、伴侶が、この映画で、ジョン(シドニー・ポアティエ)がタクシーの中でジョーイー(キャサリン・ホートン)にキスをしたが、ハリウッドでは異人種間では初めてだったと。
この映画を鑑賞するのにこういう時代背景が重要になってくると思う。
仲間と『映画ディスカッション』の指定映画(と言っておこう)になってるんだけど、私は高校生の頃、大正13年生まれの父親にコタツに一緒に座らせられて、この映画を見ている。そして、人権(多分?)についての会話を父としている。他界している父を悪く言いたくないが、マット(スペンサー・トレーシー)と同様に矛盾も抱えていた。この矛盾が映画でもわかるように、カルフォルニア州サンフランシスコでリベラルと言われる新聞出版社の革命的存在であるマットが『自分の子供のこと』となると、反旗をひるがしてしまうが、彼も若い時、妻を愛していた気持ちと同様に娘もジョンを愛しているんだとジョンの母親(ビア・リチャーズ)から気づきを与えられ、気持ちが変わっていく。マットの机の上を見れば、一目瞭然であるがフランクリン・ルーズベルト(FDR)大統領の写真と家族の写真が飾ってある。 賛否両論はあるがひとまずFDRは民主党、リベラルの旗頭で、マットはきっと尊敬しているから、写真を飾っておくのだろうとおもう。 それに、カトリックの神父が友達であるように、無宗教で宗教にこだわりなく、友達を作れる。着物を着た給仕がいるバーでのジョーイー(キャサリン・ホートン)の友達の発言でもわかるように、彼は本物のリベラルなのだ。サンフランシスコに、人種の交わり、堂々と問題点を黒人が指摘できる(例えば、メルズ・ダイナーで車を事故を起こしたシーン)ような息吹を与えたのもジャーナリスト、革新的な存在のマットが一役かっているのではないかと思われる。
娘、ジョーイー(キャサリン・ホートン)は父親マット(スペンサー・トレイシー)の影響力下でリベラルに育てられたように、私も大正生まれのリベラルな父親に育てられ、すでに、5年生の頃、差別が問題であることを知った。その後も何度かこの映画を鑑賞する機会があったが、当時の歴史的背景を学んだことで、この映画鑑賞に厚みが出てきたと思っている。
スタンリークレーマー監督ほど、この当時、センセーショナルな監督はいなかったのに違いない。それに、当時のハリウッドのコロンビアとスタンリークレーマの関係を理解すると『なるほど』こうしなければ、この映画は撮れなかったのかと思った。
下記はシドニーの自叙伝をよんでその記憶を意訳したもの。
クレーマー監督は『手錠のままの脱獄』(The Defiant Ones (1958))でシドニーを既に使っている。監督は『招かれざる客』は『必要な映画だ』と言っている。そして、アメリカハリウッド映画業界はこういう話の映画の準備はできていないが、そうであっても作ると言っていた。
『招かれざる客』Guess Who's Coming to Dinner (1967) をシドニーの見解から述べている自叙伝によると(時々誤解して理解しているかもしれない)、監督はスペンサー・レイシーとキャサリン・ヘップバーンとシドニーで映画制作のを許可をコロンビアからもらった。撮影が始まって、コロンビア側は内容を聞いてきた。監督は『家族の話で、暖かく、人間性のあるもの』だと答えた。 その後、コロンビアは 脚本を読みたいと言ってきた。そして、読んで、『危険すぎる!』 と答えた。
(これは私の考えだが、スペンサー・レイシーとキャサリン・ヘップバーンは当時大物だったし、コロンビアは彼らの映画は金になると思ったと思うし、また、既に名作を作っているスタンリークレーマーが監督だから内容を聞かず最初に了解をしたと想像する。)
そして、当時、ストーリーは『We don't usually do that!』と。『いくらリベラルな白人でも、黒人が白人の家に食事に来るということはなかった』と言う意味でもある。それに、またいくらリベラルでも、黒人が国際的な医者のステータスでもこの二人のような異人種の結婚に賛同しないと言う意味でもある。ポール・ニューマンが食事にきて、娘との結婚を許可してもらうというよくありそうな話は、全くストーリーにならない。
映画界の大物、スペンサー・レイシーとキャサリン・ヘップバーンたちは当時ハリウッドに住んでいたが、ハリウッドに住んでいても、一度も、黒人を招いて食事をしたことはなかったろうとシドニーは言ってる。この映画のシーンで、母クリスティ(キャサリン・ヘップバーン)が豪邸である自宅に戻ったとき、シドニーを見て、『開いた口が塞がらない』ような驚きを示すが、シドニー曰く、現実問題、初めて、シドニーがキャサリン・ヘップバーンの自宅を訪れたときのキャサリン・ヘップバーン態度は全く同じだったと。その後の態度を見ても、キャサリン・ヘップバーンがこういう状態に慣れていないのがわかった。
上記はあくまでも私の意訳だが、
当時、こういう現実を踏まえた状態で映画が制作されたのだった。当時に戻って考えるのは難しいが、シドニーの自叙伝の一部が現実味を与えてくれる。
かなり書いてしまったが、映画の内容にちょっと触れたい。
強烈なのはジョン(シドニー)と父親(ロイ・グレン)との会話だ。父親は父親、彼の苦労話をジョンは尊敬し、否定はしないが、父親は自分を『黒人』として考えて生きている。息子のジョンとの違いは少なくても30年はあるようだが、ジョンはすでに、自分を『一人の人間』として考えている。そのご、60年以上経った私たちも『黄色人種の日本人』としてではなく、『人間』としてもっと自分の人権を尊重するべきだと思った。
神父(セシル・ケラウェイ)の当時の寛大な発言や家族をいたわる心には頭が下がる。
映画の中のマットと同様に、クレーマー監督はイニシアチブをとって、アメリカ社会を変えた。
マンスフォードがあのような超エリートでなく、平凡なサラリーマン程度の黒人青年だったらこの物語はどうなったのでしょうか?
スペンサー・トレイシー 67歳
アカデミー主演男優賞を9回もノミネートされ、2回受賞
本作ではノミネート
キャサリン・ヘプバーン 60歳
アカデミー主演女優賞を12回ノミネート、4回受賞
本作でも受賞
このアカデミー賞の常連俳優二人が共演して、主演男優賞ノミネートと主演女優賞受賞、さらにはアカデミー作品賞まで受賞しているのだから凄まじい作品
しかもこの二人実は内縁関係
トレーシーは先妻との籍は事情が有って抜か無かったそうです
彼が41歳、キャサリンが34歳の時に初共演した「女性No.1」がきっかけになって、内縁関係に発展したとのこと
前年の1940年の「フィラデルフィア物語」が大ヒットしたばかりの頃です
キャサリンは21歳で結婚していましたが、27歳の時に夫と死別していました
二人の共演作品は9作品あり、本作がその最後になります
何故なら、本作のクランクアップの僅か17日後にトレーシーが心臓発作で死去したからです
看取ったのはキャサリン
しかし内縁の妻なので葬儀には出れなかったそうです
この二人の関係を頭に入れて、本作を観るのと知らないで観るのでは少し印象も異なり、味わいもより深くなると思います
二人のドライブインでのシーンは特にそう感じるはずです
しかも、本作のこの夫婦の娘ジョアンナ役のキャサリン・ホートンはキャサリンの姪であることは有名です
彼女は撮影時22歳、役でも23歳の設定です
ということはこの役の娘はスペンサーとキャサリンが内縁関係を始めてしばらくした頃の生まれの設定なのです
つまり、彼女はキャサリンの妹の娘という本当の関係を超えてスペンサーとキャサリンの実の娘であってもおかしくない女性なのです
だから、この3人の間には演技を超えた濃密なものが感じられるわけです
そして、シドニー・ポワチエ 40歳
大ヒット作「夜の大捜査線」は本作の公開と同じ年の4ヵ月前の公開作品
彼は本当はバハマの貧しい出で、15歳で一人でNYにでて職を点々としたので教育も無かったそうです
なのに彼は、教養があり、きちんとした服装とマナーと言葉の知的職業の黒人役が常でした
本作でも進歩的な白人なら「我が家の夕食に招いても我慢できる」と思うことのできる「白人が望む」礼儀正しい素直で経済力と教育を持つ黒人青年を演じています
本作の原題「Who's Coming to Dinner」
直訳すると「今日のディナーに誰が来ると思う?」とはそういう意味です
冷笑のニュアンスがあります
邦題はそれを「招かざる客」と上手く意訳しています
彼は23歳で結婚、その後38歳で離婚
そして本作の9年後の1976年に再婚しています
白人女優でその名前は「ジョアンナ」・シムカスです
面白い符合です
しかし彼が1970年代以降に活躍しなくなったのは何故かと考えてみると、その原因はその白人が望む黒人像であったからです
公民権運動が一段落した1970年代の黒人が望む黒人俳優は等身大の黒人スターだったということだと思います
黒人向けのブラックスプロイテーションの映画には、彼は大物過ぎたし、そのイメージも品行方正すぎたのです
本作の結末は、新しい時代への希望に溢れる物です
感動すらします
しかし、21世紀に生きる私達は知っています
半世紀たっても事態はなにも変わっていないことを
それでも当時よりは人種間の結婚も珍しく無いものになりました
本作公開当時は、白人と有色人種との結婚はそれこそ命掛けだったのです
マンスフォードの黒人の両親が反対したのは何故でしょうか?
それは息子が白人に殺されるかも知れないからです
息子だけでなく、自分達家族にも危害が及ぶことを恐れていたのです
白人が、有色人種と結婚する子供を止めようとする理由とは全く違うのです
だから二人の両方の両親からの何が有っても負けるなとの励ましは、文字通り命掛けだぞという意味なのです
そして黒人メイドのテイリーは、人種差別を打破して行こうとは考えていません
黒人は差別される境遇であることを変えられるなんてこれっぽっちも信じていないのです
だから小さな時から見てきている、ジョアンナをそそのかした男にしかマンスフォードを見ることができないのです
南部だけでなく、カリフォルニアのような進歩的な土地ですらそうだったのです
21世紀になっても当時よりは少しはましになった程度です
それはBLM運動があのように燃え上がった事でも明らかです
幾ら進歩的な事を口で言っていても、いざ自分の家族の事になれば違うことは今も繰り返されているのです
マンスフォードがあのような超エリートでなく、平凡なサラリーマン程度の黒人青年だったらこの物語はどうなったのでしょうか?
いやごく普通の黒人青年が本作を観たなら、どのように感じたのでしょうか
本作ですら微かな人種差別を感じとるのかも知れません
それが1970年代のブラックスプロイテーション映画の隆盛につながっていったのだと思います
「一発逆転」
1975年の映画
映画.comにはエントリがないのでこちらに記します
シドニーボアチエ監督&主演
この映画では、彼は教育のある立派な黒人役ではありません
アトランタで早朝から働く牛乳配達員です
彼なりのイメージチェンジの試みだったと思います
ソウルミュージックファンならマスト
なぜならカーチス・メイフイールドが音楽を担当しているからです
OST のアルバムを持ってる人は相当のマニアですね
ジャケットのボクサーのイラストが本作の役者に良く似て描かれていると感激します
映画自体は大したこと無いです
アトランタのとある教会の移転に必要な大金をニュオーリンズで弱いボクサーに催眠術をかけて掛けボクシングで一発逆転しようというお話
首尾良くいったのですが、ニュオーリンズからギャングの胴元が…というもの
まあテレビムービー程度、星3つがいいことです
それでも、カーチスの音楽で星ひとつオマケで星4つです
これもまたブラックスプロイテーションの流れの作品です
それ以上の作品では有りません
ギャングの親分役のジョン・エイモスが一番強い印象を残しています
しかしカーチスの音楽と当時の特徴的な素敵なコスチュームの数々を楽しめる人なら十分満足できるでしょう
新宿3丁目のエレベーターの無い雑居ビルの4階にカーチスという音楽バーがあります
コロナ禍が収まったならひさびさに飲みに行きたいものです
人種問題
ハラハラする会話劇⁈
スターチャンネルで、ゲットアウトのオマージュ作品として紹介されていた。
全28件中、1~20件目を表示