芙蓉鎮
劇場公開日:1988年3月26日
解説
文化大革命を背景に厳しい試練を強いられたひとりの女性と彼女を取り巻く人々の激動の時代を描くもので、87年度の中国・百花賞(作品ほか)、金鶏賞(作品賞ほか)受賞作。監督は「天雲山物語」「牧馬人」などの謝晋。古華の原作(徳間書店)を阿城と謝晋監督が共同で脚色、撮影は慮俊福が担当。出演は劉暁慶、姜文、鄭在石、徐松子ほか。
1987年製作/中国
原題または英題:Hibiscss Town 芙蓉鎮
配給:東宝東和
劇場公開日:1988年3月26日
あらすじ
1963年春。湖南省の南端にある小さな町・芙蓉鎮では市が立つ日で街は賑わっていた。中でも米豆腐を売る胡玉音(劉暁慶)の店は大賑いだった。国営食堂の女店主・李国香(徐松子)は胡玉音の店の繁盛をにがにがしく思っていた。李国香は解放戦争を戦いぬいた米穀管理所の主任・谷燕山(鄭在石)に米の特配をたのむがなかなか相手にされなかった。それでいて谷燕山は胡玉音には米豆腐の原材料の屑米をまわしていた。胡玉音は夫と二人で家畜のえさにしかならない屑米を夜遅くまでかかって臼で挽き、おいしい米豆腐づくりに精出した甲斐あって、王秋赦(祝土彬)から土地を買い店を新築するまでになった。ところが、政治工作班長に昇格した李国香が早速、この店に目をつけ、資本的ブルジョワジーの典型として店に乗り込んできた。そしてこのことが契機となって胡玉音は家も没収され、夫も殺されてしまった。1966年春。文革の嵐が吹き荒れて、状況は一段と厳しくなった。李国香までニセ左派として逮捕され、胡玉音は街きってのインテリでありながら右派の烙印を押され〈ウスノロ〉と呼ばれる秦書田とともに、さらに厳しい批判の対象にさらされていた。彼らに変わって無教養の王秋赦が党支部の書記に昇格し贅沢三昧の暮しをしていた。やがて李国香はコネを生かし復権し、胡玉音と秦書田は来る日も来る日も石畳を掃除するという処罰を課せられた。最初は口もきかなかった二人だが、胡玉音が秦書田の本当の気持を知るようになり、二人は自然にひかれ合うようになった。そして胡玉音が妊娠。秦書田が王秋赦に二人の結婚のゆるしを願い出るが裁判所から秦書田は10年の刑、胡玉音には3年の刑がいい渡たされてしまった。1979年、悪夢のような文革がようやく終り、胡玉音は没収された家などを返され、秦書田も名誉を回復されて芙蓉鎮に帰されることになった。刑の途中で胡玉音が生んだ長男・谷軍と彼女の待つ家に戻った秦書田は、家族で再び米豆腐作りに精を出すようになり、昔のように店は大繁盛した。ぬけ目のない李国香は省の機関に栄転し、革命のお先棒をかついできた王秋赦は気がふれてしまった。
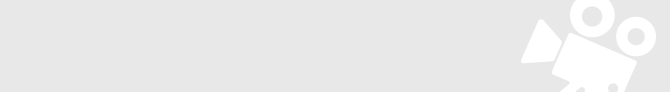
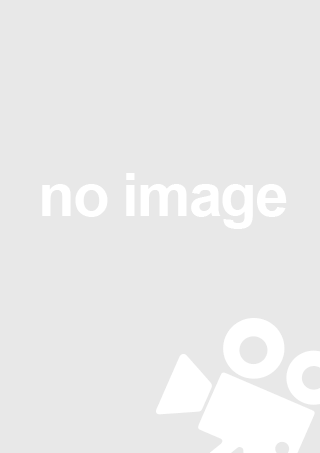


 紅いコーリャン
紅いコーリャン 三国志英傑伝 関羽
三国志英傑伝 関羽 ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 万引き家族
万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に
この世界の片隅に セッション
セッション ダンケルク
ダンケルク







