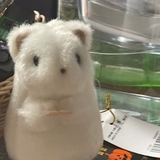オズの魔法使のレビュー・感想・評価
全58件中、1~20件目を表示
映像が素晴らしい古典ミュージカルの傑作
正直、観たことはあるんだろうけど、全く覚えていないので感覚的には初見
家族に仕事の邪魔だと無下にされ飼い犬と一緒に家出したドロシーがオズの国に迷い込み出会った仲間、考える脳が欲しい案山子、心が欲しいブリキの人形、勇気が欲しいライオンと一緒にエメラルド・シティのオズの魔法使を訪ねる旅をする物語
70年前に作られたとは思えない秀逸なプロットと飽きさせないテンポのいい演出、そして最大の魅力は圧巻の映像美、現代とおとぎの国をモノクロとカラーで分けるのが当時としてはとても斬新だったんではないでしょうか
そしてモノクロパートもただの白黒じゃなくてセピアカラーの様な品のある色合いが素晴らしかったです
児童文学のファンタジー・ミュージカルの歴史遺産としてのハリウッド映画
「風と共に去りぬ」のヴィクター・フレミング(1889年~1949年)が同じ年の1939年に監督した児童文学のファンタジー・ミュージカル映画。アメリカの映画団体AFIが2007年に選出したアメリカ映画100選では第10位に選ばれていて、いかにアメリカの映画人に愛されているかが分かります。フレミング監督の連続して制作された第二次世界大戦前の2作品がベストテン内で一番古く、アメリカ人のハリウッド映画黄金時代への郷愁もあると思われます。ライマン・フランク・ボーム(1856年~1919年)が1900年に発表した『The Wonderful Wizard of Oz/オズの魔法使い』の原作に若干の脚色を施していて、制作が「哀愁」「心の旅路」のマーヴィン・ルロイ監督(1900年~1987年)という異色さ。音楽はトーキー初期からMGM映画に携わったハーバート・ストサート(1885年~1949年)で、アカデミー賞の作曲賞を受賞していますが、この本格的に制作された子供向けファンタジー映画が好まれてきた理由の一つに、『虹の彼方に/Over the Rainbow』の主題歌があります。日本人で映画を知らなくとも、この名曲には馴染みがあるでしょう。作詞のE.Y.ハーバーグと作曲のハロルド・アーレンがアカデミー賞の歌曲賞を受賞し、主演のジュディ・ガーランド(1922年~1969年)も特別賞の栄誉を受けています。撮影が「雨に唄えば」(1952年)の名匠ハロルド・ロッソン(1895年~1988年)というサイレント期から活躍した超ベテランのカメラマン。1958年に一度引退した後に、ハワード・ホークス監督に請われて「エルドラド」(1966年)をキャリアの最後にしたエピソードからは、名監督に慕われていたことが分かります。3年前の1936年にカラー映像を経験したロッソンのテクニカラーの色彩の鮮やかさは、86年の時を経ても色褪せずファンタジー映画として充分に鑑賞できます。
ストーリーは子供向けで単純ですが、地上の登場人物が主人公ドロシー・ゲイルの夢の世界に姿形を変えて、“魔法の国オズ”に登場するところが面白く構成されています。愛犬トトを虐待するミス・ガルチが全身緑色の“西の悪い魔女”として現れますが、竜巻に遭ったエムおばさんとヘンリーおじさんの家の窓から自転車をこぐミス・ガルチが見えるところが可笑しい。農場に働くハンク、ヒッコリー、ジークの3人が、それぞれの知恵のない案山子、心を持たないブリキの木こり、そして勇気のないライオンになってドロシーの冒険の旅のお供をする設定がいい。カンザスに戻りたい願いで“オズの大魔法使い”のいるエメラルド・シティに向かい、その道中で邪魔をする“西の悪い魔女”を退治して、いざ“オズの大魔法使い”に会えたと思ったら偽物というギャグが、子供の夢にしては現実的で意外性があり笑ってしまいます。ここで素晴らしいのは、3人の願い事が困難な道中の課程で既に身についていることの成長を内包していることでした。知恵を絞ること、人に優しく接すること、そして怯えず勇気を持って立ち向かうことを経験することの教えになっています。これを日本で言えば、心技体に通じるものがあります。それでもアメリカ映画らしいのは、その証として正体のバレた似非魔法使いが、それぞれに大学の卒業証書、心の振動になぞられた時計、勲章を授けるところでした。
主人公ドロシー・ゲイルに16歳のジュデイ・ガーランド。最初は天才子役として絶大な人気を誇ったシャーリー・テンプルが予定され、映画会社のトラブルからガーランドと「オーケストラの少女」(1937年)のディアナ・ダービンに絞られたとあります。ダービンもドロシーを演じられたでしょう。案山子のレイ・ボルジャー(1904年~1987年)は、MGMミュージカルの「巨星ジーグフェルド」(1936年)の出演経験があり、ブリキ男のジャック・ヘイリー(1897年~1979年)やライオンのバート・ラー(1895年~1967年)と同じく舞台経験豊富で実力のある俳優陣でした。キャスティングも嵌っていたと思います。個人的にはバート・ラーのコメディ演技が楽しめました。“北の良い魔女”グリンダを演じたビリー・バーク(1884年~1970年)は、この時54歳には見えない美しさと品の良さ。ブロードウェイ・レビューに歴史を刻む興行王フローレンツ・ジーグフェルド・ジュニア(1867年~1932年)の奥さんだった人で、1929年の世界恐慌で破産し、女優復帰した人でした。天国から地獄を経験した経歴を知ると、この役の厚みを感じます。ミス・ガルチも“西の悪い魔女”も好演したマーガレット・ハミルトン(1902年~1985年)は長きに渡り脇役を演じた女優さん。「暗黒街の弾痕」(1937年)と「牛泥棒」(1943年)を観ていますが、残念ながら記憶に残っていません。“オズの大魔法使い”のフランク・モーガン(1890年~1949年)も、「巨星ジーグフェルド」に出演していますが、改めてこのアカデミー賞受賞の「巨星ジーグフェルド」がカラーで制作されていたら、今日もっと話題に上がっていたと思います。(因みに世界初のテクニカラー実写長編映画は「虚栄の市」(1935年)ということです)このモーガンも適役でした。ヘンリーおじさんのチャールズ・グレープウィン(1869年~1956年)は、ジョン・フォードの名作「怒りの葡萄」(1940年)で主人公のお祖父さん役を好演しています。エムおばさん役のクララ・ブランディック(1876年~1962年)も端役で数多くの作品に出演し、この役で映画史に遺る女優さんです。そして、忘れていけないのは、トト役の名犬テリー嬢(1933年~1945年)の名演でした。ハリウッド映画は古くから調教された動物の扱いが巧く、観客を楽しませていますが、このテリー嬢も健気で素晴らしい。“オズの大魔法使い”のカーテンを咥えて開けるところがいい。
1939年のテクニカラー映画制作の裏話を知ると、相当に過酷で厳しいものがあったようです。それを考えると手放しでは絶賛できませんが、アメリカ映画史に遺る作品に仕上げた映画人の努力と苦労を記憶に留めることで、いくらか許して貰えないかと思ってしまいます。サイレント初期から活躍した1889年生まれのチャールズ・チャップリンより古い生まれの舞台俳優含めた、実力ある人たちの演技をカラーで観ることが出来る貴重さが、何より尊いのです。
いざ "虹の彼方へ"‼️
今作に登場する正義の魔女と、悪の魔女の前日譚である「ウィキッド ふたりの魔女」が大評判でもおなじみ、ファンタジー映画の超名作‼️愛犬トトとともに、竜巻に吹き飛ばされ、歌うマンチキン(小人)や空飛ぶ猿がうじゃうじゃ生息、そして究極のヴィランである "西の魔女" が支配する魔法の国オズに迷い込んだ家出娘のドロシー。「脳ミソ無しのカカシ」、「心無しのブリキ男」、「勇気無しのライオン」といった仲間たちと一緒に、黄色いレンガの道をたどって、それぞれが抱える悩みを解決してくれるという「オズの魔法使い」(実はペテン師)が住むエメラルド・シティへと旅立つ・・・‼️ドロシーが家族と共に暮らすカンザスのシーンはモノクロ‼️そして家ごと竜巻で吹き飛ばされたドロシーがドアを開けるとカラー(=総天然色)の幻想の世界が広がる‼️このモノクロからカラーへの画面転換にワクワクさせられる‼️観た者誰もがすぐにドロシーと一緒に "虹の彼方に" あるオズにぶっ飛べる作品ですね‼️ホントに素晴らしい‼️今作はスんゴいスペクタクル作品であり、楽しい楽しいミュージカルであり、そしてエバーグリーンのファンタジーでもあります‼️マンチキンの国の色とりどりのカラー画面は、今観てもホントに美しい‼️エメラルドの都を舞台にしたスペクタクル、カカシとブリキ男、ライオンがドロシーを助けに行くシーンなんて、「白雪姫」の七人の小人たちみたいでホントに胸ワクワクするし、空飛ぶ猿は、これぞ「猿の惑星」とも呼べる面白さ‼️夢見ることの大切さを歌った「オーバー・ザ・レインボウ」も超名曲だし、エルトン・ジョンの名盤のタイトルの由来ともなった「黄色いレンガの道をたどって」、そしてドロシーら四人で歌う「オズの魔法使いに会いに行こう」といった楽曲たちもホントに大好きですね‼️麗しのジュディ・ガーランドら、完璧なキャストたちによる完璧なパフォーマンス‼️そして「ツイスター」の方がショボく見える竜巻の描写の凄まじさ‼️幕の裏にいる「オズの魔法使い」のキャラも、「ウィキッド ふたりの魔女」の後だと余計おかしい‼️ただ、やはり今作のキモはその物語‼️ "虹の彼方に" ユートピアや理想郷を求めても幸福はずっと身近なところ(家族)にあって、誰もが知能も、心も、勇気だって自分の中に見出せるということを改めて教えてくれる映画史に残る名作‼️それがこの「オズの魔法使い」なのです‼️
色彩の魔法
4Kで再見しました。テクニカラーの黎明期に作られた作品で、何よりもまず「色彩の映画」として印象に残ります。モノクロのカンザスから一転して、オズの国に入った瞬間に広がる鮮やかな色の世界。まるで「これが新時代の映画だ」と宣言するかのように、色そのものの存在感を楽しませてくれます。心理的な色彩演出がまだ確立していない時代だからこそ、単純に“見せるための色”がここまで力強く働いています。
物語は、心・知恵・勇気を欠いた仲間たちとともに旅を続けるドロシーが、実はすでにそれらを内に備えていたことに気づくまでの過程を描いています。外の世界を冒険するように見えて、実は「自分の中にすでにあった力を再発見する」物語です。
「魔法使いオズ」が実は空虚な存在だったという展開も、外的権威よりも自己の内なる可能性を信じる寓話として響きます。
ラストのセリフ——「もしまた心の望むものを探すときがあっても、自分の庭より遠くを探しはしないわ」——に、この映画のテーマが凝縮されています。夢のような世界を経て、現実を再び肯定する。子どものための物語でありながら、大人が観ても胸に残る普遍的な作品です。
色彩が映画という芸術に与えた“最初の魔法”を、今あらためて実感できました。
鑑賞方法: BS4K
評価: 90点
メルヘンがあっていいストーリー
CSで録画視聴。
作品は聞いたことがあったが、観たことがなくやっと観る事ができた。
よくあるストーリーだが、改めて観るとメルヘンがあっていいなと感じた。
最後はもちろん現実に戻るのだが、こういうストーリーは大人になっても
改めていいなと感じた。作品としてもよくできていた。
見応えのある映像と すばらしい音楽
少女ドロシーと犬のトト...主人公に ふさわしい。
黄色のレンガ道...主人公に敷かれたレール。
頭の中がカラッポのカカシ...劣等感を抱いている生産者のよう。
心がないブリキの木こり...知能だけはあるAIロボットのよう。
臆病なライオン...優しくて大人しい偉い立場の人のよう。
肌が緑色の西の魔女...箒に跨って飛べてカッコイイけど怖い。
その奴隷の飛ぶ猿...キメラ的な怪物のような、堕天使のような。
ドロシーを救うグリンダ...その存在は 魔女に対するイメージすら救う。
エメラルド・シティ...伝説の大魔法使い オズがいる。
見応えのある映像と すばらしい音楽で魅せられた。
世の中に置き換えて難しく考えても 面白い。
当時の最新が詰まった作品
茶色がかった日常の世界から、カラフルな魔法の世界に切り替わる演出が素敵です。
昔の作品ですが、ファンタジーな世界観に引き込まれました。
当時の最先端であろう合成技術、ミニチュア撮影、特殊メイク、デザイン、美術。
今は何でもCGで叶ってしまいますが、人の知恵を絞って作り出された見せ方が魅力的です。
いい魔法使いは、良い人なのかよく分からないキャラクターですね。
最初の20分間の特撮に感心する。そして毛がボサボサの尻尾フリフリの...
最初の20分間の特撮に感心する。そして毛がボサボサの尻尾フリフリの子犬トトの可愛さに打ちのめされる。昔に観た時と印象が変わった様な気がする。久しぶり過ぎて曖昧だが、昔は「特殊メイクがチープなのは仕方ない」だったが今は「特殊メイクが中々凄い」と思った。
当時カラーの映画はほとんど無かったらしく、映画館で見た人達は相当驚いたんじゃないだろうか?最初の20分間の特撮だけでも凄いのに。
農場のおじさん3人のハンクとヒッコリーとジークがそれぞれ一人二役で案山子、ブリキ男、ライオンを演じて ミス・ガルチと西の悪い魔女も同じ女優さんで、一人四役がオズの魔法使い、占い師マーヴェル、御者、門番を演じる。
最初のトルネードの特撮はファンタスティック!
プラグマティック
虹の向こうには何も無いし、全ては人為である。勲章をつければ勇気が出るし、ディプロマをもらえば賢くなるし、ハートの時計をつければ心を持てる。ホーム以外にいい場所なんてないんだよっ!!/それはそれとして、ライオンがかわいい。誰もしっぽは引っ張ってないし、羊さんも怖くないよ。
タイムカプセル
現在ではパブリックドメインとなるほどに古い作品。
児童文学の映像化作品であり、1939年の作品であることを考えれば目が覚めるような摩訶不思議映像力がある作品。
物語の途中でセピアから抜け出したカラーの世界は鮮やかで魅力的な世界だった。
ピンク色になった馬の存在感がすごくて好きだった思い出。(着色の際に色が無かったからピンクにしたとか聞いた気がする…)
これを子供の頃に見れたことはひとつの幸運だと思う。
と、個人的には高評価な映画ではあるのだけど、この作品のキモがおとぎ話と映像的なギミックであるため、現在の子供の視聴に耐えられるかと言えば難しいところ。
どんな体験でも時代・文化・自分の年齢など様々なものが複合しているものだと思うので、この作品は今となってはかつての子供がアルバムやタイムカプセルのように楽しむ作品になっているんじゃないかと思う次第。
ちょっとサルに襲われるシーンとか、魔女が溶けるシーンとか子供心に怖かった思い出。
あと、カカシとブリキがちょっと不気味。
over the rainbowよい
Somewhere over the rainbow♪
子供の頃に見ておきたい作品🌟
丸の内ピカデリーDolby cinema🎦
先日の『グランツーリスモ』で味をしめたリクライニング最前列シートで💕
ちょうど先日ふと「あれ?あたしって実は“オズの魔法使い”のストーリーちゃんと知らないかも」と気付き、原作を読むのか子供向け絵本で済ますのかどーしよっかなー、と思ってたところ。『ジュディ 虹の彼方に』観た時もジュディ・ガーランドをよく知らないからそんなに刺さらなかったのも残念だった。
だから今回はめちゃ楽しみにしてた😊そもそもなんで上映してるのかも謎💦でもこんな機会滅多にないから素直に嬉しい✨✨✨1939年上映って84年も前の映画とは思えない‼️そりゃセットはかなりチャッチイよ?映画のセットというよりかは『おかあさんと一緒』のセットみたいな子供騙し感アリアリ。それでも色彩豊かで夢がギッシリ詰まってる感じは十分伝わる💕現実世界はセピアで、魔法の国(なのか?)にたどり着いた後はカラーで表現されるそのコントラストも素敵😊
カカシとブリキとライオンがみんな牧場でドロシーを常に気に掛けてくれてるお兄さん達だってのもまた良い❤ ❤ ❤
ドロシーも(昔の映画特有のオーバーリアクション演技はまぁ置いといて)とにかく超キュート💜そしてトトわんちゃんもさらに輪をかけてカワユス🐶
そしてアレコレ思っても身近にある日常を大事にすることの大切さを教えてくれる素敵なお話✨✨✨
ほっこり出来ました♪ありがとう😊✌️
只々素晴らしい舞台芸術としての映画
内容は、童話オズの魔法使いを映画化した作品。孤独な少女が夢の国に行く事を望み行き着いた夢の中で、仲間達と出逢い其々の幸せについて考えて願いを叶える物語。好きな台詞は『おかしいわ!昔から知っている様な気がする?!』色の無い灰色の国から来た主人公がオズの世界で一人語りする台詞。微妙な伏線が舞台っぽくて良かったです。印象的な場面は、オズの世界観で皆んなが出迎えるパレードの迫力には圧巻です。豪華すぎてアメリカの景気回復の早さに驚きました。作り手の衣装や細部まで拘ったフォーメーションダンスには作り手の意気込みを感じる素晴らしい作品です。印象的な音楽は、有名すぎるover the 🌈です。初主演作品のジュディーガーランドの下手上手い慣れない感じか何とも味ありました。正に別名・近所の女の子だけあります。人造国家🇺🇸としての創世神話的な位置付けのある作品は、🇺🇸としての戦争や人種や格差や外交様々な問題を民主的に解決しようとする苦悩が暗喩されていて面白い。この作品を観るにあたり、NHKのバタフライエフェクト『ハリウッド夢と狂気の映画の都』を見てしまい。この映画に関する見方が変わってしまった。ジュディーガーランドの数奇な運命。最後のナレーションと言葉が印象的でした。MGM解雇後も薬物中毒や自殺未遂を乗り越えながら最後までハリウッドで生き続けた。ハリウッドという怪物に全てを捧げたジュディーの言葉。『何処へ行こうと何をしようとハリウッドから離れられないのです。(中略)もし、もう一度やれと言われたら、同じ選択同じ間違いを犯していたでしょう。それが生きると言う事だから』最後まで、キャッチコピーgirl next door近所の女の子を公私共に演じたジュディーガーランド。この映画の最後にある様に『我が家が一番』と自分に言い聞かせて生きた人生に寂寥感・諦観・優越感も覚える考える所も多い作品でした。ドロシー役ジュディーガーランド1969/6/27享年47死因・睡眠薬の過剰摂取。
物語と美術・合成の世界に迷い込み、驚いて、楽しんで、感激した。ミュージカル好きになる基本的映画。
普通に凄い映画
幼少の時にテレビ東京で見た記憶があり、大人になってからタイトルもストーリーも思い出せないまま
ただ、なんだか凄い映画だった事だけ覚えており
数年前にやっと見つけられた作品
今のハリウッドの演技とは真逆の舞台劇の要素が強い作品だが主人公が非常に愛嬌があり歌もダンスも素晴らしく出てくる役者全てが芸達者である
見る楽しさに特化してるので子供向けではあるが、技で作られているので大人も充分見れるものになってます。
CGの無い時代の限界はあるがセットの作りも素晴らしく、世界観を崩すことなく面白いお話が続いていく軽快さがある。
USのアニメやドラマ等でも、オズは何度も元ネタとして出てきていたので アメリカ人からすると
古い映画のクラシック的な位置付けなのだろうか?
リマスターされて映像的には現代に引けを取らないバージョンが出てるので、アナログの特撮と人の手だけで作った映画劇として一度は観ておいた方が感性や視野が広がる気がします。
勉強抜きにしても普通に面白いです
全58件中、1~20件目を表示