ネタバレ! クリックして本文を読む
とはいえ、この映画が遺作ではない。生活態度を変えたのかな?
キュープラー・ロスさんの説く”死の受容”が、劇中映画の主人公を通して語られる。ギャグにされて笑い飛ばされている。自虐。
ランクさん演じるアンジェリークにかぶさって、人工呼吸器をつけて病床にいるジョーが映される。アンジェリークは死の天使なのだそうだ(DVDのコメンタリーから)。初めから、死を予感させる演出。
死神でもあると同時に、DVDのコメンタリーによると、ジョーが唯一本音を話せる相手なのだそうだ。
ショービジネス界の頂点に立った監督。その自叙伝。
朝目覚めの時点から覚せい剤でテンションを上げ、不安からくるイライラをごまかすための煙草を手放せない(口から外せない)。決して、覚せい剤や煙草を味わっているようには見えない。
映画の中でも、「いつでも自分の代わりはいる」「頂点に立ったとしても、失敗したり、休んだりすれば、すぐに追放される」という恐怖が語られる。
実際に映画の中でも、ジョーの手術とショーの金勘定のシーンが、交互に映し出され、代役に打診するシーンも出てくる。
なんて厳しい世界なのか。
そんなジョーがアイディアに詰まると頼るのが、元妻のオードリー。DVDのコメンタリーによると、実際に監督と別居妻の関係はこんなだったそうだ。
だが、監督の脚色なのか、映画の元妻は、女性として見てもらいたい、家族として大切にしてもらいたい、自分はともかく、娘との約束は守ってほしいという、単なる相談役として扱われたくない思いも描かれる。演じられるパーマーさんのあの大きな目に見つめられると、鑑賞している私でさえ、タジタジしてしまう。
そして、そんな興奮を発散させるため、不安を紛らわせるために必要とするのかと思ってしまうベッドイン。
同棲相手だけにしておけばよいものの…。
と、ジョー自身は奔放なくせして、同棲相手であるケイトのことは縛るって、なんとわがままな。でも、ケイトもそうされることを望んでいたりする。
ケイト演じるラインキングさんは、ダンサーとしても第一人者で、この映画の中でも抜きん出るパフォーマンスを見せてくれるが、実際に監督とつきあっていたこともあったとか。それゆえに、”わざわざ”この役を得るためにオーディションを受けさせたとか。DVDのコメンタリーであるシャイダ―氏は「フォッシー氏はそういう残酷な面もある」とおっしゃっていた。
ラインキングさんはどんな気持ちで演じられていたのだろうか。
娘ミシェルとの関係は理想的。自身ダンサーを志していて、著名な振付師である父ジョーを敬愛している設定。母とも良い関係だが、同棲相手とも良い関係で、ジョーとケイトの結婚を望んでいたりする。
演じたフォルディさんがかわいい。ケイトとのダンスも、ケイトが圧巻のパフォーマンスを見せる横で、一生懸命、年齢的には上手いパフォーマンスで、ケイトについている様がほのぼのとする。理想的すぎる娘だが、フォルディさんが演じられると、有りかもしれないなんて思ってしまう。
他、プロデューサーたちや、練習の時の伴奏者(曲の作曲家?音楽監督?)などが出てくるが、制作現場を知らない私には???。
「頭の中はセックス、セックス、セックス」と嘆く人はどんな関係?
振り付け助手をしている女性は、舞台には立たないの?あくまで”先生”なのか。
途中までは、頭をくるくるしながら、鑑賞。映画をゆったり味わう余裕もない。
前半は、オーディションに始まって、新しいダンスを作り上げ、プロデューサーたちにお披露目するまで。
性行為を表現したと思われるダンスもある。異性愛・同性愛・ストリップや、乱交のような様。「家族とは見られない」。確かに色っぽく、エロチックなのだが、私にはどちらかと言うと、ダンサーたちの身体能力に目を見張ってしまう。その体勢から起き上がれるのかとか、その体勢を支えられるのかとか…。体を合わせていても、微妙に触れ合っていない(お互いに触れ合って支えあっていない)その動き。そして、そのダンスの終わりが、まるでホラー。生首が並んだのかと思ってしまった。どういう意味付けで、こういう展開にしたのだろうか。
ここにも、迫りくる死の影を入れたかったのか。
そして読み合わせのシーンの演出の見事さ。
ジョーのネガティブな思いと、周りの人々の馬鹿笑いの対比。
そんな中で元妻オードリーだけは、相変わらず、大きな目で、ジョーを見つめる。オードリーの、決して称賛していない、真剣な訴えのこもった目で。
そこからの、病気との付き合い方。
バカ騒ぎ。ジョー自身の存在を製作者たちへアピールするため?死にゆく恐怖への回避?
TVで見るショー。有名人を紹介する実在する番組を取り入れたとDVDのコメンタリーから。
実際に、ベッドから逃走もする。その逃避行もジョーならではの道筋。
妄想の中での、元妻・同棲相手・娘、その他大勢からのアピール。
そして、危篤状況での「バイバイ、マイライフ…」上記のショーでのジョーの紹介の仕方。
監督の自叙伝ではあるが、ジョーの役作りには、シャイダーさんに「こんな時どうする」と意見を求めたとか。二人で、実際の趣味等も語り合い、映画を通じて友達になったと、DVDのコメンタリーでシャイダーさんがおっしゃっていた。シャイダーさんは監督に寄せ、それでいて、シャイダーさんの感覚も入り交じったジョー。
そんなシャイダーさんが「バイバイ、マイライフ…」について、「(監督は)死の裏側を知っていたのではないか。だから、あれだけ、美化したのではないか」とおっしゃっていたのが、忘れられない。
「バイバイ、マイライフ…」で盛り上がったまま、エンドロールに入ってもいいのに、わざわざ、死神の元へ行くジョーを、死体袋のチャックが閉まるシーンを挿入する。現実に戻って、区切りをつけたかったのか。
驕りにもみえる自負心。かと思うとの自虐。それを振り切るかのような美化。そして与えられる赦し。
死を自覚して、自分自身を見つめ、興行できるように仕立てた作品。
私の好きな『8 1/2』に影響された映画とも聞く。
アイディアの危機感、女性遍歴、そして、『8 1/2』では製作映画の中止、この映画ではジョーの死と、エピソードも似ている。現実と妄想が入り交じるところも似ている。
けれど、ユーモアの感覚が違う。ふんわりとした雰囲気が違う。
何より、圧巻のダンスパフォーマンスが、うっとりするというより、グロテスクで、ダンスを楽しむというより、各ダンサーの身体能力にノックダウンされてしまい、私的には楽しめない。
映画としては、そう何回も見たいものではないのに、「バイバイ、マイライフ…」だけは、頭の中でリフレインする。
私自身も、自分の人生を振り返る時期に来たということか。
(引用した言葉は、思い出し引用。間違っていたらごめんなさい)






 ジョーズ
ジョーズ トッツィー
トッツィー ジョーズ2
ジョーズ2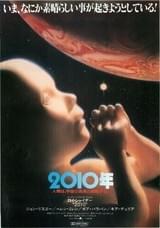 2010年
2010年 郵便配達は二度ベルを鳴らす(1981)
郵便配達は二度ベルを鳴らす(1981) キングコング
キングコング アメリカ、家族のいる風景
アメリカ、家族のいる風景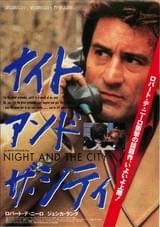 ナイト・アンド・ザ・シティ
ナイト・アンド・ザ・シティ ロンリー・ハート
ロンリー・ハート ジョーカー
ジョーカー











