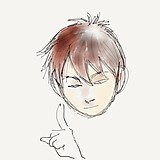砂の器のレビュー・感想・評価
全168件中、81~100件目を表示
善意は時に残酷、でもそれもまた宿命かもしれない
遅まきながら、鑑賞。テーマはハンセン病の差別、というぼんやりとしたイメージを持っていましたが、自分の全く的外れな思い込みを反省しました。
もっと大きなテーマです。人間とは、どういう生き物なのか。宿命とは何か。愛情や幸せをみんな欲しがるけれど、どれだけわかって言うのか。優生思想はいまも世の中を蝕み続ける。まず自分を見つめよ、と促されているような気がしました。
演出と役者さんの素晴らしさ、セリフなく眼で全てを物語れる子役主人公。彼の存在なくしては、成立しない作品です。映画とは何かをも教えてくれる、普遍的一本。
運命の分岐点となる田舎の巡査(緒形拳)が、わたしは印象に残りました。誰もが認める仏様のような善人。しかし社会的つまはじきの親子を救おうとした善意によって、この親子は永遠に引き裂かれてしまいます。善意とは、こんなにも危険なものなのか。今回わたしの心に刺さった棘。でも一生抜かないで、持ち続けようと思います。浮浪の親子が持っていた本物の愛情。彼らが社会的強者に勝る、最強にして唯一の財産を、巡査は悪意無き優しさで主人公から奪ってしまう。それは魂の殺人に匹敵する罪。
そして巡査は、二度も善意の罪をおかします。
失踪ののち別人となって音楽の道で自らを開花させた主人公を、なんの宿命か偶然見つけてしまい、またもや善意によって実父との再会を熱心に勧めるのです。
療養所に入った父親を、巡査は赤の他人なのに見捨てず何十年と文通します。引退した身でもなおこの親子を放っておかない。
でも。息子である主人公が、どんな思いでここまで歩いてきたか。
父と会うのを拒む、そこにどれだけ複雑な思いがあるのかを、巡査は真っ直ぐ純粋無垢で情熱のある人柄ゆえに、またもわからない。
巡査は善人夫婦、唯一欠けている点があるとしたら、子がいないことだけ、という設定です。とはいえ、全身全霊で誰にでも親身になれる、立派な人。
かたや、病という宿命を背負わされ、世間から疎まれ故郷を追われ、職もなにも持たない実父。持っているのは子だけ。巡査とは、まるで真逆。ですが実父の主人公への愛情は本物であり、人としてなにものにも変えられない、稀有な宝石をすでにこの親子は持っている。どれだけ立派な他者の善意も不要なほどの。とうてい質の違うものです。
観ていて、主人公だけでなく、この巡査もまた、砂の器なのだと気が付きました。
でもわたしは彼を責められない。巡査は巡査が持てるなりの最大級の自分を注いだ。この親子に。
それは主人公もわかっている。
しかし砂の器は、注がれたら崩れるほかありません。
たまたまお互いの人生の中で、好むと好まざるとに関わらず、ある役目を背負わされることになっている。それをまさしく宿命と呼ぶのでしょう。主人公は幼き時からずっと、あの射るような眼差しで、それを見つめ続けていたのではないか。
主人公がつくる音楽だけが、砂ではなく、本物の器として生まれました。父親の本物の愛情が、壊れない器となって、息子を通じて結実しました。しかしその昇華の恩恵に浴するのは、父ではなく、全く関係のない一般市民たちです。かつてこの親子に石を投げ蔑んだ、普通の市井の人間たちを喜ばせる役目を担う皮肉。これもまた、宿命。父子の間に流れる、強くて美しく、かなしい何かを、言葉ではなかなか言いあらわせない。
これを表現した松本清張という人があり、それを映画にできた監督や役者さんたち、凄いです。そしてこの物語をリアルにできるかどうか鍵を握っていたのは音楽でした。楽曲をつくった芥川さん達、あっぱれです。陳腐な曲ならきっと駄作になっていたはず。
人が人らしく生きていくために失ってはいけない何かを、徒労になるかもしれないが、形にして残そうとする。その魂に、人類の末席にいるわたしも震えました。
昭和の正統派ミステリー
2018年に「祈りの幕が下りる時」という映画が上映されましたが、レビューを見ると「砂の器」の名前が挙がっているのが散見されましたので今回見ることにしました。
なるほど確かに全体のストーリーの流れや設定は確かに多少似ている個所もありましたが、個人的には別の映画だと感じました。
正直な話、ミステリーとしての面白さ、衝撃度、緊張感、切なさは「祈りの幕が下りる時」のほうが上だと思います。
ただ、46年前の映画としては非常に完成度の高い映画であると思います。
特に重厚感のある演出、音楽は良かったと思いますし、昭和世代としては昔の風景(特に鉄道)はとても懐かしかったです。
渥美清がチョイ役で出演していますが、彼が出るシーンを見ると思わず「寅さん」と口走りそうになりますね。
避けることのできない運命
前半は殺人事件の被害者が死の直前に合っていた男と交わした会話で出たカメダという言葉を頼りに地道な操作を続ける刑事物。
わずかな手がかりから全国を飛び回り、少しずつ真相に近づく展開は面白かった。
ただ、新聞の電車から紙吹雪を投げる記事から犯人のシャツだと予測したのは流石に無理やりなんじゃないかなと思った。
後、刑事2人がなんかオーバーというか、なんか濃いなぁと思いつつ、違和感を少し感じた。
後半パートは、事件の概要と加賀の捨て去ったはずの過去がオーケストラの音楽に乗せて回想される。
前半と違いセリフが大幅に減ることで、御遍路のシーンに集中することができ、ハンセン病患者への非科学的な根拠による差別、偏見が痛いほど伝わってきた。それと同時に、辛い目にあっても2人で生き続ける親子の絆に魅せられた。
過去を捨て成功を手にしたかに見えたが、親子の宿命からは逃れられない。加賀という砂の器はコンサートでの拍手喝采で満たされたかも知れないが、すぐ崩れ去るのかなと思った。
最初と最後、「そんなことは決まっとる!」
もう何度見返したか忘れました。
そして、見れば見るほど、冒頭の早い段階における、
今西警部補(丹波哲郎)と吉村巡査(森田健作)の
何気ないやり取りが、粋だなあと感心するのです。
この秋田県のシーンは確かに「無駄足」なのですが、
彼ら二人の信頼関係やら捜査への熱意やらを
実は無駄なく表現しているのでないかと解釈してます。
それでもって映画の最後に、吉村巡査の問いかけに、
冷静な今西警部補が「そんなことは決まっとる!・・・・・・」と
感極まって返すシーンに繋がっていると思い込んでいます。
というよりもこのセリフのために、私は見てしまいます。
音楽がうるさい!!
前半は聞き込みと晩酌の繰り返しで淡々と進行してつまらないです。それまで台詞ばかりでしたが、中盤の長めの回想シーンは台詞が無く、悲壮感のあるピアノ曲がずっと流れていて、アニメの演出のようで狙いすぎだと思いました。しかも終わったと思ったらピアノ曲がまた来るので、しつこいです。後半はずっと経歴を読み上げるだけですが、前半は必要だったのかと思いました。全編にわたって丹波哲郎の台詞読みと前述の回想シーンから察しろという同調圧力があり、感情移入を強制される作風で、好みではありませんでした。ストーリー自体は雰囲気でごまかし、事件自体印象が薄く、難病設定をぶち込んでダシにして金を稼ぎたかったというだけの安直な映画だと思います。森田健作は千葉県知事となった現在と同じで役に立たず、いない方が良い感じです。
まさに名作
松本清張原作の刑事もの。原作未読。
橋本忍、山田洋次脚本。
丹波哲郎、森田健作、加藤剛、加藤嘉、緒形拳。
蒲田で殺人事件が起こる。
被害者の足取りを追う刑事たち。
東京蒲田
東北
山陰亀嵩
伊勢
北陸
大阪
愛人役、島田陽子さんの若い頃のお姿。
ハンセン病の患者と家族の悲しみ、苦しみ。
交響曲「宿命」
今だから見てほしい
古い映画だが、コロナが流行っている今だから見てほしい。特に後半から最後にかけて、捜査本部で丹波哲郎が主人公の生い立ちを語るシーン。施しをしようと出てきて、千代吉の顔を見るなり扉を閉めるおばさん、親子の姿を見るなりかくれる村人、二人に石を投げる子供たち(最近の大学正の事件を連想してしまった。)ハンセン病、水俣病、エイズ、そしてコロナ。人間の未知の病への恐怖心とそこから来る差別。今も昔も変わっていない。それがいかに人を苦しめ、人生を狂わせるか。緒形拳演じる巡査のような人が一人でも増えてほしいと願うばかりである。そして何より親子の絆は変わらない。すごく考えさせられる映画でした。ぜひ、いろいろな人に見てほしい映画です。
運命と宿命
乞食親子と旅路の綺麗な景色・巡査の白い制服との対比が印象的。
山陰まで来られたら、ぜひ奥出雲のロケ地を訪ねてください。
鳥取県米子市に住んでいます。
プライムビデオで先週見ました。
後半の丹波哲郎の語りとともに、親子の放浪のシーン、そして演奏のシーン、この3つが心に響き、テレビを観ながら涙を流してしまいました。
雨の降る中でお粥を親子で分け合うシーン、亀嵩地区の神社の下で、親子で隠れているところに緒形拳が語り掛けるシーン、SL列車汽笛と亀嵩駅で親子別れのシーン、涙、涙でした。
シーンの中に、大山をバックに特急列車が鉄橋を走行、松江市の宍道湖湖畔、国鉄宍道駅、国鉄木次線、出雲八代駅、亀嵩駅となじみのある場所が沢山登場しており、先週さっそく現地まで行ってきました。神社は当時と変わらず、亀嵩駅の別れのシーンは実際は出雲八代駅で撮影していたようですね。駅舎内に当時の写真が展示してありました。
八代駅のホームから線路を見ると、ランニング姿の幼き頃の和賀英和が走ってくるようでした。
悲しくも家族を思い遣る気持ちに打ち抜かれる作品
松本清張の原作小説は実家にあったが、タイトルと親が購入したことの時代錯誤的な勝手な解釈で読んでいなかった。
自分も親ほどの年齢になり、何気に見てみようかと思い立って、アマプラで鑑賞した。
ストーリーはサスペンスの流れで進んでいくが、40年以上も前の作品ということもあり、言葉ははっきり分からず、方言も強く、現代のハリウッド映画を吹き替えで見るようにスッキリ見ることはできない。
それでも俳優の演技が素晴らしく、魅入らせる力は十分にあったと思った。
前半の物語は、刑事が犯人像を延々探し求めるが、遅々として進まないように見せている。参考になるであろうことも、結構あっさり流されていたり。しかし、その前半は残り40分への単なるステップであったかのように、恐ろしい事実が明かされていく。
これは、松本清張の代表的なサスペンス物語ではなく、時代と人間の心を捉える大きなテーマを、見る人に訴えるものだと分かった。
そして、それは俳優の素晴らしい演技がいかにその訴えを切実なものとしているかを如実に伝えていると感じた。
とてもとても大きなテーマを心に打ち付けられることとなった。
圧巻の人間ドラマ
松本清張氏の私の印象:例えば、時刻表を駆使した緻密なプロットが醍醐味の推理小説作家。
だが、この映画を観ると、推理の方はかなり端折っているのだろう。前半はご都合主義にも見える展開。突っ込みどころはたくさんある。その中で、地道な捜査が手掛かりを得るところが救われる。
けれど、後半、一変。ぐいぐいと迫ってくる。
子役・春田君の目力。
加藤嘉氏演じる千代吉の子を思う心。人生に・人々に諦めきった表情。
そして加藤剛氏の演技。単なる成り上がりの栄誉にしがみついているではないと思わせる、演奏会での演技。子どもを認めないのも、単に自己都合ではなく、それまでの人生を、微妙な表情で滲み出す。
まさしく”宿命”。
そんな芸達者の渾身の演技が、日本各地の映像、そこで繰り広げられる出来事、音楽と、何倍にも相乗効果を醸し出し、胸に迫る。
惜しむらくは、観光化した遍路しか知らぬ世代に、千代吉親子の生活が想像できるのか?
途中で行き倒れになる人も多かったであろう。
ハンセン病。今では治療法が確立された病。
けれど、この映画の、千代吉のころは、治療法もわからず不治の病。
村に診療所なんてないもの。
家に、村に招き入れてはいかぬ病原菌。感染させぬことが最大の防御。
自分たちが食べていくのが精いっぱいな頃。盗まれることも防がねばならない。
それだけにひどかった差別。
そんな万感の思いが押し寄せてくる。
傑作である原作を遥かに凌駕する名作
諸事情で時間を持て余す中で視聴している旧作名画スタンダードから、本作を取り上げます。
周知のように日本映画史に残る名作であり、約半世紀を経ても色褪せない輝きがあります。
前半は、ある殺人事件を追跡する刑事ドラマで、日本各地を巡って被害者の身元と来歴を探る2時間ドラマ風展開です。身元不明の被害者の謎を少しずつ解いていく妙味はあるものの、物語に波乱もなくアクションもない通俗的なミステリーで終始しています。
犯人を匂わせる人物描写も断片的に挿入されますが、対峙するシーンもなく、従いカットは引きが多く、シーンが変わる際はテロップで表示され、何だか茫洋としてテンポも緩慢且つ淡白で、捉えどころのない、やや退屈な印象です。
但し、この前半の平板な漠然とした展開の端々に、幾つもの重要な伏線が仕掛けられていることが、後半の波瀾万丈の物語展開と、快刀乱麻を断つ結末に、哀しくも儚く収束されていき大いなる感動を生む、その手際良さと切れ味の鋭さは見事な名人芸です。
本作は、日本の社会派ミステリーの元祖ともいえる松本清張の小説を原作にしていますが、映画は原作とは全く似て非なるものといえます。
原作小説も傑作ですが、犯人を突き詰め追い込んでいくプロセスでの両者の葛藤が読者を惹きつけるものの、犯人の組立ても全く異なり、精巧なミステリー小説の域に留まると思います。
映画も、前半は原作をなぞるように謎解きミステリーが淡々と進みます。ただコンサートと捜査会議がシンクロして進む後半、次々と過去の衝撃的事実と悲劇が劇的に明らかにされ、観客に息を吐かせずヤマ場からヤマ場へと進み、その間はコンサートで奏でられる交響曲「宿命」だけの台詞無しで展開し、その上それらが日本の四季の移ろいを背景に余りにも美しく哀しく、且つ過酷で悲惨な、人間存在の不条理な生き様の壮絶な人間ドラマを見せられていきます。
後半こそ、本作の本来の醍醐味を満喫できる処であり、これはもう日本映画史に燦然と聳える脚本家・橋本忍氏の渾身のオリジナル作品といえるでしょう。
人が生きていくことの、何と厳しく辛いことか、何と強かで逞しいことか、そして何と哀しくて尊いものか。
数十年ぶりの観賞後は、痛切に犇々と胸に迫りくる感動に押しつぶされてしまいます。
不協和音
幼き「乞食」の子にとって、父親は唯一の家族であり友であり、その小さな世界の全てだった。引き離されるくらいなら、ともに飢えたりのたれ死んだりするほうが、彼にとっては幸福だったのだろう。
心優しき養父母も温かいご飯も、彼にとっては響かない。ただ父親と身を寄せ合って放浪したことだけが美しく鳴り響き、「宿命」として色濃く奏でられる。
その悲しき「宿命」には儚げで美しい女も、金と権力を持った女も、一切の卑しさも持たない養父も、そしてかつての彼があれほど求めていた本物の父親さえも入り込む余地など無く、音楽の中でのみ彼は彼として生きている。砂の器を満たそうとする水は、器自体を壊してしまう。
「乞食」の子の不満げな表情が、奈良美智の描く、不機嫌そうな子供そのもので、ただ駄々をこねているわけじゃない複雑な重みを感じた。それはおそらく子供にしか持ち得ない感情をはらんだ表情で、そこから今日の彼がつくられていったのだと思えた。
結婚や子供を持つことを頑なに拒んでいた彼は、誰よりもその子供の背負う「宿命」の重さを知っていたのだろう。
砂の器はどこまでいっても砂の器。不確かであやうく、保ち続けることなどできない。
人の耳に響いてはきえる音楽のように。
形を成さなくなった砂の器は、決して拭えぬ生い立ちの不協和音を超えて、その残像をたよりに何度も作り直され、時と共鳴していく。
名作
素晴らしい
重いテーマの映画です
午前10時の映画祭で。
初めて見たのは、公開当時、高校の映画鑑賞会ででした。
ラストで泣きすぎて、目と鼻が真っ赤なのに、
すぐ場内が明るくなり、めっちゃ恥ずかしかったです。
今回もしばらくハンカチを目に当てるはめになりました。
やはりラストの加藤嘉さんのえぐられるようなセリフ、重いですね。
もう会えなくなってしまった俳優さんも多く、45年という歳月を
あらためて感じてしまいました。
なにしろCGなんか使わなくても十分そのまま何もかも古く、w
東京の国鉄の高架を走る車両も、大学の研究室の建物も、
バブルで再開発される前の都心の風景が映し出されます。
映画って、こうしてみると時代の貴重な記録でもありますね。
ピアニストの和賀の部屋も、当時としてはすごく成金趣味の感じに仕立てたのかも
しれませんが、今見ると、なんかすごくアンティーク・・・。
婚約者の父親の政治家の応接間の和室の方が
よっぽどスマートにスッキリ見えました。
全体にやはり重厚にという製作者の意図が強すぎて、
チョット確かに要らないカットあり、台詞回しも大仰で、
今の監督ならこういう風には撮らないだろうなと思えるところが多かったです。
清張の作品は、あまり湿っぽくなく、むしろそっけないくらいの書き方をしているので、
何度かドラマ化されても、その度に入れ込みすぎるのでしょうか。
個人的には加藤健一さんが、ジープで案内する地元の巡査さん役で
出ていたのを発見出来て嬉しかったです。
全168件中、81~100件目を表示