家族
劇場公開日:1970年10月24日
解説
山田洋次が五年間温めつづけてきた構想を、日本列島縦断三千キロのロケと一年間という時間をかけて完成した、話題の超大作。脚本は「男はつらいよ 望郷篇」の山田洋次と宮崎晃、監督、撮影も同作の山田洋次と高羽哲夫がそれぞれ担当。
1970年製作/106分/日本
原題または英題:Where Spring Comes Late
配給:松竹
劇場公開日:1970年10月24日
あらすじ
長崎港から六海里、東シナ海の怒濤を真っ向に受けて長崎湾を抱く防潮提のように海上に浮かぶ伊王島。民子はこの島に生まれ、貧しい島を出て博多の中華料理店に勤めていた。二十歳の民子を、風見精一が強奪するように、島に連れ戻り、教会で結婚式を挙げた。十年の歳月が流れ、剛、早苗が生まれた。炭坑夫として、精一、力の兄弟を育てた父の源造も、今では孫たちのいい祖父だった。精一には若い頃から、猫の額ほどの島を出て、北海道の開拓集落に入植して、酪農中心の牧場主になるという夢があったが、自分の会社が潰れたことを機会に、北海道の開拓村に住む、友人亮太の来道の勧めに応じる決心をする。桜がつぼみ、菜の花が満開の伊王島の春四月、丘の上にポツンと立つ精一の家から早苗を背負った民子、剛の手を引く源造、荷物を両手に持った精一が波止場に向かった。長崎通いの連絡船が、ゆっくり岸を離れ、最後のテープが風をはらんで海に切れる。見送りの人たちが豆粒ほどになり視界から消えても、家族はそれぞれの思いをこめて故郷の島を瞶めつづけた。やがて博多行急行列車に乗り込む。車窓からの桜の花が美しい。汽車の旅は人間を日常生活から解放する。自由な感慨が過去、現在、未来にわたり、民子、精一、源造の胸中を去来する。生まれて始めての大旅行に、はしゃぎ廻る剛。北九州を過ぎ、列車は本土へ。右手に瀬戸内海、そして徳山の大コンビナートが見えてくる。福山駅に弟力が出迎えていた。苛酷な冬と開拓の労苦を老いた源造にだけは負わせたくないと思い、力の家に預ける予定だったが、狭い2DKではとても無理だった。寝苦しい夜が明け、家族五人はふたたび北海道へと旅立っていった。やがて新大阪駅に到着し、乗車する前の三時間を万博見物に当てることにした。しかし会場での大群集を見て、民子は呆然とし、疲労の余り卒倒しそうになる。結局入口だけで引返し、この旅の唯一の豪華版である新幹線に乗り込んだ。東京について早苗の容態が急変した。青森行の特急券をフイにして旅館に泊まるが、早苗のひきつけはますます激しくなり、やっと捜し当てた救急病院に馳け込む。だがすでに手遅れとなり早苗は死んでしまう。教会での葬儀が終え、上野での二日目が暮れようとしていた。なれない長旅の心労と愛児をなくした哀しみのために、民子、精一、源造の心は重く、暗かった。東北本線の沿線は、樹や草が枯れはてて、寒々とした風景だった。青函連絡船、室蘭本線、根室本線、そして銀世界の狩勝峠。いくつものトラブルを重ねながらも家族の旅はようやく終点の中標津に近づいていった。駅に着いた家族を出迎えたワゴンは開拓集落にと導いた。高校時代の親友、沢亮太との再会、ささやかな宴が張られた。翌朝、残雪の大平原と、遠く白くかすむ阿寒の山なみを見て、雄大、森閑、無人の一大パノラマに民子と精一は呆然と地平線を眺めあうばかりだった。夜更け、皆が寝しずまった頃、長旅の労苦がつのったためか、源造は眠るように生涯を終えた。早苗と源造の骨は根釧原野に埋葬された。やがて待ちこがれた六月が来た。果てしなく広がる牧草地は一面の新緑におおわれ、放牧の牛が草をはんでいる。民子も精一もすっかり陽焼けして健康そのものだった。名も知らぬ花が咲き乱れる丘の上には大小二つの十字架が立っていた。「ベルナルド風見源造」「マリア風見早苗」。






 PLAN 75
PLAN 75 男はつらいよ お帰り 寅さん
男はつらいよ お帰り 寅さん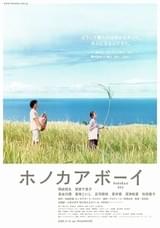 ホノカアボーイ
ホノカアボーイ 初恋~お父さん、チビがいなくなりました
初恋~お父さん、チビがいなくなりました 男はつらいよ
男はつらいよ ハーメルン
ハーメルン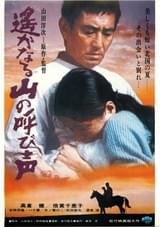 遙かなる山の呼び声
遙かなる山の呼び声 男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け
男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け 男はつらいよ 柴又慕情
男はつらいよ 柴又慕情 男はつらいよ 寅次郎相合い傘
男はつらいよ 寅次郎相合い傘








