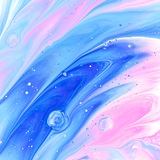硫黄島からの手紙のレビュー・感想・評価
全87件中、1~20件目を表示
いかにも日本的なもの
クリント・イーストウッド監督作品ということになっているが、「らしさ」は感じられない。『父親たちの星条旗』に、厭戦感や時代を生きた空気のようなものが込められていたのとは対照的だ。いかにも日本的な忖度が働いたように思える。戦った当事者同士が、この戦争を振り返った時に、両者にとって都合のいい映画なんて成立するわけがない。だったら、2本作っちゃおうなんていう、ありそうでなかった企画。
だからなのか、この映画は、『父親たちー』がないと成立しないのに、逆は無い。『父親たちー』は、映画として自立しているし、それ一本だけ見ても十分楽しめる。ところが、この映画は名前だけ借りて、ついでにもう一本撮っちゃったようにしか思えないのだ。興行的にも、クリント・イーストウッド作品としても、黙殺されていくとしか思えない。
日本軍主役の戦争映画では断トツの1位作品
日本人が作る戦争映画はお涙歌謡曲に合わせてセリフ回しが多い作品しかありません、
浪花節、義理と人情、愛とお涙、、、
本当にワンパターンです、大丈夫?日本映画?
この作品はそれはありません、
ちゃんと日本人が参加した「戦争」が描かれています。
ご存じプラトーンはバックミュージックも無しに淡々と戦争シーンが流れ、
見る側もリアルな戦場に連れて行かれて恐怖します、
これこそがリアルな戦争です、
先にも述べましたが、日本の監督が作る映画では無理と諦めていました。
この映画は日本軍がメインに描かれている戦争映画で唯一無二の良作品です、
監督はアメリカ人のクリントイーストウッド、
本当に素晴らしい作品を作ってくれました、
栗林中将が硫黄島で幕僚達と意見が合わなかった等もこの作品では描かれています、
栗林中将役の渡辺謙も素晴らしい演技と存在感、
ジャニーズ枠?でがっかりしていましたが、嵐の二宮君良い演技でした、
ちゃんと丸坊主にして演技もしっかりしていました。
これ、17年前位の映画なのに、、、
今の日本映画より全然素晴らしいです、
戦闘シーンでスローモーションになりバラード歌謡曲などかかりません、
淡々と戦闘シーンと緊迫感が伝わります。
監督のクリントイーストウッドは、もう一本「親父たちの星条旗」と言うアメリカ目線の硫黄島舞台の作品を同時期に作成していますので、同時にみるのをお勧めします。
日本人なら絶対に見るべき映画だと思いました。
圧倒的兵力の差
アメリカ人が作ったとは
思えない、日本軍を描いた映画である。クリントイーストウッドは素晴らしい。立場による違いを日本の映画にするとは。
しかし、2万人を越える日本兵がいたようには思えなかった。また、戦闘が1カ月以上?続いたようにも見えなかったのは
残念。
ただ、日本軍にもロケット砲のような兵器もあったことがわかる。きっと数多くあれば、活躍しただろうに。
この映画にあるように、司令官の命令を聞かない士官が多くいたのだろうか?
自分の考える戦い方と違うからと命令を無視すれば、統制が取れず負けるだろう。まあ、ここで勝つことはできない
のだけど。
中村獅童の伊藤中尉のあの後が出てこなかった。それと、西郷一等兵のその後も。
午後ロード録画視聴にて。
苦手な戦争映画だが、見る価値あり
信念と論理的思考をもつということ
死ぬまでに一度は、いや一生の早いうちに観ておきたいイーストウッドの名作
太平洋戦争内での硫黄島の戦いを描いた同監督の『父親たちの星条旗』と併せて語られることも多く、実際に続けて製作されている二作品である
演じるのが日本の俳優であるだけでなく、言語も日本語というのが非常に珍しい
海外の目を通して見た当時の日本軍の姿を描きながらも、どちらの側を讃えるわけではなく戦争そのものへの批判がまっすぐに伝わってくる。この辺りをきちんと感じ取るためにも『父親たちの星条旗』と併せて見ることを強くオススメしたい
新兵の西郷(二宮和也)と指揮官・栗林中将(渡辺謙)のW主演だが、個人的には栗林のことが強く印象に残っている
特攻・玉砕上等の軍の中でも論理的な思考を失わなかった栗林
しかし強い愛国心を持っていたことも事実で、自分の手の届く範囲で出来ることをやり抜いた人物として描かれている
信念と論理的思考をあわせ持つことがいかに大切か
そしてそんな人物がもっといたら、どう歴史が変わっていたのだろうと想像を巡らさずにはいられない
つらくも、いい映画、
硫黄島の戦いは、日本軍の持久戦が米軍に多大な犠牲を強いさせ、米国の...
映画の意義
DVDゲットシリーズ108円。 静かに、悲惨に、戦争はやはりダメだ...
歴史に残る名作
怖い
戦争映画を続けて観たんですが、この作品は正直怖いなと思いました。
戦争のリアリティなのか、死という描写が残酷すぎたからなのか…よく分からないけど。
昔プライベートライアンを観て同じ感覚になったのを思い出します。
外国人の監督の映画ということで、日本の映画とは違った凄みがありました。
これが本当にリアルな出来事なのかはわかりませんが、現代を生きる私にとっては戦争の悲惨さがあまりにもグロいカタチで見せられてる感じがして、途中で視聴をやめようかと思ったほどでした。
この時代の感覚として、天皇陛下や上官、日本という国に対しての忠誠心が絶対的なものとして描かれていることに対し、恐怖すら感じました。
それでも死への恐怖が大小あるにしても、上官にすら漏れなく描写されているのがまた恐怖心を植え付けられてる気がして、ちょっとメンタルやられました。
この作品は西郷視点の栗林閣下のストーリーなんだと解釈していますが、アメリカ軍にとっても親米かつ優秀な指揮官だからこそなのか、アメリカ人監督ならではのフィルターがかかっているような人物像のような気もします。
私自身付け焼き刃程度でしか知識はプラスしてませんが、この監督のような栗林中将へのリスペクトにも似た描写をしていることが、役を引き立ててて良かったです。
でもやはり戦争とは愚かなものだし、栗林中将も含めてですが、英雄なんていないしそう呼ぶのもおかしな事だと感じました。
本作とともに梯久美子著「散るぞ悲しき」を読むと万感こみ上げる
「地獄の中の地獄」であった硫黄島の闘い。
米軍人ならこの戦場で応召兵が多くを占め、精鋭部隊とは言い難かった日本軍人たちがいかに勇猛果敢な戦いぶりを見せたことを知らぬ者はいなかった。
「イオージマソルジャー」であると知ると、捕虜となった日本兵へ畏敬の念さえ見張りの米兵は見せたという。
本作の主人公は、帝国陸軍中将・栗林忠道。
映画の作中には直接的な描写は出てこないが、彼は陸軍中将という大変な高位の軍人でありながら、硫黄島に死を覚悟して赴任すると島内を毎日のように巡視して、栗林を見たことがない硫黄島兵士は少ないというくらいだったようである。2万以上の日本兵がここで闘い、そのほとんどがこの地で命を落としているが、彼らの「日本本土を守る」という決意は大変なものであったようだ。
栗林はヒューマニストであった。
島内に圧倒的に足りないのは飲み水と野菜。ある時、野菜がひと籠栗林のもとに届けられると、「将軍は目に涙、小刀で雀の餌ほどに細かく野菜を刻ませ、出来るだけ多くのものに分け与えられた。将軍自身は一口も召し上がらず、昭和の乃木将軍かと深い感銘を受けた」と「散るぞ悲しき」にはある。
監督のクリント・イーストウッドはかなりの年齢まで反日家であったようだが、栗林中将のような人物の人格を知り、だんだん考えを改められたようである。
イーストウッド氏曰く「戦争映画は人間性に焦点を当てて描かねばならない」とのことで、本作は日本人の心情をアメリカ人である彼がよくここまで描いてくれたと思うほど感動的なものである。
是非、この名作を多くの人にご覧いただきたい。また、原作と言ってよい内容の「散るぞ悲しき」は文庫化されているので、こちらも是非。
日本以外の世界を見てきた経験が、視野の広さに影響している
戦前の日本の軍人といえば、中村獅童演じる伊藤海軍大尉のように、部下を怒鳴り散らし無闇に玉砕したがる人間がステレオタイプだ。しかし栗林中将や西中佐のような、部下を大事にし、戦局を冷静に見れる人間もいることが分かる。この差が生まれるのは、栗林中将や西中佐がアメリカに居た経験が、彼らの考え方に大きな影響を及ぼしているからだろう。彼らは、当時のアメリカが日本よりも文明が発達していて豊かなのを目にしてきている。そしてアメリカ人にどのような人達がいるのかを、実際の交流を通じて知っている。インターネットも無く、交通手段も発達していない当時において、こういった経験の差が考え方に大きな影響を及ぼすことは想像がつく。
西中佐が、捕虜のアメリカ人サムの母親からの手紙を読み上げるシーンは切なくなる。戦場で戦う日本人もアメリカ人も、皆誰かが愛する子どもであり親である。彼らには人種の違い以外根本的な差は無い。それが戦争を理由に憎しみ合い殺し合う哀しさが、このエピソードに表れている。
栗林中将の考え方は、日本の軍人としての誇りを持ちつつ、できるだけ長く生き延びることにあるのが、彼の採る戦略や発言から分かる。洞窟を掘って立て籠もる戦略を立てたのも、危なくなったら部下に退却するように命じたのもそのためだ。アメリカ軍にギリギリまで抗い続けようとした。その時に考えられるベストを尽くす栗林中将の姿勢に、尊敬の念を抱いた。
大掛かりな大量殺人事件。被害者にも共犯者にもなってはいけない。
何を描きたかったのだろうか。
硫黄島での攻防戦。
連合艦隊も補給すらもあてにならない状況。
海軍と陸軍の隔たり。
アメリカに対しての理解のある将校と
鬼畜米英天皇万歳の兵士。
摺鉢山が徐々に陥落していくなかで
天皇万歳で自害。
いったい天皇ってなんだ?
これは現実でも思う。
この不景気の中NYに夫婦で移住。
国のお金を一切使ってないならいいが警護費用はどこから・・・
国の象徴?戦後真っ先に廃止されるべきだったのでは・・・
脱線しましたが。
傷ついた米兵を助けるよう指示を出す将校。
捕虜になるべく脱走した日本兵を
保護した後に上官を無視して殺害した米兵。
同じ思いを持った「人間」は確実にその場に存在していたのに
交わることが出来ない「戦争」と「人種」という壁。
この作品は「父親たちの星条旗」と併せて観ていただきたい。
考えさせられる作品でした。
他の戦争映画に比べたら迫力が見劣るように思える。 戦争映画に迫力を...
ウッド監督は戦争でも他の戦争ものとは違う。
戦争は人間の顔をしていない
戦争がなぜ不条理かといえば、そこでは述語がほとんど機能しないからだ。誰がどういう人間だとか、どういう出自を持っているかとか、そんなことは微塵も考慮されない。肌の色がどうとか、勲章の数がどうとかいった物理的な事実だけが絶対的権能を有している。
本作において頻発するコテコテのフラッシュバック描写は、軍人たちが皆それぞれに固有の過去を背負っていることを示す。単に郷愁や感傷を掻き立てるためではない。それらは戦火の中で否定され、焼け爛れ、やがて判別不能の灰燼となって中空に霧散する。彼らの想いはどこへも通じない。彼らの過去が饒舌に緻密に語られれば語られるほど、その絶望的なまでの不通性が強調される。戦争は人間の顔をしていない。
日本軍の描き方について、本作は安直なステレオタイプに陥っていないと感じた。特に、栗林中将と西郷一等兵の関係は「戦争映画」によくあるナショナリスティックな同胞意識とは一線を画していたように思う。
西郷はのっけから日本軍に不信感を抱いており「俺たちはどうせ死ぬんだ」というシニシズムに浸りきっている。それを見透かされてか上官から過酷な肉体労働を強いられていたところ、島に上陸したばかりの栗林の鶴の一声でその苦役を解かれる。
栗林は体罰やバンザイ突撃といった無意味な根性論的行動に対して懐疑的だ。窮状にあってもあくまで現実主義的に作戦を展開する。軍の中には彼の進歩的なやり方を「生温い」と非難する声も多かったが、西郷は次第に彼への尊敬の念を強めていく。
とはいえかつて駐在武官として欧米人との交流を深めてきたという栗林のキャリアを鑑みれば、彼の「進歩的」性格は、そのまま「欧米的」性格とも換言できる。そしてそこへ反日本軍的な西郷が憧憬の眼差しを送る。という図式は、結局のところ欧米的価値観を頂点とした史実の恣意的な読み換えに過ぎないのではないか。
この読みは安直だろう。栗林は「作戦を実行する」という物理的次元においては確かに欧米流の進歩的性格を有していたが、「戦争に臨む」という精神的次元においては、古臭く強固なナショナリズムに浸りきっていた。欧米の要人との会合で「それは君の信念か?それとも君の国の信念?」と尋ねられて「どちらも同じでしょう?」と返すシーンは印象的だ。彼は表層と深層で真逆の極を持つ人物だといえる。
また、西郷が栗林を慕うのは、彼の強靭なナショナリズムに思わず愛国心が萌したからではない。西郷は最後までバンザイを叫ばない。自決もしない。「日本軍」なるもののために命を捧げることを最後まで拒絶する。
彼はもっと素朴で人間的な恩義から栗林を慕っていたのだと私は考える。あらゆる述語が失効する戦争という空間において、なお優しく手を差し伸べてくれる栗林という存在、それは実際に見たことも触れたこともない「天皇」や「国家」よりもよっぽどアクチュアルに西郷の心を打った。彼はそんな栗林の個人的な優しさに対して個人的に報いるため、戦地へ赴くのだ。
栗林の遺体からコルトM1911を盗んだ米軍海兵に対して西郷が狂ったようにスコップを振り回すシーンは美しく切ない。西郷の命を顧みない恩義の発露に対し、米兵たちはうんざりしたような表情を浮かべる。極東の猿の考えは理解しかねる、といった具合に。彼らには西郷のごく個人的な怒りと悲しみは伝わらない。彼らは「日本軍」というフィルターを通じてしか日本人を見ることができない。
むろんそれは日本兵たちも同じだ。彼らは「鬼畜」と呼んで忌み嫌っていた米兵が、自分たちと同じように故郷を持ち、家族を持ち、優しさを持っていることを知って当惑していた。
両軍のギャップは永遠に埋まらない。戦争が終結しない限りは。
繰り返すようだが、戦争においては述語はほとんど機能しない。人が人を殺すためには、相手が人間であることを絶対に認めない必要があるだろうから。ナショナリズムとアドレナリンの美酒が効いているうちはそれでいい。極東の猿でも鬼畜米兵でも好き放題に殺しまくったらいい。
しかし酔いが覚めたとき、彼らはふと気が付くことになるだろう。己の撃った銃弾が、己の胸を貫いていることを。
全87件中、1~20件目を表示