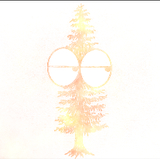2001年宇宙の旅のレビュー・感想・評価
全196件中、41~60件目を表示
ねむー
覚醒するとはこういうことか
色・色・色。色の洪水、ただただ、圧倒される。
そして放り出されたような、難解な場面。
光だらけの部屋、なのに調度はロココ調。なんで?魂の故郷はロココ形式?
時間空間の歪み? 3次元を超えた4次元の世界?
光の洪水の前の緊迫した、そして一転してスローな音声から突然、放り込まれる世界。
解釈を試みないと、自分自身が解体していくような。
自分という枠さえも超えた世界に放り込まれそうな危機感…。
とにかく、圧倒的な情報を一方的に浴びせられ、体験させられ、ただただ、受け取るほかない。
有無を言わさない、拒否することもできない。
ただ、その場で受け取るしかない。
こちらのキャパを問うこともなく…。
何が起こっているのか…?私に、宇宙に…。
理解なんてできない。
ただ体験させられるだけ。
感覚のみの世界。
統合失調症の幻覚の世界ってこういうもの?
人の理解を超えた世界ってこういうもの?
ただただ、その世界観に圧倒される。
心が、理性が、解放され、放出されるって、こういうこと?
そんな異次元を疑似体験させてくれた気分になれる映画です。
映像の完璧さは言うまでもなく、
クラッシック曲を使った優雅な世界との対比。
すべて計算づく?
こんな感覚の映画を、理詰めで作ってしまう監督。
どういう精神構造をしているのか。
ただただひれ伏すばかりです。
ニーチェの『ツァラトゥストラはかく語りき』の冒頭「神は死んだ」。
欧米諸国で神と言えば、キリスト教?聖書を元にして、唯一無二の教義を理解する世界。
そんな世界は終わり、新たな、自分なりのものを作りださなければいけないということか。
寝ているときにみる夢のような映画。
断片をつなぎ合わせて物語を紡いでみて自分なりの物語を作ると見えてくるものがある。
でも、時間が経って、以前とは違うアイテムに焦点を当てれば、また違う物語ができて、別のものが浮かび上がってくる。
完全癖の監督が作り上げた映像。細部にもどんな意味・仕掛けが隠されているのか。
音楽も監督のこだわり。何よりも監督の想いを雄弁に語っている選曲。
心地よいクラッシック。
不愉快な、羽音ととも聞こえる雑音のような合唱。
抑揚はないけれど、宇宙飛行士よりは低い温かみのあるHALの声。
何度も思い出して夢想して何度も楽しめる映画。
監督のしかけたミステリー。
想像力を喚起させられる映画とはこういう映画をいうのだと思う。
☆ ☆ ☆
【再鑑賞・再考・追記2025/9/3】
我々の向かう先
未来=我々が向う先を追及すると、原始に帰るということか…。
事の始まり。
解明されたかのような生命の歴史。
けれども、どうして受精卵は命を持ち成長するのか?
赤ん坊は、なぜ、周りの人の真似をすることを自然と始めるのか。まるでプログラミングされたかのように。
人間は、他の動物と違い、いろいろなものを使い、作り上げて壊してを繰り返すのか。
答えがあるようで答えは出ていない。
手塚治虫氏の漫画の中でも、他の作品でも繰り返されたフィクション。
人造人間、意思を持つコンピューターやロボット。
今すでに製品化されているAI、ペッパーやアトム・ロビは、まるで会話をしているかのような気分にさせてくれる。けれど…。
コンピューターによる殺人。
かえって、コンピューターの方が人を人と思っていないーただの一つの要素としてしかプログラミングされていないのだからー、人が人を殺すより、プログラミングされた命令を邪魔するバグとみなせばコンピューターの方が人を排除=抹殺しやすいのではないか。
それにもかかわらずのHALの人間臭さ。任務へのこだわり。死への恐怖。
生き残りをかけた戦い。
人と 人でないものを 分かつ要素とは何なのか?人が人であるということは?
自らの意思で動いているようなHALは人間なのか、人間ではないのか。
『博士の異常な愛情』でもそう感じたが、監督はストレートにわかりやすい表現を避け、わざと幾重にも難解にこねくり回して作っていくのが好きなように見える。トラップを仕掛け、煙に巻く。真意を巧妙に隠し、見つけられない私たちを眺めてほくそ笑んでいるような。
それなのに、それだから?
最小限にそぎ落とされた映像・セリフ・音楽。
空に浮かぶ雲を見ているかのような壮大かつ緩やかなテンポ。
かと思うと、緊迫したやりとり。
急展開の映像。
その間や、俳優たちの息遣い、予測のつかない展開・映像・音楽から目が離せなくなる。
翻弄される。
人が問うて已まない永遠の問。
×
監督が映画の中に課したミステリ―
にひきつけられて、何度も観てしまう。
地球外生命・宇宙の成り立ち・コンピューター・人間という種としての進化・我々の未来。
これらのテーマでたくさんの映画が作られてきた。
でも、どの映画とも一線を画する映画。そして多くの映画に影響を与えてきた映画。
訳が分からないのに離れられない。
超えられるわけがないのに、超えたくなる。
不思議な映画。
人類史上の宝のひとつ
もう何十回と見たであろうこの作品をネトフリで再見。今回は少し違った観点から見てみることにした。テーマは色彩とデザイン、そして音楽。クリストファー・ノーランのリマスター版は特にその辺を鑑賞するのにとてもよく仕上げている。ハミルトンの腕時計、ジョージ・ジェンセンのカトラリー。ムーンベースのロビーにはオリヴィエ・ムルグがデザインしたDjinn。勿論カードはアメックス。。。色彩も当時のモニターがグリーンであるための補色として多くの赤が使用されており最高の色彩バランス。ジェイムズ・P・ホーガンのデビュー作の『星を継ぐもの』のイントロダクションがまさに5万年を経た赤い宇宙服の男が発見されるところから始まるのはSFファンの間では有名な話。赤い宇宙服が本当に美しい。美しいと言えばオープニングの人類黎明期の風景の美しさ。そして宇宙船の美しさ。そして最後にたどりつたロココ調の彼岸には3枚の絵画が(確認される範囲で‥)これは原作によるとゴッホ跳ね橋とワイエスの「クリスティーナの世界」が・・。これだとあまりにも説明しすぎという事で変えたのであろうが、本来の元絵が誰の絵画なのかが未だ特定できない。どなたか情報をお持ちの方いらしたらお教えください。とにかく最大の驚きはこの完成度を持った作品が1968年に作られている事。返す返すもこの驚異には敬服する。
サンドイッチ、美味しそう
すごくヤバい
遂にこの作品を映画館で!しかもIMAX上映!!
大学生の時にVHSをレンタルして以来、20年ぶりぐらいに再見。印象的なカットは断片的に覚えているけど、正直中身は忘れました。ほら、ファッション的に映画観るの流行ったんです。バグダッド・カフェとかバッファロー'66とかビッグ・リボウスキとか。
んで感想。 すごくヤバい。 お前の語彙力どこ行った?という表現だけど、こう言う他に賛辞の言葉が見当たらない。学生当時の関わり方は、正直「キューブリック観てる俺カッケー」的なもの。貧乏学生の部屋にある小さなテレビ画面。音は小さなスピーカー。酔っ払いながら「なんだこのラスト」と思いつつ、ステータスとして「観た」ことにしていたのです。
はじめて映画館で観て、IMAXという素晴らしい環境でこの名作を観て、トラウマレベルで心に刻まれました。あの映像美と音楽は異常。これは、映画であり、現代音楽のMVであり、絵画でポエムだ。コンピュータが呟く「I’m afraid. 」はヤバすぎる。50年前ですって?このおじさんですら生まれてないんですよ?? あり得ない。あり得ないのです。
CG全盛の映画業界。確かにキレイだしスケール感も半端ないし、なんでも出来ちゃうんだけど嘘くさい。だからこそ驚きも何もない。火が熱く感じないのだ。でも本作のSFXには感情がある。日本ではイタイイタイ病とかの教科書に載ってた時代にあのラストのあの映像。キューブリックが実は未来人だったと告白しても、何も驚きはしない。
中学生もワンクリックで無修正のエロ動画見放題な時代。昔は黒く塗りつぶされたエロ本にバターやシンナーを擦り付けて奥の奥を覗こうと努力するしてた訳です。どちらにクリエイティブは宿るのかって話ですよ。
キューブリックの業
やはり名作だ。
旧友と再会したように観賞した
午前十時の映画祭11にて
初観賞は高校生の時のテレビ初放映。この時の衝撃が未だに忘れられず、自分にとってのベストワン映画の位置を不動のものにしている。
だが、Wikiで見てみると、日曜洋画劇場での初放送は1981年とのこと…だとしたら浪人中だ。高校の校舎内で友人と語り合ったと思い込んでいたが、違ったか。記憶というのはいい加減なものだ。
上京した後、やっと映画館で観た。その後は数年おきに観ているような気がする。
WOWOWの初放送では部屋を暗くして観た。
過去の午前十時の映画際でも観たし、シネマコンサートでも観た。
DVDソフトもBlu-rayソフトも持っているが、これはコレクションとしての喜びであって、あまり自宅のテレビ画面で真剣に観ることはない。
感受性と集中力が年々衰えていく中で難解な映画を観るのは時に辛いが、本作は「慣れ親しんだ」旧友のようで、画面を見ながら「あ、この時ってこうだったっけ?」なんて、思い出話でもするように心の中で一人で会話したりする。
モノリスと人類進化の関係とか、スターベイビーはボーマン船長が神化した姿かとか、この映画のテーマを深掘りすることは今や重要ではない。
様々な研究者が講釈を述べているし、アー サー・C・クラークの長大な続編群でシラケるほど理由付けされている。
あらためて思うことは、この映画の特殊撮影によるリアリティは、恐ろしく緻密な人の作業に支えられていたのだということ。
ミニチュアに映像をはめ込んただけの単純な合成でも、画面設計と寸分狂わない映像を作りあげさえすれば、その映像の完成度に技術が新しいか古いかは関係ない。
ルネサンス時代の描方を現代の画家は使わないが、ルネサンス絵画が今も陳腐化していないのと同じだ。
SF的な映像は、科学的考察に基づくリアリティを追求して設計された。その設計を忠実に具現化しているから、映像はいつ観てもリアルなのだ。
このヴィジョンどおりの映像を作り出すためのキューブリックの要求が如何に妥協を許さないものだったかは、携わった多くの職人たちが二度とキューブリックとは仕事をしたくないと語っていることからも想像できる。
この一大宇宙叙事詩を完成させたクリエイターたちの才能と努力に敬意を表したい。
もし、手塚治虫がキューブリックからのオファーを断らず美術に参加していたら、、、、多分途中で決裂してただろう…
午前十時の映画祭にて。 昔、昔、学生時代に見た時はあまりよく分から...
ここまでいくと神々しい
むかし観てちんぷんかんぷんだったので再チャレンジ。
結論から言うと、今回もちんぷんかんぷんだった。ただ、前回観たときはそれが退屈に直結したが、今回はすばらしい作品として観ることもできた。映像は信じられないくらい緻密で美しい。ここまでいくと神々しい。その点ではもうアンタッチャブルレコードなのかもしれない。
あと今回観て思ったのは、シーンによってはすんごい間がある。だから「退屈」に直結したんだろうけど、それが長い時間広い空間を感じさせる要素になっているんだと思った。終盤のぶっ飛ぶところ、今回も頭クラクラした。挿入される変顔にドキッとする。
解説もチラ見してはいるけど、やっぱり映画は自分でどう解釈できるかだから、そのまま放置でまた機会があれば観るかな。インターステラはやはりこれの系譜で、わかりやすい物語にしたらああなる、のだと思う。
モノリスを知らない輩
もう何十回見ただろうか
2001年宇宙の旅 アーサーC クラーク の小説の映画化
TOHOシネマの小さなスクリーンで しかも何故か映画は
更に内側に一回り小さく上映されてた なんだこれは
この映画は70mmシネラマサイズのはずなのに・・・・・
人類の進化は外宇宙の知的生命体の関与があってこそ進化したという話は
当時はあまりに突拍子もない発想でしたが さすがSF 作家は時代を超えた
着眼点がありますね 現代では実際に宇宙人からも情報が来る時代だから
地球人がここまで進化したのは知的生命体が地球人に技術や発明の
閃きを与えたからに他なりません 進化論なんて宇宙人は笑ってますよ
遥かな昔からいろいろな発明や発想は本人が考えたのではなく
知的生命体が地球人の進化を促すためにテレパシーで伝えたこと
さて2001年宇宙の旅では冒頭の類人猿がモノリスがいきなり登場してから
類人猿に道具を使うことを閃かせたこと
類人猿が持つ骨から場面が人工衛星の場面に切り替わったのは
有名なシーンですね
宇宙ステーションの中で米国ヘイウッド・フロイド博士が
ソ連の科学者チーム(エレナ博士カリーナン博士ステレティネバ博士スミスロフ博士)
といろいろ話をした後
字幕に出なかった会話 ちょっとありますね
スミスロフ博士「やはり、口は固いな」
ステレティネバ博士 「そりゃ そうよ」
フロイド博士が月面クラビウス基地で何かあったことを
隠しているな という場面ですね
400万年後に人類が月面でモノリスを発見したのは偶然ではなく人類が
発見するように磁場の異常で知らせたこと
モノリスは知的生命体なんですよ 進化を促す存在というか
何故木星なのかはわかりませんが・・・・・・。
木星にディスカバリー号が到着したらモノリスが地球人を誘導する場面
を想像しますが、
キューブリック監督はいちいち細かい説明のシーンは写さないから
当時は理解されなかったのですね
ラストの17世紀宮廷風の部屋はモノリスが地球人をもてなすために
わざわざ作った空間
そこに至るまで時間と空間を超えて ボウマン船長は一気に老けてしまった
自分を見て驚くのですが 彼はそこで飼われていたのではないか
来たる新人類の夜明けが来るまで
宇宙の神秘
名作と言われていますが、今まで一度も観た事がありませんでした。内容もタイトルからSFなのだなという事くらいしか知りませんでした。前に『インターステラ-』を観てからこの作品も気になっていたので観ました。
半世紀以上も前に作られたとは思えないくらい先鋭的な内容で驚きました。2021年の私が観ても新し過ぎてついて行けないと感じるほどでした。特にラストは衝撃的です。時間とは?空間とは?宇宙とは?色々な事が頭の中をグルグル回り興奮状態です。
宇宙空間とクラシック音楽の融合は壮観でした。また、宇宙船内での上下・縦横の常識を覆すような映像体験も驚嘆でした。映画というよりはまるで1つのアート作品を観ているようです。解釈は人それぞれというか、わかる人にはわかり、わからない人にはわからない。初見の私はどちらかというと後者の方です。先が読めない上に、ひとつひとつのシーンがゆったり進むので、まどろんでしまいそうになった場面もありました(笑)。でもラストは叩き起こされたみたいに衝撃的でした。名作と言われるのも納得です。また、所々で登場する黒い四角い物体とか、HALの存在とか、何かスゴい意味を持っていそうで興味深いです。少し時間を置いてからまたじっくり味わいたいと思いました。
半世紀過ぎても色褪せず、むしろ現実を映画に引き寄せてしまう強大な万有引力を持つ不滅の名作SF
米国の宇宙評議会からフロイド博士は月面のクラビウス基地を訪問するため各国の科学者が集う宇宙ステーションに到着した。ソ連の科学者達からクラビウス基地が音信不通となっていて疫病が発生したと噂が出ていることを聞かされるが何も答えられないと一蹴するフロイド博士。彼の本当の目的は基地近くの地中から発見された巨大な黒い板を調査すること。フロイド博士達調査団が現地を訪れた時、400万年前から埋められていたとされるその板は太陽光を浴びて猛烈な異音を発し始める。
午前十時の映画祭での鑑賞。都合3回挿入される長いインターミッションに象徴される通り交響楽団の演奏会を聴きに来ているかのような優雅な空気感を全身で感じられるのでスクリーンでの鑑賞は大正解。あえてナラティブな説明をごっそり取り除いたソリッドな作風は幼い頃に観た時には意味が解りませんでしたが、年齢を重ねた今は『人類の夜明け』、『木星使節』、『木星そして無限の宇宙の彼方へ』という3つの章で展開される物語にすんなりと没入出来ました。スクリーンに映し出される映像が製作時から半世紀以上の時を経てもなお全く色褪せないのは当時の水準を遥かに超えたレベルまで作り込まれているからこそ。ダグラス・トランブルを筆頭に結集した特撮映像のプロ達が想像した世界観は初めて観た時と同等の驚きを呼び覚まします。作中では星間航行を実現しているパンアメリカン航空が2001年を迎えることなく消滅してしまっているといった致し方ない現実とのギャップがある一方で、疫病の発生が噂されるクラビウス基地に乗り込むフロイド博士の姿にバッハIOC会長の姿を重ねるとたちまちリアルな話にも見えてしまう辺り趣深いものがあります。
人類の進化とは殺戮の連続であることを無言で冷徹に提示し、高次の知的生命体との隔絶と融合を鮮烈に描いた本作そのものがモノリスとなって以降無数のSF映画に劇的な影響を与えたこともまた本作が描いた世界観と地続きであり、そんなメヴィウスの円環の中に人間の叡智を見つめ続けてきたSF映画の萌芽を見ることが出来たことに感謝しかありません。
個人的には本作とセットで思い入れ深いのが、同じく日曜洋画劇場で観たダグラス・トランブル監督の『サイレント・ランニング』。こちらもスクリーンで観ることが出来る日を待ち望んでいます。
映画館でみたことない。
全196件中、41~60件目を表示