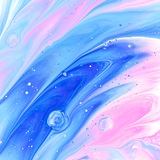王国(あるいはその家について)
劇場公開日:2023年12月9日
- 予告編を見る
- U-NEXTで
関連作品を見る PR - 配信動画検索

解説・あらすじ
長編映画デビュー作「螺旋銀河」が第11回SKIPシティDシネマ映画祭にてSKIPシティアワードと観客賞をダブル受賞した草野なつか監督の長編第2作。
出版社の仕事を休職中の亜希は実家へ数日間帰省することになり、小学校から大学までをともに過ごした幼なじみの野土香の新居を訪れる。大学の先輩だった直人と結婚して子どもを産んだ野土香は、実家近くに建てた新居に暮らしていた。その家は温度と湿度が心地よく保たれており、まるで世間から隔離されているようだと亜希は感じる。最初は人見知りをしていた野土香の娘・穂乃香は一緒に遊ぶうちに亜希に懐くが、野土香はとても疲れている様子だった。数日後、東京の自宅に戻った亜希は、ある衝撃的な内容の手紙をしたためる。
演出による俳優の身体の変化に着目し、脚本の読み合わせやリハーサルを通して俳優たちが役を獲得していく様子を、同場面の別パターンや別カットを繰り返す映像で表現。ドキュメンタリーと劇で交互に描きながら、友人や家族といった身近なテーマをめぐる人間の心情に迫る。「ハッピーアワー」の高橋知由が脚本を手がけた。
2018年製作/150分/日本
配給:コギトワークス
劇場公開日:2023年12月9日



 ミスターホーム
ミスターホーム ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 万引き家族
万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に
この世界の片隅に セッション
セッション ダンケルク
ダンケルク バケモノの子
バケモノの子