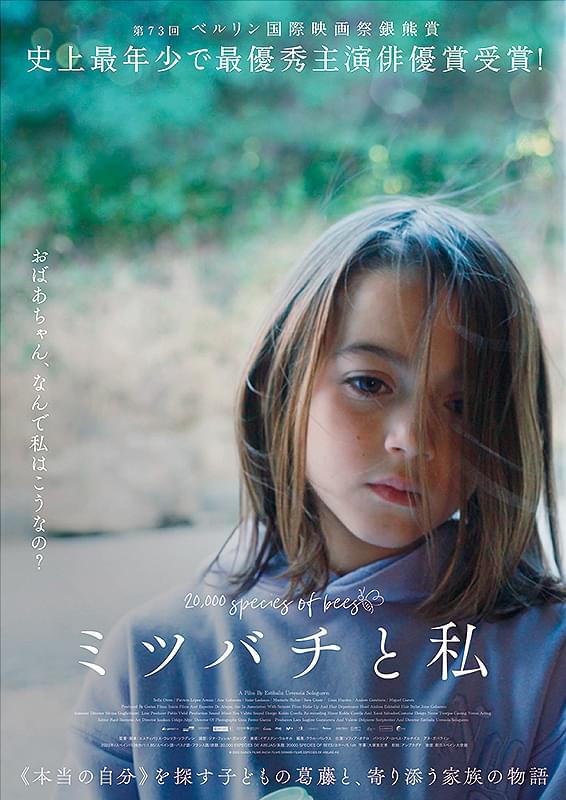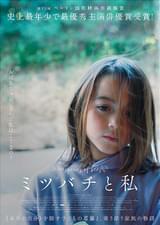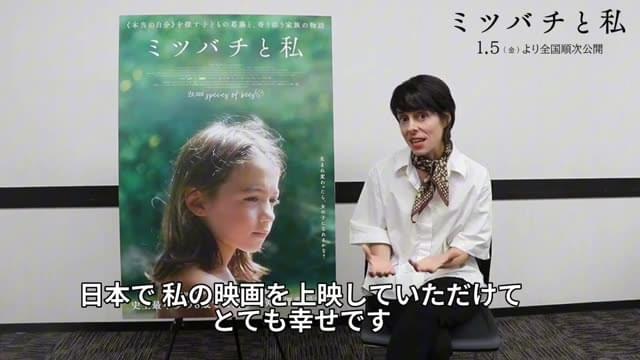ミツバチと私
劇場公開日:2024年1月5日
- 予告編を見る
- U-NEXTで
関連作品を見る PR - 配信動画検索

解説・あらすじ
自分の性自認に迷う子どもの葛藤と、寄り添う家族の姿をつづったスペイン発のヒューマンドラマ。
夏のバカンスでフランスからスペインにやって来た家族。8歳のアイトールは自分の性自認が分からず、違和感と居心地の悪さを抱えて心を閉ざしている。母はそんなアイトールを愛しながらも、向き合い方に悩んでいた。ある日、叔母が営む養蜂場でミツバチの生態を知ったアイトールは、ハチや自然とのふれあいを通して心をほどき、ありのままで生きていきたいという思いを強めていく。
オーディションで選ばれた新人ソフィア・オテロが主人公アイトールを繊細かつ自然に演じ、2023年・第73回ベルリン国際映画祭にて史上最年少となる8歳で最優秀主演俳優賞(銀熊賞)を受賞。スペインの新鋭エスティバリス・ウレソラ・ソラグレンが長編初監督・脚本を手がけた。
2023年製作/128分/G/スペイン
原題または英題:20.000 especies de abejas
配給:アンプラグド
劇場公開日:2024年1月5日
スタッフ・キャスト
- 監督
- エスティバリス・ウレソラ・ソラグレン
- 製作
- ララ・イサギレ・ガリスリエタ
- バレリー・デルピエール
- 脚本
- エスティバリス・ウレソラ・ソラグレン
- 撮影
- ジナ・フェレル・ガルシア
- 美術
- イザスクン・ウルキホ
- 衣装
- ネレア・トリホス
- 編集
- ラウル・バレラス


 ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 万引き家族
万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に
この世界の片隅に セッション
セッション ダンケルク
ダンケルク バケモノの子
バケモノの子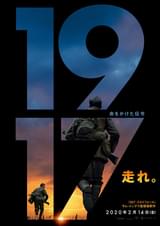 1917 命をかけた伝令
1917 命をかけた伝令