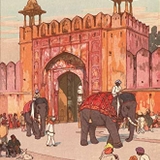怪物のレビュー・感想・評価
全1010件中、141~160件目を表示
カンヌ脚本賞おめでとうございます
カンヌで脚本賞を取ったという事で、ハードルがあがりきった状態で視聴
本作は一つの時系列を三つの視点でリフレインさせ、隠された真実を浮かび上がらせる手法を取っています。視聴者の注目を煽るための展開や、視点による感じ方の違いを強調するためのギミック(先生の飴とかね)に少々あざとさを感じるものの、エンタメ作品としては許容可能範囲。終盤、真相のインパクトを強調よりも根底に流れていた秘密のドラマにフォーカスする作劇からは一流の非凡さを感じました。エンタメ寄りで文学的なエッセンスも少し足されている、くらいのバランス感覚は好みです
言ってしまえば映画「羅生門」のアプローチをベースに、「浦沢直樹作品」のクリフハンガー要素を加え、「少年時代」に着地する作品とでも言いましょうか(浦沢直樹作品のエッセンスは韓国映画に色濃く継承されているので、そちらを思い出す人のほうが多いかも)。竜頭蛇尾に終わりがちな浦沢直樹作品の欠陥を回避するにはこんなやり方もあったのかという驚きもあり。面白かったです
怪物だーれだ
普通とは違う。
当たり前ができない。
○○らしくない。
だから怪物だ。
「あいつは怪物なんじゃないか」
「自分は怪物かもしれない」
そんなふうに、誰かを──
あるいは自分自身を“怪物”と呼んでしまうことがある。
人の数だけ真実があって、
正義の形もそれぞれ違う。
けれど、それが事実どおりとは限らない。
噂や誤解、偏見や推測で、
私たちはつい「誰が悪いか」を探してしまう。
その心理が、誰かを静かに追い詰めていく。
「怪物だーれだ」
本当の怪物って、
“社会”から「問題」とみられている人のことなのだろうか。
社会の中で居場所をなくしていく人は、
本当に“悪い”のだろうか。
もしかしたら怪物は、
存在そのものではなく、
他者の認知や社会の視線によって、
作られてしまうのかもしれない。
ラストシーン
「生まれ変わったのかな?」
「そういうのはないと思うよ、そのままだよ」
「そっか、よかった」
湊と依里はありのままの自分を受け入れられたと解釈したい。
怪物ではなく人間でした
接触ってこれだよ?
原作から入りましたが…
怪物だーれだ?
自分が感じたことと同じ思いや感想、捉え方を
すでに大勢の方たちが述べているので、
敢えて、そんなには多くは投稿されていない(と思われる)感想を書くなら、
湊君と依里君が、ただ一言ずつ発しあいながら抱き合うときの色気!
これは、もう、日本映画史に残るほどの名演技だと思います。
(でもって、そんなこと誰にもいう必要や理由なんかないし、
今後、彼らがどうなっていくのかは誰にも分からないことだけど、
そんな、おぼろげで移ろいやすくも確かな世代の震えみたいなものが伝わってきます)
いずれにしろ、すべては、まさに『藪の中』であり、「怪物だーれだ?」って感じです。
子供たちのなんと眩しいことよ
坂本裕二の脚本がさすが。
藪の中、みたいに
登場人物のいろんな視点からある出来事が描かれ、徐々に真実が明らかになってゆく。
ちょっとした偶然や惰性が重なって取り返しはつかなくなってゆく。
子供たちのなんと眩しいこと。無垢で無邪気でそして残酷。
湊と星川よりくんだけの美しい日々。
いつの世も、真実が正しく語られるには、私たちの世界は複雑すぎるのだと思った。
もし星川よりくんがもっと大切に育てられていたら。
もし湊やその母がセクシャリティに関する広い知識を持って過ごせていたら。
小さなトラブルが起こったあの時、もっと深く立ち入って根本の問題に気づけていたら。。
湊の絶望感や行き詰まり感がわかって、やるせなくて辛い。
ラストシーンはとても美しかった。彼らは晴れた雨上がりの森を駆け回り、笑いあい、幸せそうにじゃれあいながら、かつては入れなかったトンネルへと向かってゆく。
とても切ない終わりだ。
大人たちを置いてけぼりにして、彼らは幸せそうに逝ってしまった。
彼らがとても幸せそうだったのがせめてもの救いであり、大人への罰だ。
重苦しい映画かと思いきや、是枝節の傑作
序盤では、共感できない「悪人」のような存在がデフォルメされており、奇妙なホラーのように感じる。テンポ感が早かったのもあり、是枝監督らしくないと感じた。しかし、この印象も映画全体の構成の一部であり、中盤以降で見事に覆される。「羅生門」式と言われる通り、それほど斬新な手法とは言えないと思うが、認識の死角を巧妙に突いていて、人は感情を持っているかぎり常に誰かを誤解しているということを効果的に知らされる。
完全に術中にはまったので、思わず2回観てしまった。
2回目に見てみて初めて、湊の「テレビで見てるから嘘だってわかるんだよ」というセリフがこの作品の手法を象徴していることに気づいた。保利先生が「僕も片親でした」から始まる何かを言おうとしたところを早織に遮られたのも認識できた。
役者たちの素晴らしい演技も、このミスリードをうまく機能させている。
早織は、子を持つ親なら過剰にヒステリックには見えないと思う。彼女の行動はリアルで熱心な女性として描かれている。
保利先生が序盤の職員室のシーンで完全なる悪役として怒りを感じさせるが、その決定打になった応接室で飴をなめたり母子家庭だからという反論も、一応それぞれ言動の動機が中盤で紹介されただけでなく、根は良い奴だが人の言う事を信じやすく、追い詰められるとああいう言動をしかねないキャラクターが上手く演じられていた。(それでも飴を口に入れたシーンはギリギリアウトだったと思うが)
そして、そこまでに表現されてきた事を忘れさせるぐらい、星川君と湊が心を通わせるシーンは胸を打った。個人的には最初に彼らが笑い合うケンケンのシーンは息が詰まるほど揺さぶられた。シナリオと音楽には日本を代表するアーティストの名が連なっているが、是枝監督が描く原風景は共通している。
ラストシーンでは、やはり星川君と湊は亡くなったと解釈した。救急車かパトカーのサイレンが鳴り響き、校長がびしょ濡れになり、星川君の父親もびしょ濡れになる。彼らが現世・社会から解放されたことで、いじめや嘘、セクシャルマイノリティに関する悩みや周囲からの期待から解放され、純粋に大切な存在と笑い合うシーンで締めくくられている。社会がなければ、それが愛情なのか友情なのかと悩む必要もないだろう。
そして、それをあそこまで美しく描き、子どもが疾走していて、光に溢れているのは、やっぱり是枝節だなと感じた。
それぞれの単体エピソードとしては良かったものの、、、
3部構成、それぞれのエピソードは面白かったが、これを一つに繋げた時に、果たして整合性はとれてるの?という印象。
特に小学生のメイン2人が、瑛太のことについて嘘をつくのは理解できるが、なぜ他の子たちまでもが瑛太のことを悪くいう(あるいは味方してあげない)のか、全く理解できなかった。視聴時は、きっとメイン小学生2人のどちらか、あるいはやけに存在感のある女の子のうちの誰かが、クラスを(陰で)牛耳ってるのかなと思ってたんだけど、そんなこともなく。
作品の行間に雰囲気が感じられる脚本と演技はよかったが、なんか消化不良てあった。
純粋な子供達に振り回される大人達
世にも尊い物語
日常に潜む「怪物」の正体
ジャンルは特撮でもホラーでもないのに、『怪物』というタイトルが意味深だ。
本作の主軸となるのは、小学校教師の児童への虐待疑惑。学校を追及する母親(安藤サクラ)から、非難に晒される教師(瑛太)へ、そして渦中の子供(黒川想矢)へと、視点が切り替わって描かれている。
「怪物」がこの映画のキモには違いないが、その怪物とは一体何か、もしくは何を示唆しているのか。その答えを探しながら観たとしても、怪物の正体はそう簡単には暴けない。主観となる人物が変わるたびに、1つの出来事への認識が異なってしまうせいで、観客が知りたい答えは一転二転し、寸前でかわされ逃してしまう。
「怪物、だーれだ」とつぶやきながら、夜道を1人歩く少年。学校で子供たちの明るい声が響く中に、紛れて聞こえる怪物の咆哮を思わせる寂しげな楽器の音。
怪物は登場人物たちの日常のいたる所に潜んでいて、嘘を飲み込んで大きく育っていく。自己保身に走る大人たちはもちろんのこと、大人の庇護を求める無力な子供も、生きるために意図せず自分の中で怪物を飼っている。
鑑賞後は冒頭からの全てのシーンの捉え方が変わり、最初から見直したくなること必須。結末のシーンも観客に解釈を委ねられた感があり、一度観ただけでは味わい尽くせない奥深さがある作品だ。
本作は第76回カンヌ映国際映画祭コンベンション部門に出品された是枝監督の作品で、最優秀脚本賞(坂本裕二)、クィア・パルム賞(LGBTQに関した作品に与えられる賞)を受賞した。音楽は坂本龍一が担当。
全1010件中、141~160件目を表示