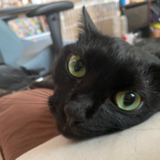怪物のレビュー・感想・評価
全1019件中、61~80件目を表示
今さらレビューする俺が怪物
見てから二年以上経った今、俺はレビューする
誰の心のなかにも巣くう怪物
人間は愚かで心がけ弱く、自分の見える一方通行の世界のみしかわからない
そんな人間こそ怪物
二年以上経った今レビューしてる心境はというと、なかなかいい
噂話と憶測による誤解
観賞後も深く心に残る
すべての謎が解けたとき、もう一度観たくなる。
二度目には全然違ってみえるだろう。
登場人物それぞれの立場になってみると、何も不思議なことはない、「怪物」なんていなかったと気づく。
映画って本当に素晴らしいですね、と言いたくなる映画。
もう一度見るべきかも
・友達へのいじめを告発出来ない事
・好きな人への愛を他人に話せない事
・事実を話せずに退職させられる事
・本心で謝りたいのに学校を守らなければならない事
・父からの暴力を訴えられない事
どれもが理不尽であるが、何かを突き破る必要があり、なかなか実行に移せない。それは自分の保身だったり、父親との関係だったり、組織に潰される自分だったりする。大人たちはそれで失敗してしまうが、最後に子供達はキチンと羽ばたいてくれる。子供にはこれから先チャンスがいくらでもあるのだから、自分に嘘などつかずに羽ばたいて欲しいというメッセージなのか。全くその通り。子供達よ、頑張って生きて欲しい。
いい作品です。ほんとうに。
いじめのシーンが幾度もありますが、首謀者が糾弾されることなく終わるのは残念でした。このままだと、虐められるのは仕方ない事のように取られかねませんよね。残念です。
さて、怪物はだ〰れだ
「かいぶつだ~れだ」
遊びの名前です。私は遊び自体は知っていましたが、この呼び方は知りませんでした。
さて、この映画の物語は怪物が居るか居ないか、誰が怪物なのか、複数の登場人物に視点が切り替えられて同じエピソードを辿ることにより、質問を繰り返して真実に近づくという構造になっています。
この構造は流石、是枝監督です。
前半は主人公の少年の母親の視点で事件の流れが示されて、なんて嫌な奴らなんだと観客に思わせますが、次に別の人物に視点が切り替えられて同じ事件を追うと、母親の視点から観た物語が全く違う様相を示します。次の人物、また次の人物と視点が切り替えられるたびに冒頭で示された伏線の意味が次々に明らかになるのはある意味心地よいです。
そしてクライマックス。
結末の余韻の残し方は、この斬新な映画の末尾を飾るにふさわしいものでした。
大げさすぎると思うのだけど…
視点が、母親、担任の教師、子供、の視点に変わっていく事で新たな事実...
視点が、母親、担任の教師、子供、の視点に変わっていく事で新たな事実も加わりつつ真相が見えてくるミステリー的な要素も素晴らしかったが、この作品は人間愛と、発言について深く考えさせられる作品だったなと感じる。
1人の人を好きになる、その対象が同性なのか異性なのか、それだけの違いによって人権がなくなって言い訳がない。人を色眼鏡で見ずに好きになる、愛することができるその尊い純粋な心をどうして、大人が、ましてや親が、踏み躙ってしまうのか。
同姓を好きになった自覚から、自責の念が生まれるなんて世の中が、いつか、本当にいつか来なくなればいいと心から思う。
こんな世の中だがどうか、子供たちには真っ直ぐに生きてほしい。
「怪物」とは。
鑑賞後の後味が思ったものと違う
この映画が話題になった当初受賞した事でLGBT関連の映画だとネタバレしたという話が出ていたけどそれで最後が分かるとか見なくても別に良いとか言えるような映画じゃなかった。
怪物の気配がずーっと映画の中に蔓延していて重たい気持ちで進んでいくのに最後の清々しさにもう涙が…
この映画のタイトルは怪物しかありえない。
CMのミスリードもとても効いている。
怪物は無邪気な噂話や囁き声の中にいる。あなたと私、2人だけの時の私と、私とあなた達の時の私。
どのアングルで物事に向き合い考えるか、他者の視点に立つためにはどうしたら良いのか、自分以外の事は点で物事を見ることしか出来ない私達は知らない事と知っている事を間違えないようにしないといけない。他者視点で見るなんて事は本当の意味では出来ないことだから。
一対一の親密な時間と他者のいる世界の見せ方と温度感がとてもうまかった。染みる。
希望がないように見えて、この世の中にあって暗いところから希望を見せてくれているように思う。
余韻が深い。
もやもやしたまま終わらされたので、鑑賞後もふと考え続けてしまいそう。
主観が登場人物分あるように、結末(真実)も観客の人数分ある。
実世界の世間話やワイドニュースと同じで、私たちは自分の中で結末を考察するんだ。それが正しいかなんてどうでもいいんだよな。
安藤サクラのパートが1番心がザワザワした。
いくつもある伏線が終わりにつれ少しずつ回収されていくが、根幹にあるような複線(というかストーリーの真実?)は放置されている。細かい複線回収の気持ちよさといつまでも教えてもらえない肝心なところにヤキモキするバランスが是枝監督のテクニックだなぁと感心している。
ああ、こんなにざわざわさせられてはまた映画が好きになるではないか。
面白かったけど
一番納得いかないのは母親目線からのストーリーのとき。どう考えても担任の先生との面談の際、1)先生が保護者の面前で飴舐める 2)「シングルマザーのあるある」発言 3)校長先生の木で鼻をくくった(今まで生きてきて、この慣用句が初めてしっくりくくる場面と感じた)対応。(それにしてもこのシーン、安藤サクラが田中裕子の鼻に指突っ込んで。面白すぎ)
担当の先生のストーリーの時、この飴舐める場面と「シングルマザーのあるある」発言についての回収は無かった。一生懸命やってる先生って感じなのになぜ、あの行動と発言になったのかの場面がなく、最後までモヤモヤが残った。
校長先生についてもスーパーで走り回ってる子供に足を引っかけるところを母親が目撃する。そのため、校長先生の「素」が垣間見えるような場面となっているのだけど、これについても回収は無かった。悪い先生ではないのは少年を楽器を一緒に吹いて交流するところを見るとわかる。
作品を見る前に芥川龍之介の「藪の中」を彷彿とさせる、みたいな書評を読んでいたのでなるほど、面白い構成だな、とは思ったけど、どう考えても上のモヤモヤが解決されなかったので、そこが納得いかない。ラストの二人をどう解釈するかよりも気になる。
難しい
同じ時系列を3部構成でまとめている映画。
1部目はその異様さに疑問を多く抱き、2部目でそれが誤解であり間違いだとわかり一体怪物はだれなのか?と考える、3部目に種明かしをするのだが結局怪物とはなんだったのか。本筋はわかっても回収されない部分が多すぎて結局疑問が多く残ってしまう。
物語の3割以上が視聴者の想像に委ねられているような作品だった。
ラスト子供達はどうなったのか...生まれ変わりという言葉を取るならそうなのか...モヤモヤした気持ちで終える。
この全ての答えを出さないところが評価を得れているのだろうか...
世界は主観でできている
タイトルのせいもあって、誰が怪物なんだと先入観を持って見てしまった。
最初は母親の視点、次は教師の視点、、、と。
視点が変わるたびに、なんなんだこいつは!!と思ってしまう。
最後のみなとくんの視点で世界がつながって、これまでのみんなの態度に納得していく。
映画だけでなく、普段の生活もそうなんだと思う。
やっぱり一面的にものごとを決めつけるのはよくないとおもった。
実世界では一面的にものごとを決めつけている人が不利益をこうむってはいないのがくやしいけど。
一番の被害者は決めつけられた人か。。
高畑充希
視点と解釈の迷宮、そこに潜む「怪物」とは
観る者の視点と解釈を揺さぶる、奥深い作品だ。
美しい風景と共に織り成す湊と依里の場面では、私自身の少年時代の体験が蘇る。秘密基地やそこで過ごす誰にも邪魔されない時間、そして言葉にできない感情。それは、大人になるにつれて失われていく、かけがえのない宝物のような時間だ。しかし、同時に、子どもであるがゆえの無力さ、大人たちの無理解に苦しんだ記憶も蘇る。
物語は一見すると、いじめやDV、モンスターペアレント、教育現場における事なかれ主義など、現代社会にありふれた問題を扱う映画のように見える。しかし、湊と依里の関係がクローズアップされるにつれ、物語に潜む場面や何気ないセリフが、彼らへの苦悩や抑圧を生んでいたことに観客は気づかされる。
「お父さんみたいになれないよ」「豚の脳みそに入れ替わる」「ぼく、もう病気が治ったよ」「生まれ変わり」…これらのセリフは、二人の関係への社会の無理解や偏見が生んだものだったと気づき、観客の心を深くえぐる。
湊と依里の関係を安易に恋愛だったと決めつけてしまうことや依里の父親の暴力の原因、ラストシーンの湊と依里の生死など、それらを詮索すること全てが、観客自身の「怪物」性を浮き彫りにし問いかけてくる。
湊と依里が追い求める「生まれ変わり」は、社会的抑圧からの逃避だけではなく、もう一度過ぎた時間を戻し、あの楽しい時間を二人でまた過ごしたいという切実な願いだ。だからこそ二人は、二人だけの場所だった廃電車を「出発」の場所として選び、あの場にいたのだと私は思う。
この映画は、見返せば見返すほど観客を永遠の間違い探しに誘い込む。視点を変えるたびに、物語の解釈が変わり、観客は何度も立ち止まり、考えさせられる。それは、保利先生の趣味である「誤植探し」にも似ている。細部に目を凝らし、わずかな「ずれ」や「間違い」を見つけ出すことで、初めて見えてくる「気づき」がある。
「怪物」は、観る者の数だけ解釈が存在し、観るたびに新たな発見がある作品だ。安易な決めつけや偏見を捨て、多角的な視点から物語を読み解くことで、初めて見えてくる真実がある。この映画は、観客自身の「怪物」性を問いかけ、私たちに永遠の間違い探しを強いる。そして、物語に潜む社会的メッセージに気づいた時、観客は深い衝撃と同時に、少年たちの「生まれ変わり」に託された願いを感じるだろう。
思ってたのと違った
すごい映画でした。そしてやはり田中裕子さんは裏切らない!
あまりにも思いがけない、すごい映画で、なかなか思いがまとまらないのですが
ボクが思うに「みんな(見てる我々も)怪物」なのだと感じます。
真実はひとつのはずなのに、関わっている人の数だけ真実は増える。
その「増えた真実」が、怪物であり、それを生み出す我々みんなが怪物なのだと。
最初、田中裕子さんの演技が「おーい!裕子!キミはそんな人ではないはずだっ!」
なんて思いながら見てたんだけども、終盤、ああもう、やはりあなたは素晴らしい!と
とにかく田中裕子さんの存在感に、演技に、セリフに、心が奪われまくりでした。
流石です。女優 of 女優 です。彼女がいたからこその、この作品の仕上がり。
子どもたちの演技も素晴らしかったし、みんなみんな素晴らしい。
是枝監督作品は初めて見たんだけど、こんなにすごい映画を撮る人なんだ!と感嘆。
脚本もキャストも何もかもが完璧だったと思います。
そしてラストは、その「増えた真実」たる怪物に子どもたちは命を奪われたのだと。
あんなにキラキラで輝いたラストは、アレは、天国なのかもと。
ずっと水色の柵で向こう側に行けなかったはずなのに、柵がなかった。
柵がなく、うわー!って、思いっきり廃線路のほうに走っていけた子どもたち。
天国に行ったんだね・・・(泣)となってしまいました。
皆さんがどう見る、どう受け止めてるかはわからないけれど。
自分は、そう受け止めました。本当に素晴らしい作品でした。
じんわり響く
やっと見れた
面白かったけど、はっきり見せてほしい。
主人公は親から虐待される同級生をホントは守ってて、好きになってしまって(男同士なのに)
先生から虐待うけてると親は勘違いして
学校に抗議にいって
先生はクビになって
最後は夢?
ちゃんとふたり行きてた??
全1019件中、61~80件目を表示