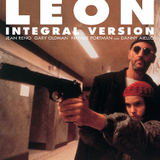怪物のレビュー・感想・評価
全1013件中、201~220件目を表示
子どもが傷つくのがただただ辛かった作品
とにかく技巧的な脚本が印象的。事実を複数視点から時系列も混ぜて見せられることでこちらの受け止め方が随時揺れ動く。わからないシーンが後から見えてくる、とか。
怪物に焦点をあてたことでセンセーショナルな面が際立った気がする。それが描きたかったことなのかな。子どもの揺れ動く感情、好意、悲しみが、見ていてしんどい作品だった。ホルンなど音の使い方はすごく面白いと思ったけど、校長の台詞が全く響かず、そこが個人的に残念。相性の問題なのだと思うけど。
誰でも手に入るものを「幸せ」って言うの
校長が「しょうもない、しょうもない」と言いながら、湊に語った「誰でも手に入るものを幸せって言うの」という言葉を考えた。
だとしたら、その幸せをみんな求めているのに、どこでボタンを掛け違えているのだろう。
母親は確かに湊を愛しているのだろうが、明らかにおかしなことがあっても、どうして遠慮してわかった風を装ってしまうのか。
保利先生は、一見異常に見える金魚も、異常ではないという感覚を持っているのに、なぜ子どもたちへの指導は表面的で通り一遍なのか。
うまく社会に適応しているように描かれる周囲の人々は、その攻撃性に対して無自覚に噂話や偏見を垂れ流すのか。
そこに共通するのは、自分にとって「訳のわからないもの」に対する恐れであって、それがすなわち「怪物」なのだろうと思う。だから「人物の誰が怪物なのかといった見方ではなく、自らの中にある怪物を自覚しましょう」という映画なのだろう。
依里と湊の2人も、この「怪物」に囚われていたが、ラストシーンでそこから抜け出したことが暗示されている。
で、どう思ったかなのだが、一回目に劇場で観た時には、様々な人物や出来事のステレオタイプな描かれ方が気になって、とてもモヤモヤが残った。今回の配信での視聴は、そこは気になったが、ちょっとは落ち着いて観られ、羅生門的なアプローチで、全体が破綻なくまとめられていることも確かめられた。
が、やっぱりモヤモヤは残った。
どうして、登場人物の誰もが、相手の話を聞こうとしないのか。自分の中のストーリーに当てはめて、わかった気になったり、相手を屈服させようとしたりするのか。
そりゃさ、障害受容(依里のLDを指してます)ができない親は山ほどいるだろうし、モンスターペアレント対応でガッツリ削られている先生たちも多いだろうし、自分が直接関係ない不幸は、無自覚にエンタメとして消費して記憶にもとどめないことだってたくさんある。
けど、当事者の相手の話を素直に聞くって、そんなに難しいことなんだっけ?…性自認と性的指向についても学校できちんと扱われる時代になってきている中、そこでとどまってしまうのか…と思ってしまった。
言い方が適切かはわからないが、一歩手前で煽られている感じがしてしまうというのが正直なところ。そうなる前に解決できるものを「どう?どう?」とずっと見せられている感じなのだ。
是枝監督、坂元裕二も好きなのにな。なんでかな。
ぐやじい
怪物誰だ
人の目線で怪物が変わる。
見える部分と見えない部分を照らし合わせて初めて真実がわかるけど、それは誰にもわからない。
嘘か本当かは誰にもわからない、怪物って誰なんでしょうね。
誰もが怪物になるし、誰も怪物じゃないし、
2人がどうか幸せでありますように。
そう思う作品でした。
長い長い小説をじっくり読んだような作品でした。
みんな苦しい
観た後に、頭の中がぐわんぐわんする映画。
登場人物それぞれの苦しさが伝わってくる。
まず、湊の母親。
夫が浮気旅行の際に事故死したという事実を封印し、夫を美化しながら生きている。
湊に対する愛情はたっぷりあるし、子どもを守るための行動力もある。
でも、ラガーマンの男と結婚しただけあって、男という生物をステレオタイプの男の枠の中でしか見られない。
それが湊を追い詰めるのだけど、湊が何に苦しんでいるのか理解できないので、勘違いして突っ走ってしまう。
湊が苦しんでいることだけは理解しているので、母親として苦しくてたまらないことは分かる。
保利先生は嘘がつけない人。
だから、学校を守るために謝罪させられる時もうまく喋れない。
教師としては誠実に子どもと向き合おうとしていたことが第二部で分かる。
にも関わらず、不器用さゆえにどんどん追い込まれていく。他の同僚達もすべてを保利先生に押し付け、ことなきを得ようとする。
湊と依里も、自分達を守るために保利先生を悪者にしてしまう。
子ども達は敏感だし、察しが良い。アンケートには、大人達が期待している答えを察して回答する。
湊は多分保利先生のことが嫌いではないけれど、何かというと「男だろ」「男らしく」と口にするため、男らしさがない自覚のある依里は保利先生に心を開かない。だから2人は自分達を守るために保利先生を悪者にしてしまったのだろう。
とても気の毒ではあるけれど、LGBTQの生徒がいる可能性に気づかなかったという点で、保利先生はやはり加害者でもある。
校長も最初は存在自体が胸くそ悪かったけれど、音楽室のシーンで本当は教育の現場が好きな熱い先生だったことが伝わってくる。
孫を誤って引き殺し、夫を身代わりにして刑務者に入れるだなんて、苦しくないわけがない。
夫が身代わりになったのは、校長を守るためではなく、校長が勤める学校を守るためなのだろう。
分かっていても、苦しくて苦しくてたまらないのだろう。でも、そのことは誰にも言えない。
音楽室のシーンで初めて校長の苦しみが分かる。
湊は感受性が強くて人の気持ちに敏感だ。
湊の苦しさが一番ヒリヒリ伝わってくる。
是枝監督は、本当に子役を活かすことが上手い。
友達として好きなのか、恋愛感情なのか、自分でもよく分からなくて混乱し、苦しんでいる。
そのうえ、依里が父親から虐待されていることやいじめに遭っていることにも心を痛めている。だけど、自分もいじめられることが怖くて、いじめから依里を助けることができない。
依里は湊のそんな葛藤を全て受け入れている。
この映画の中で、一番大人なのは、一番幼く見える依里だと思う。
依里はディスレクシアで、性自認も曖昧で男らしくはない。
でも、おそらく知能は高い。美的センスやアイディアにも優れており、天才肌だと思う。
依里の父親は、自分のセクシュアリティーを封印し、自分を誤魔化して生きてきたのだろう。
庭のゴミは気になるが、家はおしゃれだし、植物も好き。依里が花の名前をたくさん知っているのは、父親譲りで植物好きだからだと思われる。
この映画は依里の目線では描かれないので、詳しくは分からない。
きっと依里の父親は、ありのままの自分を受け入れている依里を否定することで自分自身を肯定しようとしている。でも、虐待で自分自身を肯定できるはずもなく、酒浸りになっている。
依里の父親もまた、苦しくて苦しくて仕方ないのだろう。
唯一、最も不遇な立場に置かれているはずの依里だけが、そこまで苦しんでいないように思う。
それは、依里が自分を否定せずに生きているからではないか。
そして、湊という存在に救われたからではないか。
愛されると人は強くなれる。
依里は、湊が自覚しているよりももっと強く湊の愛を感じているのだろう。
ストーリーも徐々にパズルのピースがハマっていって引き込まれるのだが、ストーリーを知った上で登場人物達の心の動きを見返したくなる。
苦しいけど、心に引っかかってしまって、何度も繰り返し観たくなる。そんな映画だった。
リアリティに欠ける部分
映画はあまり見ないのですが、映像、音楽が素晴らしくて傑作だと思いました。
特に坂本龍一さんのaquaが感動的でこの曲がラジオで流れて、それがきっかけになり、この映画に興味をもちました。
また子役の黒川さん、柊木さんの演技は、抜群にすごいと思いました。
ただこれをゲイの少年たちの悩みや葛藤の物語として捉えると、正直リアリティに欠ける部分があり、そこが残念で喉に骨が引っ掛かるような感覚を覚えました。
たったひとつの部分なのですが、湊が男性を好きで苦悩する部分が描かれていないのです。
依里が好きで悩んでいるところはあるのですが、男性全般に性的魅力を感じているところはゼロです。ここはもはやゲイの物語として足りていないところがあるというのではなく、重要なところが欠けていると言っていいと思います。
まだ幼い少年のためそういう性的衝動を描いていないという見方もあるかもしれませんが、lgbtの映画として見るならばそこを無しには通れないと思います。
そこが残念でした。
依里の方は、男性が好きだということを父にカミングアウトしたか、もしくはバレてしまっているような描写があります。
そういう描写が湊の方にもあれば納得できたかもしれません。
実際のlgbtの団体にも協力してもらっていたようですが、そこの残念な点があったせいか、葛藤する場面も、繊細な表現だとは思ったのですが、教科書的なただ見聞きした心理表現に見えてしまいました。
是枝監督のインタビューで「この作品はlgbtqに特化した作品ではありません、言葉にしにくい葛藤や感情を抱えた子どもの話と思って作りました。」と発言されているようですが、これがlgbt映画ではないなら、社会的意義という側面ではかなり薄まってしまう物語になると思います。少年、少女同士の一時的同性愛感情の話は巷に溢れていると思います。
まあそういうところを抜きにしてもとても良い映画だとは思いますが・・・。
あと、この映画を見て私が「怪物」だと思ったのが、安藤サクラ演じる麦野早織でした。一片の悪気もなく社会の異性愛規範をゲイの子どもに期待することは、正直仕方ない部分はあるもののあまりに酷です。この悪意のない発言は、子どもにはとても苦しいものだと思いました。精神的に大人になればただの苦しかった思い出で、通りすぎていけるようになると思いますが。
また作家の凪良ゆうさんが怪物の感想の記事で、最後に二人が走っていったところに追いつかないとダメですねと発言されていましたが、私も同意見です。
子どもたちになにができるか、そして子どもたちに追いついていかないとなと光のなかで二人が駆け抜けるシーンを見て思いました。
☆☆☆★★★ ※ 鑑賞直後にレビューを書き込み、一体は自分なりに納...
☆☆☆★★★
※ 鑑賞直後にレビューを書き込み、一体は自分なりに納得をしてはいたのですが、、、
その後、色々と疑問点が出始めて来てしまい…
後日、その後に感じた事を最後に加筆させて貰いました。
↓ 先ずは、鑑賞直後に書き込んだレビューを
1年以上続く実家を畳まなくてはならない忙しさに、「何とか夏頃には劇場で映画を…」とは思っていた。
「でもその頃にはもう是枝監督の新作と『TAR』は劇場では無理っぽいなあ〜」(泣)とも嘆いていた。
そんな折に先日見た「週間フジテレビ批評」での是枝監督インタビュー。
監督曰く「映画は三部構成で、エンドクレジットが終わると第四部が始まります」
そんな挑発的な言葉を聞いてしまったなら、映画ファンとしては居ても立っても居られない。
これはもう映画館に「(絶対)行かなければ!」…と思ってしまった。
と言う事で、健康診断の日を利用して無理矢理に予定を組んだ次第。
これまで観て来た中で、是枝監督の作品の傾向として〝 生と死の境 〟や〝 貧困と教育 〟と言ったテーマは、切っても切れないモノになりつつ有るのかなあ〜と思い始めている。
これまでは一部の作品を除いて自身で脚本・演出を担当して来たが、今回は人気脚本家坂元裕二のオリジナル脚本。
「自分に見えるモノと他人から見えるモノは違う」
何となくそんな意味の言葉を賞を受けた際のインタビューで答えていた。
視点が変わる事で見えてくるモノでより真実に近づいて行く。
確かにカンヌで賞を得たのも頷ける内容だったとは思うものの。作品中では既に亡くなっている人が、登場人物の中では多大な影響を及ぼしている人物であったり。自分だけの【基地】に閉じこもる少年の描き方。特定の台詞の言い回しや(受け取る人の)受け止め方の違いが、その後の展開に影響を及ぼす等。
スクリーンを観ていて何となく感じたのは、これまでの是枝作品の要素を(どことなく)繋げ合わせた様な脚本になっては居ないか?…との思いが強かった。
それだけに。第三部での前出した言葉の意味を強める展開で、坂元裕二色が出て来るに至り。この脚本でやりたかったモノがやっと見えて来た。
問題は、そこに至るまでの第一部での再三に渡るあざと過ぎる演出であり。第二部で、真実が見え始めたにも関わらず浮かび上がる《謎》の真相は何処に?と、観客を更に苛立たせる辺り。
《好きな人の為に(自分には)何が出来るのか》
少年であり少女であり、自分の想いが伝わって欲しいと思う行動も。その願いも虚しく「裏切られた」と感じた時に起こす危うさ。
この脚本には、登場人物の中で対象的に描かれている人物像が多くいる。
分かり易い例えだと、前出の言葉を話す湊に「私もよ」と言う田中裕子。
お互い子供達に翻弄される瑛太と安藤サクラ。
そんな中で、高畑充希との対象として描かれているのでは?と思われるのが、湊の事を好きなのだろうと思われる同級生の少女の存在。
それまでは何かと湊の事を気にかけていながらも。《少女》でありながら《女》としての本能が反応しそうさせたのか?突如として湊に不利な状況を語り出したりする。
映画本編での三部の導入の始まりは、地方都市でのビルの火災からだった。
この火事の真相は本編中には明らかにされてはいない。
観客には不穏な要素だけ切り取られ提示されただけだった。それこそが監督が語る第四部の部分。
考えうる仮定としては或る人物を見限る人物の存在。
この人物は少なくとも3人との関係が有ったのではないか?
《好きな人の為に(自分には)何が出来るのか》
結果的に、自分の好きな人の為に起こした行動が。好きな人を追い込んだ人物を別の意味で追い込んだものの、その人物にとっての将来的には不幸からの回避に。
更には、自分に悪事を働く人物には今風に言えば、ブーメランの仕打ちとなった可能性も、、、
意味深だった※※※※※※で無邪気に走り回る2人の少年。
その意味を(自分の中では確定してはいるが)確認する為に、機会があればもう一度鑑賞したいとも思っている。
2023年 6月15日 TOHOシネマズ日比谷/スクリーン12
※ 〝 好きな人は居るけれども誰にも相談は出来ない 〟
鑑賞し、数日経った今。↑上の鑑賞直後に書き込んだレビューが、段々と勘違いも甚だしいモノに思えて来た(。-_-。)
映画の構造は(真実は単純なのだが)そこに行き着く径路は、もっと複雑多肢に渡るのかも…と。
要は、観た人の数だけ正解に導かれる《怪物》が有るのかも知れない。
【怪物だ〜れだ】
おそらく「怪物だ〜れだ!」は、3→2→1の順番で考えると1番分かりやすいと思う。
3では好きな2人の合言葉的な意味で。
時間経過が後になる2だと、トイレに閉じ込められた時に「助けてくれるかも」と思い使うと、そこには先生が。「何だ先生か」と手を洗う。
1では、転校するのが決まっているけどもう一度逢いたい。だから秘密基地で待っている。
心配で湊を探しに来た母親。
そこには〝 いるよ 〟のサイン
「あ来た!」と思い「怪物だ〜れだ」と言うと、そこには思っても居なかった母親の姿に戸惑うばかり。
母親に送られて帰る途中に携帯に連絡が来て思わず飛び降りる。
その直前の母親の一言は「立派な大人になって欲しい」(だったかな?)
やっぱり(テレビの女装の人を見て「ヤラセじゃない!」…って言ってたし)相談出来ないからか。
「お父さんのようにはなれないよ」
【校長先生の噂】
旦那さんに接見する校長先生。
その時の様子がネットで少し話題になっていた。
ひょっとすると◯◯症を患っていて、現在の状況が分かっていないのではないか?…と。
確かに前後の会話を考えると少しずつ信憑性が増して来る。
映画冒頭での野呂佳代の噂話はおそらく…
「野次馬で居たよ」→「あそこに居たんだって」に変化しているのは明白。
写真の角度は、角田(だったかな?)の台詞で勝手に考えた可能性もある。
案外と真実は、自分がソファー(椅子)に座って見える角度ってだけで直さなかっただけかも知れないし。スーパーの場面も、あくまでも第1部は母親目線で観客のミスリードを誘う【怪物】部分なだけに、、、
まだまだ考察しなければいけない箇所が数多くあって頭の中がぐちゃぐちゃになる。
でも今はまだどうやって纏めたならいいのか…が見えてこない、、、
だから、鑑賞直後に書き込んだレビューはとりあえず一旦はそのままに。
、、、しかし、、、勘違いも甚だしいのをそのままにして置くのもまた恥ずかしい話で(。-_-。)
《12月9日プライムビデオで見放題独占配信》
人生のバイブルにしたい
安藤サクラさんが受賞したのを拝見して、ずっと観たかったのでアマプラにて。
坂元さんの脚本に度肝抜かれました。是枝監督、教授の音楽、役者が皆素晴らしいことももちろん。
一度ではもったいない、もう一度、もう二度、見返さなければと思う。
なんとなく犯人探しをしてしまっていた自分も『怪物』なのだなと。
安藤サクラの『当たり前の家族を築いて』という言葉も、瑛太の『男らしく』という言葉も、子どもたちの視点に至るまで違和感を感じなかった人はたくさんいるのではないかな。
優しさの中に、当たり前の価値観や正義の中に、誰かを傷つけたりすることはないだろうかと、自分自身も、みんながそう問いながら生きられる世界になればいいのに、と。
特段、なにが真実か、生きるとか死ぬとか、性についてとか、まだもやもや不安なことが多い青少年期の子どもたちと関わる大人たちが心に留めておくべきことがたくさん描かれていると思いました。
クラスのいじめっ子も、新聞配達の仕事してたね。
きっと、中村獅童の背景にもドラマがあることでしょう。
体罰教師がメディアに取り上げられた事件の裏側には、淡い恋がそこにあるだけで、本当のワルモノは存在していないのに、でもみな『怪物』でもある。
たった2時間でここまで表現し切る映画は圧巻。
ラストがバットエンドと捉えている人もいるみたいだけど、私には手放しに喜べるものではないけれど、二人が幸せになれる世界への序章に見えました。
タイトル通り気持ち悪い
麦野と星川の子どもらしいギクシャクした反応は観ていて怖い
起こった事象を様々な人物の立場で繰り返し見せていく事で、「ああ、そう言う事か?」と徐々に納得させられていくのは面白い。「霧島部活やめるってよ」の撮り方を思い出した。
立場や価値観、善悪などを全て濁したまま終わるので、自分自身はモヤモヤしたままで見終わってしまった。
当然ラストの捉え方は人それぞれになってしまう…。
ただ、主役の少年二人が異様なほど役にハマっている。
依里の中性と見紛える雰囲気やそこに惹かれている湊の動揺など、次第に双方向の意識が高まりを迎えた時の緊張感はちょいと凄い。
思わず「これBLだったんか?」と、ぼそり呟いたほどだ。
大人の共演者面々はいつもとそう変わりない演技だったが校長の田中裕子だけが普段見かける作品とは違うイヤな演技に徹していて、かなり異質に感じた。
モンスタ-ランキング! 一体どのキャラが一番 怪物なのかな
------- VOL.3 -------
嘘、噂、偏見、思い込み、欺瞞、差別、格差、偽り、欺心、保身、慢心、軽蔑、放任、忖度、媚びへつらい・・・憎悪の数々
これらを総称し、吹聴し そして最後に「知らんけど!」(;^ω^)
★モンスタ-ランキング★ ※感じた事言いたい放題ですみません。
第5位:麦野早織
母親だけど、旦那が女作って逃げて死亡。女作らせる原因あり?
過保護な一面。何度も学校へ面会に行き謝罪させる。やはりモンペかも。
子供の話を素直に聞きすぎたのが一因。
校長室での一幕は大爆笑の展開であった。
第4位:星川清高
父親だけど、妻が失踪。男作った?その原因ありかも。
子供を放任し過ぎ。また心身共に虐待を行っていると感じる。
息子を豚の脳人間、女みたいだと蔑む。息子への愛情の欠片も無い。
昼間っから酒飲む。粗暴な親父。初対面の担任の先生への態度は良くない。
第3位:保利道敏
あんたバカ~て思える程のお人好しの 謝罪場面にそして会見。
とにかく 謝り最中にいくら緊張をほぐす為とはいえ、それを緩和するのに
飴食べるとは。彼女に勧められたらとはいえ、場所とタイミングを弁えろ。
ちょっと抜けてる。マジでガ-ルズバ-でハッチャケてそう。
だから形勢逆転劇みたいな目に遭う。飛び降りしなかったのが幸いのメデタイ人。児童に総舐められてる先生。鏡文字の謎解き文章に気が付いたのだけが冴えてるかも。国語のうんちくキツそう。
第2位:伏見真木子
保身のため?自らの名誉のため?自分の孫を車で轢いておいて、旦那が運転やった事にしたのか。ス-パ-ではしゃぐ子供の足をわざと引っかける。
校長室 机上の写真立てを自分を良く見せる為にアザトク置き直す。
大して音は微妙なのに楽器を鳴らす。音楽先生ってこんな非常識な感じな人が多いのか。何故か子供に興味が無い性格が漂ってて良くそれで小学校の校長に成ったと思う。率先して児童を探しに行かないと。問題解決に対して旗振り役に成れてない。校長室の謝罪場面はマジなら最低な対応だと感じる。
第1位:麦野湊・星川依里
小学生だからといって、シングルマザ-、ファ-ザ-の子供だからと言って
何でも有りではいけない。湊が母へ嘘の保利先生の事を告げ問題化させた。
親に心配させる様では駄目だぞ。親を憎むなら尚更、親の様な振る舞いに成ってはいけないな。父や母を助ける存在にならないとね。
他人がどうなるのか考えないと、巻き込むような事件(放火)は決して赦されるものでは無い。人を好きに成るのは男女関係なく罪では無いよ。愛とはそう言うもんだよ。
豪雨の中、アノ場所が危ないって知ってたよね。あのサイレンの音。
出発の合図な訳がないやろ。親に心配させて探させてはイケないな。どんな遊びをしようが、何処に行こうが 必ず家に帰ってきて”タダイマ”と言わないと。
そして 今より強く生きて行かないと・・・
第0位:是枝監督
毎年周囲に期待されて映画撮ってるのが、凄い事でもあるが、精神病んでいないか心配してしまう。だからこんな作品を撮ってしまうのかもですよ。昔の伊丹監督を思い出す。だから心配しちゃうね。今作はやっぱり過剰演出が目立ってしまい、折角の脚本を十分イカせられなかったと推測するわ。
怪物を撮るなら自ら怪物で無くては無理でしょう。
監督の心の深淵を垣間見た気がします。
次作に大いに期待しております。
------- VOL.2 -------
ラジオでやってた と或るカフェCMを思い出したんよ。
「知らんけど!」編。
当事者の如く周囲には詳しく話して回るけども・・・
話の最後は 「知らんけど!」の言葉。
知っているのか 知らないのか・・・
決定的には言えないけど、最後は曖昧に真相を濁す~
きっとソレだと思うわ。
------- VOL.1 -------
公開初日、台風の影響でどこもが集中豪雨~
何て日だ!(小峠かよォ)
しかし、この物語には この豪雨に関係したシ-ンが有り、心の何処かに、ひょとして あの子達・・・無事に戻れるだろうか、
それとも誰も触れる事の出来ない世界へ旅立ってしまったのだろうか・・・ 今思えば そう思う~。
今日は先日、
第76回カンヌ国際映画祭 コンペティション部門 最優秀脚本賞(坂元裕二さん)受賞の「怪物」を観に行った。
監督・編集:是枝裕和さん
脚本:坂元裕二さん(最優秀脚本賞おめでとうございます)
音楽:坂本龍一さん(ご冥福をお祈りいたします)
MC
(シングルマザ-とシングルファ-ザ-の家族と子供達)
麦野早織(シンママ):安藤サクラさん
麦野湊(息子・星川の親友:黒川想矢さん
星川清高(シンパパ):中村獅童さん
星川依里(息子・放火・イジメ受ける):柊木陽太さん
保利道敏(担任教師):永山瑛太さん
鈴村広奈(保利の恋人):高畑充希さん
伏見真木子(校長・孫轢く):田中裕子さん
正田文昭(教頭):角田晃広さん
兎に角、ちょっと思ってた内容とは違った印象を受けました。
これは 何処の小学校でも起こりうる学級内イジメがテ-マです。
シングルマザ-、ファ-ザ-の家庭の子がタ-ゲットになっててこれを取り巻く クラスの子供達や、担任教師、周りの先生、教頭、校長の対応や 家族の親視点で語られ展開していきます。
・最初、ガールズバ-の入居してるビルが燃え盛る。必死の消火作業。
ここの火災の絵はキレイに非常に良く撮れてたと思う。
原因は何か?事件、事故か分からないがガールバ-に保利先生が通ってる噂話が広まる。事件性と関連性は分からない。しかしコノ火災は意味が有ったと後半に分かる。
・母親(早織)視点で語られる展開。
息子がイジメを受けている様で、しかも担任の先生から。
原因を追究すべく学校へ乗り込む。校長、教頭、過去担任教師が対応で一斉に謝る。全く訳が分からない母親。モンペと思われ兎に角 謝罪作戦にあう。保利先生からも謝罪を受けるが ココの一連の流れ展開が非常にコメディっぽく思えて なぜか笑えてくる。真面目にやってるんだけど可笑し過ぎだよ~。
特に飴食べ出す先生を見てギャグかと思えた。(後に理由が分かるのだが)
演出が少し過度と思われます。
・保利先生の視点展開
児童の母が乗り込んできて、説明しに行こうとするが教頭らに止められる。児童イジメ(麦野 ⇒星川イジメる)であったと勘違いしてしまう。先生に豚の脳だと、耳を引っ張られたとか言うが、この事はすべて麦野の嘘である。
周囲の先生から謝罪するよう勧められたが全く道理が通ってなく納得がいかない本人。しかしこの件が問題視され、保利先生が校内で窮地に。
学校を追いやられて雑誌にまで載る羽目に。恋人も離れていってしまい学校の屋上から飛び降り自殺をする手前まで行き・・・留まる。
ココの展開は あれよあれよとアッと言う間に先生が窮地になってて、非常に噂は怖いなと感じた。ビル火災の噂話とか、事件の真相を誰も確かめず決定打を下す~、この心理性が正に怪物を生み出すんだと思う。
・麦野と星川の視点展開。
元々二人は友達でもなく、仲良くはない。
星川は前の学校でもイジメられていて、コノ学校でも嫌われていた。また転校に成ると考えていた。楽器を返しに一緒に行ったとき隠してたお菓子を星川から貰った。そっと髪(頭)を星川が撫でてきた。話しかけて来ないでとお願いして部屋を出る麦野。イジメが自分にまで及ばない事を思っての事と思う。彼は家へ帰ってから彼が触れた髪の毛をハサミで落とす。この時点では縁を切りたかったのだと思う。
女を作って母と自分を置いて出て行って死んでしまった父を持つ麦野。
同じ様に自分と父を置いて出て行った母を持つ星川。
お互いの不幸な境遇が彼らを引き寄せ、やがて親友になって行く。
相手の事を思いやりつつも、イジメに遭う方、それに巻き込まれない様にする方。お互いがお互いを庇い合って生きていく・・・ここが一つのポイントかと。
確かに男の人に興味が有ったかも知れない星川だが、過度とは思えない。母の愛、父の愛を受けられず育った子で有ったため 甘えたかったのではと思う。
少年なら誰でも良くやる秘密基地ごっこ。彼等の心の希望、旅路をひた走る 廃墟化した車両。ここの空間だけが二人にとって、誰からも手が届かない世界であったのだろう。
・やがて・・・
保利先生は 偶然にも星川作文の鏡文字の謎を解いた。
そして、麦野と星川との仲を誤解していた事。
クラス中の皆と二人の関係性の本当の姿に気がついたのだった。
豪雨の中、麦野邸で大声で麦野に真実を理解したと話しかける保利先生。また母親も出てきて息子が居ない事に気が付く~。
そしてそれは、その時が既に遅かった事を語っていたんだと~
今、それを大人達が初めて気付き、二人の行方を探し追いかける。やがて秘密基地が有った土砂災害の現場。流し圧し潰された廃墟車両。
泥で真っ黒の窓。手で拭いても直ぐ泥で塞がれて。
激しい雨が泥をハジク。そこだけが銃の玉が当たった様な表現。
何度も 何度も そして何度も。
彼等の乗った車両の窓、心の窓を大人達が必死に開けようともがく。
ココの描写は素晴らしかった。本当に良く出来てたと感じます。
そして やっとの思いで開けた心の窓の奥に・・・見得たもの、
大人達と、子供たち二人に 最後に訪れたものとは。
ここのシーンは 皆さんの心の目で確かめて
欲しいと感じます。
ご覧頂いた方々が怪物に成らぬ様、
祈りを込めて 坂本龍一さんの最後の音色が
エンディングを優しく包み上げています。
ご興味有ります方は
是非、劇場へどうぞ!!
当たり前のことに気付かされる作品
不確定要素一部自己解決残り勝手に考察してくれ作品。
不確定要素一部自己解決残り勝手に考察してくれ作品、とでも表現したくなる。 まあ私の好きな作風ではない。
タイトルは、人の心には誰でも "怪物" が存在するという漠然としたもので、予告編で「怪物だ~れ」を煽っているが、個別な表現ではないかと。
まず内容と違う視点から。
最近、「伏線の回収が見事」とか、「ラストで疑問シーンが一気に解決」とのレビューをよく見かけますが、
その作品はなぜ、"伏線" を張っているのか考えた事があります?
それは当初の脚本通りに通常時間軸で物語を進めただけでは、物足りない作品(見応えがない作品)になってしまうから。
それを補う為、後に起こるワンシーンを前半に持って来たり、その時点でわざと説明不足に描写して考察ポイントを作り、ラストに解説描写としてまとめて表現してる訳です。
(勿論、推理物や、追想シーン・過去の出来事説明シーン等は含まない)
それにより、見る者側は考えるポイントが増え、謎が解けた満足感が、作品全体への満足感に繋がる場合も多い。
が、歴史的名作には、その様な作風の作品はほとんどない。
さて本作。 まずよい点を。
出演陣はキャスティングが上手いせいもあり、皆存在感ある演技。 私は安藤サクラより、二人の子役と永山瑛太に目が留まった。 特に子役二人が怪しい雰囲気になるシーンは、(演出的にはこんな子供までマイノリティ性愛が?と気持ちよくなかったが)とても演技には見えない。
顔が接近してもミナトは目を見開いたまま、ヨリは2度ほど瞬きするがお互い目線を外さない。
その後気まずくなる表情まで抜群で、ベテラン俳優でも難しいと思うシーンをさらりと演じている。
瑛太はミナトに「なんにもしてないよね・。」と同意を求める様な笑顔から、冷めた表情への変化が絶妙だった。
あと「TVで見てるから嘘だと分かる・・」や「体中の力を全部抜いて、諦めます・・」等、その作品の重要点を暗示している言葉が多く、台詞はかなり練られている。
(特に後者はヨリが親から○○されている事を・・)
と、出演陣や台詞表現は文句なしだが、最初のパートの先生達へのクレームシーンで、長く頭を下げ続けたり、校長の鼻を指で押さえる等は過剰演出に感じ、感情がやや離れる。
さらにミナトの異常行動で、こんな作品かと・・今度は呆れる・・。
その後、時間軸が遡る進行に戸惑い、火事も2度目?等の疑問も湧く。 幸い配信視聴なので、疑問箇所のおさらいにもう一度見て、3つのパートが主人公を変えて、それぞれスタート地点に戻って描写されている事を認識・理解。
が、こいう作品こそ、最初のパート「母親」、次は「担任」、ラストは「子供達」など、章タイトル付けて見る者に分かりやするする事が必要と感じる。
でないと、映画を見慣れてない者には、ただ難解な作品とだけで片付けられてしまう。
タイトルを付けない=観客にさらに疑問を付加してやろうとの制作側のよこしまな思惑に感じる。
↓ ネタバレ含む
もし今作が時間軸通りに全ての描写が表現されていたと仮定して考えてみて下さい。
ラストは美しい描写でも、途中わざと誤解を生むシーンを何度も作ってない?と気付くはず。
そして今作で一番やっかいなのが、不確定要素を多く含めたままでエンディングを迎える点。
火事の犯人、校長事件の真相、ミナトとヨリの生死、等々。
これらは各自で考察してくれと言わんばかり。
ハリウッド作の「TAR/ター」も不確定要素が多く、類似していたなと思い出す。
それに細部を指摘すると、貸した靴と玄関に片方残った靴が色が違う。廃墟電車シーンが3度あるが、2度目シーンでは電車右側にトンネルの入り口が見えるのに、他のシーンでは見えない。(別の場所?との疑問も・・)
線路へ繋がる道で、最初シーンは雑草が二人の膝ぐらいの高さが、ラストシーンではミナトの身長ぐらいあり、閉まっていた鉄骨柵の所と同じ道だったのかも分からなかった。
(故に、真っ白にホワイトアウトしたシーン以後が、違う世界なのかリアルなのかの想像判断にも迷う・・)
ラストの走りシーンは、生き生きと子供本来の笑顔描写が素晴らしいのだが。
見たいからもう一度視聴するのと、謎解きの為に再視聴するのは、全く意味の違う行動。
前述はもう一度感動を味わえるが、後述は理解出来ただけで終わってしまう場合も多々。
今作も疑問点や確認の為、2度半も視聴したが、ほとんどレビューを書く為の作業で終わってしまい、自身「何をしてるこっちゃ・・」と・・。
PS
クィア・パルム賞はLGBTQの関連映画に与えられる賞だが、クィア(queer)とは、「妙な、変な、いかがわしい」等の意味もある。 小児性愛者もこれに含まれる為、性犯罪を含むマイノリティをも承認させてしまう事に繋がる懸念が・・。
全1013件中、201~220件目を表示