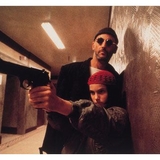正欲のレビュー・感想・評価
全400件中、1~20件目を表示
そのひと、ひとりじゃなかったらいいね
結局のところ、人は誰にも明かすことのできない嗜好があるのだと思う。そしてそれは説明できない類のものであることが多い。
わかってほしいのだけど、わかったふりはしてほしくない。ひっそりと自分の嗜好とともに世界の片隅で、息を潜めて行きて行くことが自分が傷つかずに済む方法だとわかってはいるのだが、「共感」「理解」の幻影に騙されて淋しさに押しつぶされそうになる。
自分だけが違うと思って生きている人も世間一般の常識で生きていると思っている人にもそんなに差はないと思う。「生きる」ことをどの角度から見ているかが違うだけ。でも手に持ってる「信頼」とか「愛情」とかってプラスのアイテムをいくつ持ってて、それがハイスペックなものかどうかで「生きる」ことは受け入れやすくもなるし、受け入れがたくもなる。生きにくさこそが普遍的なものかもしれない。
多様性を語ると実は答えはシンプルなものになるのではないだろうか。
生きていくうえでの苦しみや辛さはひとりで抱え込めないからオーバーフローしちゃう。
もし奇跡的に「同志」が見つかったときは、いなくならないでほしい。お互いに。
普通に生きていく事がほんとはレアなのだから。
集中力のある構成で、佳作だ。これは日本でしか作れないタイプの作品。
八重子役をされてた東野絢香がいいと思った。「貞子」感溢れる動きや仕草、眼差しが印象的。
「多様性」と言いながら一つの方向に導こうとするのは誰か
原作は未読だが、朝井リョウらしさを感じさせる群像劇。「噴出する水に性欲を感じる」という超少数派な性的指向を持った孤独な人間たちが、ようやく繋がりを見出すものの、不運な出来事が彼らに起こって、といった話。
「普通の人たち」の悪気のない傲慢さや、彼らの「普通」な姿を見る時の夏月(新垣結衣)の肩身の狭さが繰り返し描写される。立ち入ったことを聞いてくる職場の妊婦の先輩、売り場でたまたま出会う親子連れの同級生。大也(佐藤寛太)のダンスサークルの女の子が主張する「型通りの多様性」。寺井(稲垣吾郎)が家族に対して繰り返し示す、子供の教育の「普通」。
「普通」に固執する(ように描写される)寺井が最後には家族を失う一方、佳道と異端の絆で結ばれた夏月は対照的に、佳道の元から「いなくならない」ことを「当たり前のこと」として寺井の前で宣言する。まるで、同調圧力で「普通」を押し付けてくる多数派への、少数派の意趣返しのようだ。
「性欲の対象が水」という設定は、ちょっと綺麗すぎて、あまりグサっと刺さってこなかった。夏月と大也の自慰描写がかなり抑え目だったこともあり、見た側が受け入れられるか問われてつい逡巡し、己を振り返ってしまうようなインパクトには欠ける。「水への欲情」は、マジョリティの「人への欲情」となんら干渉しないので、変わってるなあとは思うが、拒否感は起こらない。
既存の倫理観から逸脱するかどうか紙一重の指向の方が、観客が試されたのではないか。超マイノリティの疎外感といえば「流浪の月」を思い出すのだが、あちらの孤独の方がヒリヒリしていた。
寺井の家庭の描写はどう解釈するか迷う部分があった。
確かに、頭ごなしに否定するかのような寺井の態度はよくない。しかし一方で、息子は不登校の理由もよく分からないし(父親への説明の第一声が子供YouTuberからの影響、動画を見せるだけで自力で説明しない)、妻は夫を責めてやたら感情的になるわ息子に片付けのしつけもしないわ、安易に右近先生に依存するわで、何だかどっちもどっちのように見えてしまった。
私が寺井の立場だったら、最初は彼に近い反応をしてしまうかな。息子が学校に行きたくない理由をまず確認して、妻の話も聞くようにはしたいけど。YouTubeで有象無象の視聴者のリクエストに答えるよりは、学業を修める方が大事だから。学校が無理ならフリースクールで。
終盤、水を愛でる集まりに紛れ込んだ性犯罪者の逮捕に佳道(磯村勇斗)たちが巻き込まれ、検察官の寺井は彼の主張した「水への関心」を誰かの入れ知恵と決めつける。しかしこれはある意味仕方のない展開にも見えた。
何故なら、仲間の1人の矢田部が性犯罪者であることは事実で、その矢田部から子供の映った画像を受け取っていることも残念ながら事実だからだ。同じ場面で「子供に関心はありません、大人の女性が好きなので」とマジョリティ的な受け答えをしたとしても、上記の状況がある以上寺井は簡単には信じなかっただろう。
だから、終盤の流れは彼ら超マイノリティへの世間の風当たりを表現する方法としてはちょっとずれている気がした(違う意図があるのかな?)。
「時流に乗って多様性を称揚しているあなたたちは、こういった人々のことまで想像して多様性を論じているか?」という問いかけが、本作の眼目ということだろうか。しかし、そもそも少数派へ想像力を持つとか、知ってどうすべきかという発想自体、自分は多数派であるという認識、そう思いたいという願望から来るものだという俯瞰の視点も必要なのかもしれない。
これは私の個人的な考えなのだが、「多様性を肯定する」とは自分と違う人間を否定しない「わきまえ」を持てばそれでいいと思っている。言い換えれば「多様性を”否定する態度を取らない”」「他人が多様であることを邪魔しない」くらいでいい(とはいうものの、相手が身近な人間だったり、自分の価値観と干渉する時はこんなことでさえ難しい)。互いの生き方の邪魔さえしなければ、内心で「水に興奮するとか変わってる……わからんわ」とか、逆に「セックスってトレーニングみたい……滑稽だ」程度のことは考えたって別に問題ない。そこで「理解しなきゃ、受け入れなきゃ」と内心を押し殺す時、あるいは「理解しろ、受け入れろ」と変容を強要する時、多様性賛美は欺瞞に変わる。
ガッキーの新境地的役柄が話題の本作だが、私は東野絢香の「こういう人いる」感が印象的だった。あと、磯村勇斗は「月」のさとくんからのこの役でなかなかヘビーな仕事の流れだなと思った。「月」の撮影終了後5日ほどで本作の撮影に入ったそうだ。さとくんで得たものが佳道に通じるところもあり、それをベースにして役に入っていったという。
メンタルコントロールも俳優の技術のうちなのだろうが、何だかすごい。
今作られるべき映画
発売当時に原作小説を読んで凄い作品だと思っていたが、まさか映画化されるとは思わなかった。この性的欲望に映像でいかに説得力を持たせるのか、この作品が描くものはシンプルなエロスではない。あまりにもレアで多くの他社に理解されないがゆえの苦悩を描く作品だが、まさに多くの観客にとって普通に提示されても理解が難しい題材だ。
現代社会のキーワードに「ポリティカル・コレクトネス(政治的な正しさ)」がある。ポリティカルとコレクトネスと2つの単語が構成されているこの言葉は、「ポリコレ」と省略されて使われることが多いが、2つの単語から成るものだと意識した方がいい。
コレクトネスという観点で本作を観ると、本作で描かれた人々を犯罪者扱いするのは「正しくない」はずである。しかし、ポリティカル(=政治)な議席の数には限りがある。全員がその椅子に座れるわけではない。政治を社会をスムーズに営むための統治で多数決を原則とするなら、多くの人が理解できない性癖の持ち主は排除されるべきとなりかねない。この作品に描かれたものは、ポリティカルとコレクトネスに引き裂かれており、この単語の矛盾を的確に指摘している。
多様な人間が暮らす現代社会は、多数決の原則で動かざるを得ない政治的な正しさだけでは包摂しきれない。だから、マイノリティは政治運動を展開し、政治的なパワーを得ようと努力してきたわけだが、現実問題として、どんな属性でも政治的なパワーを持つことが可能かというと、そんなことはないかもしれない。皆が平等になるのが正しいが、政治の椅子の数は決まっている。今作られるべき映画だったと思う。
透明感のある生々しさ。現代社会を捉えたひとつの写し鏡として。
不思議な、得体の知れない手触りを感じさせる作品だ。透明感のある生々しさは「水」のイメージからくるものだろうが、水と言っても、澄み切ったものから濁りきったもの、澄んでいるけれど危険なもの、さらには性的なものまで実に様々だ。おそらく我々はこの「かっこ」的な部分に自分なりの様々な要素を当てはめて捉えることができる。「自分を理解してくれる人なんて誰もいない」という孤独感や、同じ嗜好性を持った誰かと奇跡的に出会うことの喜び(およびその反作用)は何も今に始まったことではないが、しかし本作はあえてギリギリの淵に立った者たちの繋がりに焦点を当てる。その上で、共に気づきや安らぎを重ね、いつしかふと相手を愛おしいと感じたり、守りたいと感じたり、つまりは知らぬ間に壁が融解し、「私」が「私たち」となっていく過程に寄り添おうとする。新垣の徐々に変わりゆく表情に心奪われる。それは対極的な軸を担う稲垣においても同様だ。
欲望や嗜好に“正しさ”はあるのか
高校を舞台にした「桐島、部活やめるってよ」、就活生たちの関係を描いた「何者」といった具合に、映画化された朝井リョウの代表的な小説を並べてみると、作家としての成長に並走するかのように登場人物らの年齢層が上がり、描写される内面もまたより深くより複雑になっている。さらにこの「正欲」では、小学生の息子を育てる夫婦、かつて中学の同級生で15年後に再会した30がらみの男女、大学生らといった具合に平均年齢が一層上がり、マイナーな性的嗜好、価値観の相違、対人関係の悩みといったテーマが交錯する群像劇となっている。
水をめぐる性的興奮と快感を鮮烈に描くシーンがいくつかある。たとえば、ベッドに横たわる夏月(新垣結衣)が水に浸されていく心象風景(映倫区分がGで大丈夫か、親が未成年の子と観たら気まずそう、などと余計な心配をしてしまった)。交通事故に性的快感を覚える人々を描いたデヴィッド・クローネンバーグ監督作「クラッシュ」や、ヘイリー・ベネットが異食症の女性を演じた「Swallow スワロウ」のように、特殊な嗜好を観客に想像させる一面はあるものの、より強い印象を残すのは、ある事件の事情聴取を行う検事・寺井(稲垣吾郎)と夏月との“かみ合わなさ”だ。自分に理解できない嗜好を否定し常識で物事を決めつけようとする寺井を反面教師に、さまざまなレベルでの多様性を受け入れるには想像力と柔軟性が必要だと映画は示唆する。他人に迷惑をかけたり法を犯したりしないことが大前提とはいえ、欲望や嗜好に正解も間違いもないのだ。
こ、ここで…
出演者たちの行動、思いが後半に進むにつれて少しずつ交錯していくのはよくある話だと思いますが、その描かれ方が個人的にはとても面白かったです。
ほんとは星4以上の評価でもおかしくないくらいなのですが、終わり方というか、その盛り上がりが最高潮のタイミングでまさかあんな終わり方をするなんて…。
確かにあのラスト後を描くのは非常に難しいと思いますが、自分はどんなエンディングにせよもう少しラストシーンの後の世界を見たかったです。
わかるには分かるけど
普通の感覚を持ち合わせていない人達にスポットを当てた映画で、その人達の気持ちもわからなくもないんだけど、自分たちだけが被害者っぽくしてるのが腑に落ちない。謂わゆる普通の感覚を持った側が何も悩んでないと思ってるみたいだけど、みんなそれぞれ悩んでるしそれぞれ問題を持ちながら生きているのだ。何もお前らだけじゃないんだ、理解されないで苦しんでいるのは。そういう人達もいるという事を映画の中ですこしでも描写して欲しかったです。
ガッキーの卵巻き食べたい
陰キャ共感率98%。
陽キャの人は見ないでください。
映画として面白いか?は別として鑑賞後に、もの凄い語れる作品ではあると思う。多分、僕も2時間ぐらいは語れる。(それが映画として面白いと言うのかもしれないけど)
老害と言われる様な固定観念で苦しむ生きづらさはもちろんあるが、ただあまりにも多様性の受け皿を広くしすぎてもそれはそれでおかしくなる。何処かで線引きは必要。
正直な話、水しぶきで欲情しようがしまいが、人に害を与えなければどうでもいい。
それは警察側も思っているよ。でもそのフェチが行き過ぎて性犯罪を犯す輩がいる。
水しぶきで興奮しはる人と水に濡れた小児で興奮して性犯罪を犯す人の境界線をきっちり引ければいいけど、それって不可能に近い。だから社会はそこを大きく一括りで同じ「あり得ない」にしてしまうのではないだろうか!?
世間で言う「普通」ということについて考えさせられた。
個人的に衝撃的だったのは警察役の稲垣吾郎が劇中、多分、妻にも子供にも間違ったこと一言も言ってない様な気する。でも現代ではその一言一言が悪者扱いされるんだよね。
生きづらい世の中になったなぁ〜
色々な人の人生を交差させるという手法はよく用いられる。 無理やり交...
素朴なガッキー
性欲に正しいはあるのか。それを決めつける権利を持っている者は居るのか。
かすかな灯り
大きな抑揚もなく、淡々と進んでいく印象を受けた。
「普通」「常識」の考えにがんじがらめに囚われている人と、「生きづらさ」を抱えている人たちのコントラストがリアル。
ガッキーも顔が違ってみえるほど役になじんでいて、表情、特に目の演技に説得力があった。
特に素晴らしかったのは八重子役の方。気になる存在になった。
ラストのガッキーのセリフがこれまた素晴らしい。
「待ってる」とか「信じてる」ではない、言われたらとても心に残る温かい言葉。
全体的に薄暗く静かな映画で、生きづらさを感じてる方々の心模様を表しているかのようだったが、その言葉でかすかだが消えない灯りがともったようだった。
感想を言ったら私の中でそれは嘘になる
毛色の変わった尖った映画で、後でじわじわと面白さがわかる映画
監督が「あゝ、荒野」の岸善幸。
「あゝ、荒野」は好きな映画だったので次回作は見たいと思っていた。
(そしたらその間に「前科者」があった。まだ見てないけど)
毛色の変わった尖った映画で、後でじわじわと面白さがわかる映画だった。
新垣結衣が、最初、オーラを消した演技で驚く。
で、なんで新垣結衣を起用したのか?と思いながら見ていた。
見終わったら、なるほどと思った。彼女の表情の変化がこの映画を串刺す映画的なスペクタクルになっていると。ラストの表情はやはり新垣結衣でなければと。
映画は、ちょっとまとまりのない感じだったけど、監督にはまとめる気のなかったと思う。それぞれ尖る役者たちをしっかり捉えていけば、話は通じると確信していたような気はする。
役者では東野絢香は素晴らしい。痛々しくて泣けてくる。彼女を見るだけでもこの映画は価値があるかも。
佐藤寛太も太々しくて、繊細で、良かったし、磯村勇斗っていい役者になったと思う。稲垣吾郎も常識者を痛い感じで体現していて上手い。
全400件中、1~20件目を表示