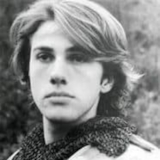ザリガニの鳴くところのレビュー・感想・評価
全444件中、261~280件目を表示
美しい情景で描かれる恋愛モノでした
湿原は観察すればどこまでも美しい自然なんだ
湿原とか沼は今までのイメージでは陰湿で暗くて怖い所だった。いや、そうではないんだ。
光、水、動物、植物。みんないきいきしていた。
ラストはやはりそうだったのか!
弁護士さんグッドジョブ。
沼系女子、爆誕💣
自分の世界だけで生きていきたい、
内向的な女性のメンタルが生々しく描写されています。
重くて難しいテーマを、よくぞここまで❗️👏
普段から弱くて大人しいフリをしている女性程、
裏で相手をコテンパンに叩きのめす事を考えているものです。
あまりの生々しさにノンフィクションなのでは❓と疑ってしまいます。
ラストシーンは視聴者に嫌な予感を与えつつ圧巻のクロージング。
事件の真相についても、彼女が本当に愛する人も。
この衝撃をぜひ劇場で❗️とオススメしたいですが、
一つだけ注意点が。
映画のシーンとして想定されるデートには全く向かないです。清々しいほどに😂
それが都心週末でも空席が目立つ背景の一つでしょうか。
オススメは1人または重め作品が好きな友達とじっくり観るか。
はたまた、自分のペースで読める原作を読んでみるか。
楽しみ方を選べる点でも魅力的。
沼系女子、そんな新しいカテゴリが出来そうなインパクトのある作品でした。
心震えるラブストーリーの秀作
原作未読の予備知識なしで観たため、サスペンスだと思っていたら、いわゆるラブストーリーで意外でした
ストーリーは特に目新しさや驚きもなく淡々と進みますが、作品自体はアメリカのノースカロライナをバックにした重厚で美しい映像と緊張感漂う上手い演出で、結果とても高い品格を備えた見応えのある秀作として完成されています
幼少期に親兄弟に見捨てられ、沼地で孤独に生きてきた少女カイヤが成長し抱くピュアな恋心が見ていて切なく、それを弄ばれた事が判った時の絶望感がたまらなく悲しかった
そして自然界では善悪が無く、雌カマキリは身を守るために雄を殺す、と劇中 口にする様にカイヤは雌カマキリと化して自分を弄び暴力的になったチェイスを葬ったのでしょう、私の中でもアリな選択です
その主役のカイヤを演じるデイジー・エドガー=ジョーンズさんが役にピッタリハマっていてエネルギッシュな確かな演技で魅せます、それに加えとても綺麗で素敵な女優さんでした、今後の活躍に期待です
最後はカイヤは人生を全うし、"ザリガニの鳴くところ"でママと再会し逝く
とても見応えのある秀作でした
信じられない
あまり事前情報は入れずに観た。
雄大な自然の中で物語が進み全体的に静かな雰囲気。
そして観ていくうちにカイアに知らず知らずのうちに惹き込まれていく。
僕は後半裁判が終了する頃には、「この物語はミステリーというよりはこの事件を通してカイアの成長を描くヒューマンドラマなのかな」と思っていた。
ただ最後の10秒でこの作品がミステリーであることが思い出される。
自分にはこの展開は予想できなかった。
というか、カイアが魅力的すぎてそういう発想にならなかったというべきだろうか。
映画が終わった後もなんだかんだ理屈をつけて受け入れようとしない自分がいることに驚いた。
作品の中の人物にそこまで惹かれていたのかと。
そういう意味で言うとこの衝撃は日本の“イヤミス”と称される作品群と似たようなところがあった。
ザリガニの鳴くところに行き着いた彼女は、そして湿地となった。
ザリガニが鳴くなんて聞いたことがない。おそらくこれは一種の比喩的表現だろう。ザリガニの鳴き声が聞こえるような世界、それはまさに人知を超えた自然界の奥深くを言うのだろう。
主人公カイアが幼き頃、湿地に建つ家で家族は仲睦まじく暮らしていた。しかし、ベトナム戦争帰還兵の父はPTSDで心を病み、家族への暴力が絶えなかった。家族はやがて幼い彼女だけを残して離散し、そして父もまた失踪する。
一人残されたカイアに対して偏見に満ちた世間の目は冷たく、雑貨屋の黒人夫婦を除いて誰も手を差し伸べるものはいなかった。彼女を受け入れてくれたのは自然豊かな湿地だけであり、その自然の宝庫に囲まれた家で彼女は生きる術を身に付け、たった一人生き抜いてゆく。
世間からの冷たい仕打ちに貝のように心を閉ざした彼女だったが、幼馴染のテイトは彼女をなにかと気遣い文字まで教える関係になる。
深い絆で結ばれた二人。しかし外の世界を拒絶し湿地から離れようとしないカイアへの思いと、外の世界とのはざまで揺れ動くテイトはカイアを裏切ってしまう。
愛する人を失ったカイアの心の隙をつくように現れたチェイスにカイアは身をゆだねるが、それも所詮はチェイスにもてあそばれただけであった。
家族を失い、唯一愛した人にも裏切られた彼女は更に世間を拒絶し、その心は湿地へと傾倒してゆく。孤独を紛らわすかのように湿地の自然観察に没頭する彼女はいつしかその自然と同化していった。
そんな時、チェイスの遺体が発見されカイアは容疑者として逮捕されてしまう。果たしてチェイスの死は事故か、カイアによる殺人なのか。
正直、出版社の人間との会食中の会話でラストの落ちは読めてしまうが、本作のテーマはもっと深いところにある。
身寄りのない幼い彼女に手を差し伸べず、狼少女だの、人と猿のあいのこだのと蔑み、拒絶した世間が今度は人間たちの尺度で彼女を裁こうとする。しかし、彼女にとって世間のいう善悪など関係ないのだ。彼女は世間からつまはじきに会い、世間とは隔絶した世界で生きてきたのだから。そんな彼女を今更、自分たち人間社会の尺度で裁くなど、彼女にとっては理不尽以外の何ものでもない。
開発によって住むところを奪われた野生動物が人里に降りてきて、農作物をあさったり、人を襲うことがある。彼らにしてみれば生きるための至極当然の行為である。しかし、人間は彼らを害獣と呼び、駆除してしまう。
自然に善悪などない。みな生きることに懸命なだけである。しかし、人間はそれに対して自分たちの尺度で善悪の区別をつけたがる。
彼女が犯したのは人間社会でいうところの殺人である。しかし、自然界では生き抜くための至極当然の行為だった。
たった一人社会から隔絶した世界で一人生き抜き、人間社会ではなく自然界に生きる彼女を人間の尺度で裁くことに一体どんな意味があるだろうか、と考えさせられた。けして殺人を肯定するわけではないけど。
本作のラストは確かに衝撃的だが、逆に妙に納得のいくものでもあった。後、弁護士さんは最高。
沼地少女の一生
ひぐらしのなく頃に‥
怖い映画じゃなかった
タイトルとポスターの雰囲気から、ホラーかスリラーサスペンスかと覚悟してたけど全然そんなことなかった笑
沼地、都会、それぞれに生きる人たちが、ルールと本能に翻弄されながらも必死に生きていく姿が印象的。
物語に衝撃的な展開はないものの、沼地に生きる主人公、自然の描き方、人間関係の描き方がうまく、飽きずに見ることができた。
特に沼地での生活という概念自体が馴染みがなく、新鮮だった。
性的なシーンもあるが、人間的な性と動物的な性や、ベッドシーンを使っての世界の対比がうまく表現されていて、それがよりテーマを際立たせていた。
チェイス役の人はどこかでみたことあると思ったら、キングスマンの人だったのね。高貴で一癖ある役が似合う。
ラストはびっくりだけど、自然な感じで後味はとてもいい。
湿地の映画
ストーリー、映像共に素晴らしかったです!!
両親に捨てられ、町の人からは避けられ、湿地で1人になった少女カイヤ。
唯一優しくしてくれた雑貨店の夫婦からもらったドレスを大事そうに撫でているシーンは胸が打たれました…ちゃんと女の子なんだなと。
湿地の中で一人という特殊な環境で生きてきたカイヤにとって、人間も湿地の生態系の一部に過ぎなかったんだろうな。ただ、出版社との会食のシーンで、カイヤが語っている言葉は、自分に言い聞かせているのかなとも感じられました。
自然美
アメリカ西海岸の田舎、湿地帯の美しさと怖さ
極上ラブストーリー
日本でやるなら斉藤由貴(尾崎豊→川崎麻世の頃)で
割とドロドロした映画ですね??
最初から最後まで主人公のナレーションで、
センチメンタルに終わる感じだけど、そこで見せてるのは、
カイアの絵日記を見つけて驚愕する夫。
「おっそろしい女じゃった〜〜〜!」とでも字幕入れますか。
でも、そこ、すっげーサラっと描いてテイラー・スウィフト流しちゃう。
原作者は動物学者って事で、主人公にも善悪の観念のない動物を据え置きました。てか?
お父さん暴力ふるう人だったって事だけど、
カイアにもその精神受け継がれてますね??
それがDVホイホイとなって、男たちに暴力ふるわせてる向きもあるかと。
チェイス、って可哀想な人だと思うよ。
本音で話せるのが、カイアだけ。
世間体とかいろんな社会のしがらみの中で、
制約の中で生きてるから。だから、フィアンセも本当に建前なのだと思った。
(例えばここを同性愛とかの設定にしたら、もっと分かりやすくなったのかも。
本当は同性の事が好きだけど、建前で異性と結婚せざるを得ない、みたいな。
りゅうちぇるかよ)
もうちょっと動物的な部分を強調しないと何を言いたい映画なのか分からない感じが。
単なる「かわいそうな女性映画」にする事は、全女性を馬鹿にしている事にもなるのでは。
チェイスが「クソ野郎」なら、カイアもクソ女。
動物に善悪がないのなら、チェイスにもカイアにも、お父さんにも善悪ない。
それぞれが必死でサバイブしているだけなんだ。って?
もういなくなった家族の事を思い出して流した涙は、最後のオチでカピカピに乾いたのだった。
それは、生き延びるための必然
ノースカロライナ
アメリカ合衆国東海岸の中部
山岳・平野・海岸の分布がまんべんなく
気候も温暖で済みやすいため
全米第9位の人口である
今作はそのノースカロライナの
自然の中でもボートでの移動が
当たり前のような湿地帯が舞台に
書かれたディーリア・オーエンズの
ミステリー小説の映画化
でどうだったか
小説原作だからというわけでも
ないでしょうが画面外の
インフォーメーションが多く
常に見る側の裏をかいた展開は
最後までハラハラ見れました
わりと一本道で退屈な洋画の
ミステリー映画と違い
ほうと思わせる部分もあり
面白かったです
どことなく不自然なところは
あちこちあるんだけど
なんだろう
日本人には合ってるかも
しれません
1960年代が舞台
湿地帯で見つかった地元の名士の
息子チェイスの死体を子供が発見
警察は近くにあった物見小屋からの
転落死と断定
しかし警察や地元住民はあたかも
特定の「湿地の娘」がやったに違いない
と決めつけるような噂を広め
遺留品に残っていた赤い繊維が
その「湿地の娘」と言われる娘
カイアの家にあったニット帽と
一致するとそこから
逃走するカイアを逮捕し拘留
殺人容疑で告発されてしまいます
「帰りたい 死刑でも何でも関係ない」
頑なに口を閉ざすカイアですが
弁護を申し出たミルトン弁護士が
少しずつ彼女から話を聞いていきます
湿地の娘とは何か?
カイアは元々兄弟で大自然の中で
仲良く暮らしていましたが父親の暴力に
耐えられなくなった大好きな母親が失踪
他の兄弟も家を去りカイアは
兄のジョディからお前も出ろと
進められますがカイアは
「窮地になったら
ザリガニの鳴くところへ逃げろ」
と母に言われたことを忘れず
父との接触を避けながら母が
帰るのを待っていました
学校にも行かせてもらえないカイア
でしたが周辺にはテイトという
同い年くらいの少年もおり
支えになっています
おそらく戦争の後遺症で
他人を極端に信じなくなっていた
父との距離感がわかってきた
カイアに父は少し優しくなりましたが
そんな二人のもとについに母から
手紙が届きますが父はその手紙を
見るなり燃やして父まで
いなくなってしまいます
カイアは一人になってしまいますが
ここから凄いのが彼女
ムール貝を採りに行き前から
ガソリンなどの取引をしていた
ジャンピンとメイベルの
黒人夫婦の営む店に交渉に行くと
聖書に教えに忠実で優しい
メイベルは事情を察して
一人になったカイアを色々
手助けしてくれます
カイアは学校もなじめず
一人になった家で母が描いていた
動物や植物を観察しては
ひたすら絵を描く毎日
そんな生活をしながら
ティーンに成長したカイアは
他人との接触を極端に避ける毎日
ですがある日青年に成長した
テイトに再会
読み書きができないカイアに
テイトは少しずつ教えていき
カイアは家にあった書物を
読めるようになっていきます
テイトは家にあったカイアの
絵に感心し二人はプラトニック
ながら恋が芽生えていきます
このように
テイトは漁師の息子ながら
非常に頭がよく
父からは大学に行って立派に
なることを期待され自分も
望んでいました
そして大学に合格し喜ぶ
テイトですがそれはカイアとの
別れを意味します
カイアはやはり悲しみますが
必ず迎えに来る
6月の花火を一緒に見ようと
約束しテイトは去ります
そしてテイトはメモを渡し
カイアはその言葉を信じ
6月におめかしして約束の
場所で待ちますが・・
テイトは来ませんでした
カイアはやはり人を信じなく
なってしまいます
その後湿地で遊んでいる
「いいとこの子」チェイスが
カイアとひょんなことから出会い
積極的に言い寄ってきました
最初は避けつつも心に隙間があった
カイアは受け入れてしまいます
そんな折に町に
テイトが戻ってきてその様を知り
チェイスだけは絶対ダメだと言いに
カイアの家に来ますが
まぁ顔も見たくないですわね
どうもテイトは自分の元へ
来てほしい気持ちはあったようですが
何を言ってもカイアは
湿地から離れることはないだろうと
達観し会いに来れなかったのです
それを打ち明け懺悔すると
カイアはすこし態度を和らげます
確かにチェイスはどうも合いそうな
人間ではないのは自身もわかって
いたのでしょう
一方でカイアは
家の土地の所有権を得るには
未納の税金を納めなければならなかった
事でテイトの残した出版社のメモへ
自分のイラストを送ると
すぐさま本にしたいと返事が来て
5000ドル(1960年代当時で180万円?)
を手にし税金も納めて所有権を
手にし改装してきれいにするなど
自活能力に磨きがかかってきました
その後チェイスは予想通りカイアに
力づくで強引に迫ってきますが
カイアも強いのでボコボコにやり返すと
自宅を荒らされたり仕返しが
ひどくなってきました
そんなところへテイトが来て
チェイスに殴られた顔では
出版社のところへ行けないと泣く
カイアに負けるな行けとテイトは
強く言います
そしてカイアはテイトに言われるまま
ジャンピンの店でバスの時刻表を
メモさせてもらい朝一のバスで
町を出ていきました
その晩の未明にチェイスは
死体で見つかっています
ここで裁判シーンに戻ると
検察はカイアをチェイスの殺人容疑を
陪審員に訴えます
チェイスの母親も息子が大事に
していた貝の首飾り(カイアが贈った)
も付けていなかった
この娘が殺して奪い返したのだと
訴えます
しかし決定的な証拠はなく
ミルトン弁護士は先入観にとどまらず
湿地で一人でたくましく生きてきた
カイア境遇もかんがみて
犯行時のアリバイもある彼女を
決めつけで判断しないで欲しいと
陪審に訴えます
その結果
カイアは無罪を勝ち取ります
その後カイアは図鑑出版を続け
テイトと結婚し子供ももうけ
湿地で幸せな日々を過ごし
途中世話になった黒人夫婦の
ジャンピンの死も経験し
ついには老婆になります
そこでふと夜中にボートを
こぎ出した先で
カイアを引き取るつもりだった
のに手紙を破られ思いかなわず
病気で死んでいった母の幻影を
見ます
その後戻ってきたボートに
駆け付けたテイトが見たのは
事切れたカイアでした
家にある書物などから
思い出にふけるテイトですが
「生存するためにしかるべき行動をとる」
と描いた本に描かれたチェイスと
その首に付けられた珍しい貝の
ネックレス
そのネックレスがその本に
忍ばせてあったのです
テイトはそれを見て
戦慄するのでした
これが何を意味するか
わかりますね
ジャンピンも墓場まで秘密を
持って行ったのですね
この映画の面白いところは
結局父親の忠告もテイトの言うことも
素直に聞いてそれが正しかった部分が
あったという部分
その中で生き抜いたカイアが
自然の中で見つけた教訓
「生物が生き延びるためにする
行動に善悪はない」
これが人間社会の裁判という形式で
決して越えられることはなかった
という皮肉と重なってる
とこが個人的に面白かったです
海外での評価は高くなかったらしいけど
説明不足と思われるのかなこういう
造り?
「誰も私を見なかった」
カイアという女がいた。湿地に暮らす彼女に家族が居なくなったのは随分昔のこと。暴力を振るう戦争帰りの父親がすべてを壊し、母、兄弟、遂には父親も彼女を見捨てた。カイアを見ていたのは湿地だけ、カイアを知ってるのも湿地だけ。10余年たった独りで湿地に引きこもって生きてきた。
そんなカイアの魅力に溺れる男がふたり。幼い頃、まだ家族がいた頃からカイアを気にかけていた優しいテイト。カイアもテイトも湿地を愛していたので意気投合する。しかし、湿地には何も無い、仕事がない…と、彼は去る。そこへやって来るのが町一番のクォーターバック、チェイス。いわゆるカーストの頂点にいる町の人気者。こいつがドヤ顔でハーモニカを吹き鳴らし、カイアを口説く。でも実はこのハーモニカ男には婚約者がいた。町で鉢合わせてその事実を知ったカイアは、自分勝手で暴力的なチェイスに追われるようになる。「違うんだ、説明してやる」何も違うくはない。カイアは知っている、DV男の生態を。カイアは知っている、湿地で生き抜く術を。ホタルの光が2種類あるように、カマキリのメスはオスを食べるように、自然に生きるものたちは、ただ生き抜くために。そこに倫理はなく、罪もない。部屋いっぱいの鳥の羽根、果たして彼女は学者か魔女か…?遺された彼女の絵日記には、湿地の生き物たちが。危なかったら「ザリガニの鳴くところ」まで。カイアはそうやって生きた。
原作者のディーリア・オーウェンズは生物学者。美しくミステリアスなノースカロライナの湿地と言葉、それだけで価値があると思う。そして実は法廷シーンにカメオ出演しているらしい。かわいい。
映画館で見るべき美しい映像
野生児、、。
犯人は元彼?
で、彼をかばっている??
と思ったけど、彼女はそんな人間臭くなかった。
裁判では自分たちとは違う人間への偏見や思い込みで有罪に傾くが
こんなピュアな人間が犯罪なんてできるはずがない、と、裁判ではひっくり返る。
そう、本当に彼女はピュアだった。
狩りもする、逆襲もする野生動物だったのだ。
悪意のない純粋な人間は殺人などするわけがないという思い込み。
湿地に生きる野生動物のような美しい彼女。
最後はもうストーリーとかそんなのどうでも良くなった。
湿地が教えてくれたこと
1969年、ノースカロライナの湿原で金持ちの息子チェイスの遺体が発見される。容疑者は、『湿地の少女』と呼ばれるカイヤ。そして裁判で明らかになってくるカイヤの過去と湿地の暮らし。
父親の暴力によって母親や兄弟が次々に去り、一人置き去りになった少女に、町の人々は手を差し伸べることなく、わずかな理解者の手助けだけで生きてきた少女。貝を売り、湿地の生き物を観察し、スケッチするカイヤ。
主演のデイジー・エドガー=ジョーンズの表情が素晴らしく、感情を爆発させる姿に胸を打たれました。
ミステリーとして完璧とは言えませんが、丁寧に観ていくと、あれはこういうことだったのかとわかります。
湿地には多様な生物が棲んでいて、自然が美しいです。
湿地と沼地は違うのだそうです。湿地を進んでいくとたまに現れるのが沼地で、陽の当たる湿地と違い、沼地の水は暗くて中が見えないんです。沼地にもまた違った生き物がいますが、よく見えません。あの鳴き声はザリガニなんでしょうか。
全444件中、261~280件目を表示