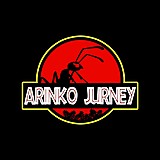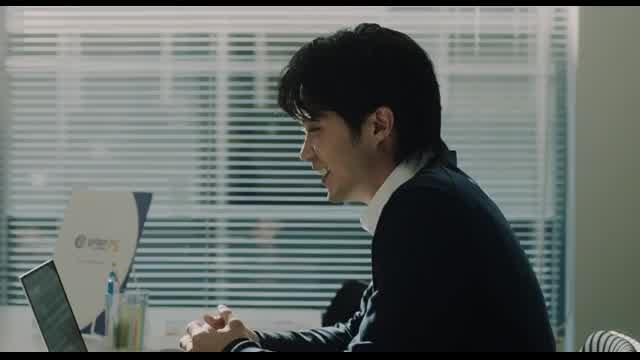PLAN 75のレビュー・感想・評価
全399件中、61~80件目を表示
高齢化社会で死の選択
75歳で生死が選択できるようになった社会での物語
ミチさんは死にきれず
ヒロムはおじの死体を持ち逃げし
コールセンターの人は疑問を持ち
マリアは疑問を持ちながらも仕事を行い
おじさんは死ぬ
リアリティなし。
年の初めに観る映画ではないような気もしたが自宅で家内と。倍賞千恵子を始めオーラの無い俳優陣ばかりである上に演技力はあったのでリアリティは感じられたが、設定そのものが受け入れられなくて話について行けなかった。アメリカではバイデン(81歳)かトランプ(77歳)と大統領選を争う状況なのに75歳で区切るというのはいくらなんでもないだろう。プラン85とか95ならもう少しリアリティが感じられたのかもしれないが。岡部(磯村勇斗)は死亡届を出していないのに叔父さんの火葬ができるのか?ミチ(倍賞千恵子)は朝日を見た後どうするのか?設定に無理があって撮影を途中でやめてしまったような感じのエンディングだった。又、カタール政府の資金が入っているのは何故なのか気になった
病気で助からない人を殺してあげるという国があるみたいだけど、もしかしたらこの映画みたいなことをする国も出てくるかもしれない。
倍賞千恵子さんのインパクトが凄かった。
この役は妹の美津子さんでもいいと思うけど、美津子さんはいつも同じような役をしていて『護られなかった者たちへ』でも同じような役をしているからあえて千恵子さんにしたのかもしれない。
倍賞千恵子さんは昔美人女優でならした人だし、山田洋次監督作品のイメージが強い。
代表作は『寅さん』で、『幸せの黄色いハンカチ』とか『家族』にも出演している。
妹さんと違っておばあさん役はあまり見たことがなくて、個人的なイメージでは今でも若い頃の美人女優のまま。
その人がいきなりおばあさん役なので驚いた。
更に凄いのが声とか喋り方とかの演技の感じが昔のままのこと。
人間は年をとってくると「わたしゃおばあさんだよ」みたいになってくると思っていたけど違うと思う。
そうなったとしてもそれは演技的なもので、経験値は増えるけど中身は若い頃と変わらないと思う。
人によって違うと思うけど、青年期で完成するみたいな時があって、あとは死ぬまでそのままいく感じじゃないのかな?
自分もたぶんそうだと思うし、アイドルの人とか見ていても、若くして完成してしまって、後はこのままおばあさんまでいくんだろうという人がけっこういる。
そういうことを、倍賞千恵子さんの昔と変わらない演技を見ていて考えた。
それに加えて昔見た作品と重なってしまって、あまり金持ちの役はなかったし、あのキャラクター達の最後はこんな感じなのかなと思った。
内容的には以前松田翔太さんの主演で映画化された『イキガミ』とか星新一さんのショートショートで最近NHKでドラマ化された『生活維持省』みたいなことだと思う。
やっぱり人間は、必要以上に生物を殺しまくり、食いまくり、貴重な地球の資源を使いまくって地球環境を破壊するから、地球環境にとってはいない方がいい生物かもしれない。
人間同士でも争いあって、自然界の掟なのかもしれないけど、弱肉強食で、強い人が弱い人から巻き上げるみたいなことばかりやっている。
このままいくと結局、この映画みたいに、最終的にはまた『楢山節考』的なことになっていくのかもしれない。
個人として考えてみても、生きるのは非常にめんどくさいから、死ねばめんどくさくないし、何もいらないので、死ぬのが一番効率がいいような気がしないでもない。
頭ではそう思うけど、本能的には、周りに迷惑かけまくって、非常に情けない状況になったとしても、生きていたいというのが本音かな?
あといやなのが死ぬ時期がわからないこと。
明日かもしれないし、何十年先かもしれない。
永遠に生きるみたいな気分で生きているけど、人生で確実なのはいつかは死ぬということだけ。
わかっていれば、いろいろ準備をしてやりたいことやってサヨナラできるけど、明日どこかで突然死ぬというというのは勘弁してほしい。
死んでしまえばわからないからどうでもいいんだけど、死んだ後も多少生きているみたいな変な妄想がある。
その辺のところでいろいろ揺れているのに、この映画のように「政府がお手伝いするので死にませんか?」と言われたら本当にやってしまうかもしれない。
病気で助からない人を殺してあげるという国はけっこうあるみたいだけど、もしかしたら期間は長いかもしれないけど助からないという意味では同じなので健康な人も希望者は殺してあげるという国も出てくるかもしれない。
最後の「リンゴの木の下で」は黒澤監督の『生きる』の「ゴンドラの唄」パロディー的なことなんだろうけど、比べたらコメディーか?と思うくらいいろいろ情けない映画ではあったけど、個人的には面白かった。
自分が安楽死を導入すべきと思っているからなのか
ちょっと主人公に感情移入出来ない。主張が無いので全然気持ちが伝わって来ないのだ。死を強制することは間違っているし、暗黙の了解として75歳過ぎたら死ぬべきというのも間違っている。だが、死を救いだと思っている人がいるからこそ自殺もあるのだ。生きたいと願うのは自由だし、本来それを邪魔される謂れは無い。無言の圧力になるというこの制度の問題点はそこにある。
しかし、後期高齢者と区分される75歳ともなれば個人差こそあれ身体的にあらゆる部分にガタが来る。そして75歳で10人に1人が認知症、80歳過ぎれば4人に1人と激増するのだ。つまり75歳というタイミングは自分で自分のための客観的な判断が出来るラインとして見なすことが出来る。レカネマブなんて薬も出たが、認知症の進行抑制を期待できる効果があるとされるだけで発症したら手遅れ。認知症にも程度はあるが、記憶が定着しない、トイレが出来ない、自分が自分で無くなる、家族の顔さえ忘れてしまう。そんな状況になったら、自分は正直生きていたくない。それはそんな自分の姿を家族に見せなくないという思いもあるし、もし孤独ならば老後の楽しみも無いだろう。
高齢者に関わらず、不治の病であるALSなどのことも考えれば本当に現実で安楽死を導入する話し合いを一刻も早く始めて欲しい。まだまだ元気で生きられる、生きがいがある、そんな人たちは長生きするべきだ。どんな状態になったとしても家族で支えてあげたいというのは、すばらしい心だし自分も親を出来る限り支えたいとは思う。だが、本人が選択して死を選ぶというならば説得こそすれ、翻意出来なければ見送るだろう。本人の意思を無視してまで胃ろうさせて延命治療する今の日本は正直異常である。それこそ個人の尊厳を無視しているのだ。
今はこんなことを言っている自分でも、いざ75歳となったら翻意するかも知れない。だが、もうダメだ、生きていることに希望を持てないという時にこの選択肢はあるべきだと思う。ガンになった人が苦しい治療はもう嫌だと言えば、無理に治療することは無い。そのように安楽死も選択肢の一つになればいいと、自分はこの映画を見て改めて感じた。
コントラストから呼び起こされる思い
観ている途中で気がついたが、この映画、至る所で、画面の真ん中に境目がくる構図が出てくる。単に監督の好みというわけではなさそうだなと思っているうちに、陰影と光のコントラストも様々な場面で使われる。
なるほど、一見そうは見えなくても、対比的に提示されたものから様々に感じ取って欲しいというのが、監督・脚本の早川千絵の目論見なのだろう。
心臓に疾患を抱え手術が必要な子どもと元気で健康な老人、地中海クルーズに行かれる者とスーパーのサバを贅沢と考える貧困層等々、あげ出せばキリがない。
考えてみれば、この世の中は対比に満ちている。そしてそれは、一人の個人の中にも存在する。
主人公だけではなく、plan75に関わる仕事をしている2人の若者たちも、その対比の矛盾と向き合い悩む。でもそれは、彼らは真っ当に生きているからこそだろう。
対して、この映画の中で、対比が隠され、矛盾がないように描かれているもの(老人殺しを正当化する者、謎の会社、plan75の対応のレクチャーをする指導員等々)の気持ち悪さといったら…。
細かく説明されていないが、これから主人公はどうするのだろう。一番隠されているのは、個人の意思を超えた、社会の事情。それと向き合って、彼女はどんな最後を迎えるのか。
そして、この映画を観ている自分自身も現実社会の中でどんな最後になるのか。
日常ではあまり考えずに生活をしている「自分自身の最後という問題」は、当たり前に、常にすぐ隣にあるということを思い知らされた。
倍賞千恵子がすごいのはさることながら、個人的には、河合優実がとてもよかった。
公設「楢山節考」へと、時代は循環するのか
昔 観た「ソイレント・グリーン」(1973年米)を思い出す。
「人口抑制」と「食糧危機」の難題を一挙同時に解決させた、近未来予言の問題作だった。
「ソイレント・グリーン」も、そして本作「プラン75」も、《それ》を自分で選んだ高齢者たちは、一様に穏やかで、幸福そうな最期の姿として描かれていた。
《システムの妙》が、それを実現させていたのだ。
・・・・・・・・・・・・・
【あと何年生きるつもりですか】
さて、
レビューアーの皆さん、お年はおいくつですか?
お勤め先で、またご家族で、将来の事とか、定年の話題は上がることはありますか?
「エリカ38」を観たとき、樹木希林のインタビューを読みました、
共演で親友の浅田美代子に対して樹木いわく
・絶対に家を買っておきなさいよ
・65過ぎたらもう誰も家を貸してくれないのよ
僕の会社では、そのあたりの話題は、同年代の社員同士の切実なテーマとなっていますね。
寄るとさわるとその話。
自分の体について、最近の不調とか、良い病院の口コミとか。
いろんなサプリや塗り薬。その効果や失敗談(笑)や、
子供にかかるお金。親の看取りへの物心面の準備。
定年延長やら、年金やら、寿命やら、生活保護のことやら。
そして、
「あと何回お給料をもらえばその翌月から自分は無職となって、冗談じゃなくマジ無収入になるのか」という計算。
そしてもうひとつ実感するのは、身内や知り合いは喪中ばかりで、僕らの年代は年賀状も減るのですよ、
そんな年末年始。
↑↑
それを横で立ち聞きしている若い人たちは一様にポカーンとしています。
「老い」や「定年」というワードは、彼らにとってはギャグか、もしくは「木星」とか「銀河」のような、まだ考えたこともない、遥かに遠い絵空事のようです。
還暦はおろか定年など、あたかもSFの世界の話題に聞こえてしまうのなら、彼らのああいう反応も、仕方ないことですよね。
先日入社して、僕が担当して仕事を教えた若者は「お母さんが51歳」なのだそうです。
愕然としました。それならすべては無理のない話です。
・・・・・・・・・・・・・
【雇い止め・保証人なし】
映画は
ホテルのルームクリーニングのパート従業員、倍賞千恵子さんの毎日を追っていきます。
本人たちの「老い」と「将来への不安」。
そして“自らの始末”を、自分で責任をもって付けようとする高齢者たちの身だしなみ。
この姿、美しいのだと思います。肯定すべき生き様です。
飛ぶ鳥跡を濁さず と言いますもの。
倍賞さんはクビになってもロッカーをきちんと片付ける。布巾を洗って干す。寿司桶を綺麗にして返す。
この「プラン75」の申し込みカウンターでは、本人たちの熟慮の末の、彼らが決めた真摯な姿に、それはあらわれています。
円熟の姿。謙譲の美徳ですよね。
日本社会の高齢化と少子化は、もはや笑ってはいられない状況にあります。
あと100年で日本の人口は半分になるのだと見積られているのですが、低め安定で落ち着く100年後までは、国庫の税収は低下し、福祉補助の受給者は逆にうなぎ登り。労働者の数は圧倒的に足りなくて、これはけっこう厳しい世の中を我々は体験するのだろうと想像します。
お隣中国などは、あの取り返しのつかない一人っ子政策の後始末で、今や国家は致命的な状態のはず。
「国は困っているだろう、よくわかる」。
「私も困っているから それがわかるの」 。
「ちょうどいい頃合いかも。優遇ポイントも付くらしいし、それに乗るとするか」。
・・こういう流れかと。
・・・・・・・・・・・・・
【安楽死希望者と、理由は分らないけれどそれを阻止しようとして暴れる若者】
駅前や、市役所での のぼり旗を立てた「プラン75」の申し込み所。
国家としても苦肉の策ですね。
国民の間にパニックや「優生思想」への抗議行動が起こらないように
極めてハートフルなイメージで、笑顔での対応。パンフレットもTVコマーシャルの政府公報も 穏やかで優しい。
ちゃんと職員の応対マニュアルも備わっています。
カウンセラーもケアマネもよく働く。
「お気持ちよくわかります」
「いつでもキャンセル出来ますからご心配はいりませんよ」と。
しかしその実、国家の危機なのです。政府は金のかかる高齢者の口減らしを、決して後退させることなく国策として強行に推し進めているわけでした。
国のこの願いと、老後に不安を覚えている当事者たちとの《心情的なマッチング》が、あまりにも上手く行けているので、シナリオがお見事でした。
行く先が見えないのです、国も個人も。
そんな時代の設定がすべて理解できるし、僕自身も心が動くし、あれこれ想像もつくだけに、何とも言えない思いが込み上げてしまう映像でした。
劇中、叔父の安楽死を止めようとして、公務員としての務めを忘れる男性や、脱走を助けようとする施設職員が出てくるのは、先述の「ソイレント・グリーン」も同じ。
でも、その若い人たちの気持ちに感謝しながらも そっとしておいてくれよなと、それをなだめるかのような老人の姿も同じ。
ナチス・ドイツが本当にやっちまった”ガス室ベルトコンベアー式"でないだけ、「プラン75」は、今日的で、民主的なやり方なのかもしれません。
・・・・・・・・・・・・・
【DVDを見終わったあと、布団の中で考えた】
でもね、言ってみれば、
死ぬのが怖いから
貯蓄だ、ホームだ、年金だ、と我々は大騒ぎするのです。
発想の転換をして自分の死を受容すれば、あーら不思議、本当はなんにも困らないお話なのです。
騒ぐのは、「自分は死なない」とか、「長生きするはずだ」との、根拠の無い、非科学的な思い込みをしている人のすることです。
もういいかなーと思ったら、水だけ飲んで食を断てば1ヶ月で、綺麗に、静かに、楽に、人生を閉じられます。
ぜんぜん怖くない。
僕はこの方法を取りますよ。多分。
これは満足なエンディングでしょ?
どうだろう。
お国に命を献上する「特攻隊」とか、
お国の推奨する死を受け入れた人にのみ授与される「英霊」称号とか、
そしてこの「プラン75」への受付窓口の笑顔とか、お褒めの言葉とか、感謝状とか、支度金とか、埋葬サービスポイントとか。
そういう
《我々の極めてプライベートな個々の死に方》を、お上に優劣付けてもらうようなことはしなくてもいいと思うのです。
うちの犬もネコもチャボも、慌てず騒がず静かに死んで行きました。
外野に指図されることなく、感心するほど、命は まったく彼らのものでしたねぇ。
僕は、出来ればですが、あれに習いたいのです。
倍賞千恵子さんは、宵やみ迫る町並みを見つめながら映画は終了。
自分が死ぬのは初めてのことなので、不安なのは僕も隠しようがないけれど、出来ればそんなふうにしてみたいなと。
布団の中でずっと考えました。
・・・・・・・・・・・・・
【倍賞千恵子】
歌に、演技に絶品の、
松竹歌劇団=SKDの華であった女優の倍賞千恵子さん。
ラジオで時おり流れる彼女の「さくら貝の歌」や「かあさんの歌」がとても良いですね。
この名女優が辿ってきたのはトップスターの人生です。でも彼女がお姫様女優やらセレブ女優にはならずに、彼女がずっと庶民であり続けたのは、
やはり「寅さんシリーズ」のお陰ではないかなと思いました。
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
【おまけ、終活の知恵】
ちなみに「お金のまったくかからない死に方」についてお教えしますね、
大学病院の医学部への「献体」を今のうちに申し込んでおくのです。
臨終後、遺体搬送の寝台車の料金、
火葬等にかかる一切の諸経費、
望むなら大学病院の納骨堂への納骨、
すべてが0円、無料です。
慰霊の式典も大学がサービスでやってくれます。
うちの叔父夫婦はこれをやってのけたので、親族中のリスペクトの的です。
うちの両親も申し込み済みです、
年に一度の総会で、お土産にもらえるお弁当が楽しみなのだと、父は言ってます。
ただし、僕も申し込んでみたところ
「もう余っているので受け付け停止中」とのことでした。これは
・献体を申し出る篤志家が増えたのか、
・医学生の減少によるライヒェ=遺体の余剰か、
はたまた
・もうそこまで“無料”を聞きつけた生活困窮の高齢者が増えてきている、その結果なのか、
思いは複雑です。
ちなみに「献体」は、大学病院に登録申請書があるのですが、申請が満杯理由での不受理でも、枠としては都道府県別での受け付け故、献体が不足している他県への融通も情報の提供もやっていないとのことでした。
サービス悪いね。
えっ、僕ですか?
はい。長野県在住なのですが
第1志望校は 東京女子医大での解剖実習です。
身も心も純粋。まったく汚れなきわたくしの願い。
(このギャグだけは若い後輩たちにも、ようやくウケました)
テヘペロ。
現実になると迷うだろうな
................................................................................................
75歳になると安楽死を選べる時代が来た。
老人への風当たりはキツく、倍賞は同年代の友人達と共に解雇された。
再就職もできず、それで賃貸住宅を借りることもできない、八方塞り。
さらに友人も孤独死し、ついに安楽死PLAN75に申し込む。
死を迎えるまで毎日?週1?担当者と15分くらい会話ができる。
それが楽しく、個人的に会うまでの関係になったりもした。
そしてついに死の時を迎える。全身麻酔みたいな感じ。
ところが倍賞は心変わりしてマスクを外し、生き残って脱出。
................................................................................................
で結局その後どうすんの?って終わり方。
まあそれはそれでいいような気もするけどな。
でも最後の方は曖昧で余計なシーンが多過ぎる気がする。
遺品整理係が遺品の大金を着服したのかも曖昧やし、
叔父の遺体を搬出した男がスピード違反で警察に捕まったり。
そのシーンっているのかな・・・そんなことは感じた。
人道的な問題はあるやろうが、この制度はいいかも知れない。
それが正直な感想なんやけどな。果たしてこんな未来は来るのか?
おれが決めることじゃないんで、当面は目を逸らして生きてこう。
75歳で自分の人生を選択できる世の中。 現代の75歳ってけっこう元...
一石を投じる意味では佳作
<映画のことば>
お年寄りって言うのは寂しいんです。
誰かに話を聞いてもらいたくて仕方がないんですね。
そういう方々に寄り添って、じっくり話を聞いて差し上げるのが、皆さんの仕事です。
実際、やっぱり途中で「やめたい」ってなる方がすごく多いんです。
そうならないように、皆さんがうまく誘導してあげなくちゃいけない。
人間ですから、不安になるのは当たり前ですよね。誰も好き好んで死にたいなんて思わないですよね。
そういう気持ちには、きちんと寄り添うことが大切です。
そのうえで、利用者様がこの世に未練を残すことなく心安らかに旅立っていただけるよう勇気づけるーそれが私たちの役割です。
☆ ☆ ☆
「駕篭に乗る人、担ぐ人。そのまた草鞋を作る人。」ー世の中は、いろいろな立場の人から成り立っている訳ですけれども。
立場が違えば、価値観も、ライフスタイルも、当然に違ってくることでしょう。
そういう違いの一切を捨象して「75歳」で線引することの無意味さということが、本作を通底するように、評論子には思われました。
つまり、個々人の特性に着目することなく、75歳以上は一律に社会的には無用・無価値と分類するもので、それは弱者・劣者に社会的な存在すら認めない優生思想の一種であって、政策としての当否を論ずる以前に、その前提として「個」の尊重を欠くことのできない民主主義社会での議論として、「外道」のそしりを免れないと考えます。
上掲の「映画のことば」は、覆っても覆いきれないプラン75のそういう矛盾をはからずも糊塗しようとするものとして、本作の中では重要な意味合いをもっていると、評論子は思います。
また、高齢者問題というと、年金保険料の負担など、若年層への負担ばかりが注目されがちですけれども。しかし、多くの高齢者は持病を抱えて病院にかかることで、若い医療従事者に雇用の場を提供し、公的介護保険の自己負担分を支払うことで介護産業を需要者として支え(そこでも若年労働者が多数雇用されていることはいうまでもない)、年金を原資として衣食住の需要を満たすことで経済の循環にも、立派に与っている。
そのことに思いが至ると、プラン75の「無意味さ」というのは一層明らかになると思いますし、そういう「無意味さ」の象徴としてか、ラスト近く、ミチ(倍賞千恵子)の、生気の抜け切ってしまったような、まるで魚か能面かのような無表情が、評論子には、印象に残る一本になりました。
現下の社会に切実な問題に、果敢に一石を投じようとする点では、佳作では、あったと思います。
『PLAN75』、次作に期待。
カンヌ国際映画祭・カメラドール特別表彰という触れ込みで、2022年に公開された映画です。高齢者の生き方、高齢者の存在を考えさせられます。
■リアリティが感じられない理由
なぜ、この映画には、リアリティが感じられないのか?
1976年生まれの早川千絵監督が持つ高齢者に対する誤解に起因しているか。あるいは、高齢者をめぐる古い社会通念が、この映画からリアリティを奪っているなのか。
「PLAN75」というタイトルが示すように、映画では75歳になると生死の選択権を高齢者に与える法制度が設けられ、その制度に翻弄される人々を描いています。
しかし、現在の75歳は、身体的にも精神的にも映画で描かれた人々より元気です。
日本老年学会と日本老年医学会は、心身が健康な高年齢者が増えたことから、高齢者の定義を75歳以上に引き上げるべきだと提言しており、75歳は高齢者の入口に差し掛かったにすぎません。
タイトルを付けるとすれば「PLN85」、女性中心に描くのであれば、男女の寿命差が5~6歳あるので「PLAN90」とすればよかったのかもしれません。
■ステレオタイプな高齢者の苦悩
年齢設定はさておき、
この映画のユニークなところは、生死の選択権という「法制度」を設定したところで、高齢者の社会的存在について問題提起しています。
ただ、この物語設定が、有効に機能するには・・
1) 超長寿化等によって多くの高齢者が苦難を抱えるようになり、
2) その結果、多くの高齢者が潜在的に死の願望を持つようになり、
3) それを法制度が後押しする
といった前提が必要です。それであれば、生死や善悪について深く考えることができます。
だからこそ、この物語設定に負けないように「”多くの”高齢者が抱える苦悩」をしっかり描く必要があります。
映画で描かれているのは、どちらかというと貧困に置かれている高齢者の苦悩でした。しかし、高齢者の8割が持家に住む現状の日本では、住宅難や就職難は高齢者共通の問題ではありません。
それでは、高齢者の貧困問題を取り上げたのでしょうか?
確かに高齢者は経済的・社会的に多様で、その中で貧困問題はむしろ若者世代以上に深刻です。しかし、PLAN75という法制度は全高齢者を対象にしたもので、制度的に貧困層にアプローチできるものではなく、それでは設定が曖昧になってしまいます。
このように、物語設定が面白いにもかかわらず、「多くの高齢者が抱える苦悩」の描き方が、ステレオタイプだと感じてしまいます。
■シニアの実存を描いて欲しい
それでは、「多くの高齢者が抱える苦悩」、潜在的に死の願望を持つような苦悩や問題はあるのでしょうか。
一つあるとすると「老い」の受容です。
もちろん、老いの受容は今に始まった問題ではありませんが、近年の超長寿化によって、老いとの向き合い方は大きく変容しています。
例えば、高齢者が働きたいと思っても働く場がないという就職ミスマッチは、特に元気で働く意欲を持つ高齢者が増え、働きたい期間も長くなって、拡大の一途をたどっています。
そして、これは映画で取り上げられたように貧困層に閉じているわけでなく、経済的に豊かな高齢者にも起きる新たな問題です。
このように横断的に拡がる高齢者の「社会からの疎外」を、超長寿化が後押ししてしまっていて、社会制度だけでなく1人ひとりが持つ通念を変えない限り、解決が難しい問題になりつつあります。
早川監督には是非、その繊細なタッチで、高齢者のリアルな実存の問題について描いてもらいたいというのが素直な感想です。
現実的なテーマ
涙が止まらない、当たり前を疑え、考えよ!
75歳の実祖母と重なり、
涙が止まらなかった映画でした。
Plan75という現実では考えられない制度が当たり前になった日本では、高齢者を安楽死させる制度が当たり前のように存在しており、若者はその制度を当たり前のように受け入れ、事務的に処理をこなしていく。そこに2人の若者が疑問を抱き始める。
「当たり前を疑え、考えよ」
と言われた気がします。
2016年に起きた障害者施設の襲撃事件を元にした演出もよかったです。
奇しくも映画を見た翌日に、安倍元首相の銃撃事件がありました。
犯人は政治的思想を元にした犯行ではないようですが、
映画内の冒頭で「国を変えるために銃撃事件を起こす若者」が描かれており、
日本の未来を考えるよう問われた気がしました。
誰にも頼れない男はつくづく弱い生き物
レンタル110
最近ご無沙汰だったTSU○○YAからクーポンが届き利用
週1本ペースを乱してまで観たかった
公開時は劇場が少なくて断念した
で スクリーンで観ておけばよかったと後悔する傑作だった
倍賞千恵子と磯村勇人とフィリピン女優
3人それぞれがPLAN75と関わる
磯村のおじとかPLAN75のカウンセラーも加わる
現実ではないが設定が絶妙だ
おそらく国から業務委託されているような民間会社とか
後始末を外国人労働力に頼るとか
アルバイト的なカウンセラーとか
支度金だか手当だかが10万円とか
主役3人の演技卓越
倍賞千恵子はさすが
磯村はなんだか誠実な半官半民的な職業人
ヤクザと家族から注目していたからな
フィリピン女優も素敵だ
3人の一瞬の邂逅がいい
この監督は上品だ 全部見せない
あとカウンセラーの女子大生が二重マル
意地を張って誰にも頼れない男はつくづく弱い生き物
誰かと関与できる女性って強い
でこういう傑作を撮れるのは女性なんだな
この作品も他の人のレビューが早く読みたい
説教くさい
内容が中途半端
劇中、大変良く出来たPLAN 75のCMが流れるが、PLAN 75に携わるスタッフの苦悩、PLAN 75の死体処理の杜撰さなど、PLAN 75に対してかなりネガティブな場面が多い。最後のミチの決断に至った過程はPLAN 75の運営としてはあり得ないミスが発端となっており、最後のシーンは結局、何が言いたかったのか不明。
ありきたりの「生きる喜び」を伝えたかったようにも思える。
本作はもっとPLAN 75 を肯定的に描き、徹底的にユートピア的政策として描き、現実でも国会において審議入りするほどのアピールをしてもらいたかった。国民が毀誉褒貶の議論を交わすきっかけとなるような作品に仕上げるべきだと思う。
実際、現時点での医療も中途半端で延命処置はできても健康寿命を延ばすことはできない。他人様に迷惑をかけたくないと考える高齢者も少なからずいる。天寿を全うし老衰で亡くなる人は限られてきた。延命処置を望まない人も多い。
そのような中、この映画は社会に対して何の問題提起になっておらず中途半端。
監督はPLAN 75に対して否定的に考えているのだろうが、その上であえてPLAN 75が作り得るユートピアを徹底的に描き、最後のカットはあの世へ旅立った人々への餞としてもらいたい。
日本の近未来がこの映画に
高齢化社会を抜本的に解決できる法案が求められている中、75歳以上の高齢者が死を選ぶことのできる権利が激論の末、立法する。
その事から始まる政府主導でのプラン75という安楽死サービスを開始する。
安楽死サービスを受ける老人は生前に10万円給付される。使い道自由。
そのサービスを提供する若者はプラン75を選択した高齢者に対して、心のケアまでを施し、安楽死へと誘うことが仕事となる。
政府主導で劇中のテレビでは、「人は産まれる事は選べないけど、死ぬ時期は選びたい。」などと連日メディアCMが流される。
高齢者や生産性を失った人々が生きていることが憚られ、肩身の狭い状況を世の中全体に作られてゆく。
そして生活を営もうする老人に突きつけられた問題は住居問題。これは現在も既に起こっている事柄。更に加速度が増してゆく。
少子の為に人手不足から、政府が高額で外国人労働者を雇い入れ、介護職から亡くなった者の遺品の整理を行わせるという内容。
この映画はこのままではこうなりますよ‼️という警鐘を声高に淡々と描いている。
ソイレントグリーンの舞台は2022年!今年でっせ
あちらは60歳で人生強制終了。ワタシはアウト
こちらは75歳で希望者のみ安楽死。
間の長い演出がおまえらこんなことで世の中いいんですか?
と我々に答えを委ねる。
ですが
なんで自殺やめたん?
なんで叔父を助けようとしたん?
フィリピーナ要る?
世の中の不条理に対し言いたいことは一杯あるのに説明不足が多いなあ。
心に染みるまではいかない。
60点
5
MOVIX京都 20220621
自由のある世界線のおはなし
働く意思・生きたい意志のある人が生きられない世界は、あってほしくない。
でも、もうこれ以上頑張れない人に「選択の自由」はあるべきだと思っている。
末期がんで延々と苦痛と恐怖に耐えるのは、果たして必要なことなのか?
がんの父を看取って、ある意味拷問だと感じた。
高齢で年々重くなり病気や痛みでいっぱいの体を抱えながら、いつ終わるともしれない日々を耐えるようにしか過ごせない人もいる。
映画で、死ぬ選択をした人たちを優遇するようでいて最後はあのお部屋っていう点はひどいと思ったけど、引っかかるのはそこだけかな。せめてちょっと綺麗な個室を使わせて欲しい。
見終わった私の感想は「うらやましい」でした。
この心身の苦痛を骨身で感じるのは、他の誰でもなく自分。
いくら手を差し伸べてくれる人がいても最終的にどうにもならない部分もあるのだから、オランダのように自分で決める自由がいつか許されればいいなと思う。
たぶん監督が描きたかった思いとは違うと思うけど、でもそれも映画の醍醐味だよね?
余計なセリフや仰々しさなく、美しい景色、見える光景で語っていくとてもいい映画でした。
見たあと何日も色々思い浮かんでは考えていました。
最近見た映画の中では、私の中ではナンバーワン。
若い人で今見てピンとこない人は、自分が高齢に近づき・身内を看取る、そうなり始めた時期に見返すと、たぶん見えるものが全然違ってくると思います。
全399件中、61~80件目を表示