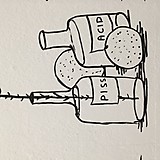土を喰らう十二ヵ月のレビュー・感想・評価
全125件中、61~80件目を表示
ふたりの関係が料理を共に喰らうだけでなく、具体的にどんな愛し合う関係だったのか、突っ込みが足りない気がしました。
「雁の寺」「飢餓海峡」「はなれ瞽女おりん」など生前、小説の映画化が多かった水上勉が1978年に女性誌に連載した随筆「土を喰う日々 わが精進十二ヵ月」が本作の原案となりました。水上は映画会社にいた時期があるそうです。自分が書き残した小説ではなくエッセイを元に、自身を模した主人公を、年を重ねても色香を漂わす沢田研二が演じたと知ったら驚いたかもしれませんね。
生きることは食べること。誰かと一緒に食卓を囲めたら、なおさらいいですね。四季の移ろいとともに暮らし、自然の恵みをいただくこと。そんなふうに生きられたら、最高でしょう。
そんな料理エッセーの装いの中で、生や死、人間としての欲や業に向き合う登場人物たちの姿が端正に描かれます。穏やかに過ぎる日々、それがこんなにドラマチックに感じられました。
同様の作品で思いつくのは、橋本愛主演の『リトル・フォレスト 夏・秋』(2014年) 、『リトル・フォレスト 冬・春』(2015年)が挙げられますが、やはり本作の方が圧倒的に味わい深かったです。
加えて、本作はとても贅沢な作品です。
信州は白馬の集落で、1年半もかけて美しく移ろう四季の風景をカメラに収めるなんて今の邦画製作では考えられないほどの予算無視した長期ロケに取り組んだことになります。何しろ立冬から立ち上げ、再び立冬に至るまでの二十四節気(今でも立春、春分、夏至など、季節を表す言葉として用いられています。1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたもの)をその都度ロケしていますから、主演の沢田研二はおそらく撮影期間中は白馬の現場に貼り付けになっていたものと思われます。
また主人公のツトムが暮らす山荘は、水上が晩年を過ごした長野県東御市と近い、白馬の廃集落の茅葺屋根の古民家を撮影用に再生したもの。畑も開墾したというから、DASH村を作り上げたといってもいいでしょう。かまどや囲炉裏があり、2人が食事をする居間は大きな窓から季節で移り変わる外の景色が見え、その居心地の良さに、自然と役に成りきれたと出演した松たか子も絶賛していました。
もう一つの主役が、料理研究家の土井善晴が作る数々の精進料理です。スタッフが現場の畑で実際に育てた旬の野菜を使った煮ものや胡麻豆腐など、特に湯気の立つタケノコを大きな皿にドンと盛った若竹煮のド迫力には、たまりませんでした。俳優たちの気持ちがそのまま、画面に滲み出ていていたのです。
「土井さんの料理は、味が濃すぎず薄すぎず、出汁が勝ちすぎてもいない。塩梅がちょうどいい。演技じゃなく、誰でもああいう顔になりますよ。おいしいものを食べたい欲求と、ツトムさんに触れたい欲求はきっと同じなんでしょうね」。松たか子でも思わず素になって味わってしまったのでした。
とても良い塩梅の映画だったのです
作家のツトム(沢田研二)は、人里離れた信州の山荘で愛犬と暮らしていました。少年時代を過ごした禅寺で精進料理を学び、それを日々の暮らしに活かしていたのです。
冬は雪を掘り、菰で守られたホウレン草を掘り出し、茹でます。春、夏、秋と土の中から畑で育てた野菜が掘り出され、土を洗う場面が繰り返されます。さらに周囲の山々で採った木の実、キノコ、山菜で料理を作る日々でした。毎日、食材を収穫するツトムの行動が次第に当たり前に思えてきます。タイトル通り、人の営みと大地が近い暮らしぶりでした。
楽しみは、時折、担当編集者で恋人の真知子(松たか子)が東京から訪ねてきて一緒に食べる特別な時間を過ごすこと。
一方で、13年前に亡くなった妻八重子の遺骨を墓に納めることができずにいました。八重子の母のチエ(奈良岡朋子)のもとを訪ねたツトムは、八重子の墓をまだ作っていないことを咎められます。のちにチエは亡くなります。チエの葬儀はツトムの山荘で営まれました。
葬儀が終わり、ツトムは真知子に山荘に住むことを提案します。真知子は考えさせてと応じましたが、この後二人の心境が変化する大きな出来事が起こったのでした。
圧巻はチエの通夜のシーン。予想よりも多くの人が集まり、真知子も東京から駆けつけ葬儀の準備に追われたのです。大勢の参列者に振る舞う料理を2人で捌かなくてはいけませんでした。しかも大雪で仕入れが出来ず、材料は畑の野菜や買い置きのもので凌ぐしかありません。
台所に、ツトムの指示に応える「ハイヨ」という真知子のリズミカルなかけ声が響きます。胡麻豆腐にはじまり、ツトムの手際の良さに圧倒されました。誰かのために生き生きと料理を作るツトムの姿はに思わず見惚れてしまう真知子の表情が印象的でした。
掘り起こした芋の土を丁寧に落とし、皮をむき、包丁で切っていく。ツトムが食材を扱う手つきは、器用ではないけれど丁寧でゆったりしていて、そこはかとなく色気が感じられます。さすが沢田研二!
「ナビイの恋」などの中江裕司監督は、ツトムの手の動きを追いかけ、まるでドキュメンタリーのようにその工程を映し出したのです。
ところで、野菜は土の中で身を太らせ、山菜は降り注ぐ陽光に葉をいっぱいに広げます。旬をいただくということ、そして土を喰らうことは生命の絶頂を摘み取り、身に取り込むことなのです。業の深い行為なのです。そこから念仏ならば、ご恩報謝の感謝の心が自然と湧いてくるものですが、残念ながら幼い頃に禅寺で修行したツトムには、その観点が抜けていていたのでした。
なので人と関係を断てる山里に暮らし、自給自足の仙人のような暮らしから悟りの雰囲気を楽しんでいたのです。それはわたしから見れば、身勝手な野狐禅のように思えました。それが露呈するのが、ツトムが心筋梗塞を起こしてしまったことから。タイミングよく真知子が駆けつけていなかったらツトムは確実に死んでいたことでしょう。当然ツトムは妻の死、そして自分の死とも向き合うことになります。悟りの雰囲気だけ楽しんでいたツトムには、死を受け入れようともがきつつも、生に執着するのです。本来仏教は執着と迷いを立つ教えなのに、ツトムは迷いもがきます。中江監督が生み出した場面が秀逸です。
ここまでネタバレ無し!
【注意:ここから一部ネタバレあり】
そして出した結論は、一人で死ぬまで生きていくこと。その結果、倒れる前には真知子に一緒に住もうとプロポーズしたのに、ツトムの方から別れを切り出すのでした。
いくら真知子に負担を負わせたくないという愛情から出た言葉としても、これまでの真知子の献身に感謝が足りないと思えました。「身勝手ね」と怒りながら立ち去る真知子の悲しみにいたく同情してしまったのです。
・・・・・・・・
ここからネタバレ無し!
それにしても沢田のツトムは絶品です。老境の作家の枯れた雰囲気が、里山の風景となじんでいた。それでいて真知子と2人きりの場面はほのかに上気した空気を生み出し、心に生まれたさざなみも巧みに伝えてくれました。自身の人生が染み出すような名演たったといえるでしょう。脇を固める奈良岡朋子、火野正平も、人生の達人像を具現化していた演技でした。加えて大友良英のフリージャズが、軽やかに物語に重なりました。
最後に一つ気になることがあります。
前半、カメラは台所と居間を行き来して、寝所は映されません。締め切り間近にふらりと現れる真知子との雑味を抑えるためかと見ていたら、寝所は後半、ツトムの死を意識した棺のように2度、出てきます。これでは真知子はツトムの老いを強調する小道具の感が拭えず、松の生かし方がもったいないと思えました。ふたりの関係が料理を共に喰らうだけでなく、具体的にどんな愛し合う関係だったのか、突っ込みが足りない気がしたのです。
画面から伝わる美味しさと犬の可愛さ
ほんわか田舎の暮らしに、土井善晴さんによるたしかな料理……
『孤独のグルメ』『きのう何食べた』に通じる、画面から伝わる美味しさ。
さらに素晴らしいものが画面に。
沢田研二の演じる主人公ツトムの、愛犬「さんしょ」。
ああ、さんしょの頭をグリグリ撫でたいっ!
雑種っぽい、一見無愛想なツンデレっぷりがたまりません。
あと、気の弱い義弟を演じた尾美としのりが、演技として犬だったので可愛かったです。
映画としてみると、人物関係のうち恋愛部分の描写が少々希薄なのが惜しかった。
ただ、作品の主眼は「(老境の)生き方」だろうから、これでいいのかも。
こころ洗らわされる良い映画だ。
染み染み
素敵です!野菜を洗う音、切る音、煮る音、食べる音
土井先生ファン風のベラランお姉さんが
たくさんいらしてました💖
野菜の音が、たまらない!
野菜を摘み、洗う、まな板の上で刻まれ、
鍋の中に
忘れていた記憶の中の"音"が、
心地よく蘇ってきました。
野菜一菜、一品の料理が
なんと素敵なことか!
ジュリーが何気なく発した京都弁が
土井さんの声とシンクロしてる、不思議。
(ジュリーも京都出身でしたね)
80代の夢の生き方なのかもしれません。
胡麻豆腐と筍、無性に食べたくなる。
炒めるよりも焼く煮る蒸す
思い出す映画がある
『人生フルーツ』
山暮らしではないが自然があふれる自宅の庭に野菜を育てそれを食す夫婦のお話
山暮らしに憧れる私は驚いたものです
住宅地でもこんな暮らしが出来るのだと
でもやはり、自然を愛でながらの生活に憧れがつきません
街で暮らしたって死ぬ時は死ぬ、毎日の生活で便利を取れば稼がねばならない
いったい何のために生きているのか、そんなことを歳を重ねるにつれ思うようになってきました
毎日を「ありがたい」と思いたい、大切に生きたい
松さんの食べっぷりには敬服いたしました、火野さんはボソリと「昔の人はこんなに美味いもの食べてたんだな」と、誰かに食べてもらうことは幸せなことなのだな
時の流れが『人生フルーツ』より幾分早く感じたのはまだ沢田さんが若いせいなのかも
ほうれん草の薄紅色の根元探しに行かなきゃ
一種のドキュメンタリー
「キネマの神様」で演技に不安を持ったものの、松たか子と共演し、しかも大好きな〈ご飯映画〉ということで、そこそこ期待していた、沢田研二最新作。想像通りの出来栄えで、四季のある自然豊かな日本という国に住んでいることに、すごく感謝したくなる作品でした。
この映画、非常に独特で、一種のドキュメンタリーのようなテイスト。1本の映画として綺麗にまとめるために、ストーリーがおまけ程度に加わっているような感じです。そのため、物語としてはパンチがなく、どこかぎこちなさを感じてしまうのだけど、四季折々、美味しいものたくさんの日本の良さが、12ヶ月を通してしっかり描かれているため、全くもって飽きません。
ドキュメンタリーと感じる部分はこれだけでなく、一部の棒読み演技を除き、作品全体がこの上なく自然という点でも。虫や鳥などの生物、そして各月の天候なんかはもちろんのこと、ちょっとした会話や動作も、作られている感じが全くない。ただただ、田舎に住む男のある一年を密着したみたいな。これがすごく居心地が良くて、この暖かな空間にずっと居ていたいと思っちゃう。そんな映画です。
懸念していた沢田研二の演技は、「キネマの神様」からは考えられないくらい良いものになっていて、松たか子との相性も抜群。山に訪れ、植物を採り、家に帰って、料理をする。この姿が沢田研二の良さを存分に発揮できていていました。彼のナレーションも、流石歌手なだけあって、聞き心地が最高です。ジュリーファンは必見でしょう。
この映画見たら、日本愛が深まり、自然の美しさを実感でき、そして何より料理がしたくなります。肉や魚が無くとも、こんなにも素晴らしい料理が出来上がる。不便ではあるだろうけれど、この暮らしにどこか憧れを抱きました。デジタルデトックス(=携帯やテレビなどの俗物的な物に触れないこと)もしてみたい。あと、この映画見たら、ジャンクフードなんかを食べることに、躊躇いを覚えます笑 映画後にマックを食べようかと思っていた私は、急遽定食屋に向かうことにしました。
なんとも味わい深い作品です。
「おいしい給食」「きのう何食べた?」など、日本は料理映画を作る才能に長けています。劇場で絶対に!という映画では無いですけれども、是非とも多くの日本人に見て欲しい良作です。よし、大根と筍、買って帰ろう。
精進料理好きには最強の「飯テロ」映画となりそうな一作
『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015)が、連続するアクションを通じてテーマを物語っていく作品であるとすれば、本作は食材を採取し、調理する描写を通じて物語を語っていく種類の作品です。原作(原案)のエッセイを著した作家、水上勉と料理研究家の土井善晴の人物像や思想が混ざり合ったツトムという老作家を、沢田研二が飄々と演じています。
松たか子演じる真知子との年齢の離れた恋愛関係も、言葉に頼ることなく食事の時の表情や会話、並んで料理を作っている時の立ち位置など、具体的な所作でおおよそ理解させてくれます。そして当然のことながら、土井善晴が指導した作中の食事はどれも見事に美味しそうで、食事時に空腹で鑑賞したらお腹の虫が鳴くこと間違いなしです。撮影にあたってスタッフ自身が、丹念に食材を育てたということもあって、味噌ひとすくい、青菜の一枚に至るまで、愛情が伝わってきます。
表題の通り、本作は主に、山奥で生活するツトムの一年を、「食べること」を通じて描いていますが、季節感のある風景映像だけでなく、春は優しく、夏は硬い光質を、照明効果の入念な計算と調整により表現しており、画面全体で季節を感じることができます。
また「車」を文明批判の象徴として使っているといった分かりやすい記号的演出も幾分散見するのですが(親戚の夫婦など、振る舞いが分かり易すぎ!)、そうした思想的な側面の描写はそこまで押しつけがましさを感じさせず、むしろややそうした思想、生活を相対化しているような描写も含まれています。
鑑賞後は食べ物に対する愛情が間違いなく増す一作です。
昔の歌声で
憧れ
酷い映画
たまにはこういう質素なものも
土を喰らう十二カ月のその名の通り、土からとれる自然の恵みをいただきながら過ごす一年を紹介するという映画。地味であり、これといった見どころもないが、だからこそ「十二カ月」なのだろう。
自然の恵みをいただいてただ生きるという、都会ものにとってはすでに懐かしさを感じない古風な日本を淡々と描く。一年通して描く。あくまで淡々と描くのだが、そこで生きる人間には確かにドラマがある。好きな人と一緒においしいご飯を食べたり、病気で死にかけたり、死を想いながら生きることにしたり。
映画の醍醐味のひとつに他人の経験を仮想体験できることがある。ヒーローが出てきて派手なアクションを繰り広げることも、歴史の転換点でたいそうなドラマも経験することもできないが、質素に生きておいしいものを作って食べる仮想体験があっても良いと思う。
それにしてもあのゴマ豆腐はおいしそうだ。印象に「おいしそう」がないのが悔やまれる。食べたい。
生きることは単純なことなのに、人は色々と考えて自分から難しくしているように思う
前半は明るいノリで年の離れた恋人ともうまくやっているように思える、この部分だけなら山奥で自給自足の生活、小説を書いて暮らしている、誰もが憧れる田舎暮らしと見えるけど、これは健康な体があって、勿論多少のお金もなければ続けるのは難しいかもしれないと思ってしまったわ。
主人公のツトムは小説家という設定なので、一人でいるのが苦にならない好きという人は良いかなと思ってしまったけど。
映画の中でもスマホや携帯を使っているシーンはないし、真知子との連絡は電話だけみたいだ。
一緒に暮らそうかとツトムから言い出したけど、後半ではやっぱり一人の生活を求めるのは現実が見えて死に対して考えを改めたせいだろうか。
勝手だと責める真知子もだけど、こういうとき、最初に話を持ちかけられたときに即決したほうがいいと思うのだ。
年の差は分かりきっているし、少しでも二人の時間を過ごしたいなら悩む時間の方が勿体ないと思うのよ。
食べて体を動かして生きて行くのは単純で死が怖いというのも人間なら当然、シンプルなことだけど人は難しく考えてしまうんだろう。
使い切れないほどの金があっても体が弱かったり病気で動けなければ人生は幸せとは言えないと思う、でも、その反対も有りなのだ。
奥さんの遺骨をどうするのと真知子は最期の別れ際聞くけど、それを伝えなかったのは男としてのプライドか見栄、優しさなのか、どうなんだう。
松さんの演じる真知子は力強くてしっかり者という感じがするので別れた後は前を向いて、ツトムの元を訪ねたり、電話をかけたりという事はしないだろう。
でも、他の女優さん、例えば井川遥さんだとツトムがご飯を食べているときに、いきなりやってきてお「お腹空いたー」と家の中に入ってきそうな気がする。
「結婚したんじゃないのか」と聞いても、んっ、なんのこと?ととぼけそうな気がするのだ。
丁寧に生きる
旨そうなん
たまにはいいんじゃないかな。
全125件中、61~80件目を表示