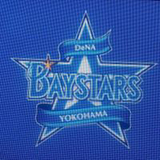ONODA 一万夜を越えてのレビュー・感想・評価
全81件中、21~40件目を表示
一体、何と戦っていたのか
フィリピン・ルパング島のジャングルで30年間も潜伏していた小野田少尉の物語を、フランス人監督が、日本人俳優と日本語で映画化。3時間近い作品だが、全く飽きさせない。
小野田少尉が発見されたニュースは、小学生の頃に見たが、そこに至る経緯などは知らなかった。その前にグアムで発見された横井さんに続いて、日本の敗戦を知らずに生き残っている兵士がまだいたのかと驚いたが、特にその時の軍服を着てこわばった表情で敬礼している姿が強く印象に残っている。
映画化にあたって、アラル監督は、史実をベースに物語を再構築したようだが、もし日本人が作ったら、もっとウエットで、大和魂や武士道精神といった色が付きそうなところを、極めて淡々と、冷酷に描いている。
陸軍中野学校での上官からの命令を守り、ゲリラ戦を遂行するためだけに、田畑や家畜を襲い、時には住民を殺害して、とにかく生き延びようとする。父親からの呼びかけも謀略とみなし、逆に、秘密の暗号伝達かと考えて解読しようとする。
彼らは、一体、何と戦っていたのだろうか。
戦争の悲惨さ、不条理さというより、一つのことを信じ切った人間の恐ろしさ、凄まじさ、そして虚しさが、この作品のテーマであるように思う。不寛容、断絶が広がる現代社会に共通するテーマとして、日本人ではなくとも、この稀有な題材に惹かれたのだろう。ラスト、日本人の記憶にある敬礼姿ではなく、茫然自失とした姿で描かれているのも、そのことを強く感じさせる。
小野田少尉役の遠藤雄弥、津田寛治をはじめ、役者陣はみな良い。特に、イッセー尾形、仲野太賀は、他の役者では考えられないほど。
2012年は、MINAMATAとこの作品が公開された年としても記憶されるだろう。
小野田さんを知らない世代にも見て欲しい
当時私は子供だったので、小野田さんと横井さんの区別が曖昧だった。ただ、敬礼姿をTVで見たのは覚えている。
スパイ作戦の重要な任務であると教育された日本兵達が、ひたすらジャングルを歩き回る、何のためか明確な答えを探しながら。戦争とは、勝手な思い込みと一方的な欲望を達成させるための暴力であることがわかる。
孤独な悲しみを乗り越えて生還した小野田さんの話を語り次ぐことで、時代は違えど、戦争を繰り返してはならないという想いは伝えていくべきだと痛感した。
何年か前、TVでドキュメンタリーかなんかを観ていておおよその内容は...
何年か前、TVでドキュメンタリーかなんかを観ていておおよその内容はわかっていたので、それの細かいところが補完された感じ。
なんか日本映画にしては割とちゃんと日本兵を悪い感じに描いてるなーと思ったら、監督は外国人だったのか!納得。
些細なことだけど、ドキュメンタリーでは母親とのやりとりだったはずのところが父親とのやりとりに変わっていたけどこれ変更したのはなんか意味あったの??
戦争を知らないぬるい人生を生きられているありがたさを噛み締めると共に、限られた情報と環境下に置かれる怖さを思い知った。
信念を持つのは良いことだと思うけど、洗脳というか特定の事物に傾倒し過ぎたり忠誠を捧げてしまうのは危険ということも改めて再確認した感じ。
終戦後に命を落とす羽目になってしまった戦友二人が気の毒で仕方がない。
何が正しいのか判らなくなる怖さ
なぜ最後の場面での小野田の敬礼がないのか??
日本最後の兵士の衝撃の史実
長い
見応えアリアリ
どれだけ時間がかかっても
終戦の知らせを受けられず、戦後30年以上も救援部隊を待ち続けた小野田少尉と、彼を日本に戻そうと島に降り立った青年の物語。
こういう人が居たという事実は何となく知っていたけど、詳細はわからずに観賞。
戦争は終わっているとは言え、それを知らないわけだし、30年以上も限界を極める生活を送っていたなんて想像できませんね。どれ程の緊張感の中生きていたのだろう。
米兵は来なくとも、気候や病気等々、見えない敵はいくつも潜んでいましたからね。
序盤から粗終盤まで、ルバング島での少尉達の姿が描かれる。数多くの苦難や疑心、仲間内でも考えの対立で彼らは日々、心身ともに疲弊していたのでしょう。
そして仲間との別れの数々。本当は戦争は終わっているという事実がまた哀しい。。
また、玉砕は許されない、という考えもあったのですね。自分が抱くイメージとは逆だったので。まだまだ知らないことは多いなぁ。
紀夫青年の勇気も凄いですね。言うて相手は軍人ですから。彼こそが、小野田少尉達が待ち続けた人物なんじゃないかな。
小野田少尉の涙が意味するものは・・・?
全体を通し、改めて戦争犠牲は多種に渡るのだなぁと教えてくれた作品だった。
赤津氏が言っていた、「何の意味があるのか」。
答えは勿論わかりませんが、意味が無いと言うのなら、その意味が無かったという事こそが、大切な意味になるのではないでしょうか?
改めて、戦争は繰り返してほしくないと、強く願った作品だった。
あ~佐渡~え〜の続きはおのれ次第
やられた!
悔しいな。なんで日本人の監督はコミック原作やミステリー小説などの小説原作の映画化ばっかり作ってんだろ。
だからと言ってアメリカ人の監督が撮影したらこうは行かない。
フランス人の若手監督が撮ってくれたからこんなに素晴らしいものが出来上がったんだな。
日本人目線でどこに出しても恥ずかしくない仕上がり。
ひたすら感謝だ!
津田寛治の目の演技が良い。
テレビで見せるコミカルな演技とは全く違う。
小野田さんそのものに見えてくる。
そして、仲野太賀の旅行家は勘弁して下さい!
この映画どうやってキャスティングしたんですか?
知ってる人がいたら教えて。
もう彼にしかだせないよこの味は。
人懐っこく小野田さんの心を溶かすこの演技!津田寛治と仲野太賀のシーンは鳥肌が立ちました。
若き日の戦士たちの姿を描く大半の数々のエピソードは全てこの瞬間のためにあったのか!
ラジオを聞いた後の作戦会議のシーンとか海でおよぐシーンとか素晴らしいシーンもあったし、ちゃんとしてるよこの映画。
作ってくれてありがとうという感謝しかない。
戦争を知らない子供たちの私。
そして、戦争を知らない子供たちという歌さえ知らない平成生まれの人達、色んな人が知るべきことをなるべく毒がなく、素直に描いてくれたなと思いました。
佐渡~え〜の歌、上官の真似じゃダメなんだよな。
自分の頭で考えて行動してそして一万夜を超えて生き残る!
この映画を観た者も、佐渡~え〜の続きは自分で作って行って欲しい。
小さい時のニュース
なかなかの力作
予想以上によかった。
知っている役者が数人しか出演していないし、それほど話題にものぼっていない作品なので「どうかな?」という感じで観にいったけれど、結果、3時間という長さを感じさせない、なかなかの力作でした(僕が大東亜戦争や旧日本軍のことに、とくに関心があるせいかもしれませんが)。
「戦争の悲惨さ」などという言葉を聞いてもどうもピンと来ないけれど、この作品に描かれているような戦争のディテールに接すると、ぐっと戦争というものを身近に感じる。リアリティーを感じる。このような、戦争のディテールを知ること、想像することこそが戦争体験のない我々には必要だと僕は思うのです。
イッセイ尾形、やっぱりうまいですね。作品にアクセントがついて、厚みがでるような気がします。
それから、仲野太賀。彼は、これからの日本映画界を背負って立つ存在でしょう。
ただ、原作・監督ともに日本人でないことが、なんか残念だった。
このテーマは、日本人の手で映画にしてほしかった。
それにしても、それにしても……なんとも、やるせないなぁ。
日本の平和は、このような出来事の上に成り立っているということを、戦後の平和を享受している我々は忘れてはならないと思います。
現代人に訴えかけるもの
小野田少尉の野戦記。
今、映画化される意味って何なのだろう?
戦後76年、帰還から47年、没後7年・・・
全て中途半端。あえて節目ということで言えば来年が生誕100年にあたるということぐらいか。
それはともかく、多様性であるとか個人の尊厳が重視される現代、特に本作が制作されたフランスにおいては滑稽に思えるほど、それこそ、中世の封建時代的な時代錯誤の思考回路を持った兵士が、ごくごく最近まで存在していたという日本という神代の国の特異性を(当時の日本でも小野田さんは稀有な存在だったであろうが)揶揄する意図も多分にあるのでは? と思ったが、少し考え過ぎか?
おそらく、今の日本でなら企画段階でボツになるのだろうし、海外だからこそ映画化されたのかな、とも思う。
とは言え、史実に忠実に丁寧に描かれていることもあって見応えはあり、三時間弱の長編でありながら飽きずに見られた。
特に、今まで映像作品で触れられることの無かった陸軍中野学校の様子が詳細に描かれているのが良かった。
出来ることなら、小野田さんを発見した冒険愛好家・鈴木紀夫氏が小野田さんに興味を抱いた過程も盛り込んでくれると更に良かったかも。
それにしても、優男のイメージの津田寛治がまさかの小野田少尉役。でも、日焼けした肌にこけた頬、ギラギラした目付きは正にジャングルで生き延びてきたコマンドーのそれで、見事な役作りだと思った。
喜劇であり悲劇
小野田氏が日本会議のメンバーであり、亡くなるまでずっと右翼的な考えを持ち続けた事に非常に興味がありました。あの惨たらしい戦争に対する怒りや贖罪は最期まで持つことはなかったのかと。
劇中、小野田氏と小塚氏は日本のラジオを聴いていました。捜索にきた小野田氏の父親と兄は戦争は終わった事を訴えていました。彼らはルバング島での雰囲気からも戦争が終わったことを理解していたと思います。
しかし、彼らは自分達が創作した物語から出ることはありませんでした。自分達が創作した物語から出られなかったという方が近いかもしれません。小野田氏は谷口上官の命令が無いとこの物語から出られないと言いました。彼の主体性の無さ、私には実に滑稽に映りました。
彼らが創作した物語は、実に勇ましい物語です。しかし、現実は違いました。第二次世界大戦で亡くなった日本人は310万人で、兵隊の8割は餓死で亡くなっています。アメリカが原爆を作っている時に、日本は竹槍訓練をしていました。それが、現実です。
この愚かな物語を初めに書いたのは、大日本帝国です。つまり、小野田氏は大日本帝国が創作した物語に敗戦後も更に物語を付け足していったに過ぎません。だから本作は喜劇であり、悲劇でもあるのです。
今の自民党の議員にも大日本帝国が創作した物語から出られない人間が散見されます。どうやったら日本がこの物語から出られるのか?まさか、上官からの命令がないと出られないのか?だから、この物語が誤りだった事に主体的に日本が気がついた時に、初めて日本の民主主義が始まるのではないでしょうか。
私はクストリッツァ監督のファンなので、クストリッツァだったら小野田氏をどうやって滑稽に、日本の戦争をどうやって悲しく撮るんだろうと思ってしまいました。観てみたいです。
久々に面白いと思った日本人主演の映画
新宿の歌舞伎町TOHOシネマで見てきました。
劇場は小さいところで、それでも人がたくさん入っていてました。
劇場で見た久々に面白い日本人主演の映画でした。最近の邦画はお金がかけられないことやあまりいい監督が出てこないこともあり低迷しています。しかし、本作はフランスの監督が撮影し国際共同制作ということでとても面白い映画に仕上がっていると思いました。3時間弱の映画で長いですが、小野田少尉の30年を3時間に詰め込んだ分濃度が高いと思いました。
以前から小野田少尉の体験を映画化したら面白いだろうなと思っていました。実際に制作されて大変嬉しく思っています。
小野田少尉は30年の戦争生活のなかで、ルパング島の現地人を30人ほど殺害しているらしいですが、本作で現地人との戦闘シーンは隊員の生死がかかったところでしか描かれていないために少なめです。そして、劇中で小屋を立てて生活するシーンが続きますが史実だと横穴を掘っていたそうです。少々脚色はありましたがそれでもドキュメンタリー、人間ドラマとしての映画であるため人物の心情描写は文句無しに良かったと思います。
今の日本で小野田少尉の体験だけでなく戦争の記憶は薄くなってきています。だからこそこのような映画を作って後世に伝えていく必要があると思います。私はまだ学生ですか多くの戦争映画を見てきて学びがあるばかりです。
戦争を知らない子供たちにこそ見て欲しい映画作品だと思います。
3時間ドラマ的なドキュメタリーの様な作品
過去の記録だけではない
全81件中、21~40件目を表示