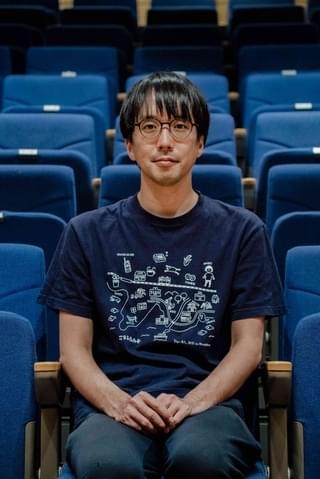オレは広島出身だし、舞台はなじみある呉市だから、どうしてもひいき目はあるもんだが、「この世界の片隅に」に並ぶ呉映画の代表作といっていい。
「この世界の片隅に」がオレのおばあちゃんの話であるならば、これは、オレの話であり、オレの娘の話だ。
「こちらあみ子」
・
・
・
しかし、まあ、情報量の多いこと。これを21日間で撮ったとのこと。ちょっとどうかしているほどにヤバい。スゴイ。原作未読だが、本作を観れば、作り手がどんなに原作を愛し、咀嚼し、腹に落とし込み、作り上げたのかが、滴るように感じる。
オレはこのあみ子を特別な子とは思えないし、ましてや発達障害だという風にも思っていない。あえて言うなら、ノリ君の苗字が分からないところぐらいか。
■見える世界
カメラは基本、「ある視点」で少し距離をとってあみ子を描写する。時にあみ子からの視点となるのは、
・サチコのホクロ
・同級生の小坊主
の2点。
お父さんの新しい奥さんになるサチコをホクロオバケというあみ子にコウタは自分のハゲをみせ、わしははげか、兄ちゃんか?と尋ねる。あみ子は兄ちゃんだと答え、コウタは「そういうことじゃ」と返し、あみ子はへたくそなスキップで「お母さん♪」と喜ぶ。
実際にサチコと生活すると、ホクロばかり見てしまうあみ子。
しかし、臨月のサチコが病院から帰ってくるのを、猛暑の中、外で待つあみ子。そのあみ子をみて、「びっしょりじゃね」とサチコはあみ子の顔、頬を手で愛おしく(一方で執拗に)汗をぬぐう。この時にあみ子から見るホクロはなぜか小さくなっている。
ここで初めてあみ子から見て、ホクロオバケではなく、お母さんになったのだろう。
しかし、実は死産という結果で、あみ子の家庭は崩れていく。(オレはこの死産の理由が、サチコの崩れようからして、ちょっとイヤな想像をしているが、ここでははっきりと描かれていない)
もう一点、同級生の小坊主との会話。小坊主のある言葉を境に、風向きが変わる。(本当にカーテンの揺らぎが変わる!)そこから小坊主はあみ子からの視点となる。
子供は残酷だとか、無垢だとか、発育障害だとか、親からして、人間からして、そういうことではなく、向き合うきっかけは誰にだって必要だ。
この2点はあみ子の視点。そして大体を占める「ある視点」だが、これはラストとエンドクレジットでわかる。
「おーい、水はまだ冷たいじゃろ」と問いかける声は、エンドクレジットでトランシーバーが横に書かれた監督、いや監督だけでなく、オレらの声なのだ。
「大丈夫じゃ」と答えるあみ子。
「ある視点」とは監督のこの作品への誠実さの表れであり、またオレらの誠実なまなざしでなければいけない。
■予兆
落ちてこないミカンは、その後の誕生日の食事の悲しい出来事の予兆。
とうもろこしのビシャビシャは破水の予兆。
テレビで流れる「フランケンシュタイン」は「ミツバチのささやき」のオマージュと、そこから聞こえる悲鳴は、病院にいるサチコの悲鳴。
保健室でのチャイムの音の音程がズレるのは、その後の悲しい出来事の予兆。
玄関のすりガラスは不安を感じさせ、玄関からところどころ物語が展開する。
■お気に入り
あみ子が霊の音を感じ始めるところはちょっと「エクソシスト」を思い出し、家の階段もちょっと「エクソシスト」を感じさせるんだよね。だけどそれはホラー的な見せ方ではなくって、あくまで作り手が映画好きってことだろう。(サチコの伏せた髪はさすがに貞子ではないだろう)
ノリ君の腹キックを不謹慎に笑ってしまったり、保健室の先生役播田美保が妙に怪演で笑ってしまった。
追記
ちょいちょい挟む小動物
「僕らはみんな生きている」
そういうことじゃ。





 福田村事件
福田村事件 朝が来る
朝が来る ピンポン
ピンポン 止められるか、俺たちを
止められるか、俺たちを 光
光 空気人形
空気人形 ルート29
ルート29 ニワトリ★スター
ニワトリ★スター 殺意の道程
殺意の道程 白河夜船
白河夜船