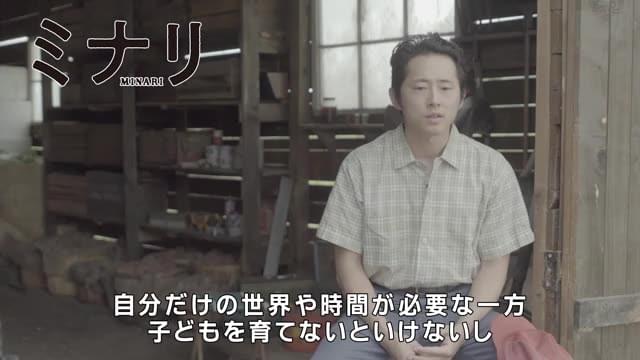ミナリのレビュー・感想・評価
全237件中、1~20件目を表示
聖書を暗示する要素に満ちた物語を紐解く
アーカンソーの解放感ある高原風景の中、冒頭からちょいちょい暗雲のようなエピソードが提示される。鑑別後に処分される雄ヒヨコの煙、夫婦の不和、不便そうな土地での幼い息子の病、怪しい隣人。
妻モニカの母スンジャの登場で多少頬の緩む場面も出てくるものの、家族の先行きへの不安感が常に見え隠れし、倉庫の火事というカタストロフィでめげそうになった。終盤に希望の予兆をチラ見せする程度の救いのシークエンスがあるが、きっとこのあとセリがバカ売れしてお金持ちになったんだよ、と自分で脳内補完しながらエンドロールを眺めていた。
スンジャを演じたユン・ヨジョンは確かに圧巻だ。序盤の家事もせず奔放な姿から、孫への深い愛情を示す姿、病んで弱った姿まで。韓国のハルモニだけど日本の80年代のおばあちゃんもこんな感じだよね、と思ってしまう普遍性を感じた。彼女に着目して見るだけでも、十分見応えのある物語だ。
ただ、宣伝にあるようにアメリカの各映画祭で軒並み受賞し、ロッテントマトの批評家支持率100%という評価に対する実感は、鑑賞中には得られなかった。
色々調べたところ、町山智浩氏がpodcast「映画ムダ話」で解説している聖書エピソードとのリンクの説明が一番腑に落ちた。監督もインタビューで聖書との関連に言及しており、それなりに妥当な解釈のようだ。
聖書にインスパイアされた物語は多いが、監督の実体験に基づいたリアリティ、アメリカ人の開拓民魂に通じる設定に加え、聖書の物語がこれだけ随所に織り込まれているからこそこの作品はアメリカで高く評価されているのだろう。
裏返せば、アメリカ以外の非キリスト教圏では監督の意図が十分には伝わらない場合があるのではないだろうか。私は、聖書由来の背景を後から理解はしたものの、知識欲が満たされたに過ぎず、キリスト教徒が享受するであろう感動はおそらく体感出来ていない。自己弁護になるが、これは文化の違いによる限界で、見る側の理解力のなさとは違う要因だと思う(思いたい)。
町山氏が内容転載OKである旨言及しているので、自分用の備忘も兼ねて、ごく一部(podcastは本作の話だけで70分ある)の内容を書いておく。自分で調べて短くまとめた部分もありますが、基本受け売りですみません。
【ジェイコブ】
ヤコブ。サタンに神への信仰を試され、様々な苦難に会う。神の祝福を得るため天使と格闘し、祝福を勝ち取ってユダヤ人の始祖となる。キリストは、彼が掘ったとされるヤコブの井戸に立ち寄った後ガリラヤで病気の子供を救う。また、ヨハネ福音書「ひとりが種を蒔き、ほかの者が刈り取る」に掛けて、移民1世代目が苦労し、2世代目以降がその成果を享受することをジェイコブが体現する。
チョン監督の父親(移民)がモデル。なおチョン監督の韓国名イサクはヤコブの父親の名前。
【ポール】
聖パウロ。知恵で神を知ることは出来ない(コリント人への手紙)という記述から作中のような人物設定にした。
【デビッド】
ダビデ王。イスラエルに繁栄をもたらす王でヤコブの末裔。子供の頃のチョン監督がモデル。
【冒頭の引越トラック】
側面の会社名CATHER TRACK RENTALは、アメリカの小説家Willa Catherから。チョン監督が本作を作るきっかけになった「私のアントニーア」作者。
【トレーラーハウス】
ノアの方舟。ハリケーンが洪水にあたる。
【モニカのジェイコブへの批判】
約束の地になかなか辿り着かないモーゼに対する民の反乱。
【川のほとりに育つミナリ】
出エジプト記で神がモーゼの祈りに応じ天から降らせたマナという食物。イザヤ書44章で神がヤコブに語った内容にも掛けてある(神が乾いた地に水を注ぎ、ヤコブの子孫が恵みを受け、流れのほとりの柳のように育つ)。川辺に蛇が現れるのはエデンの園がモチーフ。
【祖母スンジャ】
運命そのものの象徴、神の化身。不幸や幸福をもたらす。病を治す(不安がるデビッドを抱きしめて眠った後スンジャが病み、おねしょをした。デビッドは病が改善した)。家族をひとつにする(火事によって結果的に家族の絆が復活する)
【太陽の映像】
神の奇跡の象徴。作中には太陽の映るシーンが3回あり、その都度奇跡が起こる。
【ダウジングで発見した水源にジェイコブが置く石】
ヤコブが神からイスラエルの名を受けた時に建てた祭壇。
開拓精神
2000年代にLAに住んでいたが、韓国からの留学生が多かった。LAのコリアタウンも急速な勢いで発展していて、LAにいながらにして国の勢いを感じたのをよく覚えている。
アメリカ全体の人口比率からすると少数だが、移民者の中では韓国出身はかなり多くて、米国移民者の出身国として9番目に多いそうだ。移民が増加し始めたのは1980年代だそうで、この映画が描くのはちょうどその頃だ。本作で描かれる韓国からの移民一家は、韓国移民社会にとっての先駆者的な立ち位置になるだろうか。
韓国人一家が主役であるために、言語の多くはハングルで、それが理由でゴールデングローブ賞では外国語映画部門にカテゴライズされたことが物議をかもしたが、本作が描くのは、初期の移民としてより良い生活を求めた彼らの苦労であり、それはアメリカの建国精神とも言える開拓者精神だ。その意味で、本作は確かにアメリカ映画だ。アメリカンドリームという言葉がまだ有効だった時代の物語だが、単純なサクセスストーリーにせず、多くの犠牲を払う夢のほろ苦さにあふれた作品になっている。祖母役のユン・ヨジョンが抜群に良いアクセントになっていて、作品全体を引き締めていた。
この一家の暮らしをずっと、ずっと見守っていたくなる
目下、アメリカ映画が多文化的な進化を続けている。これもその流れを強く感じさせる一作だ。韓国からアメリカ、アーカンソー州へ越してきた家族。彼らを待ち構える運命は決して前途洋洋とは言い難い。だが、本作には眩い光がある。輝きがある。何よりもこの映画は一つの文化に閉じこもることなく、常にあらゆる観客の感性に向けて開かれた大らかさを持っているかのよう。土の香りや植物の緑。農作物のみずみずしさや木漏れ日の美しさ。とりわけ変幻自在に全編を彩る「水」と「火」は印象的で、これらは対極的なイメージでありながら、いずれも家族を写しだす鏡とさえ言える存在だ。兎にも角にも、従来の米映画が描かなかった新たな物語であり、なおかつ”開拓”という意味合いではあらゆるアメリカ人に通底する側面を持った本作。家族を演じた面々のハーモニーが素晴らしい。新風を吹かせる”おばあちゃん”や隠遁者風のウィル・パットンの味わい深さも絶品だ。
家族がたくましく生きる姿が静かに深い感動を呼ぶ
この作品は1980年代のアメリカ南部を舞台に、韓国出身の移民一家が理不尽な運命に翻弄されながらもたくましく生きる姿を描いた家族の物語だ。農業での成功を目指す父に「バーニング 劇場版」で印象的な演技をみせたスティーブン・ユァン、荒れた新天地に不安を抱く妻に「海にかかる霧」のハン・イェリと演技派俳優が顔を揃えた。さらに韓国で敬愛されているベテラン女優のユン・ヨジョンが毒舌で破天荒な祖母を演じ、その存在感ある演技が絶賛されている。監督・脚本は、「君の名は。」のハリウッド実写版を手掛けることでも注目を集めている韓国系アメリカ人のリー・アイザック・チョン。
しかし本作は韓国映画ではない。「ムーンライト」など話題性と作家性の強い作品で高い評価を得ているスタジオ「A24」と、「それでも夜は明ける」など良質な作品を手掛けてきたブラッド・ピットの製作会社「PLAN B」が、チョン監督の脚本にほれ込み、タッグを組んで作った映画だ。劇中の大半が韓国語であるにもかかわらず、このような強力な体制で、韓国人が主人公の企画が成立したのは、多様性が求められている昨今の社会情勢やそんな企画を探しているハリウッド事情も追い風となったのであろう。ユァンはブラピとともに製作総指揮にも名を連ねている。
チョン監督は、葛藤する夫婦、親の子への愛、そして祖母と好奇心旺盛な孫の絆という3世代の家族を見つめ、所々にどこか懐かしく美しいカットを挿入しながら、運命に打ちひしがれても人生は続いていく貴さを描いている。祖母が請け負い、失い、そして子と孫に残すものが、静かに深い感動を呼ぶ。
本作の成功はほんの1部分に過ぎない
描くのは一言で言って「人生」。アメリカ、アーカンソーの荒れた土地を耕して農場を作ろうとする韓国人移民一家に降りかかる、苦労と災難、夫婦間のすれ違い、子供たちのゆっくりとした成長、世代間の融合、etc。実は最近、あまり描かれることがなかった生きることそのものがもたらす、切実さと静かな感動がここ
にはある。あえて書き加えるなら、慣れない場所に住まい、同化することの困難さ、その力強さが、妙に心をざわつかせる。ミナリとは、どこにでも根を張り、成長する韓国産セリのことだとか。なるほどと思う。それは、監督のリー・アイザック・チョンと主演のスフィーヴン・ユァンたちが築いてきた、韓国にルーツを持つアメリカ人たちが歩んできたリアルな時間にも繋がるからだ。彼らと同じ移民2世3世たちは、この映画に自らを重ねただろうし、また、受け入れた側のアメリカ人たちは、母国について改めて思いを馳せたに違いない。そうして観客の裾野は広がり、結果、今年の賞レースをリードすることになったのだと思う。本作を観て感動したJ.J.エイブラムスは、自らがプロデュースする「君の名は。」のハリウッド実写リメイクの監督にチョンを指名したことでも分かるように、アジアン・パワーはハリウッドに深く根を張り、逞しく成長を続けている。「ミナリ」の成功はほんの1部分に過ぎないのである。
期待値を上げ過ぎずにタイトルの意味を踏まえながら見ると、見え方が変わる秀作。
本作は、本年度アカデミー賞で、作品賞、監督賞、主演男優賞、助演女優賞、脚本賞、作曲賞の6部門にノミネートされました。
正直この結果には、2つの驚きがありました。
まずは、舞台はアメリカでも言語はほとんど韓国語なので、ゴールデングローブ賞のように「国際長編映画賞」(外国語映画賞)が対象かと思っていましたが、そこにはノミネートされなかった点。
そして、主要な6部門でのノミネートとなった点です。
この映画は、「期待値を上げ過ぎると、アレ?」となる可能性は低くないと思います。
なぜなら、そこまで大きな事件も起こりませんし、基本「家族の日常」を描いているだけなので。
そのため、「アカデミー賞主要6部門ノミネート」ということで期待値を上げないことが大事です。
作風としては、小津安二郎監督作品に近いと思います。
今で言うと、その流れをくむ山田洋次監督、是枝裕和監督作品といったところでしょうか。
本作は、韓国系アメリカ人のリー・アイザック・チョン監督が、半自伝的な映画として脚本も書いています。
1980年代のアメリカ南部を舞台に、韓国から移住した一家が農業で成功するという、アメリカン・ドリームを掲げつつ、丹念にその家族の様が描かれています。
アカデミー賞のノミネートで納得なのは、やはり祖母役のユン・ヨジョンの助演女優賞でしょうか。
「おばあちゃんらしからぬおばあちゃん」を見事に演じ切っていました。
さて、本作を楽しむカギは、やはりタイトルになっている「ミナリ」でしょう。
「ミナリ」は韓国語で、日本では「セリ(芹)」と呼ばれる香味野菜のことです。
このセリは、日本でも普通に栽培されていますし、雑草の如く、たくましく地に根を張り育っています。このセリが、どういう風に作品と関わっていくのかに注目するとメッセージ性がより伝わりやすくなると思います。
An Awaited Tale of American Rural Life
The story of a Korean family settling on an Alabama farm in the 80's points to the bigger picture of how the immigration experience in the US and elsewhere is a phenomenon with plenty of terrain for fresh and interesting entertainment. Equal parts heart-warming and sad, the character dynamics of the family members and their religious neighbor make the film fun, though it's melodramatic at times.
移民の国アメリカではだいぶ受け取るものが違うだろう
かつてアジアから大きな夢を抱いてアメリカへ渡った人々がたくさんいた。アメリカじゃないけど渡った日本人にアントニオ猪木もいた。
希望に満ち溢れてるはずの生活は決して楽なものではなく、こんなはずじゃなかったと夫婦で罵り合ってしまうのもわからんでもない。
そこに突然異星人のごとき母がやってくる。正直品が良いとは言えない人物だ。でも心根は悪くない。生命力にあふれている。娘はそんな母を嫌がりながらも尊敬してる部分もあり、なんとも複雑な感情が共存する。
それを感じ取るのか孫たちも戸惑いを見せるが、異星人は次第に溶け込んで家族の一員になっていく。この流れが自然でリアルな一家を見ている気分になる。
彼らを待ち受けるのは過酷な運命だけれども、それでも家族で助け合っていく。そんな流れをくんできた家族が、きっとアメリカには沢山存在するのだろう。
この作品はアメリカの人々の、祖父や祖母の話と受け止められるんだろう。そう思えばアカデミー作品賞も納得だった。
苦悩
何気ない家族の何気ない日常を本当にうまく描く韓国作品・・・・!!
禍 転じる‥
淡々と進む物語
逃げろ、雄鶏。
幼稚園の頃、
すぐ近所に養鶏場と養豚場があって、幼稚園から帰るとそこに入り浸りだった僕。動物がとにかく好きだったのです。
60年も前のことだ。
思い返せばどちらも衛生状態は最悪で、それはそれは鼻がひん曲がるほどの悪臭だったはずなのだが、TVの「野生の王国」のファンでもあった僕は、柵を乗り越えて僕に喰いかかって来ようとする凶暴で小山のように大きな豚の、その絶叫と歯噛みする口腔と犬歯の嫌らしさと、吐く息と血走った目を間近に観察に行く。
そしてブタを堪能したあとには隣の建物に移動し、
今度は聴覚がどうにかなりそうな鶏舎の、耳をつんざくニワトリの騒音と、アンモニアと、高い体温からくる熱気にこの身を任せていた。
毎日やってくるこのチビ助を面白がってか、
「おい坊主、ヒヨコ持ってくか?」とおじさんが訊いてくれる。
メスはやれないがオスならくれると言う。何でオスだけ?
「オスは玉子を産まないからそのままスコップでブタの餌として放り込む」のだそうだ。
ブタの口腔を思い出す。
オンドリに生まれないで良かったと今でも思う。
ヒヨコは貰わずに家に帰り、僕の足もなんとなく遠のいた。
・・・・・・・・・・・・・
【ミナリ】
孵卵場の煙突の煙から映画は始まる。
役に立たないオス雛は焼却処分されるんだ。
弱肉強食の新天地アメリカで、心機一転、大きな借金をして移り住み、韓国野菜をその地に植えて、自分たちの天国を夢見る一家の物語。
・・・・・・・・・・・・・
喉がカラカラで水脈が欲しいとき、
そして生きることに疲れ果てて、心と体に 滋養強壮のミナリが必要なとき、
(忘れていたけれど) 自分がさすらいの”移民“だとふと感じる時に、
この映画は鑑賞者にそっと寄り添ってくれるんだろう。
おばあちゃんは命のタネを持って来てくれた。というか、おばあちゃんが命のタネそのもの。
何と言うことはない、普通の家族のストーリー。だからこんなにも地味で「オスカー候補」とか驚くけれど、
移民によって建国されたアメリカという国だ。自分のRootsに思いが及びゆくこの映画で、観衆やアカデミー賞審査員の心が揺すぶられたのも当然だろう。
韓国人農夫の男は後に引かない。
自分の決断を翻すことは出来ない。虚勢を張る。特に妻の前では、だ。
オスのヒヨコは役立たずだ。
男は威勢ばかりが強くて、自分のプライドが引っ込まないのだ。
そして妻。異国での生活と、夫の世話と、子育てでギリギリの妻。
意固地な夫に心底困り果てた妻モニカの目が男には辛い。しかし移民の男は後に引けないのだ。
「男の鑑定士が、(自らの分身である)オス雛を選別して焼却炉送りにする」っていう心的ストレス外傷は、女の鑑定士のそれとは違う。
玉子を生まず、結果を出せないオンドリは燃え尽きて焼却処分されるのだと男は知っているから、だから
かつて文無しになった男が自殺をしたこの農園で、この男は井戸が涸れても、借金を積み増ししても、水道水で野菜を育て続けた。
まるでオス雛の助命を求めるかのような足掻きです。
そんな移民夫婦のクソ頑張り物語でした。
・・・・・・・・・・・・・
さて、
おばあちゃんのあの失火で、彼は自身の生き方が、目が醒めることができるのだろうか、
森のせせらぎにおりていって、そのみぎわで柔らかな緑色の若葉を愛で、人心地を取り戻して、涼しい水辺で彼は憩うことができるんだろうか。
火と水が対照的に、象徴的に描かれていましたね。
アーカンソーの草原は寂しい。
帰ろうか。帰ろうか。
今は、ふるさとを遥か遠くに離れてしまって、ふるさとではではない新しい土地で冒険をし、進学し、就職し、結婚や子育ても体験し、
夢を見て、夢にやぶれて、希望を探し、しかし途方に暮れ、
でも今を頑張っている女も。男も。
・・そんなあなたへ捧げられた映画だと思う。
まったりしているが芯のある作品
夫婦喧嘩物語
西部開拓史では無いが見知らぬ地で農業に臨む姿は、ある意味、原点回帰の趣があるところがアメリカでの評価に繋がったのでしょう。
一方、80年代といえば、まだ人種差別も酷かった時代、それでも、この韓国移民の一家は差別どころか地元の人々に優しく受け入れられている点は意外でした。
農業に用水は必須なのに下調べもせずに行き当たりばったり、水道水では割に合わないでしょう。農業を甘く見る夫に不安を感じる妻の気持ちも判らないではないが、のべつ幕なしの夫婦喧嘩にはうんざりでした。
文化の違いと言うこともあるのでしょうが孫に花札を教える祖母というのも頂けませんね。
一家で力を合わせ新天地で成功を掴みとるというシンプルな感動ストーリーでないところがドラマツルギーなのでしょうが、キャラクター設定を含め雑味が多すぎてしっくりきませんでした・・。
セリ
アメリカ人はほぼ移民で、日本人はほぼネイティブ
もういないですが、うちのおばあちゃんはセリ農家でした。
歩いて行けるくらいの距離に住んでました。
地元に「ねまれ」という方言がありまして、
「家に上がってゆっくりしていってね。」という意味です。
さんざん遊んで帰ろうとすると、「なんで?」って言われます。
「晩御飯食べていけばいいでしょ。」と言う意味で言われているのです。
”近所”や”知り合い”ってだけで信頼し合い、
ドアに鍵なんてしない、いい時代のおばあちゃんでした。
助け合うのが当たり前なので、”助け合う”という概念すら
なかったような気がします。
生きる能力がなく、人としての価値観がないと
意味がないから誰よりも頑張る父親。
他の家庭と同じように都会で”普通に”暮らしたい母親。
そして、簡単に周囲に溶け込み、ゆっくりだが
着実に成長している子ども。
時代や科学は急速に変化していても、
自然環境はいつも美しいままそこに存在している。
何をいがみ合う必要があるのか。
他人を否定する必要があるのか。
自分一人では生きていけないだろう?
そこに種さえ植えれば、セリは勝手に生えて
あなたを助けてくれるのに。
2年前にいなくなったおばあちゃんに
笑われているような気がした。
ミナリ
面白かった。
この「面白い」の正体はなんなのだろう。謎に注目してみていたが、わかりやすい謎というものはこのお話にはなかったと思う。
それぞれがそれぞれに思惑を抱えていて、それが全員うまく行っていない。デビッドは、男らしい夢を追いかける。家族との両立をしようとするが、仕事にかける思いはやはり大きい。家族との安定した生活より、やりがいや、欠けるものがある方が燃える。一方妻は、家庭を守ることだけを考える。やりがいや仕事などより、まずは息子と娘、そして旦那。生活水準の向上。より良い暮らしを求める。
これは面白いなと思ったのは「老害」というもの。おばあさんは、周囲から見れば完全なるお荷物である。子供2人のお守りのために呼んだのに、逆にお守りされる側になる。金は盗むし、アメリカの生活に慣れそうとしない。わがままで横暴。責任感など一切ない。が、1番タチが悪いのはそれを悪いことだと思っていないことだ。正義を執行していると思っているところ。間違いなく迷惑をかけているというのに、それが正しいという自分の固定概念が抜けない。
整理してみても、私の思う「生の感情」が出る作品。ということではない。しかし、なんとなくこの作品にも「サスペンス」を感じるのだ。もしかして僕は単純に「悲しい」話が好きなのだろうか。うまくいかない。思うようにいかないところにサスペンスを感じるのか?
「悪者」は1人だって出てこない。さまざまな見方で誰もが「悪者」になる。
前回の映画で出た「生の感情」の発生。それは、もしかしたら観客の「生の感情」なのかもしれない。映画を見ていて、普段は隠しているつもりでもふと出てきてしまう「生の感情」が出る瞬間が心地いいのか。
例えば、子供がおしっこをおばあちゃんに飲ませようとした時、やってしまえ!と思った。おばあちゃんが、火を倒してしまった時、こいつ本当に嫌なやつだな。と思った。
でも、仕方がない。老人だから。このジレンマ。すごく嫌なやつで最低だけど、仕方がない。そういうものなんだと受け入れざるを得ない。
普通の映画レビューみたいになるが、最後木の棒で水源を当てるやつに頼るのが、やはりこの映画のキモ。周りを当てにせず、孤立し、自分の信頼するものだけを周囲に置くことだけが全てではない。主人公はとにかく足掻くが、足掻き方が違う。男のロマンを求めるのはいいが、賢く生活していかなければ、成功は掴めない。これがどんなことにも言えること。
というテーマが見えてきたが、そんなことはどうでもいい。自分がこの映画を見てどう思ったのか。どう感じたのか。
僕はこの映画を見て1番に思う感情は「やるせない。どうしようもない無力感」足掻いて足掻いて頑張っているのに、成功は逃げていく。
全237件中、1~20件目を表示