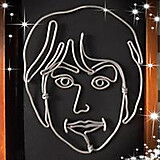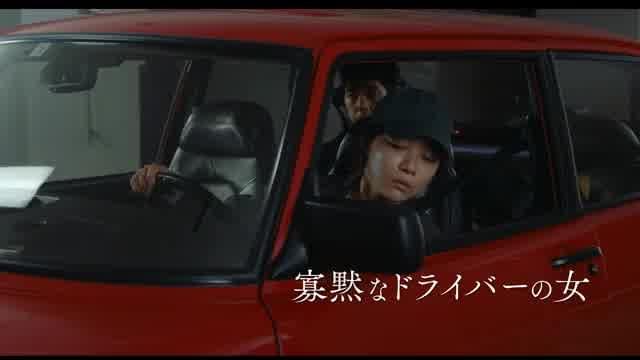ドライブ・マイ・カーのレビュー・感想・評価
全797件中、301~320件目を表示
村上春樹の世界
なのかな、と思いながら観ていたが、ゴドーもワーニャも観たことない自分には難解。感情を込めずに台詞を言うという稽古がよくあるのかもしれないが、音のテープから流れる台詞回しがあまりに棒読みで?だった。パンフでわざとだとわかったが。三浦さんの芝居も硬い。タバコに火をつける仕草など、慣れていない感じ。岡田さんはつかみどころのなさが良かったが、車の中での意味ありげな告白は取ってつけたよう。脚本の問題かと思いながら観た。
海外の評価は高いので、村上春樹さんの世界観が評価されたのではと思うし、ネタとしては面白いとは思う。古典を知らずしてこの映画は理解できないと言われているような気がした映画。
3時間は必要
ドライブマイカー
3時間越えの作品
自宅で配信で視聴出来るおかげでテレビ前に飲み物スタンバイでリラックスして見ようと、見始めた…
が、冒頭から引き込まれてそれどころではない。
夜明けの淡い明かりが窓から差し込む高層階の一室で
夫婦の営みと、交わされる不思議な会話。
シンプルで洗練された内装にインテリア、
何一つ無駄な物はないと思えるこの部屋が
この夫婦にとってこの上なく居心地の良い場所。
リビングの大きな鏡がそんな2人の生活をずっと、
静かに見守って来たのだろう。
あの日その鏡に妻の秘密が映り込むまでは…
妻が自分に何を言いたかったのか?
一生解けない謎と後悔を抱える事になった主人公が
もう1人の重要な登場人物(?)である
年代物の真っ赤なサーブを運転してどこかへ向かう。
そして、初めてタイトルが表れるのだけど、
そこまでで約40分。
いつまでも幸せが続くと思っていたのに、妻は秘密を残して突然この世を去った。
主人公の家福は舞台演出家兼俳優。
地方都市の演劇祭に招かれて公演までの数ヶ月を過ごす事になるのだが、その間、専属のドライバーがあてがわれる事となり、家福のサーブが初めて他人に運転される。
このクルマ、2シーターなので後部座席に乗り込むのがいちいちめんどくさい。
ここにも夫婦だけが使い、そしてずっと2人を見てきた車なんだという監督の意図を感じる。
劇中劇と、妻が語った物語と、現実
それらが複雑に絡み合って展開していくのだが、
家福が役者達に棒読みでセリフを読ませるのと同様
家福自身もあまり感情を表に出すことはない。
それはドライバーのみさきも同じ。
どこか同じ匂いをお互いが徐々に感じる様になる。
ネタバレを承知で言う
人は誰もが「キミは悪くない。キミのせいじゃない」
と、誰かに言って欲しいと願っている。
『あの時、こうしていれば…』何かが変わっていたかもしれない。
変わることを恐れて、自分だけが傷つけばいい。
その想いは正しかったのか?
長い旅の終着地を連想させる北海道の雪上で
家福は初めて涙を流す。
その傍らにはみさき。
大きな事件は何も起こらず、淡々と主人公の心の旅が続く。
劇中劇とリンクしながら、静かに静かに
観客の心の奥に染み込んでくる。
こんな作品がアカデミーにノミネートされたのが嬉しい。
ここのところハリウッドを席巻しているアジアンエンターテイメント。
『パラサイト』や『ミナリ』の韓国人監督作品に続いて
今年度は是非、日本人監督に作品賞を取って欲しい。
#ドライブマイカー
#西島秀俊
#濱口竜介監督
#三浦透子
#岡田将生
三浦透子さんに尽きる。
好みが分かれる
村上春樹さんの作品がもともとあまり得意ではなかったのですが、村上春樹のファンの人に誘われて一緒に見に行きました。
最初の導入のシーン?がどうしても受け入れられず、その後も登場人物の独特な言葉遣いやキャラクター、ベットシーンが……。加えて、映画自体も難解で途中から眠くなってしまいました。途中の夜景のシーンが綺麗で良かったです。
一緒に行った村上春樹ファンは「とても面白かった」と言っていたので、好みが分かれる作品だと思います。村上春樹感が満載なのでファンの方やあの世界観が好きな方にとっては、とても面白いと思います。
一番恐ろしいのは、それを知らないでいること
映画「ドライブ・マイ・カー」(濱口竜介監督)から。
約3時間(179分)が、あっという間に過ぎた作品だった。
今回は、台詞を聴き漏らしたくなくて、邦画なのに、
珍しく(字幕)バリアフリー日本語を設定した。
村上春樹さんの作品は、登場人物の名前が読みにくい。
主人公は「家福」(カフク)さん、妻の名は「音」(オト)さん、
さらに「山賀」(ヤマガ)さん「渡利」(ワタリ)さんなど、
文字で確認しないと、漢字が浮かばない苗字や名前が多かった。
私の場合、苗字が頭にパッと浮かばないと、どうしても、
それが気になって入り込めなくなるから、字幕は正解だった。
さて、前置きはさておき、気になる一言は、
「真実というのは、それがどんなものでも、
それほど恐ろしくはないの。
一番恐ろしいのは、それを知らないでいること」を選んだ。
作品の中、あちこちに散りばめられている「一番恐ろしいこと」
何気ない生活から、世界を揺るがすような事件も、
本当は何も知らないのに、知った気になっていたり、
もっと深い何かを見過ごしていたりする恐ろしさかもしれない。
世界で注目されているこの作品、世界の人々に伝えたいことは?
そんな視点で見ると、唸ってしまうよなぁ。
ワーニャ伯父とソーニャ
原作の小説に丁寧に肉付けされたもうひとつの「ドライブ・マイ・カー」
家福とみさきのカタルシスが劇中劇ワーニャ伯父のラストに繋がる。
「どんなにつらい人生でも仕方がないわ、歩いていかなくちゃ…。あちらの世界でやっと一息ついて美しい人生を始めることができる…。」
異国の地で二人はワーニャとソーニャのように寄り添って暮らしていくのかな…そんなことを考えたラストシーンでした。
うーむ。
村上春樹の世界のセリフの難しさを感じたなあ。
もちろん映画用に直してると思うけど、冒頭のシーンをクリア出来る人と、拒絶する人がいると思う。私は村上ファンで、原作を読んでいるのであの世界観に慣れている。
村上作品はアンチも多い、その人達が最も嫌うであろう世界観が冒頭に凝縮されており、
私的には冒頭からタイトルまでの導入部をカットすればもっと締まった良い映画になったと
悔やまれる、妻が亡くなった後からスタートし、あくまでフラッシュバックで妻を登場させる。演劇のシーンも長過ぎると思ったが、監督が原作に足した部分を表現するのに必要だったのは理解できる。原作にはない部分の方が面白かった、村上春樹作品の映像化の難しさを
またも痛感することになった。
日本アカデミー賞
能動的な鑑賞が必要な映画
まぎれもない名作。
また、映画館で観るべき映画。
邦画だからテレビでいいかなー、とちょっと思ったが、映画館で観て良かった。
ただ、ある意味で難解で、観る人が映画に何を求めているかで全く評価が違ってしまう映画とも思った。観る人を選ぶ。
村上春樹はほとんど読んだことが無いが、この映画はすごく文学的であり、原作もこんな感じなのだろうな、と思った。
それにしても長い! 序章にあたるところが終わるところでオープニング・クレジットが表示されて、軽く混乱した。あまりに序章が長くて、「もしかしてこれエンディング・クレジット?」と思ってしまったからだ。
この映画は「演劇」をテーマにしているが、この映画そのものが演劇的なところが面白い。謎めいたストーリー、謎めいたセリフや行動、それらの意図は映画の中ではほとんど示されない。意図は鑑賞者が考えながら、感じながら、感覚をとぎすませながら観るしかない。そして一瞬でも気を抜いてしまうと、映画への関心を維持し続けることができなくなってしまう。映画鑑賞に対してきわめて能動的な態度が求められる。
音(おと)が夢うつつに語る物語、チェーホフの脚本が奇妙に現実のできごとや主人公の内面にリンクしている。まるでフロイトの夢診断のようだ。
演劇、文学というものの本質は、その物語の中に自己を投影し、何らかの答えを得ようとすることなのかもしれないな、と思った。
僕は昔から「聖書」という存在がどんな風に信仰者の支えになっているのかピンとこなかったのだが、この映画を観てそれが分かったような気がする。聖書の中で偶然目にとまった一句が、まるで神からの啓示のように感じることがあるはずだ。そういう形で信仰者は自己の内面を見つめることで神と対話するのだろう。
演劇者にとってたぶんチェーホフの戯曲は、まるで聖書のように、豊かな奥深い示唆を含む、特別なものなんだろう。
ただ、ぼくは残念ながらチェーホフの戯曲を読んだことがないので、この映画の登場人物たちにいまいち共感できなかった。主人公のやっている「多言語演劇」の何がすごいのかまったく分からないし、彼らの演じる「ワーニャ叔父さん」も面白いと思えなかった(少なくともお金だしてこの演劇を観たいとは思わない)。なんか徹底的に芸術を追及しててすごいな、って思うくらい。
この映画は「こだわり」を手放していく過程、傷ついた主人公の再生の物語とも読める。「車」は妻への思いそのものの象徴であり、主人公は車を他人に運転されること、車を粗雑に扱われることを異常に嫌がる。
しかし、避けていた妻への自分の本当の思いに向き合うことで、徐々に自分の気持ちを解きほぐしていく。ラストシーンでは、ついに主人公は車への執着から解放されたことが示唆される。
個人的に不満だったのは、高槻が車の中で長語りをするところあたりから、この映画のリアリティ・ポイントが変わってしまったように感じたところ。ここまでは映画の世界観はぎりぎりのリアリティを保っていたと思うのだが、このへんから妙に演劇的になってしまって、「こんなん現実でありえんやろ…」と思ってしまうシーンが多くなってしまった。一人の人物が会話もせずに演劇の脚本を読むように語るってのは現実にはそうそうない。
====================
追記
主人公の演劇論について、謎が多いので自分なりに自由に想像して考察してみた。もしかしたら全く的外れかもしれないが…。
まず、「感情をこめずに台本を読む練習」が出てきたが、これはいったい何なのか?
おそらく、役者が演じようとして演じることを矯正するためなのではないか?
映画に「うまく演じようとしなくていい」というセリフがあった気がしたが、まさにこれは演劇に限らず、あらゆる表現に共通する普遍的なアドバイスだと思う。僕自身、スピーチにしろ、プレゼンにしろ、文章にしろ、何らかの作品にしろ、「うまく〇〇しようとしなくていい」というアドバイスを何度諭されたか分からないほど批判されたし、僕自身も他人にこの言葉を何度も繰り返し言っている。
「『うまくやろうとする』ということが意識されている」、ということは、そこには演じようとする役者と演じられるキャラが分離しているということだ。観客はそこに、「うまく演じようとしている役者」をみるのであって、「キャラ」そのものをみているわけではない。
「演ずる意図をせずに演じること」の重要性はとてもよく分かる。僕は映画を観るとき、できるだけ役者の存在を意識したくない。無名の役者しか出てこない映画が理想だ。もし有名な役者が出ていると、どうしても「演じている」ということを意識してしまい、映画の世界に没入しにくいからだ。
役者が脚本を完璧に記憶し、自分自身を完全に捨て去って(忘我の境地となり)、脚本に対して何の意図ももたず、まさに操り人形のように演じたとき、そこにキャラそのものが立ち現れる…、これが主人公の演劇論なのではないか?
別の見方をすれば、これは役者が自分自身を空っぽにして、そこにキャラを「憑依」させているのだといえる。演劇の起源の1つとして、シャーマンが神や精霊を自身に憑依させる神楽のようなものがあると思うが、そういった考え方に近い。
主人公は妻の死後、「ワーニャ叔父さん」の役ができなくなったというが、これは、数々の悲劇にさいなまれ続けるキャラに主人公自身が過剰にシンクロし、演劇と現実の切り替えができなくなってしまうせいだと思う。
では、主人公のやっている「多言語演劇」というのは何なのか? 多言語演劇の面白いところは、役者どうしは相手の言っていることを理解していない、ということだ。少なくとも、理解する必要はない、と主人公は考えている。
それでも演劇が成立しているのは、脚本が完全に決まっているからだ。役者たちは決まったセリフを言うだけなので、相手の言葉を理解している必要はない。
ここからはほぼ完全に僕の妄想だが、多言語演劇というのは、現実世界の暗喩なのではないか。我々は他人とコミュニケーションしているつもりでいるが、実は全くコミュニケーションなどしていない。していると思い込んでいるだけ、相手の言葉を理解しているつもりになっているだけだ。
多言語演劇のある種のいびつさ、というか、不完全さ…、それを観客が観たときのいらだちや不便さの感情というのは、他人とは実は永久にコミュニケーションがとれないものなのだ、という絶望的な孤独感や、それでも不完全なまま世界が動いて進み続けているという、不安定感と同義のものなのではないか。
さて、最後の謎、主人公の多言語演劇と、音(おと)の夢うつつにおりてきた物語は、どういった意味で「同じ」だと言えるのか? それは、物語に「意図」が存在しない、ということなのではないかと思う。少なくとも「意図」を求めない、ということではないか。
音の物語はもちろん、音が考え出したものではない(おりてきたものだ)から、意図などは存在しない。しかし意味がない、ということではない。いや、意図がないからこそ、そこに無限の意味を見出せる、ともいえる。物語は観客に意図を押し付けない。しかし観客は自然にそこに自分の内面を見てしまう。音の物語の魅力はそこにあるのではないか。
そして主人公の多言語演劇もまた、注意深く意図を排除しているように思える。そこには頭から終わりまで一字一句チェーホフの戯曲が再現されるだけであり、いかなるアドリブもなく、ある意味で全く機械的な複製の作業をしているにすぎない。しかし意図が無いからこそ、やはり観客はそこに無限の意味を見出しうる、といえる。そしてその無限の意味を見出しうるほど豊かな内容をチェーホフの戯曲は内包しているのだ、と主人公は考えている。
ちょっと飛躍しすぎかもしれないが、考察終わり。
脚本が凄いと思いました
2014年の単行本の時に買って
原作は読んでいたはずだけれど、
(家のどこかにあるはず)
今回、映画を観て、
その後、文庫本を買い直して
もう一度原作を読んだ。
映画には原作の要素が全てあり、
かつ、それを見事なまでに広げて、
印象深い作品になっていた。
車の中で聞く
セリフを覚え確認するための
カセットテープがあるのだが、
それが登場人物の心情や、シーンと
有機的に絡み合って、
クライマックスに向かっていく。
劇中劇の完成する過程と、
主人公の家福の心の葛藤が解消する様が
見事なまでにシンクロして、
唸ってしまった。
この原作をあの映画に仕上げた
関わった人たちの凄さに、
改めて驚いた。
見終わった後で、
時計を見て、
3時間経っていたことに驚くほどに、
時間を感じさせない映画でした。
ちゃんと村上春樹だったと思います。
脚本が素晴らしかった
原作の小説、ワーニャおじさんは読んだことがないが、現世ではなく天で救われるのよという下りはグッときた。しかも手話。抱きついて。
地理オタクでフォッサマグナの通る糸魚川(親不知)や、車が好きで飛びついた口ですが、意外にも劇中劇とリアルをうまくリンクさせた3時間の尺になるのも納得いく仕上がりだと思いますし、劇場を出る時の満足感が凄かった。
私事ですが、この映画が公開されたころ、親不知のGoogle mapのクチコミ閲覧数がめっちゃ伸びましたのでそれも嬉しかったです笑
三浦さんの声、西島さんの眼差し、全てが自然。
日本アカデミー賞8冠おめでとうございます。
海外の映画賞を獲得しだしてから
ずっと気になっていて、やっと観れました。
とにかく、ドライバー役の三浦さんの声のトーンに
引き込まれました。女性でも男性でもない、
まるで動物が人に化けたかのような、
ピュアで澄んだ声色。
西島さんの眼差しは、賢い良馬のように優しい。。
動物にたとえ過ぎてしまいましたが、
常に、ざわざわ、モヤモヤはするのに、
緑燃ゆる風景を眺めているような、
リラックスした気分で、、
気づいたら終わってました。。
最後の最後は、監督の言いたい事を西島さんが
絞りだしていて、泣いてしまいました。。
なんか軽く高原を散歩したような、
不思議な読後感、、、
あー、もう一度、館で観ようかな、
そんなふうに思ってしまう
不思議な風みたいな映画でした。
芸術作品として。
タイトル通り
難解で退屈な展開ながら、最後にはしっくりきてもう一度見てみたくなる不思議な作品
ちょっと冗長で難解な作品ですが、最後まで見るとじわじわ面白さを感じる不思議な作品です。中盤までずっと腑に落ちなかった難解なストーリーが最後の最後で急にストンと自分のなかに落ちてきます。
序盤は文学的で難解な台詞が無機質に淡々と読み上げられる退屈な展開が続きます。また、舞台稽古のシーンもやたら冗長でその退屈さに拍車をかけます。
中盤以降は主人公が奥さんの自宅不倫の現場を目撃したり、その奥さんの突然死に遭遇したり、舞台の主演俳優が殺人事件を起こしたりといった様々な出来事が起きるのですが、事態の大きさとは裏腹に、不自然なほど淡々と粛々と静かに物語が進んでいきます。
その不自然さをもたらしているのは一切の感情を押し殺したような主人公の無機質さで、奥さんの不倫現場や死を目撃した時ですら、表情も変えず淡々と対処しているのですが、その無機質さの正体が最後のほうでようやく解けます。すると、それまでの不自然さやモヤモヤ感が一気に晴れ、それまでの物語が一気に線で繋がります。
まあ、なんというかとても不思議な作品で、賛否がはっきり分かれる作品だと思います。気の短い人や難解な台詞回しに耐えられない人は間違いなく無理でしょうね。
全797件中、301~320件目を表示