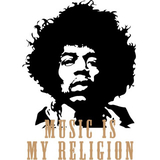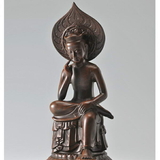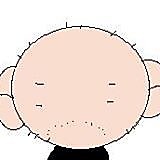ノマドランドのレビュー・感想・評価
全505件中、101~120件目を表示
マクドーマンドは、渋柿女優(褒め言葉)
一言「劇場で観ればよかった!」
その理由は、全体的に暗い夜の場面・遮るもののない荒野の場面が多く。
家だと外の光(朝に観た)や、TVの大きさがねえ・・・。
本題。
採掘場の閉鎖で、「郵便番号すら消えた」町・エンパイヤ。
そこから仕事を求めて、キャンピングカーで移動する主人公・ファーンが。
「ホームレスじゃないの、ハウスレスなのよ」と。
放浪の民=ノマド、として暮らす話です。
淡々とした話ではあるのだけど。
行く先々で出会う、同じノマド仲間や職場の人。
ハウスレスでも、お互い助け合う社会が描かれているのが、好感度大。
印象的なシーンを一つ。
ファーンは、親(か祖父母)にもらった皿を大切にしてたけど。
途中で他人の不注意で、割れてしまう所。
短いシーンだったけど、「形あるもの、いつかなくなる」って感じで。
個人的には、ノマド生活を続ける腹を括った気がしました。
主演のフランシス・マクドーマンド。相変わらず渋柿テイスト満載(褒めてる)。
この役は、彼女だったからこそ成り立ったでしょう。
エンドロールで初めて、出演者たちがノマドの人だったことを知り。
でもでもしっかり演じていたのにも拍手です。
ドライブ旅行が好きでカナダやアメリカを旅するとなんとキャンピングカ...
ドライブ旅行が好きでカナダやアメリカを旅するとなんとキャンピングカーと出会うことが多いか。
夏のバカンスを楽しむ当たり前のアメリカ流のレジャーとばかり思っていた。
いつかはキャンピングカーでアメリカ、カナダの自然の中を旅したいなあと思っていた。
がこの作品を見てハウスレスという存在を知った。
そこには一人一人が違う事情を抱え渡り鳥のような生活をしていて寄り添っては離れていく。
映画は自然の中のアメリカらしい綺麗な風景の連続でまた旅したくなる。
初めて聞いたノマドという存在。根無し草なのだろうか?
「一緒に住もうと」と云われて安住の地を得れたのに、その夜はベッドで眠れずに車に戻って夜明けを待つ主人公。夜明けとともに出て行く。
その先の不安はなかったのだろうか?
収入源となるアマゾンの配送物の梱包や公園のスタッフなど結構バイト口はあるんやなあと思ったけれどお金に困るシーンもあり現実を突きつけられる。
人生について色々考えさせられる映画だった。
ところで「プリウスに乗ってる」っていってたノマドさんがいたが自分もあのプリウスに乗ってたけれどキッチンはついていないし狭いのでは?
まあ、燃費が良いので移動には最適かも・・・
自由ゆえに責任が伴うノマドという生き方
各国の映画祭で数々の賞を受賞しているノマドランドを鑑賞させて頂きました。
とても素晴らしい映像美で、主人公が長年住んでたエンパイアから必要最低限の荷物を車に積んでノマドとなるところから始まるのですが、平原の道をただ車が進んでいるシーンを後ろから撮影しているのが、本来ならば無機質な車が進んでいるだけのはずなのに、映像美も音楽でなんだか切なさや、儚さや強さを感じます。
物語の後半にも同じようなシーンがあるのですが、不思議なものでそこにはまた違う感情も感じます。
それはきっと登場された方々の暮らしぶりや言葉に重みがフランシスマクドーマンドさんの演技がプラスされてるからなんだろうなぁ。
エンターテイメントな作品ではないですが、
現代のノマドの方々の話しや暮らしぶりを観ていると胸に迫るものがありオススメです。
人間も自然の一部
自然が呼んでいる
のっぴきならない事情でノマド生活を余儀なくされているのかと思ったら、必ずしもそうではない。スマホも持っているし、タバコも吸う。ぎりぎりまで切り詰めているわけではなさそうだ。
実は身寄りもいて、定住生活ができないわけではないということがわかってくる。帰るべきところがないホームレスなのではなく、家を持たないという選択をしたハウスレスなのだ。実の姉からと、ファーンのことを憎からず思っているデイブから、二度の定住生活の誘いを断って旅を続ける。
彼女をノマドであることの誇りなのか、意地なのか。
ただ心奪われる絶景の大自然の中で生きていたいだけなのかもしれない。
自分の中のB面
様々な要素が詰まっている映画
終活…旦那に先立たれ、父から貰ったお皿を大切にしていたり、彼女の人柄を感じます。
物にも魂って宿るなぁと感じました。
歳を取るということ…体の自由がきくうちは、自分がどんなふうに生きていたいかを実現できるけれど、元気なうちしか出来ない。
ジェンダーの壁も感じだけど、これはどんな環境でも同じなので省きますね。
一人の気楽さと寂しさを受け止めて生きるということは年齢や環境に関わらず皆、同じなのかもしれない。
季節労働の虚しさも感じました。Amazonは賢いなぁ。上手に人を巻き込むビジネスを今後は考えるべきなのだと思いました。
家族を持つこと、人と助け合うこと、自分の信念、お金
このバランスがうまくいく人って本当に数限られてるだろうなぁと思いました。
そしてフランシスのオスカー女優賞は当然だとも思いました。
トイレのシーン、川でのシーン。表情と心情が伝わってきたし、隣人に優しくする姿は彼女の日常がわかるなぁと思いました。
隣人に親切であることは忘れてはいけないと感じました。
自分の居場所、生き方…
に尽きる映画。画面も曇り空が多く、寒く、笑うシーンはない。当初、夫に先立たれ、車上生活を余儀なくされた孤独な高齢女性の貧困問題を扱う映画だと思っていた。確かにノマド生活を送っている人々の多くはそうなのかも知れない。いや、確かなことは言えないし、そもそもノマドという言葉も、そういう人々がいることも知らなかった。しかし、フランシス・マクドーマンド演じるファーンは自らの意思で、流浪の旅をし続ける。働き先を変えながら、そこで出会った仲間とずっと一緒にいるわけではなく、互いに別れ、またどこかで出会いを繰り返す。姉に一緒に暮らすよう言われても、旅先で出会った男性から共に住むよう誘われても、自分の居場所は違うと断ってしまう。普通なら将来の不安から、定住、温かいベッド、食事、風呂、何より落ち着く家、家族がほしいのだが。。彼女にとっては亡くなった夫と、共に暮らした家のみが暮らせる場所だったのか。出演者の中には実際にノマドをしている人もいると言う。映画としてはこういう人々もいるんだなぁと思ったくらいであまり共感はできなかった。
眠くなってしまった
現代の社会問題の先にある普遍的な思想。
Nomad. Workamperの実態をノンフィクション作品を元に映画化されている。監督はクロエ・ジャオこの作品でアジア人初のゴールデングローブ賞監督賞を受賞、アカデミー賞で作品賞、また、非白人として初めて監督賞を受賞。原作はジェシカ・ブルーダー著 ノマド: 漂流する高齢労働者たち
この映画を知るまでこのようなアメリカの現状を知る事が無かった。現代のnomadと言われる人達の中心は1950年台〜70年代にかけてのビート族、ヒッピーと同じような生活を送っている高齢者達。ある人はウーバーによってタクシー運転手の仕事がなくなり、映画の主人公はリーマンショックによる工場の閉鎖に伴いネバダ州のエンパイアがゴーストタウン化して職を失ったのをきっかけにバンに住みながら生活するハウスレス生活を送る事になり、荒野に作られたアマゾンの巨大工場で働いたり季節によって複数の日雇い労働で日銭を稼ぎがら車上生活を送ることになる。
仕事がなくなるきっかけも職に着く先も誰もが知っているグローバル企業の名前が出てくる。アメリカではウォルマートの巨大な資本力によって次々と街から商店街などの個人店がなくなり、結局、個人店で働いていた人は生活がままならない程の安い賃金でウォルマートに雇われるというのも事実として聞いた事がある。日本にはまだこのような高齢者は居ないにせよ資本主義社会の行く末として、この事実だけ切り取っても考えさせられるものがあるが、映画の魅力としてはここからで主人公のフランシス・マクドーマンド演じるファーンはただ孤独なだけではなく、人間力もあり人にも好かれるので、自分の姉やキャンプで出会った同世代のイケメンオヤジから一緒にすまないかと誘われる機会があるものの、それを拒み自ら何度も荒野に出ていく。in to the wildという映画があったが、ビート族やヒッピーから始まり20代男子なら一度は憧れる、社会の飼い犬になんてならずに快楽を求めて動物のように自然の中で生きていくという思想に60代の未亡人のおばちゃんや高齢者達が目覚めているという衝撃がまずある。もちろん実際にその生活を送ることは人を選ぶと思うがそれはおそらく年齢や性別に関係なくやってみたらもう家と限られたエリアだけで終える人生なんてつまらな過ぎるという目覚めがあるのだと思う。ただその一方で映画の画面は恐ろしいほどに美しい引き絵の広大な自然の中に小さく強く一人生きているおばちゃんを描いていて、その心情を写すBGMも切なく悲しみに満ちている。こんな孤独は耐えられないと感じざるを得ない撮り方をしているのだが、その生活を選択している本人達だけが、安心安全な生活を送っている人よりも、生きている事のダイナミズムを感じながら腹をくくって強く生きていて、どこかでそんな生き方に憧れてしまう感覚もある。正直なところ、少し間延び感を感じて少し集中が切れて時間を気にした時があったのだが、この映画に関しては必要な演出でありすぐに自己反省につながった。つまり、最近テレビを見ていても間延び感や展開が遅いと感じることがあるのだが、それはYOUTUBEやSNSがこれだけ発展する以前は無かった事だと思う。インスタントに展開や結論を求めてしまっていて、ゆったり感がなくなってしまっている事に改めて気付かされた。本来の人間らしい心地のよいリズムで生きているのか、巨大企業の産物であるインターネットやスマホによって便利になったがそれが幸せにつながっているか、という事にいみじくも気付かされた。俺も家族がいなくなり一人になった時に荒野に出ていけるのだろうか。翌日、家に帰ってしまいそうな気がする。
こういう生き方
現代の西部劇であり「イージーライダー」の続編でもあり
今年の冬に公開予定のマーベル映画「エターナルズ」の監督作品ということ、またアカデミー監督賞作品でもあるということで興味を持ちAmazonレンタルで視聴。「ザ・ライダー」は未見。
今年3月公開ということで、ある程度の内容や事情は把握して見たんだけど、最初に思ったのは「映画館で観るべきだった」という後悔。
物語というよりはセミドキュメント的。
登場人物も主人公のファーンを演じるフランシス・マクドーマンドとファーンに、思いを寄せるデイブを演じるデヴィッド・ストラザーン以外は本当のノマドの人たちが登場する本作は、言葉や物語よりも映像で語るタイプの作品であり、彼ら、彼女らの後ろに映る雄大な自然もまた重要なファクターで、ぶっちゃけ36インチテレビの画面では本作の魅力がかなり目減りするのは間違いない。
本作に登場するノマドの人たちは総じて高齢者であり、日本で言えば団塊の世代。
つまり、美しい理想の世界と自由を求めたヒッピー(フラワーチルドレン)世代なんじゃないかと思う。
しかしながら、夢破れて社会の一部に収まった彼ら彼女らが、老年を迎えた今、再び社会から放り出され幌馬車のようなRV車で仕事をしながら国中を放浪するとは、何とも皮肉な話だと思わずにいられないし、僕くらいの年齢になるとそれは近い未来の自分の姿かもしれないと思ってしまう。他人事だとは割り切れない。
なので劇中、自由を謳歌するノマドたちの裏に横たわる「自己責任」という名の不安に、どうしても目が行ってしまうんだよね。
原作は未読だけど、内容的にはこうしたノマドを安く使って搾取するアメリカの大企業に対して問題提起をしているノンフィクションだと聞いているけど、本作はそんな原作とは趣が違って、ファーンの目を通して見たノマドの人たちの誇り高き暮らしぶりを、壮大な自然と共に(その厳しさも含め)抒情的に描いているように見えた。
美しい景色と複雑な感情の重なりあい
エンドロールまで観ると
共感するのは難しい
全505件中、101~120件目を表示