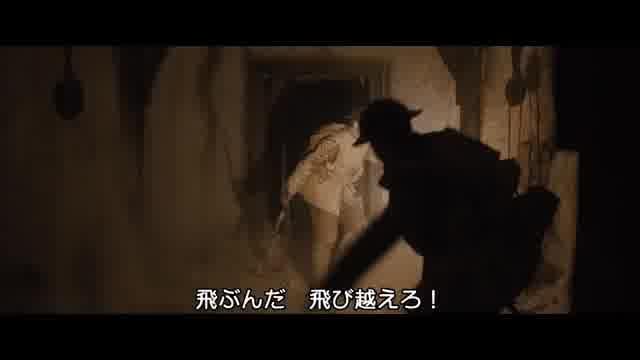1917 命をかけた伝令のレビュー・感想・評価
全650件中、181~200件目を表示
塹壕の長さを感じられる
新体験!
第二次世界大戦。戦況を左右する重大な伝令を託された兵士が、伝令を伝えるために戦場をただただ目的地へと進む。
カメラは彼をワンカットで追いかける。
観客は何の説明もなしで戦場に放り込まれるんだけど、映像から伝わってくる情報量がもの凄い。
緊迫感、戦場の広大さ、突如始まる戦闘、ぬかるみの不快さ、死体のおぞましさ、恐怖感も安心感も。主人公のスコットフィールドと時間も空間もともにすることでこんなにも身に迫るものがあるんだなと。
普通の作品だと一部で取り入れられたりする手法なんだけど、全編でやってのけるのはホントに凄い。
惣田監督の観察映画とも似てるなと思ったけど、こちらの方はぐっと主人公の目線に引き込んでくる。
あと、アンチャーテッドとかプレステのアクションゲームやってる感覚にも近い。
臨場感だけじゃなくて、映像美も素晴らしかった。
きっと実際の戦争もこうだったんだと思わせるような、長閑な時間と、緊迫の時間の緩急。死体がそこら中にゴロゴロ転がる戦場の風景。広大な野原。夜が明けて行く青の美しさ。空深い森からかすかに聴こえる歌声。戦闘シーンは多くはないものの、風景や死傷者からもまじまじとわかる戦争の残酷さ。はっとする瞬間が何度もあって、脚本も素晴らしかったなと。
スコットフィールド上等兵の、おそらく彼の人生でもっとも長くドラマチックな1日をこんなにも鮮やかに表現していることにただただ感服。
もう一度映画館で観たくなる作品。
「必ず戻って来て」泥沼の塹壕から走り出した二人の伝令
カテゴリーは戦争映画だが、一秒後に生きている保証のない切羽詰まった戦場の恐怖と、束の間の深い友情に胸を打たれる。
第一次世界大戦は汚泥と悪臭に満ちた塹壕戦だと言われ、毒ガス戦ともいわれる凄惨なものだったらしく、運良く帰還出来ても大半は精神を病んだと聞いている。
そんな大雑把な知識しかなくても、映像の緊迫感はリアルで、選ばれた2人の伝令が、味方塹壕の先端から荒れ果てた前線に這い上がるショットでは、狙撃兵の銃弾が今にも飛んできそうなサスペンスの描写が素晴らしい。
ドイツ軍の罠にまんまとはまった1600人の部隊の中に彼らの兄が居るという、上層部のずるい人選が尻を叩き、適中突破のスリルの中に男の絆を織り込む泣かせどころが上手い。
胸ポケットのハードカバーに入れられた家族の写真に「必ず戻って来て」とあるのが救いで、日本の様に「天皇の為に死んでこい」とは大違いの反戦映画だ。
人生はカットも編集もないドラマ
『24』のようにリアムタイム編集をしても十分緊迫感はあっただろうが、戦場のリアルを描くためにワンカットにこだわったのは圧巻。そこには編集のきかない希望も残虐も同居するのだ。
ストーリー自体はまさにタイトルの通り「命をかけて危険な前線まで伝令を届けに行く」だけなんだけれども、まさに今そこに生きているかのように駆け抜ける俳優たちの度胸と演技力はさることながら、どうやってその映像を可能にしたかと思わされるカメラマンたちの覚悟と実現力が素晴らしすぎる。
あんな泥だらけで凸凹の道や川のなか爆撃のなか、塵や泥や水しぶきをレンズに浴びずどうやって撮り続けたのか、否応なしに考えながら観入ってしまう。
どこまでがシナリオで、どこまでが現場のハプニングなのか。(「カメラを止めるな!」の返り血を浴びた画を敢えて使ったこととの差を思い起こさせる)
映画を観た後にメイキングを見たが、本当にカメラのパスや、クレーンや車に飛び乗らせていたとは脱帽。
ただ実際に長回しだけで撮ったのではなく、限りなくワンカットに見えるような映像に仕上げたそうだ。だとしてもその緻密に計算し尽くされた躍動感にただただ呆然とせざるを得ない。
斬新な異端作
1カット影像が売りだけど、大事なのはそこじゃない!
アカデミー賞受賞作で1カット影像が売りの大作。ということで、戦争映画好きとしては期待半分心配半分で観に行きました。
第一次世界大戦の戦場で、敵の罠を知った司令部が、最前線の部隊に攻撃中止を命令するため、2人の兵士に伝令を命じてその二人が悪戦苦闘して命令を遂行するというストーリーです。
映画の売りは、前編1カット影像と言う事。最初から最後まで1台のカメラがずっと主人公達を追い続けるという、とても難しい撮影方法を取っています。(もちろん上手く編集してつないでいるだけなのですが)しかし、その凄さよりも、それによって得られる副次的な効果の方が僕は素晴らしいと感じました。
それはまず第一に、1カットで撮るために練りに練られた脚本です。無駄を省いてテンポ良く作られた話の進み方が非常に良く出来ています。本来映画はいくつものカットを別々に撮って、後で編集でつなぎ合わせるわけですが、編集の仕方によっては冗長になったりあるいはせせこましくなったりと、本来の脚本で描きたかった事とは別の印象になってしまう事もままあります。しかし、1カットで撮るために、最初に脚本を何度も推敲しているため、シーンの構成に無駄が全くないのです。
第二は、1カット撮影という緊張感です。NGの許されない撮影のためか、非情に緊迫した影像が見ている方にも感じられるのです。これが戦争映画としてピッタリで、キリキリと胃が痛くなるような緊迫感が映像から伝わってきます。
そんな副次的な効果によって伝わってくる映画のテーマ、それは戦争の無残さです。主人公のスコフィールドは元々相棒のブレイクに誘われて命令を受けたため、最初この命令に乗り気ではありませんでした。しかしブレイクの兄が最前線にいて、命令を伝えないと戦死するかも知れないと知り、徐々に使命感が高まっていきます。そしてそのブレイクの死によって、彼の遺言と最後の姿を伝える役も引き受け、命がけで戦場を駆け抜けるのです。
彼の走る姿を映すカメラは、同時に戦場の様々な影像を映していきます。あちこちに無残に散らばる戦死者の遺体。メチャメチャに壊された街や、人々の生活。そして塹壕にうずくまる疲れ切った兵士達。この無残さを伝えるための1カット映像なのだ、と観ている人間に訴えかけてくるのです。
ようやく最前線に到着するも、第一陣の突撃命令が下り、その中を横断しながら部隊指揮所にたどり着くスコフィールド。直ぐに攻撃中止の命令が下り、彼の使命はとりあえず成功に終わります。しかし、指揮官はこうつぶやきます。「来週はまた別の命令が下る」と。友の命さえ失う命がけの伝令も、結局は戦場のたった一つの駒に過ぎないという事実。なんという残酷、何という無残。ただ一つの救いは、司令部を出る際に、入り口に立っていた少佐がつぶやいた「ありがとう」の一言。彼の連絡は、とりあえず1600名の命を明日につないだのだから。そしてブレイクの兄に弟の死を伝えるシーンは、涙無しには観られませんでした。死ぬかも知れない兄が生き残り、助けに行った弟が死ぬなんて…。合掌。
見に行く人のために一言。この際1カット影像というのは忘れなさいと言う事。そこに拘っていると、肝心のストーリーを追うのがおろそかになりますので。大事なのはそこじゃない!戦争の無意味さ・無残さを是非感じ取って欲しい作品でした。
圧巻のVFXと撮影技術に感嘆❗️
ワンカットライクってどうなんだろうと思ってた。最近の映画はカット割りが多い。まあ、カット割りが多い方が強弱がつけられ引きつけやすしね。しかし、そんなのは杞憂だった。
IMAXレーザーで見たというのもあるが、圧倒的没入感、何が起こるか、まさに一寸先は闇‼️主人公と一緒に伝令を伝えるため戦地を駆け抜けたかのよう。
今作は反戦だとかメッセージ性がどうとかではなく、現代の映画の技術全てを見せつけることが目的な気がした。
戦闘機が墜落するシーン。普通主人公たちの顔ズームくるし、何回も数秒毎にカット挟んで、誤魔化すでしょ。それをワンカットで行うことでこんなにもリアルさが増すなんて。全く違和感なくしたVFX技術には改めて驚かされた(°_°)
他にも照明弾で照らさせる、夜の破壊された街並みと影、臨場感を引き立たせる音楽、どこからともなく聞こえてくる音楽などなど。全てがこの異次元の映画体験を引き立てていた。
今作を最大限に楽しむにはIMAXレーザーが良いです(^^)
あと、彼らは生きていたを見ると当時の生々しさがより伝わってくるので是非❗️
今作、何回取り直したんだろう🤔
カンバーバッチ6ヶ月待ってたらしい、あのわずかなシーンで2300万ドル💵払われたってライアンジョンソン監督が言ってたよ😲
年一でハードな戦争映画がみたい!
技術
バードマンの時よりも技術は向上されてるみたいだ。あんな事もこんな事も出来るようになってる。
ただ…映画としてはどおなんだ、と思う。
「全編1カット風」
この演出技法が作品に必要であったかと問われれば絶対ではなかったと思える。
意味付けは出来ると思う。
戦争映画である事から、過ぎていく時間とか戻らない命とか、そおいうものの印象は深く表現されてたように思うのだけど…作品としてはのっぺりした印象だった。
映像見本市を見てるようでもあった。
業界へのプレゼンならば満点の仕上がりだとは思う。
本作品を見て思うのは「よく出来てるなぁ」だ。この手法が緊張感を増してくれる風でもなく、感動をもたらしてくれる訳でもなかった。
1カット風に出来るのは凄い事なのだけど、1カットでやんなくてもいいじゃんと思えちゃった事が残念だった。
どおせなら「この作品は1カットじゃないとダメだったんだ」と思いたかった。
大変な撮影だったと思う。
撮影環境も従来とはガラッと変えたのではと思うし、カメラも違うんじゃないかと思ったり…この作品がもたらした技術革新は結構なモノじゃないのかとは思うけど…技を観たいわけじゃない。
ラストの平原を疾走するカットは凄い良かった。なんだろう…やっぱ何を撮るかによるんだろうな。演者の心情にリンクするというか…表現するというか。
そんな基本的な事を改めて考えた作品だった。
ぶっちゃけ途中から飽きる。
二番煎じ以上の技術革新はあったんだろうけど、コンセプトとしてはやはり、二番煎じであった…。
映画を観て「上手に撮ってんなぁ」は褒め言葉でもなんでもないと思う。
むしろそこを評価されたら失敗だと思う。
殆どワンショット!
実際は違うのだろうけれども、全編ワンショットで途切れなく続く。すごい技術だと思う。ただ、実際の戦場はもう少し汚かったろう。主人公の一人が救おうとした敵に呆気なくやられるのは、戦争の不条理感を出そうとしたのだろう。
凄いものを観てしまった
IMAX前列での鑑賞をお勧めしたい。
映画はこんなにも体感型になっていたのか。
軽く酔うくらいのめりこんだ。
緊張安堵恐怖、また緊張、と休む暇のない映画だった。
観終わったあと、本当に疲れていたし、しばらく現実が嘘のように思えてしまうほど、感覚が戦場に残っていた。
観客はみんな主人公になりきってこの180分を過ごす。
だからこそ、最後、どれだけ彼が必死で、ありったけの力を使い切ったかが分かる。そして、その瞬間に涙せずにはいられない。
そして劇場から出るとき、自分も必死で生きなければならない。何かに突き動かされるような使命感でいっぱいのわたしがいた。
"いつ何が起こるかわからない"という意味ではパニック映画のようでもあるし、ある種エンタメ映画と捉えられても仕方がないのかとも思うが、アカデミー賞は本作が撮るべきだったと個人的に思っている。
いやセットも凄いし、役者さんもめちゃくちゃ頑張ってるしね。
不謹慎だと思われるだろうが、やはり戦争映画の緊張感は他の映画では味わえない。あとスピルバーグの戦争映画がものすごく見たくなっている自分がいました
本当は「彼らは生きていた」も鑑賞したかった…
くそう…
一上等兵のある1日
第一次世界大戦の最前線が舞台。上等兵2人に託された、攻撃中止の伝令。敵が潜む中を潜り抜け、命がけで伝令を届ける、実話に基づいた物語。
戦争映画は、これまでにも多く観てきたし、ダンケルクも戦場の怖さがヒシヒシと伝わりました。しかし、本作のワンカット映像は、より戦場の臨場感が伝わり、伝令を届けるスコフィールドの必死さと同化でき鑑賞。
今ならあっと言う間に、伝えられる命令なのに、当時は、伝令を届けるだけでも命がけ。一上等兵の命も、軍の中では単に1駒に過ぎず、使い捨て。その中で、敵軍の飛行士を助けたばかりに、殺されたブレイクの死や敵地の女性と子どもに優しさを見せた場面、ブレイク中尉の対応は、命の大切さと共に、人としての生き方を訴えかけてきました。
ワンカット映像とはいうもの、当然、そこには上手な繋ぎ目があるのでしょうが、どこまでも続く塹壕は、実際に掘って撮影したそうで、川に落ちたシーンや穴埋めの場面も、どうやって撮ったのかと思うほどの緊迫感がありました。
最後に来て、マッケンジー大尉が、ベネディクト,カンバーバッチだたり、ブレイク中尉が、ゲームオブスローンのロブ役だった、リチャード・マッデンだったりして、登場人物のサプライズで、より楽しませてくれました。
2020-17
伝えたいこと。伝えたい人。
戦争映画は、その情報量の多さに整理ができず、苦手感はないのですが、毎回隣に林先生を置きたくなります。
本作は、その点、とってもシンプルでわかりやすい。しかも、ワンカット(風)で自ずと引き込まれる。
関係者の数も少ないから、それぞれのドラマや思惑といったものではなく、主人公とその友人のドラマ。
大切な人に会って伝えたいことと、大切な人の命を奪う戦争の悲惨さをダイレクトに伝えてくれました。これはワンカットの為す術かも。
主人公の友人役のディーン・チャールズ君、ほんとにリチャード・マッデンに似て、さらにタロン・エガちゃんにも似てますね。
個人的にこの兄弟の演技に心を揺さぶられました。
コリン・ファースや、ベネカン、マーク・ストロングといった大物俳優の出演シーンは、ほぼワンシーン(ワンカットなので語弊がありますけど)なのも、主役にスポットを置いたことで彼のドラマが際立ち、よかったです。
戦争映画では情報量を処理できず、脳内酸欠になるので必ず飲み物なり食べ物なり買っていくのですが、本日、上映時間を間違えて劇場入り→買ってる時間がねえ!
というわけで手ぶらでしたが、見入ってしまいおそらく瞬きすらしてなかったです🙊
ワンカット(風)だとわかっていたので、始まる前は物語的にはいくつのシーンなんだろうと数える気で満々でしたが、
見入ってしまい、エンドロールのときに手が✌️になっている自分がいました。
観ていて疲れた
終始緊迫した雰囲気の映画なので、観終わったらなんか疲れた感じがしました。二人で最後まで行くと思っていたので、あー。となりましたが、思い返してみるとたしかに予告でも途中一人しか出ていませんでした。
そこかしこに転がっていた死体も割とグロいのあったけど、ミッドサマーほどクロさ感じなかったのは、それを感じさせるためではないのかなとか本筋と関係ないこと考えていました。
ある一連のシーンに圧倒されて
見終わった瞬間に、映画館でもう一度見たいと思う作品は久しぶりだった。
2度目の鑑賞を終えたところでこのレビューを書いている。やはり、もう一度見たい。
カメラが1人の人物を追い続ける作品を見たのは初めてで、まずはその特殊さに興奮してしまった。
映画素人の感想なので恥ずかしい。(ワンカット風の作品は他にも作成されていることも後から知った)
とにかくこんなことは初めてだった。
記憶の断片を繋ぎ合わせた物語を見るのではなく、ある人物の「今、ここ」での経験をリアルタイムに共有すること。
言葉通り、映画を「体験」すること。
一方、エンドロールの直前に現れるのは、この話を語ってくれた監督の祖父への献辞である。
これまでの「体験」は、ある物語が変容した姿だったのかと気がついたとき、監督の思いを受け取った気がして、なんだか胸がじんわりした。
もうひとつ、興奮したことがある。
「ワンカット風」と言われるこの作品は、一度わかりやすく中断される。
この中断の後のシークエンスが、あまりに圧倒的だったのだ。
瓦礫ばかりの夜の街が目も眩むほどの強い光で照らされる。照明弾と言われるものと、炎の光。十字架の影。
大戦の経験がシュルレアリズムに繋がる要因のひとつだったといつか読んだことがあった。
死体ばかりの塹壕、荒れた戦地で強烈な光を目にした時(炎、爆撃、あるいは星の光)、その美しさに思わず現実を、自我を忘れるような経験をしたらしい。
それを、まさに追体験できたと思えた。
この世の終わりかと思えるほど恐ろしく、涙が出そうになるほど美しかった。
何度でもこの作品を映画館で観たいと思うのは、何よりこのシークエンスのためなんだろうと思う。
(そのしばらく後にも、また美しいシーンが続いてゆく)
ワンカットとも言えるし、ある意味シームレス?とも言える気がする。
生活と戦地と、生と死と、現実と夢、それらの境界が隠されているような感じ。だからこそ先に挙げたあの中断(暗転)は気になる。
こうして映画を見た後でいろいろ考えているのもまた初めてで、私にとって特別な1本になったみたい。
いろんな方のレビュー読むのも楽しい。
特別な映画体験をぜひ映画館で!と宣伝されているのをよく見るけれど、ここでの「映画体験」とは音響や映像を楽しむアトラクション的要素にとどまらないことを言ってみたくて、また戦争映画に対して「良かった」という言葉で評価すべきなのか不安だけれど素晴らしい作品だったことを伝えたくて、このレビューを書きました。
地方都市では公開が終わり始めていて、悲しいな〜
タイトルなし
まさに、be part of one
全650件中、181~200件目を表示