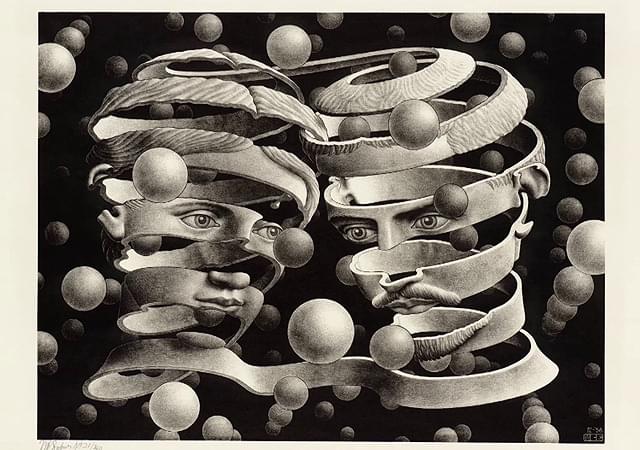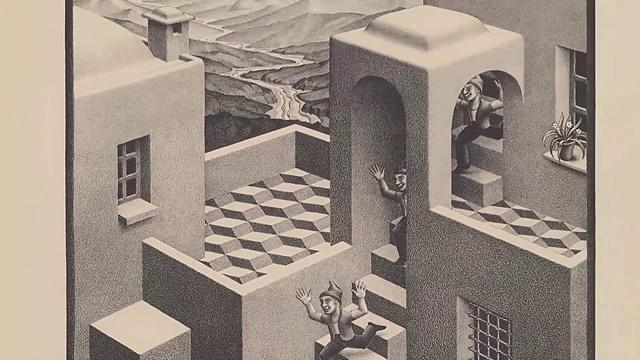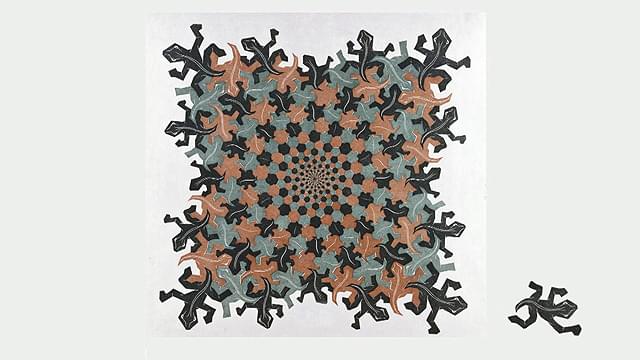ネタバレ! クリックして本文を読む
(1)まさかエッシャーにも・・・
エッシャーの作品は、“純粋なアート”とは言えないし、“数学者の玩弄物”の悪いイメージがあった。
エッシャー自身も、この映画の中で、自分は「アーティストではなく、数学者」であり、「他の芸術家は“美”を求めるが、自分は“驚異(ワンダー)”を求める」と語っている。
そのため自分は、これまで興味が持てず、その生涯については知らなかった。
しかし、本作品を見終わった後、軽い衝撃を受けて、帰宅後にエッシャーの画集に食い入るように見入ってしまった。
作品に独特の“人間性”が感じられるようになり、今まで“よそよそしく”感じられた「エッシャーの世界」が、眼前に一気に開けたのである。
他のモダン・アーティストの例に漏れず、人物を理解することによって、作品の理解が進むということが、まさかエッシャーにも当てはまるとは、この映画を観るまで考えもしなかった。
ただし、この映画が提供する情報は、質・量ともに、たいしたことはない。ネットで手に入るレベルのようだし、良く知る人には退屈な内容だろう。
エッシャーほど、「大器晩成」という言葉が似合うアーティストも珍しい。
世界を驚かす作品を生み出すのは、イタリアを去ってベルギーに移住した1937年(39歳)以降である。
この映画では、(a) 少年期からイタリア滞在期の無名時代はどうだったのか、そして、(b) なぜイタリアを去ったことが、のちの“驚異”的作品を生み出すことにつながったのかが、鮮やかに示される。
(2)前半 ~少年期からイタリア時代まで~
この前半部分は、普通はあまり語られないと思われ、この映画の一番の価値なのかもしれない。
病弱な少年時代。メスキータ先生との出会いと版画への転向。イタリアの風景との出会い。そして、結婚と家庭の話。
エッシャーも、南国の太陽のもとでワインをたしなむ旅人であり、恋人を想って夜の街を徘徊する傷心の青年だったのだ。(ただし、この時期のイタリア各地やスペイン旅行の詳細は、本作品では端折られている。)
時々、エッシャーが描いた風景画の後に、実際の風景写真が映し出されるが、比較すると、かなり写実的に描いていることが分かる。
また、自然の細部を正確に描写しようとしたが、「見れば見るほど、とらえどころがない」ことに気付いたというエピソードは興味深かった。
「ローマは夜の方が良い。バロックの過剰な装飾を闇が隠すからだ」と言う。そのため、毎晩、デッサンに出かけて、翌日に版画を制作するのだ。
この前半部を振り返れば、いかに数々の出来事や偶然が、エッシャーを導いたかに驚かされる。
もし、メスキータに出会っていなかったら・・・。
もし、病気療養のためにイタリアに行っていなかったら・・・。
もし、ファシズムが迫らずに、そのままイタリアにとどまっていたら・・・。
唯一無二と言えるエッシャーの絵は、この世に存在しなかった可能性が高い。
だからといって、ムッソリーニに感謝するわけではないが。
(3)後半 ~「エッシャー」の誕生~
後半は、イタリアを去った(1935)後の展開となる。雪が嫌いでスイスを離れ、ベルギー(1937)、そして故国のオランダに移住する(1941)。
伝記部分は、前半と変わらず充実している。
戦争中は、自分が自転車で買い出しに行かねばならず、創作が全くできなかったこと。
師のメスキータがナチスに拘禁された時(即座にアウシュヴィッツでガス死)、急いで200枚の作品を保護したこと。
ずっと肉親の財産が生活の頼りだったが、戦後(1951, 53歳!)に有名雑誌に載ったことで、急に知名度が上がって金が入るようになったこと。
精神を病んでいた妻のこと。
60歳を過ぎて、エッシャー自身に結腸ガンが見つかり、手術のたびに創作が中断されたこと・・・。
もちろん、エッシャーの作品世界についても、じっくりと紹介される。
スイスで快適でなかったエッシャーは、妻の髪を洗う音から“波の音”を連想し、「海へ行きたい」と願う。そして、版画作品の提供を条件に、地中海巡りの船に乗せてもらう。
この14年ぶりの、2度目のスペイン・アルハンブラ宮殿への訪問(1936)では、より深くタイル装飾パターンを学び、たくさんのデッサンを残す。と同時に、幾何学模様しか使えないイスラムの制約を残念に感じて、「自分には、“鳥”や“魚”は欠かせない」と思う。
この“欲求”あるいは“野望”こそ、まさに“エッシャーのエッシャーたる所以”だろう。
災いが転じて福となる。ちょうど期は熟し、“刈り入れ時”だ。
イタリアを去り、描くべき風景を喪失したエッシャーは、アトリエに籠もる。
そして、自己の内面に向かい、思考で生み出した「自分にしか表現できない」形を、画材で再現していく。
ここからが、我々がよく知る、思わず膝を打つような独特のアイデアの「エッシャー作品」の誕生なのだ。
(4)作品の制作および解説
エッシャーの造形には、色々なタイプがある。
(a) “正則平面分割”
(b) 螺旋(「終わりのないひも」)
(c) 反射(球・水たまり・「眼」)
(d) 相対性(“でんぐり虫”・「階段」)
(e) 平面と空間の拮抗(「版画の回廊」・「描く手」)
(f) 不可能な建物(「下ったり上ったり」)
いくつか作品が紹介されるが、中にはCGを使って、虫やハ虫類を動かしたり、絵をねじるようなプレゼンテーションで楽しませてくれる。
(a) “正則平面分割”というのはエッシャーの造語のようで、「テッセレーション」のことだ。
もともと、描画の対象と“背景”は「同じ意味をもつべき」とするアイデアは、すでにハーレムの学生時代からあった。
それが、アルハンブラ宮殿のタイルを見て“繰り返しの法則”を知り、一気に開花する。
“終わりのない数(円の極限)”の一群の絵では、最初に試した“外から内に”徐々にパターンを小さくする描き方に不満で、逆に“内から外に”パターンを小さくすることで満足な結果が得られたという。
“絵物語”(「サイクル」・「出会い」・「メタモルフォーゼ」)では、3次元の物体が2次元のパターンへ移行し、さらに2次元から再び3次元の立体性を獲得していく連続的な変化が描かれる。
科学者に大人気のエッシャーだが、エッシャー自身は、純粋な数学的手法では創作できないと言う。だから「自分なりに愚直に解決するしかない」。
エッシャー作品の素晴らしさは、数式からは自動生成できない「子供のような遊び心」と芸術的センスだ。
奇想の数学的空間に、“トッピング”されたように存在する、奇妙な人や虫の姿。
タイルのように敷き詰められるのは、アルハンブラ宮殿のような幾何学的形態ではなく、鳥や魚やハ虫類、そして異形の人間や天使や悪魔。
そうして、「科学者と芸術家の間を“ただよう”」のだ。
エッシャーは、色に頼った絵画制作はしない。
色を必要とするのは、形を塗り分けるためであり、他の画家にとっては当たり前の、“美”や表現としての色彩という発想はないように見える。
よって、「銅版画家」の感性と言って良いのだが、しかし面白いことに、エッシャーは「凹版」で制作することは、ほとんどないのだ。
版画の技法は、ほとんどが木版(板目、木口)とリトグラフである。(ただし、映画にも出てくる「眼」は、メゾチント(凹版)の作品である。)
エッシャー自身が、小型のプレス機で版画を刷っている姿が、映像に出てくる。
また、エッシャーは、自分の画力が高いとは考えておらず、重要なのは「自分に厳しく、どれだけ歯を食いしばって頑張れるか」であり、一方、「ほとんどの人は(エッシャーのような)情熱が欠けている」と言うのである。
(5)おまけの話
その他、作品とは、直接には関係のない話もある。
教会のパイプオルガンや「マタイ受難曲」を聴いた時に、「想像力が解き放たれて」見たシュールな“飛翔する幻覚”が語られる。
また、「バッハの音に打ちのめされる」とか、「バッハと私の作品はつながっている」と語り、バッハの音楽を好んだようだ。
“ヒッピー”やロック音楽のミュージシャンには、エッシャーは“サイケデリック”に見えたのか、人気が高かった。
エッシャーに無断で「蝶」や「椰子」の絵が、極彩色に色付けられて複製されたり、ミック・ジャガーから、レコードジャケットの依頼もあった。
彼らの鋭敏な感性は、エッシャーを単なる「だまし絵」の画家とも、数学的な絵とも見ていない。
エッシャーにとっては迷惑な話だとしても、作品の“芸術的側面”を物語るものとして面白いエピソードだ。
アニメーションに興味をもち、“メタモルフォーゼ”を題材とした芸術的な映画を夢見るが、「退屈だろう」とあきらめる。
なお、エッシャーを「マウリッツ」と呼ぶのは、失礼なのだそうだ。
(6)結局のところ・・・
ラストでは、「自分の作品だけで第二の人生を満たせる」というエッシャーの言葉が紹介されるが、どういう意味なのだろう。
もはや新しい発見は求めてはおらず、自分の作品の出来映えにまだまだ不満なので、第二の人生で、それらの完成度を高めていくという意味だろうか?
クラシックからロックまで、音楽が騒がしい映画である。(エンドロールでは、バッハがロック風にアレンジされる始末だ。)
80分とは到底思えないほど、盛りだくさんの内容で、自分は大満足だった。
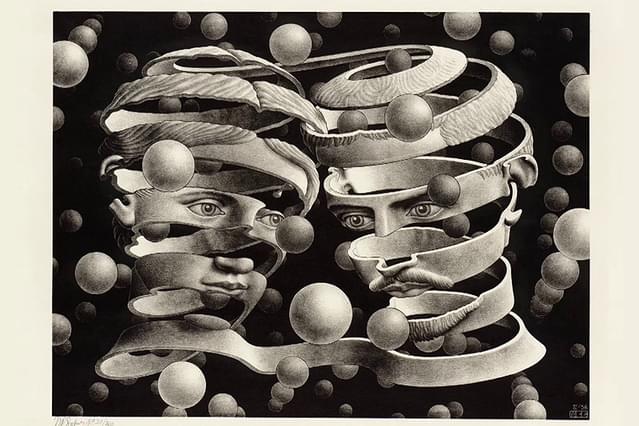


 行き止まりの世界に生まれて
行き止まりの世界に生まれて FLEE フリー
FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方
ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ
ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露
シチズンフォー スノーデンの暴露 わたしは金正男を殺してない
わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ
ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ 妖怪の孫
妖怪の孫 名付けようのない踊り
名付けようのない踊り