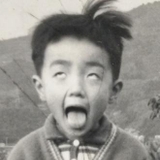おいしい家族のレビュー・感想・評価
全45件中、21~40件目を表示
LGBTと家族。エッチ、スケッチ、ワンタッキー
「エッチ、スケッチ」に続く言葉として、最も多い回答がワンタッチ、続いてマイペット、サンドイッチが来るらしい。地元ではマイペットばかりだった記憶があります。それをこの離島にすむ瀧がギャグとして使うとは!いやはや、20代の監督ふくだももこのなせるわざか・・・というか、今時の若者なら「エッチ」の意味さえ昔と違うだろうに。
現役の高校校長先生である父親・青治を演ずるのが板尾創路。お笑い出身で映画監督もこなすし、『私の奴隷になりなさい』や『ジムノペディに乱れて』では美味しい役もこなす。もうポスト北野武と言ってもいいくらいの存在だ。
お母さんになってしまい、子連れの男性・和生と結婚するというお父さんだが、弟はスリランカ女性と結婚するし、多様性豊かな家族となった。しかも、学校でも亡き妻のワンピースを着てることに生徒たちは何も言わない。最初は驚いてたであろうけど、違和感もなく寛容的なところが素敵でした。「魔法」という言葉も何度か使われてますが、まさに「愛の魔法」。とくにゲイであるわけでもなく、愛があれば男女問わないという孤独からの解放も亜熱帯気候のなせる気質なのだろうか。
とにかくLGBTに関してはノーヘイト。都会から帰ってきて困惑する燈花だけが浮いてしまった形だ。連れ子であるダリアもアイドルを目指したいとか言って、肌を焼かないように日傘をさしていた。瀧(三河悠冴)とも微妙な関係だが、彼らのぶっ飛んだコスプレも最高。女装することさえ正常な感覚に陥ってしまう。
帰りにおはぎを食べたくなること間違いなし!なのですが、なぜあの場面でおはぎだったのか。毎日ごはんは5合炊きだろうし、ごはんだとばっかり思ってた。そして、冒頭の燈花夫婦の赤白にこだわった料理風景があんときなこに変わり、どこかへ飛んでいってしまった。
可笑しみ溢れる様々な家族の姿が、愛おしい。おはぎ食べたくなったよ。
慣れが日常を形成する。
父さん、母さんになろうと思う。母さんって呼んでいいぞ。
トランスジェンダーとかでもなく、女装癖とかでもなく、ただ「母」なろうとする父の話。そんな恰好をしなくたって母親の役目はできるだろうけど、より「母」近づこうとする努力。愛って、女とか男とか、恋とかセックスとか、そうものとかにとらわれることなんてなんもなくて、ただそばにいたいって感情なんだと思えた。カズオは「いろんなものをなくした俺たちに愛だけをくれた」と言って穏やかに笑う。そんな、仰向けの犬が腹を見せて甘えるような無抵抗感。そういう愛を持ちえた父だと気づいたからこそ、父さんの「いいんだなんでも。生きていればそれでいい」の言葉が橙花の心にドカンと響いてくるんだろうな。
多様性を受け入れるのは、愛。そして人間、食うことで感情がリセットできることがある。おいしいものならなおさらだ。お母さんになるって、つまり母性愛で家族を包んであげますよ、って宣言なんだ。女装の中年男が周りに違和感なく溶け込んでいるのがはじめはシュールに見えたのだったけど、最後にはそのどこが変なのかさえも感じなくなっていた。つまり、見ためなんてそのくらいつまらないこだわりなのだ。
結婚式。入り江じゃなくて大海をバックにしたラストショットが実にいい。狭い世界から、大きな世界に解放された気分になれた。この映画は、自分の環境につまずいているいろんな人々へのエールだね。
100通りの家族
お母さんが・・・
とりあえず海があんましキレイじゃない。だから島である必要あったのかしら。
あと島だから、なんでもオッケー感が、全体に漂っていて、ちょっと違和感ありました。
けど、話自体が全てファンタジーなので、島という限定された舞台の方がわかりやすいのかもしれませんね。
歌って踊ってのくだり、はっちゃけるんならもっとやれば良かったのになー、と思いました。だってこれ、全部が全部はっちゃけファンタジーの話でしょう。
妙にいい子ちゃんぶった感じで終わってしまったのは残念です。
お母さんが、彼女にとって、そして父にとって、家族にとって、どれだけかけがえのないものだったのかが、いまいち伝わりませんでした。
話のテーマであるはずなのに、父の女装ということに対することがメインに持ってこられていて、少しないがしろになっている気もしましたが、皆さんはいかがでした?そんなことないのかしら。
あと、みんなやたら服のまま海に入るんですね。私は好きですけど。またー、感少しありました。
中途半端。
家庭内ダイバーシティ
銀座で美容部員をしている女性が、母親の三回忌で実家のある離島に帰省したら、父親が母親の服を着て高校生の娘を持つ男と暮らしており、父さんは母さんになると告げられる話。
スリランカ人の嫁と結婚している弟は父親の格好は勿論再婚をあっさり受け入れるし、父親が校長を勤める高校の教師も生徒もその親たちも、誰もが普通に受けいれている状況に困惑する主人公という展開。
最後まで本人から「母さんになる」の真意を説かれることがなく、周囲から語られることからイメージした内容と実態が自分的には一致せず…そんなことどうでも良いんだ!本題はそこじゃない!と言われたらそうなんだけどね。
とぼけていたり、ハチャメチャだったり、明るくコミカルに力技!?で多様性を説かれまとめられた感じがする。
松本穂香の不思議な魅力に浸った
監督の芯の強い想いが伝わって来る、良作
「別に良いじゃん」が普通の世界
温かい作品
素敵な景色と優しい空気
全45件中、21~40件目を表示