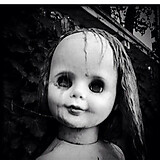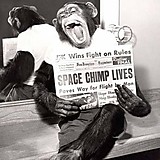ある少年の告白のレビュー・感想・評価
全89件中、1~20件目を表示
Smart Indie with Stars
With the linear, comic book TV entertainment-style logic of modern movies, one might think the intellectual promise of humanity has been a facade since the dawn of evolution. Enter Joel Edgerton, who though may not across the board be praised as one of the finest auteurs of our era, certainly knows how to empathetically unpack a controversial subject more astutely than any of his contemporaries.
最も同性愛に厳しい人間は誰か
同性愛矯正施設に入れられた少年と、家族の葛藤を描いた作品。父が保守的な田舎町の牧師という立場で、信仰心と社会的立場から息子の同性愛を認めることのできないことへのいらだち、夫に逆らうことはできないが、息子を愛する母親、そして、同性愛になってしまったことを両親に対して申し訳なくおもってしまう息子。三者三様の葛藤が痛ましい。
欧米のホモフォビアは宗教心からくるゆえに苛烈を極める。「イミテーションゲーム」で描かれたアラン・チューリングも、晩年同性愛矯正のために薬漬けにされてしまった。アメリカでは未だにこういう施設が禁止されていないそうだが、宗教心からくるゆえに改善するのが極めて困難な問題なのだろう。
ホモフォビアを過剰に持ち出すのは、時に同じ同性愛者であることがある。これは、様々な問題に言えることだ。時に女性に最もきびしく当たるのが女性自身であるように。自分は耐えた、だから耐えずにいる奴が許せない。人間はあまりにも複雑で、弱い生き物だなと思い知らされる。
重くやり切れない実話、ではあるが
「ザ・ギフト」を観て、ジョエル・エドガートンすごい、監督と脚本の才能もあるんだ!と感心したので、今作も当然期待していた。実話に基づく社会派の内容ということで、新たなジャンルに挑戦したのは買うが、映画としての面白さは残念ながら監督デビュー作にとどかなかった。今も米国各地に残る同性愛者の矯正施設を告発する姿勢は支持するし、牧師の息子という親子関係が問題を一層複雑にしていることも興味深い点ではあるが、優等生的な意見表明や啓発の域にとどまっている気がする。
ニコール・キッドマンが演じる母親がラスト近くで行動を起こす展開で救われた気持ちになった。オーストラリア出身のエドガートンがオセアニア人脈で主要キャストを配役したか。ラッセル・クロウはNZ出身だし、キッドマンはハワイ生まれの豪州育ち。怖い施設職員を演じたレッチリのフリーも豪州出身。ただしルーカス・ヘッジズは米国人だが。
重い
重くて面白いものではなかったけど最後まで魅入ってしまった。
ある時少年が同姓愛であると気付き、両親が更生施設へ入れるという実話。
施設は最低最悪の酷い所だったけれど、それよりも両親との関係の方が興味深かった。
本人は同性愛として生きなければ生きてる意味がないし、父親は神父という社会的地位から世間体もあるし、それでも母親は子供の唯一の理解者でありたいと願う。
愛する子供の親であるけど立場の違いから分かり合えないという悲しさ、それでもいつかは分かり合える日が来て欲しいというそんな映画だった。
貫禄のある神父がラッセルクロウだと気づいたのは半分くらい観てから。
変わるとは思いの外簡単ではない
物語の中心は同性愛者の矯正施設での出来事だ。
同性愛者は病気ではないので、治るとか治すとかいう問題ではないのは今では常識だが、物語の当時では治るものと多くの人が考えていた。
治らないものを治す、その方法は自我の破壊、思考の破壊だ。
神の名のもとに人間を壊す。精神疾患の患者にするロボトミー手術のごとく、治療というよりは破壊。
恐ろしくおぞましい施設での「治療」は、中世の魔女狩りに似た狂気すら感じる。
しかしこの時この中で狂っているのは回りの人間ではなく、同性愛者である主人公たちだ。という事実がまた恐ろしい。
そして、おかしいのは自分ではなく、回りの人間たちだということに気付き、主人公は自分を守るため行動を起こす。
それは同性愛を受け入れられない牧師の父との対立を意味し、息子か神かの二択を迫られることとなる。
信仰心の薄い日本人には、信仰を守りつつ息子を受け入れるという選択を取ることを容易に感じるだろう。
しかし、長きにわたり正しいと信じていたものを僅かでも否定することは、自己の否定と等しい。
私などには簡単に思えるバランスを取った両立は熱心な牧師である主人公の父には不可能だったのだ。
僅か数十年前の出来事であるが、本当に恐ろしいと思うのは、今でもアメリカではこの物語の感覚と大差ないだろうということだ。
数年前にハリウッドスター(間違えたらマズいので名前は伏せる)が、合衆国大統領は科学を信じている者がなるべきだと発言して騒ぎになった。
日本人の感覚では当たり前の言葉すぎて何のことやらと思うだろう。
しかしアメリカ人の多くは、大統領は科学よりも神を信じている者がなるべきだと思っているのだ。
大学で教鞭をとるような人が、地球は平面だと信じていたりする国。それがアメリカ。
そんな、敬虔を通り越して愚かにも思える人々に対し、信仰にとって真に大切なことは神ではなく、人だと、当たり前にすら思えることを訴える作品だった。
同性愛の人が親に受け入れてもらえないという話を日本でも聞く。
そこに信仰まで絡んでしまうアメリカにはこの先十年や二十年では変われない根深さがある。
うーん
なんというか、子供の成長というより
親の成長や幼さを描いた作品だったように思う。
ある意味、主人公は父だと思った。
理解したい、いや、理解できない。
それすら、自分を正当化するような、予防線を張るようなもので、本当は理解する気がないのかもしれないなと思った
世間一般に異端とされるものを恐れるがあまり、本当に大切だったはずのものを見失ってしまう恐ろしさを感じた。
いや、あの父親は、息子そのものではなく、品性方向で正常な息子を愛し、求めていたのかもしれない。
この作品の大人たちは、誰もが責任から逃れようとしているように感じた。
母は最初から味方できなかったことを悔いているが、結局は父の決めたことだから自分は関与していないと逃れようとしている。
父も言わずもがな、少年の告白について大して聞きもせず矯正施設に送ることを決めたはずの過去を葬り、そのアドバイスをした牧師や友人に責任を擦り付けた。
これは大人の弱さを描いていると言っても過言では無い。
窓から手を出したらあかん
いや、それは本題ではないのだが・・・。
アメリカや西欧は日本に比べて同性愛に寛容なイメージを持つ人も多いかもしれないが、一方でキリスト教と文化が密接に結びついていて、宗教に熱心な家庭な多く、その多くは保守的である。
家族を悲しませているという本人の罪悪感をあおり、矯正施設でやってもいないことを「告白」させられる。逃げ出せる人ばかりではないだろう。
多様性を尊重する、と言えば簡単に聞こえるが、たとえリベラルを気取っていても実際に子供が同性愛者と知って動揺しない親は少ないだろう。親は、自分たちのように結婚して子供をもうけて欲しいと、出来れば良い大学へ行って年収の高い職業について欲しい、など思いやりという形の身勝手な期待をかける。我が子が一生結婚しない、子供ももうけない、孫を抱くこともない、と言うことをすんなり受け入れられる親は少ない。実際のところ異性愛者であっても誰もが結婚できるわけでも、子供を授かるわけでもないのだが。
近年、同性でも結婚できる国もあることにはあるが誰もがそういう国に生まれられるわけではない。
この映画は事実に基づいているが、どんなに同性愛に対する制度が整っていたところで最後は家族と向き合うしかないのだと考えさせられる。そして現実に安易なハッピーエンドは来ないのだ。
ルーカスヘッジ
受け入れる、受け入れられることの難しさ
自分を、自分の考えを最も受け入れてほしい相手は最も近い存在である親、子供だ。わかってもらえないと、この上なく寂しく、悲しく、不幸だ。ルーカスがゲイのカミングアウトを両親にする際、ごめんなさいと告げるのが印象深い。親を思うからこそ、その考えにそぐわないことを知ってるからこそ、絞り出すように伝えた。親も、愛する子だからこそ、人並みの幸せ、一般的な幸せを送ってほしい、治してほしい気持ちから矯正施設に入れてしまう。この手の施設がある事を知らなかったし、苦しんだ人々が多くいることも知らなかった。共生社会、ダイバーシティと聞くようになったが、実際、自分の子だったら、苦悩するだろうし、その姿をラッセル・クロウが好演していた。父とは違い、次第に息子の気持ちがわかり、母親の愛で救うニコール・キッドマンも良かった。映画では父親が牧師で、キリスト教が描かれていたが、宗教も癒やしを求める者にとっては良いが決して押し付けるものではないと感じた。エンディングで実話だったことがわかり、親子が困難を乗り越えたシーンが映され、感動的。派手さはないが考えさせられるストーリー。
タイトルなし
一人の少年の告白によって明るみになり
アメリカを驚愕させた“ある事件”……。
一部の教会が神の名のもとに人間性を
強制的に変えようとする人権を無視した
“プログラム”を行っていたという事実
ガラルド·コンリー の実話を
ルーカス·ヘッジズ 主演で
ジョエル·エドガートン が映画化
.
社会の光と闇
誰にでも多少の偏見があったり
無意識にでも誰かを傷つけたり
自分をも認められなくなる場合もある
様々なマイノリティを認めるには
自分と違った立場や価値観を持つ人の
声を聞き耳を傾けることから
作品を通してそう語りかけている
.
.
原作者 ガラルド·コンリーは
現在夫とNYに住み
LGBTQコミュニティのために執筆と活動を通じ闘っている
実際のサイクスは2008年施設を去り
現在テキサスで夫と暮らしている
映画の完成時36州が未成年の矯正施設を認可
LGBTQの米黒人70万人が
矯正施設の影響を受けている
──────エンドロールより
.
『フリをしろ』辛い言葉でした
宗教って、、、
アメリカは同性愛には理解があると思っていた。違った様だ💦同性愛矯正施設というものがあることを知らなかった。映画の様な事が、施設内で本当に行われていたのなら恐ろしいことだ。
子孫を残す為には男と女の組み合わせが自然な事だろうけど、普通ってなんだろう?人の気持ちは色々で、男同士だって女同士だって、人それぞれでいいではないか?自分の信じる宗教がそれを許さないのなら、信仰を変えてもいいのでは?神様は赦してくださるのでは?と、お寺でご先祖のお墓に手を合わせ、観光に行けば神社で御朱印を集め、クリスマスにはケーキを食べる、特に宗教を意識していない私には語る資格はありませんね😣
エンドロールで実在の親子の映像が映って、神父を演じたラッセル・クロウ、似てますね!ただ、どんどん大きくなってる気がします。グラディエーターの頃の面影があまり無いような、、、ニコール・キッドマンもそっくりではないけど似せてます。実在の人物を演じる事が多々ある様に感じるけれど、毎回似せてきてますが完全に似ないのは元が綺麗過ぎるからでしょうね🥰
グザヴィエ・ドランも今回は俳優として出演している所も見所でした。
プロテスタンティズム
ショックだ
以前ドラァグクイーンたちが 同性愛の矯正施設に入れられて辛かった、という話をしているのを番組で観たことがあり、そんな施設があるのか…とドン引きしたことがあった。まさかその施設について描いた映画があったとは。
同性愛を病気と考える親や矯正施設のスタッフたち、その言動は不合理で衝撃的で、かなりショックを受けた。
そんな考えに対して共に戦うべき仲間?のはずの同性愛者たちも一枚岩ではない。淡い初恋の相手かと思いきや強引にレイプしてくる者、矯正できると狂信的に信じて長期治療を望む者、上手く立ち回ってサッサと卒業しようとする者など皆ひと癖あり、主人公の悩みや戸惑いを聞いてくれるような相手ではない。ゼイヴィア(グザヴィエ?)だけが唯一、自分はゲイなのか?自分の生き方は正しいのか?と自問自答してくれる主人公の心情に寄り添ってくれるけど。
今は考えが多すぎてまとまらない。
神の名の下で
キリスト教社会派ドラマ
牧師の家族の息子がゲイで、キリスト教の同性愛者の矯正施設に入れられることに。
「同性愛者は罪である」ので矯正が必要という信念の元に自己否定をさせるという、愛のない矯正施設の実態。
何十年も前から同性愛者は生まれつきのものと言い続けられていますが、未だ叫び続けなくてはいけないのは悲しいことです。
時代にそぐわない宗教は、ただの人をコントロールするための道具だと思っています。
「自分自身の中に神様がいる」と映画中のセリフでもありましたが、邪悪なものとそうでないものって心の中で分かります。
宗教のルールに縛られすぎるなという社会派ドラマでした。
Boy Erasedというタイトル
洋画のタイトルが日本語にすると違う事がよくある。
Erasedという、「消し去られた」という強い意味を持つ単語をあえて日本語タイトルにしなかったのはなぜ?
確かに映画の内容は、ある少年の告白なんだけど。
この"Erased"がこの映画の一番伝えたいところだと感じた。
ゲイであるという、一般的にはマイノリティーといわれる性であるが故に、その人の人権も尊厳も奪われるようなシーンが多々ありました。
同じ人間なのに、なぜ、たかだか性が男性or女性に属さないだけで、あそこまで否定されねばならないのか。
それも誰よりも安心できる存在でいて欲しい両親に。
鑑賞中に何度も胸が痛くなった。
同性愛者嗜好を治療するための矯正施設で起こった、実話を元に作られた本作には驚くようなことがたくさんありました。
キャメロンが罰を受けるシーンなんて、ただただ腹ただしく、悲しくなりました。
棺桶置くなんてどんな頭してんのかしら。悪魔なんてホンマにおると思ってんのかい!このアホが!と。
泣きながら兄の背中を最初で叩く小さな女の子が、とても可愛そうだったけど、あの子の涙はどちらの涙だったのか、、、
悲しいシーンが多い中で、グッときたシーンはやはり母親のシーンでした。母親役をニコールキッドマンが演じていましたが、相変わらずお美しい。すごいねスターは。いつまでも輝きが衰えない。と、そこは置いておいて。
①ジャレッドに迎えに来てと電話をもらいすぐに飛んできたママ。迎えの時間でもないのに息子から電話がかかってきてすぐに応答できたのは、母親はうすうす施設のおかしいところに気付いていたのかもとも思った。
施設を離れる際に、サイクスに向かっていった「shame on you! shame on me too」のセリフ。
ど迫力でしたが、母親の怒りが相手にも、自分にも浴びせられていましたね。何者でもないオッサンが何偉そうに施設なんかやっとんじゃい!と。そして、愛する息子をありのまま受け止められなかった、寄り添ってあげられなかった自分にも恥を感じたのだなと。
②ジャレッドとレストランみたいなところで話すシーン。自分がいつものように夫に黙って従ってしまったこと、それによって息子にとても辛い思いをさせてしまったことを悔いていると告白したシーンはただただ涙が止まりませんでした。母親として我が子を守れないなんて、本当に辛かったでしょうから。でも、どれだけ遅かったとしても、人間は変われることを自身で気づけたことがお母さんの一番良かったところだと思いました。
映画の最後に実際のご家族の写真が2枚うつりました。
どちらも笑顔だったことが本当に良かった。
世の中にはたくさんの人間がいます。
その人間をたった二種類のグループに分けられると思うこと自体が私にとってはありえないし、意味がわかりません。
また、本作では宗教がとても影響しているなと感じさせられました。信仰というものは時に人を助け、救ってくれるけれど、人間は弱いからそのことに甘えてしまいます。一人一人が考え、他人の尊厳を邪魔せぬようにいられればなと思いました。
アメリカには70万以上の方がまだこのような施設に入所しているとエンドロールにありました。
自分が自分らしくいられるお手伝いをしてくれるのなら良いけれど、この映画のような施設であれば正直必要のない場所に感じました。
アメリカでは、現在でも70万人のLGBTが矯正施設に入所させられているという事実に驚いた。
日本にも存在するのだろうか?
こういう現実があるからこそ、アメリカはLGBTの権利に関する運動が盛んなのだろう。
矯正施設の「治療」は、忖度というか、強制はせずに自分の意思であると感じさせるのが悪質だと感じた。
自分が悪だと自身で認識させる。本当に残酷。
病気の治療で暴力を振るわれることなんてあるだろうか?
繰り返し語られることが「元に戻す」ということ。
その「元」っていうのがキリスト教に由来しているから問題は根深い。
自分を「善」だと信じる者たちは譲歩のしようがないことが恐ろしい。
考えを改めてしまうということは自分の価値観を変えることだからなかなか叶わない。
ただ、自身の家族を痛めつけることが正解なことなんて存在しないだろう。
全89件中、1~20件目を表示