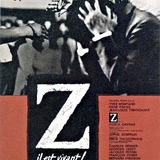Fukushima 50のレビュー・感想・評価
全432件中、361~380件目を表示
評価は難しいけど風化させてはいけない話
「いい映画」とか「面白い映画」と表現していいのかは微妙だけど、自分の中では高評価。
映画はいきなり震災のシーンから始まる。前置き一切無し。まだ9年だもん。観客だって忘れるはずない。
あの時あの瞬間を東京で過ごしたわたしも酷く揺れたのを覚えてる。津波の被害、東北地域での被害が日々報告されていたけど、津波に馴染みのない自分には現実味が無く感じていたのも思い出した。でも実は250キロ程離れた福島で猛者達が命をかけて原発の暴走を止めてくれたからこそ今の自分の生活が続いている事に気付かされ、東日本大震災と自分がこの映画のおかげで初めてリンクした。
映画だから多少の脚色はあると思うけど(というか脚色で無かったらヤバ過ぎる💦)、作中の「総理大臣」の描き方が酷い^^;
専門知識もないくせに現地にヘリ入りするせいで、現場で戦う人たちのスピード感に遅れを来す。一方で行った方がよさそうに思える東電の東京本店の幹部は誰一人として現地入りしない。最終的に理由はわからないままもとゎいぇ奇跡的に収まったからよかったものの、大切な事が出来ないで余計な事ばかりしていたように思える当時の描写は、大事故が起きる瀬戸際だったことを見せ付けられ今更ながら恐ろしく思えた。
皮肉なことにこの映画が公開されてる今、日本を含め世界中でコロナショックが起きている。当時の政府の対応の悪さをいろんな方面から批判されたのがわずか9年前。予測できない事態が起きてる訳だからPDCAサイクルのPは無理としてもCheckとActionを9年かけて見直して改善していれば今の対応だってこんな付け焼き刃とか場当たり的な対応になって無かったように思えるんだけど、現実はそううまく行かないって事なんでしょうか。
もどかしいな〜
日本こそ災害時、非常時のの緊急対策エキスパートになる資格がある国なのに残念。
2回目観賞をためらう名作
結局、現場にしわ寄せがくる・・・
東日本大震災の時はテレビにしがみつくほど集中していた。なにしろ原発のことがさっぱりわからず、随時解説者が説明してくれても理解不能でした。覚えていることといえば、「枝野寝ろ!」とネットで騒がれていたことだけだった(恥)。
今作は再現ドラマのごとく、福島第一原発で何が起こっていたのかを忠実に描いていて、本店や官邸からの命令と対処法を知るベテランとの葛藤劇でもある。素人目からすれば、水素爆発の可能性というのも信じてしまうし、想定外の津波ではあるものの何とかなると思ってしまう。それが中央制御室と緊急時対策室という内部からの物語によって、目からうろこ状態になってしまいました。
自然の驚異。津波の高さの予測。やはり人間の手によって作られたものは、未知数の災害によって呆気なく破壊されるものだということ。しかし人間の培われた叡智は困難に立ち向かう強さも生むし、人々が繋がっていて愛や友情があるのだということも教えてくれた。
地震や津波による死者・行方不明者の描写を無くし、あくまでも原発内だけの記録と家族愛に絞ったのも潔いと思うし、これからの原発の在り方や危機対応について考えさせられる作品となっていました。大きな事故でいえば、この福島第一原発、スリーマイル島、チェルノブイリなどなど、すべて教訓として生かして未来の地球を考えなければならないなぁ~
観賞中、誰もが3.11の当日を思い出すはず。
何度も泣きそうになりました。
『Fukushima50』鑑賞。
*主演*
佐藤浩市
渡辺謙
*感想*
東日本大震災、、忘れもしません。
当時、僕は会社に入社してから1週間後に起こりました。あの時の出来事は9年経った今でも鮮明に覚えています。TVで見た巨大な津波、迫り来る大量の水、恐ろしかったです。
東日本大震災を題材にした映画を観ていいのだろうかと一瞬思いましたが、福島第一原発で働いてる人達の奮闘した姿がリアルに描かれているのだと知り、非常に気になってしまったので鑑賞しました。
冒頭からまず、ビビります。3月11日14時46分に発生した巨大地震。原発で働く作業員・伊崎と吉田所長、周囲の人達が予想を遥かに越える事故に奮闘する姿がリアルに描かれています。イライラや怒号、特に吉田所長は一番イライラしてたと思います。口だけ命令する本店の人や名前は出しませんが、当時の総理がただキレてるだけで、信じられません!
「何言ってるんだコイツ。」
作業員の1人が思わず呟いたこの台詞。僕も同じタイミングで呟いてしまいました。(^^;
原発の専門用語がかなり飛び交ってるのでイマイチわからない所もありますが、作業員たちの戦ってる姿に何度も泣きそうになりました。あと、津波や爆発など辛いシーンがあって、心に突き刺さる場面が多かったです。
アメリカからの救援、「トモダチ」素晴らしいです。
色々な感情が揺さぶられる作品でした。。
3.11で亡くなられた方々にご冥福をお祈り申し上げます。
想定外は必ず起きます。技術者も辛いのです。
歴史に残る危機に対処する人々を描いた映画。登場人物へのインタビューに基づき”事実に基づく”と謳うある意味再現ドラマ。浪花節となるのは商業映画故でしょう。
後世に残すべき映画だと言えます。
事故調の報告書なんて見ないし、記事を読んでも抜けてしまってる。政治家、経営者、現場責任者、一社員、協力会社そして被災者、それぞれの立場で反省すべきことが見えてくると思う。
安全神話とも絡むが、プランBを口にするだけで叱責される企業風土や国民感情がこの災厄を生んだのでは。技術者から見れば妥協点(想定)を決めるのは経営者や政治家。津波が10mを超える可能性が有るのは確か。で、何メートルを想定するか。妥協点がおかしければもちろん異議を唱えるが絶対の根拠はない。
そんな中で技術者の思いも感じる。欠陥品と揶揄されたGE製F1でも圧力容器は倍の圧力に耐えた。次に作った原発は非常用発電機を高台に設置してた。
あまりニュースでは扱われなかった自衛隊や米軍も描かれていて良心的。
トモダチ
何も終わってない
リアルに徹した見事な映画
原作は門田隆将の「死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発」で、映画の脚本をノベライズしたものも出版されている。門田氏の原作は、3.11 の大震災後に何百冊出されたか分からないほどの原発関連本の中で、紛れもなく歴史に残るであろう数少ない名著である。著者が取材に綿密に取り組み、吉田所長をはじめ夥しい人物の証言を得て書かれており、事実の正確さと読みやすさにおいて非常に卓越している。この映画はこの原作に非常に忠実に作られている。
私は福一には行ったことがないが、福二には建設中に見に行ったことがある。今から 40 年ほど前のことで、出張の書類に目的を「見学」と書いたら「視察」と訂正するように求められて、国立大学の教員というのは偉そうなんだなと可笑しく思ったのが未だに忘れられない。地表の土砂を大規模に除去して岩盤を剥き出しにした上に建屋を建設し、鉄筋の太さと密度はそれぞれ通常の建物の3倍であり、直下型の地震で震度7にも耐えられるという説明に非常に納得させられた。同じ沸騰水型原子炉であるが、福一の原子炉は福二と違うメーカーのもので、設計構造が全く違うという説明を受けた。3.11 の大震災では福一福二とも高さ 20 m を超える大津波の襲来を受けて全電源喪失(Station Blackout、SBO)の非常事態を迎えたが、福二は水素爆発も起こさず、何とか今日に至っている。
まず驚いたのはセットの見事さである。長野県の諏訪市に作られたというセットは、40 年前に見た原子炉建屋内部の光景と全く遜色なく、まるで本物の原発を使って撮影したのではと思わせられるリアリティを持っていた。実際に撮影できない海底の地震や原子炉内部の映像は CG であるが、そのリアリティも非常に高かった。あの時何が起こっていたのかを視覚的に捉えることができるのは有り難いと思ったが、これが新たな風評を生むのではと心配する向きもあるのは十分察せられる話である。
原作にほぼ忠実な脚本は淡々としていて、感動や感涙を押し付けることもなく、原作を読んでいると許し難い思いに駆られる首相周辺の描写もまた淡々として事実のみを語ろうとしていたように思われたが、それでも、この当時の政府がいかに無能で余計なことばかりしていて、しかもいかに見下した態度だったかが嫌というほど察せられた。個人的にはもっと首相と政府の無能さを強調してほしいところだった。あの無能極まるクソ菅が無意味な視察を強行したために、ベントが予定より6時間も遅れて1号機と3号機の原子炉建屋が水素爆発を起こしたのである。
原子炉はマトリョシカのように多重殻構造になっていて、中心にあるのが原子炉圧力容器で核分裂反応を閉じ込めている容器であり、それを冷却するための付帯設備などをもう一つの原子炉格納容器が囲んでいる。更にその周りを原子炉建屋が囲んでいる。いわば、圧力容器が人間で言えば下着にあたり、格納容器は上着、建屋は家のようなものである。沸騰水型の場合、圧力容器の中で加熱された水はそのまま発電用のタービンを回転させてから元の容器に戻る構造になっており、圧力容器はもちろん、格納容器の中まで放射性物質が充満している。核燃料を棒状に保っている金属容器はジルコニウムでできており、圧力容器内の水位が下がると数千℃もの高温となって、周囲の水蒸気と反応して水素を発生させる。
映画ではこうした説明が全くなかったのが難点であった。あえて説明シーンを用意せずとも、いくらでも台詞の中に潜り込ませることができるはずなのだが。それによって、圧力容器は言うに及ばず格納容器まで溶けて放射性物質を振り撒いたのがチェルノブイリ事故であり、一方、福一の事故は建家の水素爆発までしか起こっておらず、ベントによって圧力を下げたことによって辛うじて格納容器は保たれたという相違を明示することができたはずである。
俳優は、渡辺謙と佐藤浩市の圧倒的な存在感が素晴らしく、火野正平や緒方直人らの確かな存在感も見事であった。現場作業員役の俳優たちは、水素爆発発生後のシーンでは全面マスクを着用しての演技となり、表情が伝えにくくなってるにもかかわらず、その熱い思いがひしひしと伝わって来た。ナレーションを廃して全てが俳優の演技に委ねられていたため、役者に求められていたものは非常にレベルの高いものであったと思う。首相役の佐野史郎はいかにも憎々しげで好演であったが、一昔前の村野武範ならもっとリアルに演じてくれたのではないかと惜しまれた。米軍の司令役でダニエル・カールが出ていたが、得意の米沢弁を封印して見事に英語のみで演じ切っていた。
岩代太郎の音楽はいつもの通り非常に水準の高いもので、いずれの曲もクラシックの演奏会でプログラムに入れる価値のあるものばかりであった。五嶋龍のヴァイオリンと長谷川陽子のチェロの演奏も非常に見事なものであった。
演出はリアリティに徹しており、非常に見事なものであったが、事故直後の場面では同時に複数の人間が叫ぶような場面があり、聞き取りにくかったのがやや残念であった。「トモダチ作戦」に出てくる米軍ヘリや、首相を運んだ自衛隊のヘリは本物を使っており、米軍や自衛隊の協力を得たシーンは非常に見応えがあった。演出上の虚構を極力廃した製作姿勢は、非常に立派だと思った。所長から退去を勧められた自衛隊員の返答には思わず目頭が熱くなった。協賛企業にド腐れウソ日新聞がないので出せた台詞ではなかったかと思った。多くの人に見て頂きたい映画である。
(映像5+脚本4+役者5+音楽5+演出5)×4= 96 点。
ホラー映画より怖い
終始、涙が止まらなかった作品。
一人一人がみんな必死に動いている。
命を懸けた仕事。
人は失敗を経験して成長していくもの、最近私は、特にそう感じています。
東日本大震災の時になぜこのような事態が発生してしまったか。
それに通ずるものがあると思います。
当時の失敗はあまりにも大きかった。
想定外と言う方が正しいかもしれない。
それは作品の最後で語られるが、これを経てどう成長するか。
まさに人と同じでしょう。
僕自身も当時、東京で地震を体験しています。
その時、当然怖かったですが、より近い福島の人たちはもっと怖かった。
当たり前のことですけど。
正直、どこまでが事実でどこまでがフィクションか分からないですが、震災がテーマの作品は、やはり一般のホラー映画より怖い、現実的だから。
ましてや、僕自身も体験しているのでよりそう感じる。
想定外(敢えて満点にしてます)
吉田所長が亡くなる前に、伊崎に宛てた手紙の内容が全てなのだと思う。
東電の役員を相手に行われていた裁判の争点でもある。
想定外なのか…。
いつか鳥インフルエンザがヒトヒト感染で大変な事態が発生することを想定して、特措法も作ってあったのに、今回の新型コロナウイルス肺炎の感染拡大にも政府が手を拱いているように思えるのは、想定外と言って良いのだろうか。
想定外は言い訳として万能なのだろうか。
福島の双葉町はずっと全域避難が続いてて、避難指示の一部解除は一昨日3月4日のことだ。
この原発事故から9年も経過している。
福島の復興はまだまだだ。
最後に、復興五輪が云々と流れるが、福島が復興してるわけではない。
今後の汚染水のことを考えると、取り得る方法は限られてて、海産物の風評被害とか想定される問題は山積だ。
あの津波は想定外だったのだろうか。
識者の助言はあったことは提言などでも明らかで、上層部はこれを知っていて、コストやなんやで放置していたのではないのか。
東電の上層部は、学者はこんなこと言ってるけど、相当なコストかかりますから、そんな大それた津波はきっとこないだろうから、対策は、このままで良いですよねって放置してたんじゃないか。
それに、責任を分散させるために、これは経済産業省・資源エネルギー庁にきっとお伺い立てていたに違いないですよね……。
これらは、多くの国民が共通して抱いている疑問だ。
このFukushima 50の勇気や行動には胸が熱くなる。
皆、生きていて良かったと心から思う。
感謝の意も伝えたいと思う。
しかし、復興もそうだが、もう生まれ育った家に帰ることさえ叶わない人も、まだ、多くいることを、僕達は忘れかけてはいないか。
今、僕達は真剣に、福島の、被災地の復興は成ったのか、今後のこうした人禍(敢えて、こう書かせてください)に見舞われることのないようにするためには、どうしたら良いのか、どのように政府や国策のエネルギー政策を監視したら良いのか改めて熟考するべきではないか。
そんなことも考えさせられる作品だと思った。
被災者の方には、この映画で、人の目が感動のストーリーに向くのではないかと懸念する人もいるように思う。
当たり前だ。
ポイントをいくつにするか逡巡しましたが、日本人はきっとバカではないから、真剣に考えてくれるだろうとの期待値で満点にします。
津波は怖し。
今明かされるあの日の真実
映画としては微妙な出来。当時を振り返る再現ドラマとしても微妙。
話の題材、話のプロット、俳優陣、
素材はとっても良いのに上手く料理しきれてない感じ。
編集、シーンのつなぎ方が悪いのか、
1つの話(パート)が唐突に始まり、尻切れトンボに終わる感じが終始ある。
ニュース番組のシーンをブリッジにするとかして
現在何が起きつつあるのかを解説する部分があったほうが良かった。
そうすれば、報道では全然分からなかった現場の奮闘感が引き立ったはず。
また、ハッピーエンド風にまとめているけれども、本当にそうだろうか?
奇跡的に爆発を逃れた2号機ではあるけれども、
2号機から噴出した放射性物質で福島は汚染されてしまったわけであり
その事実は受け止めなければならない。
それもちゃんと映画で説明しておくべきではなかったのか?
現実、史実、ふんばり、耐力、愛・・・
最後まで頑張るのはやっぱり現場の人間なんだなって
この作品は、3/11の東日本大震災で起きた原発事故を防ぐために戦った男たちの物語
暴走してしまった原発を食い止めるため、必死になって色々な対策を講じる
実際の現場がどんなだったかよくわからないが、
放射線レベルが危険域に達している中での過酷な作業などを考えると
頑張った人たちには頭が上がらないと思った
そして、このような事態を全く考慮にいれていなかった、日本の自然に対する認識の甘さを
再確認するためには良い映画だったと思われる
さらに、役職と知識がマッチしていないトップやいらない視察を行う現職の総理大臣、それに対して現場に責任を負わせる役人たちの横暴など日本の政治的な問題点を浮き彫りにしてくれている
この作品をただの娯楽作品として、鑑賞するのも良いが
こういった日本の問題点をみんなで再確認する良い機会ではないかと思われる
全432件中、361~380件目を表示