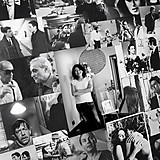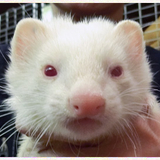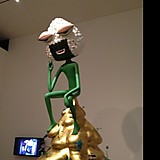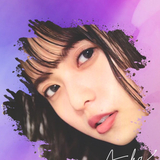グリーンブックのレビュー・感想・評価
全942件中、701~720件目を表示
もちろん
期待通り!文句はない。
これが実話ベースのストーリーであるということに大いに勇気づけられる。
自分と他者との違いを、怖れるのではなく敬い、愛する態度を持った人間でありたい。
ドクターの言う「dignity」という言葉が深く印象に残った。
人としての尊厳はかくも踏み躙られやすいのだ。
彼が徹底して暴力を嫌う様には、Martin Luther King Jr.の演説を思い出した。
"In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force."
そしてトニーの素直さに救われる思いがした。彼は心の底から素直で、オープンで肯定的だ。
彼が彼自身の存在を肯定していることからくる、人間的な温かさ。
ドクターの演奏を聴いて「天才だ」というシーンが良い。耳も(音楽に対しても)素直で柔軟なトニー。
音楽も良かった。ポップソングのBGM、ドクターの演奏シーンともに。
人種差別がテーマでは無い
予告編が良いだけに…
実話と知って驚いた⁉️
あらすじは知っていたが、そうとは知らなかったので、巻頭で実話との表記にびっくり! よく比較される「最強の二人」が実話なのは、鑑賞前から知っていたが、「ドライビングM i s sデイジー」は舞台の映画化だったので、この作品も映画のためのフィクションかと思っていた。最後に本人たちの写真も披露され、本当の話なら、もっと感動的だと思った。イタリア系ではないヴィゴが、体重を20k gも増やして、コテコテに演じていておもしろかった。マハーラシヤが、「ムーンライト」の麻薬の売人とは打って変わって、インテリのピアニストを演じていて、見違えた。私が特に心震えたのは、ドンの孤独だ。カーネギーホールの上階に住んでいて、召使いも抱えて生活はリッチだ。でも、一緒に家族は誰もいなくて寂しそうだ。本当はクラシックを弾きたいのにレコード会社からポピュラーを弾いた方がいいと言われ、それに甘んじている。北部ではまだいいが、南部では白人からは差別され、黒人からは何を気取っているんだという目で見られる。彼はどちら側にも属せない人間なのだ。そんな孤独がひしひしと伝わってきた。あと気に入ったのが、手紙のエピソード。最後にそうかと納得させられた。見終わった後もすごく清々しくて、気持ちよく映画館を後にした。
1962年の晩秋アメリカ南部を車で走る。
60年代が舞台の、粗野な白人と洗練された黒人の物語といえば、そのス...
入れ替える→元に戻す
「黒人運転手」+「白人客」という組み合わせは50-60年代のアメリカにおいては当然のように見かけられる光景だったろう。
だが「白人運転手」+「黒人客」という逆の組み合わせをやってから、元に戻してみる。最後だけ、黒人に運転手をさせてみる。
するとどうだろう。周りの人々からしてみれば当たり前の光景に、当人たちにしか分からない特別な何かが育まれていると感じられる。
当たり前の光景がいかに特別なものであるか、それは長い旅路を経た2人の主人公(そして観客の我々)にしか分からない。
奴隷として強要されたのでもなく、生活のため仕方がなかったのでもなく、親愛の情から、運転手という役割を買って出る。
それは一切の差別のない世界においてかくあるべしとでも言うかのような、「自ら望み、喜んでやる」という自己決定に従った行いであった。
「黒人運転手+白人」という構図はいかなる事情を抜きにしても差別的である、と決めつけるのではない。
「黒人は貧しく粗野」「白人は豊かで教養がある」と一般化するのでもない。
「超富裕層の黒人」「貧困層の白人」という例外的な存在、個別の事例を踏まえ、よくある光景の背後にある物語を読み取ろうとする。
「黒人は皆等しく貧しく、困窮しており、救済が必要である」と考えることもまた差別である。
黒人だから、白人だから、といったフィルターを取り払って、個人の事情をよく知ろうとすること。
それが差別的ではないということの本質ではないか。
個々人の抱える事情=ドラマを経由してみる。
すると、「反差別的なようでいて差別的な人」からみれば差別的にも思える光景の背後に、こわれないよう守りたくなるほどの親愛の情があるのではないか、という可能性に気づかされる。
そのような可能性を見落とさないよう、個々人の事情に耳を傾けようという気にさせられる。
(もちろん、ドクター・シャーリーの金持ちぶりは映画向けに誇張されているだろう。それを差し引いても、当時の黒人として彼は例外的にリッチだったろう。だから黒人運転手と白人の乗客を見るたびに「その背後にドラマがあるかもしれない」などと考えるのも愚かに思える。ポイントはあくまで、黒人(に限らないが)=被差別対象あるいは社会的弱者、のような認識がむしろ弱者を弱者のままに据え置いてしまうこと、への警句にあると思う)
人種差別を扱う作品にしてはめずらしく…
楽しめる映画
また、会いたい。みていたいこの二人を。あの家族を。
いい映画。
高校時代に観ていたような映画に、久しぶりに巡りあったなーという感じだった。
なぜ?
CGメイン・今はやりの映画、ではなかったから?
ロードムービーは鉄板だから?
実話にもとずいている、その奥深さから?
音楽、すごく素敵だから?
抑揚の効いたストーリーはこび、脚本、俳優達の演技が素晴らしいのはもちろんだが、当時の日常、さりげない会話、景色、出来事を積み重ねていくことが魅力的だった。
人種差別を高所から扱うのではなく、二人が遭遇する日常を、たんたんと時系列で重ねていく。温度差なく体験した。だからこそ移入できる。『なんで。こんな仕打ちを受けるのか…!』。
ある意味『この世界の片隅に』みたいでしょ。と思った。
トニー・(リップ)・バレロンガにまた、会いたい。
ドクター・シャーリーのピアノをまた、ききたい。
奥さん、ドロレスがいい。
人種差別がここまで…
この映画を見てはじめて、人種差別がここまでひどいと言うことかわかった。
日本に住んでるから、全く感じたことない衝撃だった。
映画の中の二人は乗り越えて、お互いいい方向に進んだけど、この映画がきっかけで人種差別が減ったらいいな。
人生を前を向いて運転出来る。素敵な作品♪
今年のアカデミー作品賞を受賞した作品と言う冠だけでなく、好きな要素が盛り込まれた作品だけに観る前から期待してました。
ただアカデミー作品賞受賞作は賞狙いの意図とお堅い感じがしなくもないので、その辺りに一抹の不安を覚えながらも鑑賞しました。
で、感想はと言うと、素晴らしく素敵な作品♪
始まって直ぐに“これは素敵な映画が始まる”と言う予感に胸の高鳴りがしました。
カラフルで色彩豊かな60年代のアメリカの街並みとポップなアメリカン・オールディーズナンバー。
美味そうなファーストフード。
少し背伸びをしたくなる素敵なジャズ。
普段は合間見える事の無い人物同士が8週間の時間の中で知り合うだけの十分な“何か”が起こるであろう旅。
最初から最後までワクワクしました。
様々な人が書かれてる通り、「最強のふたり」に共通する部分も多々ありますが、より複雑で様々な要素があります。
上流階級で上品。ピアニストとしての名声も得ていて、金持ちで雇い主の黒人のドク。独身。
どちらかと言うと下流階級で粗暴で下品w。仕事に溢れて雇われている、黒人が嫌いなトニー。既婚で幸せな家庭があって、奥さん気立てが良くて綺麗。
合わない筈の2人なのに、互いが徐々に通じ合っていくのが染み入る様な感じで、旅先で起こり事件や出来事も旅先なら起こりうる事なので納得。
事実を元にしているだけに過剰な脚色が無いのも良いですね。
「最強のふたり」よりも少し複雑なのは互いの立場の設定と、人種差別が色濃く残る地域の事と「LGBT」問題なんですが、それぞれの問題が作品の本質を加味していても邪魔をしていない事が素晴らしいです。
終盤に差し掛かってドクの心情の告白は切ないものがあります。
黒人である事から白人に強いたげられ、同じ黒人からも軽蔑される。
自分がとちらからも孤立する疎外感と孤独。
ドクの叫びがキリキリと突き刺さります。
また、ラストで行うコンサートで古くからのしきたりとばかりにレストランでのドクの食事を認めないのに、契約を盾に自身の正論を発する支配人にはムカムカ。
他にも人種差別に対してムカムカする所も多々ありますが、その都度頼りになるトニーだったり、ドクの凄い人脈だったりで事件解決。
ラストの黒人御用達のダイナーでのライブではスカッとしながらも同じ黒人達に受け入れられた様な時間に少し優しい気持ちになって、長時間の運転に疲れたトニーの代わりにトニーのクリスマスに間に合わせ様と運転をするドクの優しさにじんわり。
トニーの家族とのクリスマスパーティに自ら出向いたドクを暖かく出迎えたファミリーに胸熱になって、ドロレスとドクが互いに伝えた言葉に涙腺崩壊。
ツッコミがあるとすれば、ドクとトリオを組んでいた二人は嫌な奴の様に見えてもそうではないが、だからと言って理解はあっても実は良い人だったと言う訳でもなく、もう少しキーパーソンになるかと思いきや、そうでもなかった事。
ドクとトニーが最後のコンサートをキャンセルして、出ていったけど2人の事は触れられてなかった事かなw
ドクがトニーに運転中に何度も言っていた“前を向いて運転しろ”の言葉はただ単に安全運転だけの言葉では無い様に感じます。
人生に対してもそうだし、むしろ自分自身に向けて、発した言葉ではないのかな?と感じました。
「最強のふたり」「ターミナル」「ジャージーボーイズ」が大好きで、これらの作品に通じる面白さがありつつも、面白くて、クスッと笑えて、何処か爽快で、少し人生や社会に悩んで、良い涙が流せる。とても素敵で素晴らしく、いつまでも余韻が残る作品です。
アカデミー作品賞を受賞するだけの素晴らしい作品です。
未鑑賞の方は是非!絶対にお勧めです♪
お守り
黒人ピアニストDon Shirleyの運転手としてコンサートツアーに同行したイタリア系アメリカ人Tony Lip。外見だけでなく、中身もオセロの石のように正反対な2人のロードムービー。
品行方正な佇まいが、まるで高貴な生まれのようなShirleyに、口達者でガサツで食べてばかり(^_^;)のTony。この2人のやり取りがとても面白かったです。
性格、教養、趣味、言葉遣いにマナーと、何から何まで異なる2人に共通しているのは、たとえアウェイでも、自分らしさを貫こうとする姿でした。しかしそんな「最強のふたり」も、Deep Southではそう甘くないと、身をもって経験することに。
このロードトリップを経てTonyの差別意識が変わるのは想像に難くないですが、Shirleyの態度も変わりました。
天才が故の孤独はありがちな気もしますが、自分をそこら辺の奴らと一緒にしないでくれ!というShirleyのプライドにより、お高くとまっている雰囲気がありました。上流階級の白人と同等かそれ以上に、どれだけ品位と教養を身につけて挑んでも、受ける待遇は改善しないことへの憤りから、むしろ彼自身、下品で粗野なTonyを見下していた節もあったのではないでしょうか。肌の色が違ったらもっと自分の音楽は評価されていたのだろうかー Shirleyもきっと自問し続けたでしょうが、孤高の玉座から降りて黒人達のバーで演奏するのも悪くはないと、彼も壁を取り払って柔軟になれたようでした。
違う世界で生きてきた2人が得てきたものは異なるけれど、それが互いに良い学びになっていました。
このコンサートツアー、実は1年半ものロードトリップだったそうです。2人のピンチを救ったあの電話は、ケネディ大統領暗殺の数日前だったとのこと…。
同姓同名かなと思っていましたが、Tonyは本当に俳優だったんですね。
“Green Book” のGreenは作成者の名字が由来ですが、本も車体も、途中で「拾った」翡翠のような青緑色で、平和と調和をもたらすようなお守りでした。
“You don’t win with violence, Tony, you win when you maintain your dignity.
Dignity always prevails.”
“Don’t wait for him, Doc.
This I know...the world’s full of lonely people afraid to make the first move.”
楽しめました
文句なし、素晴らしい傑作
余韻を楽しめる
全942件中、701~720件目を表示