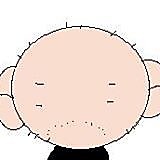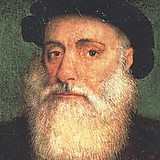ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオスのレビュー・感想・評価
全34件中、1~20件目を表示
音楽を愛し、翻弄され、愛された人生
もうこの映画の何に感謝したいって、オマーラ・ポルトゥウンドとイブライム・フェレールの若き日のテレビ出演映像と、大切な思い出として回想するオマーラの顔が見られたこと。
ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブに参加した時に、唯一現役バリバリのスターだったオマーラと、ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブがなければ、音楽を捨てて忘れられていたかもしれないイブライム。その二人の過去とその後を描いたことで、音楽を愛し、音楽に翻弄され、音楽に愛された人生そのものが浮かびあがった気がした。
ドキュメンタリー映画として秀逸であるとか、なにか突出しているとまでは感じなかったが、キューバという国の歴史と現在の変貌とが背景に据えられたことで、ひとつの音楽の盛衰を俯瞰するような感慨が湧いた。
キューバ音楽の歴史と精神を学べるが、音楽の魅力は前作に軍配
W・ヴェンダースが監督した前作は、長く活動の場に恵まれなかったベテラン音楽家たちが米国人ギタリスト、ライ・クーダーの呼びかけで集まり、セッションやコンサートの場を久しぶりに与えられて生き生きと演奏する姿と、キューバ音楽そのものの魅力を伝えることに主眼を置いていた。
今作はキューバという国の歴史を紐解きながら、同国固有の音楽の発展と不遇の時代を示すことで、音楽の精神の領域にまで迫ろうとする。さらに楽団のメンバーたちに個人史を回想してもらい、革命と西側との断絶に翻弄された彼らの人生を浮き彫りにする。高齢のメンバーたちゆえ、長年にわたる取材の中で1人、また1人と他界していくのがなんとも物悲しい。いや、人生の終盤で一花咲かせたことを祝福すべきだろう。
オーディオビジュアル的な観点からは、近年のコンサートなどを高画質・高音質で収録した映像が乏しく、名演を満喫するとまではいかないのが惜しまれた。
歌い続けて生き抜いた人達
【BVSC☆アディオス、そして、オラ】
ヴィム・ヴェンダースの「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」のレビュータイトルを、”音楽の原点”と書いたが、実は、なぜかは、こちらの映画で触れられるので、その精神的な背景は記したつもりだが、具体的なことは書かなかった。
キューバ音楽の「ソン」は、原住民が滅ぼされ、アフリカから奴隷として連れてこられた黒人が、作った音楽だ。アフリカの鼓動とヨーロッパの音楽が出会い、融合し、その後、ヨーロッパだけではなく、アメリカの音楽にも大きく影響を与えたのだ。
「なぜ、こんな悲しみの歌を、世界中の人々は支持するのか」
キューバ音楽ソンの多くが悲しみの歌だ。
ヨーロッパが進出してきて、原住民の多くを殺害、アフリカから奴隷として連れてこられた人たちが、現在のキューバ人の祖先だ。
独立のための闘い。
多くの同胞が死んだ。
もともといた原住民も含めて、ソンは鎮魂歌なのだ。
しかし、決して暗いことなどなく、明るく生きようとする力を内包している。
だから、「火事だ、火事だ、俺は燃えている!」と歌うのだ。
ソンは、悲しみを乗り越えたことを伝えるキューバ人に流れる血のようなものだ。
だから、決してなくならない。
歌は魂。
こうしたことが背景にあって、カール・マルクスの社会主義思想が、キューバに根付いたのかもしれない。
過度な利潤を追求せず、格差を好まず、暴力には屈せず、平等で、穏やかに暮らせる世界。
ハバナ・カール・マルクス劇場での”ラスト”・コンサートとは言うが、1999年のヴィム・ヴェンダースの映画撮影から、BVSCの多くが亡くなり、でも、新たなメンバーも加わった。
アディオスだが、オラ!
オバマが端緒をつけた国交正常化を、トランプが放棄してしまったが、再び、良い流れが来ることを祈る。
このBVSCアディオス公開前に亡くなったフェレールが、ヴィム・ヴェンダースのBVSCで、カーネギーホール・コンサートの後、「実は、ニューヨークは憧れだった。英語はこれから勉強する」と言っていたのを思い出した。
この音楽を聴きたい人は世界中にきっと多くいる。
次は、BVSCオラだ。そう信じている。
【キューバ・ミュージックの素晴らしさを大画面で再認識し、「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」のメンバーのその後を鑑賞させていただき、感涙に咽ぶ。】
見事な続編
アディオス…
ありがとう
そうか、あれからもう20年も経とうとしているのか。
もともと爺婆映画好きな私だが、大学生の頃に出会い、年寄の魅力以上に衝撃を受けた本作。
ダンサブルなラテンのリズムと哀愁たっぷりのメロディ、そして爺さんと婆さんならではの渋さと色気と軽妙さ、人生の深みにガツンとノックアウトされ、アルバムをひたすらリピートして聴いた。
本作に出会わなかったら、私の人生は少し変わっていたんじゃないかと思う。
本作はメンバーたちの人生にぐっと近づき、よりドキュメンタリー感が強かったのだけど、イブラヒム・フェレールのあの哀愁そのもののような歌声と、彼のこれまでの人生とが重なって、涙なしには観られなかった。
前作でも、音合わせで空気が変わる瞬間に感動したが、本作のライブシーンにも心が震えた。
本作が世に出て、ヒットして本当によかった!
日本の民謡にも通じる市井の人々の歌の豊かさと力強さに、彼らの存在を通じて気づいた人も多いんじゃないだろうか。
音楽史に永久に残るであろう偉大な人々たちよ、素敵な音楽と人生経験をありがとう。そしてさようなら。
音楽とともにある日常を描く
1998年のヴェンダースが監督した「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」の続編。
バンドのメンバーも(さらに)年を取り、また鬼籍に入った者もいて、“最後のツアー(アディオス・ツアー)”に出ることになった…という触れ込みだったので、そのツアーの演奏を楽しむ映画かと思ったのだが、そうでもない。
キューバ音楽の歴史とその背景となる政治史、そこに重なるミュージシャンたちのライフヒストリーが描かれる。
世界的なヒットとなった前作に至る経緯が描かれ、ちょっと前作のメイキングっぽい趣き。
ホワイトハウスでの演奏シーンなど、ヤマ場はあるにはあるが、さほど盛り上げては描いていない。
このメリハリのない演出に退屈を覚えるかも知れないが、その抑えた筆致に“日常性”が感じられるのも事実。
キューバのミュージシャンたちは、偉大ではあるが、超絶した存在とは違う。
世界ツアーやホワイトハウスなど特別なステージではなく、日常を過ごしながら、そこに存在しているのがキューバの音楽なのだ。
キューバのディーヴァ、オマーラはこう語る。
命を奪うことは出来ても、人から歌を奪うことは出来ない。
なぜなら、人にとって歌うことは自然なことなんだから。
キューバの革命的ビッグバンド
らしく、グラミー賞を獲るなど、かなり一世を風靡したようですが私はその御高名を知らず、これの前作も未鑑賞でして、 、
自分がファンのアーティストのフィルムならさぞ楽しめたでしょうがそうでもなく、この作品に関しては映像やサウンドにかなりノイズの入った古い資料映像から拝借している場面が結構な時間あり、それにちょっとうんざりして楽しみ辛かったです。
🎶ジャンルも好みでもなんでもなかったのに何故観に行ったし⁉️
趣味で音楽を少しかじっている姉が良かったよ〜とお薦めしてくれたから期待大で行っちゃいました😳
彼女曰く、登場したギタリストなども知っておったようで、また95歳で亡くなられたコンパイさんなんてとてもsexyなんだと。
ちなみに妻は良かったと言っておりました(が、彼女にしては低めの65点だと)。
本題とは外れますが、今のキューバ人というのは元々そこに居た現地人を、一人残らず皆殺しにしたスペイン人の侵略者と彼等が連れて来たアフリカ人の奴隷達の末裔なんだそうです。そこはちょっと引いてしまいました。
音楽が産まれる時
☆☆☆★★ 《人の命は奪えても、歌を奪う事は出来ない》 アフリカか...
☆☆☆★★
《人の命は奪えても、歌を奪う事は出来ない》
アフリカから、奴隷としてキューバに移住して来たのをルーツとする、キューバ人としては。歌を歌い続ける事は、人生を生き続ける事でも有る。
1998年に、世界中でムーブメントを起こしたBVSC。
初期の主要なメンバー達の、ムーブメント後のその後から。現在未だに進行中のツアーまで。まだまだこのBVSCが発展を続けながら走り続けているのを余すところなくカメラは密着する。
最初のムーブメントから、社会情勢は大きく変化。
その後に、かっては敵対関係に有った、アメリカとキューバとの関係は一気に氷解。
2国間での国交正常化に於いて。如何にこのBVSCによる音楽の力が、それに貢献して行ったのか…を、分かり易く映し撮っている。
作品中には、主要だった初期メンバー数人のその後が詳しく描かれており、それこそはまさに人生を謳歌した姿が収められていた。
上映終了後には多数の拍手有り。
これは国境を越えた人生の賛歌。
2018年8月19日 TOHOシネマズ/シャンテシネ3
すごいなー、と。
「期待以上でした」
踊らにゃソン
前作に比べると、過去の映像の引用やキューバの歴史も俯瞰して、注釈編というか「メイキング・オブ〜」という趣もある。ある意味、点鬼簿でもある。
ラテンのリズムに強烈な牽引力があり、いつまでも聴いていられる感じ。ホーンセクションの入り方もたまらない。
一番印象に残るのは、イブライム・フェレールで、あのクシャっとした顔でステップを踏みながら美声で歌うところに、得も言われぬ魅力がある(憂歌団の木村充揮にも似ている)。ずっと靴磨きなどで糊口をしのいでいたというエピソードもすごい。
ホワイトハウスでの演奏も、キューバとの国交正常化を果たしたオバマの時代ならではのことで、トランプが見たらさぞ苦々しく思うだろうな。
gracias!
今はなきシネマライズで「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」を鑑賞したのは20代の時。老人の概念が変わり、歳をとることが楽しみになった。私もあんな風に歳をとりたいと憧れた。そして40代の今になって、18年後の彼らと再会する。
18年後の彼らは、よぼよぼになりながらもやはり人生を楽しんでいた。亡くなる直前まで人生を全うしていた。だけど私は20代の時よりも18歳も歳をとり、人生を楽しむ事が難しいことなんだと知ってしまった。人生には色々な困難が待ち受けていると分かってしまった。だからこそ、彼らとの再会は「自分の人生を生きる」ことを改めて考えさせてくれる良い機会となった。まさかまた彼らに会えるなんて思ってもみなかった。
大好きな「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」。私はあなたたちの暮らしているキューバを見たくて、行ってしまう位好きでした。adiósそしてgracias!いつまでも忘れない。本当にありがとう!
好き嫌いでいうと嫌い!
音楽にそれほど関心ないし ブエナビスタと言えばG1馬だし 見るものなかったので見た
評価は良いけど このテ映画は媚びた評価になりがちだから信用できないし でも車を運転してる時に オオタキエイイチとかアライユミ流れていると なぜか心地良いという よくわからない力が確かに音楽にはあるし
ひょっとしたら とてつもなく感動するかも そうじゃなければ寝るかも
結局 そんなに感動もしなかったし かといって寝もしなかった
この寝なかったということが大切で
フツウで何も起きないし とてつもないことが起きるという絡み合った事実を また自分たちの思いとはかけ離れたところから自分たちの音楽が評価されたことに抱いた違和感も 時流がまるごと呑み込んで行くさま を淡々と描いているだけ 人はみんな死ぬので悲哀があるのはあたりまえ
なんだけど 映画はドキュメンタリーには ひょっとしたら勝てないかも と一瞬思わせる 力強さはあったかも
好き嫌いでいうと
嫌い!!
20年弱を経ての後日譚...では無かった!
ライ・クーダーがリリースしたキューバの老ミュージシャンとのコラボレーション・レコーディングを基に、ヴィム・ベンダース監督がメガフォンを取って製作された1999年の音楽ドキュメンタリー映画「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」から20年弱の歳月を経た姿を映したドキュメンタリー作品。コンパイ・セグンドなどの前作の中心となった何人かを他界により失い、残されたメンバーと後継者達からなるグループによって行われる最後のツアー「アディオス」ツアーの模様を中心とした、「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」続編であり完結編と言える内容。今作では、前作でスポットの当たらなかったミュージシャンの人生も捉えて、より多くのメンバーの足跡を辿り、志半ばで逝ったメンバー個々のパーソナルな部分にも触れている。これで「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」は終焉するのだろうから、そりゃセンチメンタルな部分はあるが、悲壮感が微塵も感じられないパワフルな演奏は、熱い魂が炸裂する熱すぎる音楽でした。その熱さを感じて意思を継ぐであろう次世代のミュージシャンにより、その後もキューバの音楽は熱く鳴り響いていくのだろうという期待を抱かせる。ちょっと切なくて、でもものすごく熱い作品でした。
全34件中、1~20件目を表示