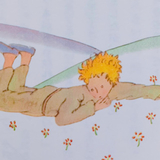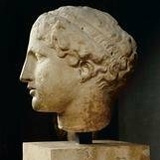日日是好日のレビュー・感想・評価
全311件中、61~80件目を表示
本を読んでから観ました。
私は原田マハさんの本を読んでから最近映画を観ました。
このお話は大好きで、「一期一会」の大切さをとてもよく教えてくれるお話です。
お茶の一つ一つの入れ方に主人公は「なぜ?」と意味を聞くシーンがあります、映画ではその一つ一つの細かいお茶の入れ方や作法を細かく話す樹木希林演じる先生が
見ている私も思わず「なぜこんな面倒な淹れ方なのかな」と問いたくなるようなシーンになっており、とっても良かったです。
まるで主人公と一緒に、お茶を習っている気分になります。
ネタバレになりますが、私がこちらのお話を読んで観て思ったのは
考えるより感じろ、ということかと思いました。
日日是好日という言葉はその日をありのままに。
という意味がありますが、まさにその時その日を感じ、ありのままにいること
それがとても大事なことなんだと思わせてれるお話です。
自粛期間中、「やることがない」「つまらない」と思いがちですが
そんなことはなく日々の些細なことに楽しみやその時の幸せがあるということ
とても深くて素敵なお話でした。
樹木希林さんの演技は本当に素晴らしいです。
引き込まれます、本当にお茶をやっている先生みたい。
黒木華ちゃんの演技も、原作の主人公とピッタリだと思います。
後半がいい
疲れたとき、困ったときは、
メリル・ストリープ(米)
ヘレン・ミレン(英)
樹木希林(日)。
頭でばっかり考えてはいけない。
五感を使って感じることも大切。
沁みた。
そして、話には聞いていたお茶の四季を垣間見られたのも楽しかった。
やめたくなったらやめればいい。
美味しいお茶を飲みにくればいい。
あんな言葉をかけられる人になりたい。
綺麗になる黒木華。
モチベーションを感じない
お茶事の稽古を通して二十四節気の巡りと主人公の人生を淡々と描いた映画。
こう書くと綾鷹かおーいお茶の映画のようだが、果たしてそういう想像を上回れたかどうか。結論から言えばそれは叶わなかったようだ。
ありふれた街並み。畳に座って悟達の域に達してるいつもの樹木希林。和の季節感と人生・日常生活。こんなお題が並ぶと是枝監督を否応なく想起するし彼はそういうのを非常に上手く撮るが、この監督はちょっと狙いすぎて失敗したように感じる。
茶器やお菓子はとりあえず正面からアップのインサート。庭や自然はハイビジョンテレビやビールのCMのような綺麗なだけの撮り方。風景も小道具もセリフも全て深みがありそうでない。一言で言えば記号的だ。あえてそうしたというよりは、監督があんまり茶道や日本の芸道を通して感得する世界観や美意識を汲み取れていないと感じた。
主人公の32まで独身実家暮らしのアルバイターの身分でのほほんと毎度新しい着物着て茶道教室に通い続けているというのはかなり特殊な事だと思うが、そんな彼女の私生活については全然掘り下げずモノローグでぶつ切りに挿入されるだけ。完全に観客置いてきぼりで、今どういう状況・心情なのかも年月ごとの心情の変化もさっぱり分からない。共感どころか彼女についてほとんど何も知ることが出来ない。最低限そこはしっかり描かないと人生の「道」感が全く伝わらないと思うのだが。それは原作エッセイで補完してねという事だろうか?だとしたらこの主役のいる意味とは何なのか。
フェリーニフェリーニ言ってるが時が経たないと分からないものの象徴みたいに扱うのは失礼だ。彼の代表作『道』とこの映画を重ね合わせようとするのも本当に失礼だ。
最後にモジって締め
「この映画で起きることはいつも突然。心の準備なんか出来ない。後はその悲しみに2時間をかけて慣れていくしかない。」
お茶の時間
まさに、お茶のような映画
派手さはないが、観た後色々考えてじんわりしみてくる映画。
これはエッセイが原作なんですね。まさか、こんな長いスパンを描いているとは思わず観たので「20年も時が経ったの?!」と驚きましたがなるほど。
人生山あり谷ありの中で、いつでもブレない習慣があるのって良いなと思いました。
お茶は、一期一会をかみしめたり(映画の中でも言われていた「この人とはもう会えないかもしれない」ということ)、季節を味わったり、昔の人には色々意味があったのでしょうね。
最後は世代交代を思わせる終わり方で、樹木希林さんが亡くなったこととリンクして深い余韻をかんじました。
茶道つええ
この映画を見ると、厳格な作法の指導者たる人物は、意外におおらかな性格を持っているものだ──という仮説を容易に信じることができる。
それは、むろん、お茶のことだけではない。
たとえば、わたしたちが、かつて出会ったことのある、柔/剣/弓道の師範だとか、あるいは禅僧だとか、あるいは、商業でも農業でも工業でも、その仕事の技術を極めた達人は、もはや厳しさを通り過ぎて、まるで樹木希林のように朗らかで鷹揚なことが、往往にしてある──ものではないだろうか。
その道のプロや、本物なひとほど、その外観や、性情に、丸みを持っているものではないだろうか。どんな分野でもいいが、そんな古豪に出会ったことはないだろうか?
もちろん性格も教え方も厳しい教官もいるが、あんがい、すごいひとほど爪を隠すことを、わたしたちはけっこう知っている。
本作の樹木希林は、そのことを、思い起こさせる。
ところが、樹木希林は女優であって、お茶の先生ではない。
それを、忘れて見ていた──わけである。
それは演技力ではない。と思う。
樹木希林は「演技」をしているだろうか?
じっさいはどうなのか知らないが、演技をして、それをもって、役に寄せている──とは、思えない。
晩年、印象的だったのは駆込み女~や母の記や万引き家族の樹木希林だが、あれらが演技によるものとは思えない。
なんていうか、それを演技だと言ってしまうなら、あまりにも泰然自若すぎる。
そもそも「そうでない方はそれなりに」で大流行したフジカラーのテレビコマーシャルの岸本加世子とのやりとりでも樹木希林が演技していた──とは思わなかった。
雰囲気に「絶対的な日常」を持っていて、カメラの前で演技しても、それが演技に見えない人だと思う。
その凄みが、この亡くなったのと同年の映画にも余すところなくあらわれていた。
ところで、わたしはお茶のことはぜんぜん知らないが、本作を見ると、お茶の作法を習得することによって、お茶の作法が習得できる──だけではないことがわかる。
つまり典子(黒木華:演)が、そうしたように、人生の岐路で何かの決断をするにあたって、なんの関係もないはずの茶道が、彼女に雄弁な助言を与えていることが、わかる。
また、大切な人の死にたいする悲しみを茶道が癒やすことも、わかる。
だからこそ、それが道と呼ばれるゆえんも納得できる。
20代30代にお茶を習いはじめ、そのことと自分の人生の出来事を、強引に重ね合わせている──わけではない。
ほとんど必然的に、茶道の精神が、人生を扶け、活性化させてきた──と、この原作者は言っているのである。
それが「日日是好日」につながっている。
ただし、父が倒れた──に至る描写はかなりフラグ立たせて、感傷におとしている。
原作未読なので比較できないが、監督のカラーも入っている(と思われる)。
しかし本作にあらわれる、大森立嗣監督のカラー(個人的に大森立嗣監督のカラーだと思われる描出)は、他の同監督の映画よりも、はるかに少なかった。
──のでよかった。
茶の湯を催して、静寂閑雅の境地にはいる・・・。
わたしには風雅のかけらもないが、千利休にいたって大成したその道が武家時代の必修作法だったのは、まぎれもない事実である。
たとえば戦(いくさ)のような場面でさえ、雌雄を決するのに、それ(茶道)が作用したかもしれない。
もっと単純に解釈するなら、作法が乱れるならば、平常心をうしなっていると、自分を顧みるバロメーターになり得る。のが茶道だと思った。
原作は未読で、原作者についても、よく知らないが、映画中「それでもやがて、私みたいな人をフリーライターと呼ぶようになって、あせることはなくなった」というナレーションがあったので、おそらくフリーライターの草創のような人物なのだろう、と思う。原作も読んでみようと思った
なんか浮かばないタイトル
うまい言葉が何も浮かばないけど、
いい映画だと思います。他の人のレビュー読んだら、なるほどなと思いました。緻密に繊細に作り込まれた映画なんですね。
僕は、知識もないし、いいレビューもかけませんが、思い浮かぶことを自分の記録として羅列します。
日本古来の伝統。お茶って千利休からなのかな。調べたら千利休は戦国時代や安土桃山時代の人でしたね。
鶴田真由が劇中で言っているように、昔、電話も何も、無かった時代、一度人と分かれると、次にいつ会えるかわからない、そんな時代では、お茶は一期一会だった。
お茶は四季や日本の行事、伝統も関係しているんですね。
雨の日でも雪の日でも寒い日も暑い日もその四季や自然の音などを感じ、あじわい、たのしむのだ。だから毎日が良い日なんだね。
淡々と映画は進む。急展開やどんでん返しなんてない。ただただ日常があり、ただその中で主人公は、就活、友達の結婚、失恋、父の死があり、彼女の長い年月がお茶とともにあった。12年は長い話だ。
こういう、しみじみした映画もいいです。映画っていろんな映画があり、多様性があるからいいですね。
フェリーニの映画を子供に見せる・・・?
すぐ理解できることはすぐ行き過ぎていくけれどもすんなり入らないことはゆっくり入っていく・・・ようなセリフが最後の方に出てきます。
映画の冒頭にフェリーニの「道」という映画を見たエピソードは映画の途中と最後の方に出てきますが、先のセリフとフェリーニの映画を子供に見せることと話は違うと思うのです。そこが最初引っかかってしまってのどに魚の骨がひっかかるような違和感が映画を見ている間ずっとありました。
お茶の作法に意味があるか、順番を覚えることに一生懸命になっている主人公たちですが続けることによって理解できてくるところがある、そういうことなのだろうと思います。私は子供のころ習字を習っていましたが、高校生の授業の時に書道をしたときは墨をすって授業の開始を待つまでのひと時が心を落ち着ける作業なのだと自然と理解できていきました。子供のときに墨汁で半紙に書いていたときとはまるで異なりました。無駄な作業のように思えることも実は無駄ではなく、儀式でもなんでもそうですが、それに伴う作業や衣装をみにまとっていくことによって普段の自分から少し離れて、心構えのようなものができていくのだ、と今では理解しています。
最近ソロキャンプが流行りで動画を見ると小川のせせらぎに癒されるというコメントが多く見れます。私もその一人です。この映画ではさまざまな水の音を聞かせてくれます。わいたお湯をお茶碗に入れる、水をお釜に入れる、季節ごとの雨のさまざまな音。さみだれ、しぐれ、はるさめ、日本語にはたくさんの雨の呼び名がありますが、雨の呼び名に限らず、言葉の種類が多い対象はその言語を使う人種とのかかわりが深いのだと聞いたことがあります。昔の日本人は雨を単なる「天気が悪い」現象とは思わず、家の中でその物音を聞きながらゆっくり生活をして思いを巡らしてつきあってきたのだと気づきました。
茶道から生まれた言葉「一期一会」。映画の中でも語られますが、昔は今ほど簡単に会うことはできない、特に遠方の人とは、もう一生会うことは無いかもしれないという出会いは現在よりもっと多かったであろう、だからこそ生まれた言葉なのでしょう。現代よりも昔の人の方が1日1日を大事に生きていたのだろうと思いをはせました。この映画のタイトル通りだと思います。
あまり興味を持って見始めた映画ではなかったのですが、思わぬ拾いものをしました。これは樹木希林さんに負うところが大きいと感じます。お茶を点てる姿、正座している姿、手をついておじぎをしている姿、どれも自然体で演技ではなく、にじみ出てくる感じでした。いい役者さんでした。
記録用
和の心地よさ
無駄なことこそ美しい
1人の女性の20年の成長物語をお茶を習うことを交えて描く映画。
.
最初、多部ちゃん演じる美智子と典子が2人でお茶を習っていくんだけど、その先生と2人の雰囲気が絶妙に居心地が良くてずっと見てられる。樹木希林と2人の空気感めっちゃ良い。幸せな女性たちだけの時間。
.
お茶という渋い題材を扱っていながらも、割と若い世代も楽しめる映画だと思う。お茶を習いたいなとは残念ながら思わなかったけど(笑).
.
大森立嗣監督ってこんなに優しい映画を作ったかと思えば『Mother』『タロウのバカ』みたいな過酷な現実を描いたのもあって、情緒不安定すぎて(笑)でも、一人の人が成長or変化していく姿をじっくり描くというのは全部同じなんかな。
.
無駄なことこそ大切みたいなお茶の考えも、『セトウツミ』の無駄な時間を過ごすことが青春ってのと一致するし。色んな人の人生をじっくり見つめるのが上手い監督なんだな。
まずまず
コロナで疲れた今だからこそ
コロナでいろいろな価値観が変わろうとしてる今の世の中にまさにぴったりでした。まるで、導かれて作られたように思えました。
今まで私たちは心に空いた穴を埋めよう、何かを手に入れて満たそうとするやり方が当たり前になっていたと思います。
この映画を観て、ひとつの物事を丁寧し感じることの豊かさを知りました。私たちは毎日窮屈な日々を過ごし、四季が移り変わりや人ただ時間を過ごすことで心を満たす術を持っておらず、必死に心を埋めようとして埋まらないを繰り返していると思います。
雨はうっとうしく雨音を楽しむなんて考えにもならず、寒さの厳しい日は春が待ち遠しくなり、寒い中でこそ感じる楽しみに気付けていないと映画で知りました。
この映画を観るまで、日日是好日の言葉さえ知りませんでした。映画でその意味を丁寧に教えてくれています。
鑑賞した人がこの思いを受け取って、毎日自分らしく幸せに過ごせていけたらいいなと思いました。
序盤は茶道の所作の教材のビデオみたいで、難しそう…となるのですが、等身大の主人公たちなので追体験が出来てどんどん引き込まれてました!
本格的な茶道のお話ですが、興味がなくてもこの映画を通じて、様々な事が見えてきました。人生について考えさせてくれる素敵な映画でした。
よかったね華ちゃん 樹木希林さんと共演できて
大森立嗣監督作品ですが、原作があります。女性目線を崩していないのですが、自宅から30分のアパートに引っ越してから、鶴見晋吾のお父さんがちょっと近くまで来たから寄っていいかと電話をかけてきたけど、今日は用事があるから、ごめんなさいと断るけれども、夜、気になって自宅に電話するシーン。お母さんが出て、今日お父さんから電話もらったんだけど。お父さんもう寝てしまったよとお母さんに言われて、電話を切ったあとに、典子が、あ"ーっと叫ぶシーンがあって、数日後にお父さんが亡くなります。あ"ーっは何を思って、あ"ーっになったかが、気になって仕方ありません。用事はドタキャンになって、それならお父さんと会えば良かったという、あ"ーっだったんでしょうか? 新しい恋も実らなかったことを間接的に表したのでしょうか。お父さんが亡くなったあとにも、回想シーンであ"ーっがあります。前後の静かなシーンと比べて、ちょっと違和感があって、、ナレーションでもいいから、説明を入れてくれれば良かったです。
鶴田真由さんも復帰していて、とても良かったです。
樹木希林さん、ありがとうございました。
華ちゃんのいろいろな表情や髪型を着物が見られて良かった。二十歳から10年ちょっとの間を演じて、全く違和感ないのがすごいですね。
樹木希林さんの一期一会の話しが重くて仕方なかったです。
日日是好日 にちにちだったんですね。日々是精進のわたし。
葉脈のなかで動く葉緑体の映像がきれいでした。
全311件中、61~80件目を表示