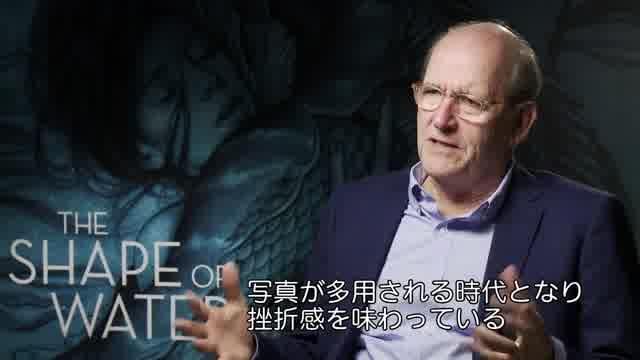シェイプ・オブ・ウォーターのレビュー・感想・評価
全668件中、41~60件目を表示
入り込めなかった
監督が、美女と野獣で野獣が最後にイケメンになるのは
納得がいかないとインタビューに答えているのは、
私も同感なので期待して観に行きましたが。
美女と野獣の場合は、まだ見た目が野獣であっても、
中身は人間なので、知的な交流や理解があった。
そこに愛情が生まれたとしてもそれほど疑問は感じなかった。
しかし、この映画では、いくら多少の言葉理解力があるとはいえ。
あの程度では犬や猫が人間の言ってることを多少理解してるレベルでは?
明言はされていないけれどもヒロインも同種では?という
匂わせがあるので、言葉が無くても通じ合えるって
言いたいのかもしれないけれど、だとしたらそれをもっと
全面に出してもらわないと、ペットを性欲処理の対象にしちゃった感があって
違和感もだけどまず気色悪く感じてしまった。
もう少し半魚人が人間的交流ができる相手であったら、
声の出ないヒロインが自分の気持ちを歌い上げるイメージ場面が
とてもいい場面に思えただろうと残念。
画面はきれいだし曲も良いのにもったいない。
社会的弱者
口のきけないプリンセスと、捕らわれの両生類の《究極の愛の物語》
私とは不思議と波長が合いました。
とても感動しました。
第90回アカデミー賞で作品賞他4部門受賞作。
ギレルモ・デル・トロが監督・脚本・製作を手がけました。
口のきけないプリンセスは、美しくもなんともない中年の、
孤独な清掃員です。
イライザ(サリー・ホーキンス)が勤務する政府の極秘研究所に、
不思議な生き物が運び込まれます。
大きな機械仕掛けの水槽に入った生き物・・・
アマゾンの神と崇められる半神半魚の両生類です。
そおっと覗いたイライザは、
手話やアイコンタクト、そしてゆで卵のオヤツ、
そしてプレイヤーでかける音楽とダンスで、心を通わせるのです。
魔物と人間の禁断の愛です。
(なぜそんなことが可能なのか不思議ではありますが、
(私はすっかり映像と音楽の魔法にかかってしまいました)
しかし幸せは長くは続きません。
研究所の責任者で軍人のストリンクランド(マイケル・シャノン=怪演)は
怪物を殺して解剖する・・と決めるのです。
この辺りから映画はダークファンタジーからサスペンスに
大きく舵を切ります。
しかしイライザは同僚のゼルダ(オクタビア・スペンサー)と、
友人の画家ジャイルズ(リチャード・ジェンキンス)の助けを借りて、
怪物を助けようと計画するのです。
この映画は異形の生き物と人間(?)の女性の愛の物語です。
イライザは生き物とプラトニックではない、本物のセクシャルな
愛を交わしますし、サリー・ホーキンスは全裸の可憐な裸身を
さらすのです。
(パディントンのブラウン家のお母さんの、何という一面でしょう!!)
そして付け加えたいのは音楽の美しさ。
場面場面に合った歌い上げるミュージック・ナンバー。
(実際に、ホーキンスが歌い踊る夢の中のシーンは、ミュージカル映画です)
まるで『シェイプ・オブ・ウォーター』は水の魔法にかかった映画です。
私は最初から夢見心地でした。
(感動を共有できたら嬉しいです)
「アメリ」に似ていたことは許すとして
猫を食うのなら、頭からは食わんでしょう。普通、肉食動物は、内臓から食うよ。脳みそ好きなのかな、なかなかのグルメ。
まぶたとは別に、半透明の膜が目にあったけれど、あれは「瞬膜」。サメ類・両生類・は虫類・鳥類・一部のほ乳類にある。腹筋に見える模様が腹筋だとしたら、ほ乳類。パカッって開いて、ペ○スが出てくるのは、イルカやクジラと同じだ。ひれは当然、魚類。ウロコっぽい物が、はがれてもきていた。2つの呼吸法は、よくわからなかったけれど、ハイギョっていう魚類と同じかな。総合的に考えると、魚類が近い感じはするけれど、頭なでてもらうと毛が生えてくるっていう魚を聞いたことはないので、微妙。そんな魚、わたしも飼いたい、なでてほしい。
3~5%濃度の海水で飼育、とホフステトラー博士がイライザにアドバイスしていたように思う。アマゾンで捕獲設定だったと思うけど、ならば、淡水で飼育しなきゃ。汽水域で捕獲?でも、1960年代にあんな大型の生物が、ジャングルの奥地以外で発見される、というのもちょっと不思議。それに、バスルームを水浸しにして愛し合うシーンでは、塩がどれだけ必要だったか、たくさん買い置きしてあったんだね~ぇ。
「ロケットに乗せて宇宙に飛ばす」アイディアはナイス。ロケット内では肺呼吸させる?それとも海水を宇宙に送り込む?ちょっと重いけど。
この物語、半魚人と人間の女性の愛の話、ではないでしょう。
イライザの首の傷、あれはもともと彼女が、エラの痕跡というか、未使用のエラをもっていた、ということだと思う。川に捨てられていた孤児だった、というのだから、もしかしたら半魚人と人間のミックスだったのかもしれない。だから、半魚人と同じように音声言語を使わない。食いちぎられた指もけっこう平気。卵好きも共通の性質?お風呂にはいるとオ○○ーしちゃうのは当然。そして、当たり前に半魚人に心惹かれていく。最後にエラが開眼したのは(開鰓したのは、か?)、彼女の本来の居場所を見つけた、ということだと思うのです。
黒人、ゲイ、ろうあ者、掃除夫。半魚人は、差別を受けるマイノリティーのメタファー。イライザの「わたしの話をちゃんと聞いて!」という言葉、もっとも大切なメッセージなのでしょう。
自分にはあんまり…
悪役が胸クソ悪い。本当に見ていて気分が悪くなるほどひどい。良いテーマなのに胸が悪くなるシーンがあまりにも多すぎた。作品自体は悪くなかったけど、1回見ればいいかな…全体的にそんなに面白いとは感じなかった。好みの問題かな。
無駄に甘ったるくないのは、とても良かったです。性のことや夫婦のこと、男女差別やマイノリティへの差別、貧困など、綺麗事が無い中で展開される愛の話であった点が良かった。
ただ、あんなに傷が簡単に回復できるのであれば、魚人がラボで拘束されている時に研究者たちが真っ先にその神の力に気付きそうなもんだけどね。棒で殴られたり電気で折檻されたりして流血するようなケガを負ってたんだから。あと、イライザが「良い人ね」って言ってた研究者、魚人を連れ出す時に人を殺してますけどね…あと、イライザの急なミュージカルシーン。テレビで、ダンスや歌が写るシーンはたくさんありましたが、効きが弱くてやや唐突に感じてしまいました。
魚人が段々可愛らしく見えてくる。
撮影大変だったろうな…魚人スーツ着て、女優さんもいっつもびしょ濡れ。ラストシーンも雨でずぶ濡れ。
異形だからこそ純粋な愛のカタチ
デルトロはホント期待を裏切らない。
モンスタームービーでここまで純粋な愛のカタチを描くなんて誰が想像しただろうか。
モンスターながら、不快感を感じない「彼」のデザイン。「彼」に出会ってから、明らかに美しく変わっていくイライザ。ともすればグロテスクになりかねない異種の交わりさえロマンチックに、上品に描いている。
正直、現代の映画を見慣れている我々は、人間ぽい別の生き物を異性としてみる事にすでに慣れている。マーベルにしても、スタートレックにしても肌が緑だろうが、多少トカゲっぽかろうが、それらの恋愛事情を普通に受け入れている。これは多様性を受容できるようになってきているということなのだろうか。
何にせよ、本作が名作である事に変わりはない。
って、まぁアカデミー賞4部門も取ってるんだもんね。
レトロなSFチックさ
【恋愛映画ではなく、唯一無二の存在との邂逅映画】
◉好き嫌いが分かれる絶妙なラインの映画
好きか嫌いかで聞かれれば、若干半魚人に対して気持ち悪いと思いつつも映画自体は好きだと答えるだろう。特に音楽シーン(冒頭など)や水の演出、光の使い方、シーンの切り替えなど、一つ一つの細かい部分が洗練されていたように思う。
特に色使いに関しては、この映画のように黒とも白とも言えないグレーカラーの演出は、まるで人生における中年期の様相を表象しているかのようにも思える。中年期と捉えるとネガティブなイメージが浮かぶ。しかし、今作では独特の味わい深さから不快さなど微塵も感じず、ただただ映像に魅せられてしまった。最初から最後まで一気に見た映画。ビバ!中年期の美しさ!!
繰り返しになるが、改めて気持ち悪いか、気持ち悪くないかで言われたら若干気持ち悪いと思ってしまう映画だ。たびたび繰り返すのはやはり受け入れられない気持ち悪さがあるからだ。すまない。おそらく、自分が登場人物や主人公の女性に共感できていないことからくるのだと思う。
そもそも登場人物は若さという意味において美を体現した人物でもなければ、その片割れは人間ですらないわけで、現実世界からするとファンタジー作品といえる。そのため、同じ経験をすることは稀にあっても、ほとんどない人が大半だろう。稀というのは、人間ではなく、虫に恋するかもしれないし、物に恋をするかもしれないといった要素を含んでのことである。この共有しきれない経験の差によって共感に至らず、気持ち悪いと感じてしまっているのかもしれない。
◉感想
この物語は半魚人と中年の女性の恋愛という"異種族間"恋愛ストーリーのように思われるが、私はそうは思わない。というのも、半魚人と中年の女性には共通点があるからだ。それはお互いに話せないということ。この共通点において2人は異種族ではないと考える。私自身は声を使ったコミュニケーションをとることができるため、彼女の世界を真の意味で理解することは難しいのかもしれない。しかし、彼女自身が抱える葛藤のようなものはなんとなく想像することができる気がする。多くの人が声を使ったコミュニケーションを取る一方で、自分にはそれができない主人公。この映画の時代にはインターネットもSNSもないため、現代のように同じ共通点を持つ人と簡単につながることはできない。そのため、自分だけが世界から取り残されているかのように、まるで新海誠監督の映画に出てくる登場人物たちのように、自分と関わる人たちとの世界観に対して違和感を常に感じていたのだと推測される。
だからこそ、中年の女性は半魚人との声を介さないコミュニケーションにおいて、彼自身を理解しようとしたし、彼に理解されているように思えたのかもしれない。
昔の詩人は、「あなたを感じる。あなたの愛が見える。」という表現をしたようだが、まさに声ではなく、2人の間には通じ合う何かがあったのだろう。そして、それが恋愛のきっかけになったのかもしれない。しかし、これを恋愛ととるのかは鑑賞者に委ねられる。恋愛以外には「私たちは分離されてしまった片割れを求めている。」と聖書に書いてあるように、肉体の片割れを探す1人の人間(中年の女性)が、その片割れに出会った物語だと捉えることもできるからだ。
振り返れば、これは2022年2月から上映されている『CODA』とも共通している部分がある。『CODA』では、耳が聴こえる人と聴こえない人の世界観を深掘りし、それぞれが抱える葛藤にスポットライトを当てる。
耳が聴こえる人にとって感じる世界と、耳が聴こえない人にとって感じる世界は、地球という環境を共有していても、お互いが全く同じ世界を共有できているとは言い切れない。なぜなら、互いにコミュニケーションツールが異なるからである。人間は言語を発明することでコミュニケーションを容易にしてきた。
しかし、言語を介していても他者の心を読み取ることはできないし、同じ言語話者同士でも伝えないと伝わらないことがしばしば起こる。細かい点では、解釈の違いなどのずれは言葉にしなければ訂正が難しい。そういう意味では、そもそも言語における意思の疎通とは知ったかぶりのやり取りのような気もしてくる。
その一方で、声を使わない(言語を介さない)場合はどうだろう。最初から言葉のように曖昧なものに依存しないからこそ、意思疎通のために何か見えないものを通して相手を感じることができるかもしれない。
このように考えると、この物語は半魚人と中年女性の異種族恋愛ストーリーではなく、理解し合える片割れに出会い、共に生きていくストーリーといえるのではないだろうか。
テンポが良く、思ってたのよりシンプルで、思ってたよりグロくなかった...
テンポが良く、思ってたのよりシンプルで、思ってたよりグロくなかった。なまなましいシーンはあったけれど、それは重要ではなく、なくてもいいくらい。全年齢対象できるようにすればよかったのに...と思っちゃう。本当に良かった。他にいろいろ思ったのは、セットが非常に良い。そもそも映画館の上にすんでるとか良い。オーナーも好き。
ゆでたまごのせいでバレんのかと思ったけど違ってた。
ストリックランドが嫁とヤッてるシーンが一番いらない。指の血が...とかも関係なかったし、家族シーンは権力側の人間という事をいいたいのか、イライザとの対比で見せているのか。
ホフ博士は(ディミトリ)根性ありそうだったのに最後は何で喋ったかね。言わなさそうだったけど。死後に手掛かりが出てきてバレる...みたいな展開のほうがしっくりくる。良キャラだったのに、さいごイヤになった。
ジャイルズ(リチャードジェンキンス)がとても良いキャラクターをしていた。自分に忠実じゃないか。良識はあるもダメな部分が結構あってそこがまた良い。パイ屋のイケメン目当てで店に通うので、まずいパイが冷蔵庫にびっしり入ってる。ダメポイント。酒で失敗してる過去があり、ハゲを気にしてカツラをかぶる。
はじめは救出を断る。イケメンが黒人差別にゲイ差別だったので傷心→イライザ、君を手伝うよ。この流れも人間くさい。
ハゲなおったら大喜びして魚人への評価が変わるとこも人間くさい。
純愛ストーリーとしての評価が高い作品なのだけど、ストリックランドを差別と権力の象徴のように描かれていて、差別される側の人間がそれと戦う物語でもある。ラストも良かった。
グロテスクな美女と野獣?
半魚人と人間のラブストーリー。「美女と野獣」的なやつかな?と思って観始めたら結構ド直球にエロシーンがあるので家族で観る時は要注意です。
人間と異種族の恋愛ストーリーは少なくないですが、相手が半魚人となると人間とかけ離れすぎて違和感が強かったです。そもそも主人公が半魚人に惹かれる理由が良くわからないし、周りの友人たちもそれを普通に受け入れて応援しているのがありえない。どう考えても気持ち悪いです。また、軍施設の極秘機密のはずなのに、ただの掃除係である主人公が何の障害もなく半魚人と逢瀬を重ねられるのもガバガバすぎます。
おそらく「半魚人」は物語のテーマや監督の伝えたいことのメタファーか何かであって、細かいところに真面目に突っ込むべきじゃないのかもしれません。完全にファンタジーとして楽しむのが正解かな。
マイノリティ同士が心通わせる瞬間が美しい。
1960年代を舞台にした現代のおとぎ話。
クラシカルなファッション、街並、小道具、音楽のセンスに目や耳も楽しい。
主人公が恋する相手は異形の半魚人だけど、もはや本質はそこじゃない。
性的指向、人種、国籍、ハンディキャップ、色んな角度からマイノリティが描かれそのたび共感していくので、半魚人との恋もすんなり飲み込めていたのが面白い体験だった。
恋愛ファンタジーに昇華させて、美しくお洒落にレイシストを皮肉る様はしびれたし、日本ではエンターテイメントでありながらふわっと社会に異議申し立てできるアーティストは多くないのでその視点で洋画は楽しい。
互いが数少ない友人であるイライザとゲイの隣人ジャイルズとのやりとりは、温かくてピュアに互いを大切にしていて、孤独な彼らは気づかないだろうけど、こんなに美しくて幸せな人間関係は簡単に築けない。
サリーホーキンスはまるで物語の中で生きてるようで、発話障がいで言葉を持たないのに彼女の感情は手にとるように分かるし、いつのまにか彼女のことを可愛らしくて愛らしいと思っていて自分に驚いたり。
美しい恋愛ファンタジーかと思いきや綺麗におさまり切ることなく、彼らの愛が性愛なのか純愛なのか考えさせるシーンがあったり、恋愛のありのままを映して出していてとてもピュアな映画だった。
美しさと醜さ
不完全ではないわたしを。
せめてる
開幕ヌードだったり、のんびりしたスタートでヤベェおもんないかも思ったけど杞憂でした
敵役の男はワル悪の悪だったけど、一回の失敗で失脚するシーンとか前後半でズタボロになってるシーンとか見るとかなしーってなるよね
いやー愛愛してましたねって感じ。ゆで卵から始まる恋ってか
おっさんがいきなり手を取って引かれて、そんで客を追い返すシーンは情報量多くて禿げました
博士はもうフラグビンビンでしたね。生きて欲しかったけど
それを言ったら初っ端から千切れた2本の指くんも治って欲しかったけど、宿主があれじゃあな…残された家族かわいそう
かわいそうで言ったら、真面目に偽造ID見抜いた警備員君が死んでしまって残念だ
子供の頃見たら理解できてなかったな自分は。神様出てきたシーンで笑う
もし現代劇だったら、凡作になっていたであろう
悲しくて、美しくて、そして意外に楽しいお話。
半魚人と、口のきけない女性のラブストーリーという、かなりの変化球ですが、内容はおとぎ話にあったような悲喜劇。ふたりの恋が成就するのを見守っていたくなる不思議な空気に包まれています。
その秘密は、この映画の舞台をあえて冷戦下のアメリカにしたことだと思います。もし、現代のお話にすれば、よくあるモンスター映画で、「キングコング」とか、「ET」などの名作を超えることは難しいでしょう。でも、昔話にしたことで純粋に男と女の愛の形にフォーカスできたのだと思います。
同じ監督の「ヘル・ボーイ」に似たようなキャラクターがいたので、そのころからこんな作品の構想があったかもしれませんね。「半魚人と若い女性が愛し合うことは可能だろうか?物理的に、生物学的に」みたいな発想が始まりなんじゃないかと思うのですが。
オスカーノミネーションの派手な話題が先行して、ずいぶんとハードルが上がっていますが、見終わって正直それほど感動もなく、がっかりもなかったので、意外なほどフラットな心境です。サリー・ホーキンスは上手だなと思いました。並みの女優さんだと、あそこまでファンタジックにアプローチできないと思います。
2018.3.1
全668件中、41~60件目を表示










![[#D2TV]](/dbimages/profile/613830/photo_1585465394.jpg)