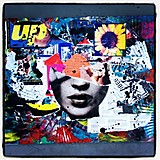ウインド・リバーのレビュー・感想・評価
全59件中、41~59件目を表示
survive or surrender
舞台はWyomingのWind River。
その一角を占めるIndian Reservationは、Arapaho族を含むIndigenous Americansが追いやられた不毛の地。
事件捜査の過程で、この地域が抱える闇の深い数々の課題が浮き彫りになっていきます。
かつてインディアンが生活の糧としていたバッファローは根絶され、多くの産業も農業も根付かず、一年の大半が雪に埋もれたような土地柄。住民達の心も凍傷にかかり、ルーツへの誇りは勿論、将来の夢も希望も凍てついているようでした。屈強な戦士の血が流れているイメージの”インディアン”の子孫が、根を上げたくなるほどの戦闘相手は、過酷な自然環境と社会問題。現実逃避したくても、娯楽すら容易に得られず酒や薬物に溺れ、大雪に抑えつけられた鬱憤と憤怒は、平穏な生活を望んでいるだけの人々からも、ようやく咲いた美しい花を無惨にもぎ取り踏みにじります。
過去に殆ど全てを強奪したのに、
再建の機会を与えることのないまま、
これからもどこまで奪う気なのだろう。
世界を変えられないなら、
この境遇で静かに強く生き延びるのみ。
ただただ、命を守るのみ。
隙を見せれば終わる残酷な弱肉強食の世界。
最後の銃撃戦が凄まじいです。
吹き飛ばす威力が、正義の怒りを表しているようでした。
共に娘を失った父親達の絆が涙を誘います。
痛みを受け入れてこそ素敵な思い出も残るのだと。
井戸水を飲んでいましたが、過去のウラン採鉱の影響で汚染されている可能性があるようです…。
エンディング曲が、凍りついた感情を溶かすような音色でした。
“Luck don’t live out here.....Out here, you survive or you surrender. Period. That’s determined by your strength and by your spirit. Wolves don’t kill unlucky deer. They kill the weak ones. You fought for your life..... Now you get to walk away with it. You get to go home.”
アメリカは田舎もヤバイ
感想は「アメリカは田舎もはヤバイ。」ですね。
法の目が届かない所に、人口が少なくとも武器を持ってる輩がウヨウヨしてたら怖いですよね?
しかも今作はインディアン留保地が舞台。
ユタ州に住んでいた私は、そういう土地が割と身近にあるのは知ってて、その時初めて受けた説明は、「アル中とヤク中のネイティブアメリカンが昼間っから仕事もせずにウロウロしてるから絶対に入るな。殺されそうになっても警察は来ないぞ。」だった。
今思うと凄く差別的な説明だったなと思うけど、この作品で実際にインディアン留保地が複雑な土地である事が良く分かる。
ストーリーは、1人のネイティブアメリカンの女性が森の中でしたいで見つかる。その犯人を外部からやってきた女性FBI捜査官が、その土地特有の事情に翻弄されながら、地元ハンターと探す。
ストーリーの節々にネイティブアメリカンの悲惨な現状と差別が描かれ心が痛い。詳しく言うとインディアン留保地は、州ではなく連邦警察の管轄になる為、レイプ、失踪、殺人事件が表に出てこない。
それが作品のメインテーマ、というかメッセージ。で、クライマックスは銃撃戦になるんだけど、「これが現代のアメリカで起こっている事なのか…。」と思うとゾッとします。
町山さんは、「これは西部劇です。アメリカには、まだ西部劇みたいな社会が残っているんです。」と言ったのは仰る通り。
日本に置き換えれば、刀持ったサムライが田舎の方に行くと、まだいて斬るか斬られるかの状況が、まだあるようなもの。本当に怖い話です。
暗喩
色々と暗喩が多いのかとも思う。
物語の軸は、寒村で起こった殺人事件を解き明かすって事なのだけど…この話しが「ネィティブアメリカンの失踪」なんてものからインスパイアされてるからタチが悪い。
それらの失踪事件の統計は取られていないらしく…そんな事から考えると、この話自体が取られない統計の内情にも思え、後味が悪い。
この寒村は限界集落かの如く、閉塞感があり人の出入りが少ない。そんな中、主人公であるハンターはFBIに対し、刑の執行を匂わす。
そして、おそらくならこの刑事が反対するなら見殺しにするつもりでもあったろう。
それが出来る環境と覚悟はあるのだと思う。
物語の中「ハンター」は、執行人かの如く悪を断罪はする。
ところが失踪事件の内情とかを考慮に入れると、コイツが実に不鮮明な立ち位置を醸し出す。
このハンターは、自分の良識の範囲で執行してた。ラストなどはご丁寧に雪山迷彩をして、目立たぬように。
ちょっと、アレコレうがった見方をすれば、奥の深そうな脚本だった。
この寒村がアメリカの縮図とするなら…。
レイプや殺人などをピックアップしてる訳ではなく、それらを事件ごとなかったものにしている「ハンター」が、かなり際どい存在。
実際、事件が粗方片付いた時、彼を連行する組織などはなく、日常が帰ってこようとしてる。
違和感の正体はこれで…当事者が口を塞げば追求できない現状があるという事。
この「ハンター」がアメリカのネィティブアメリカンへの黙殺だったり隠蔽だったりって部分を担ってるのかもと思った時に、インスパイアされたって意味が、ぼんやりと浮かび上がるような気がした。
極寒の自然を舞台にした骨太のサスペンス
ネイティブアメリカンの居留地で起こった若い女性の殺人事件。
それを過去に同様な事件で娘を失ったハンターと若いFBI捜査官が追う。
特にネタバレ禁止のどんでん返しがあるわけでは無い。
ネイティブアメリカンの生活・人生の厳しさ、自然の厳しさを舞台に物語はハンターが獲物を追うように淡々と進んで行く。
そしてクライマックスの銃撃戦。
ラストの犯人への「処罰」。
これも主人公が淡々とすすめるがゆえに重厚感が増す。
FBI捜査官や署長、被害者の父親など、主人公の周りのキャラクターにもう少し深堀があっても良かったと思うが、余韻のある秀作。
『レヴェナント』の現代版
『ウィンド・リバー』は,『レヴェナント』の舞台を現代に置き換えたものだ。
主人公はネイティヴ・アメリカンの女性と結婚し、彼女との間に生まれた娘を氷点下の大地で失った白人男性だ。娘がどのように死んだのか、その経緯はよく分からないままだ。娘の死がきっかけかは分からないが,妻とは離婚したらしい。
その彼が解決しようとするのは,自分ではない人間の娘が被害者となった事件だ。なぜなら、そうすることによって少しでも償いになるという期待があるからだ。全うできなかった父親としての役割を果たすことができるという期待があるからだ。被害者もまた自分の娘同様にネイティブ・アメリカンの血を受け継いでいる。被害者となった少女の父親は主人公の知人である。娘を失った知人に自分を重ね合わせることによって、主人公は父親としての役割を全うしようとしているのだ。
アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督の『レヴェナント』は、『ウィンド・リバー』同様、ネイティヴ・アメリカンの女性との間に生まれた我が子を殺された父親の復讐劇だ。『レヴェナント』が、怒りや憎しみを原動力とする主人公を描く一方で、『ウィンド・リバー』は、より温かみのある父性が主人公を駆動しているように思う。
『ウィンド・リバー』と『レヴェナント』の共通点は、「我が子の弔い合戦の物語である」というだけではない。復讐が主人公が直接手を下すことによって完成するのではない点、法・公権力・モラル・マナーではなく、個人の物理的・肉体的な力がものをいう世界=自力で生きる世界を舞台にしているという点においても、2つの作品は共通している。
主人公は過酷な環境を自力で生き延びるが、主人公の目的である「弔い」を完成させるのは、主人公ではない。『ウィンド・リバー』においては過酷な自然であるし、『レヴェナント』においては作中で西洋人よりも自然に近い存在であるネイティヴ・アメリカンなのだ。
2つの作品が共にこのような結末を迎えることには、どのような意味があるのだろうか?
『ボーダーライン』同様に、広大な自然の中を突き進む乗り物が重低音と共に突き進む様が、空撮を用いつつ描かれた。『最後の追跡』でも同様に乗り物で広大な大地を駆け巡る主人公が描かれていたが、砂漠や雪山といった広大な環境で、乗り物は,無力な人間に心強さを与えてくれる。
州全体で50万人程度の人口しかないワイオミングの人口密度は2.26人/平方㌖であり,東京都の6,283人/平方㌖と比較すればもちろんのこと,47都道府県中最下位である北海道の68人/平方㌖と比較しても圧倒的な差がある。年間降水量は東京の1/5程度で農耕もできない。州の平均標高は2,000m程度,最低でも900mはある。東海岸までは最短でも2,000kmほどあるし,西海岸からはロッキー山脈を越えなければならない。冬は雪が積もり行動が制限される。人が定住し,現代都市的な生活を送るにはコストがかかりすぎるし,お金の使い道=娯楽も少ない。
このような枯れた土地柄と,ネイティヴ・アメリカン。2つの要素は物語の「背景」として描かれるのみで,具体的に事件にどう結びつくかは直接語られることはないが,物語に奥行きや深みを与えてくれる。実際,ワイオミングという土地について簡単にでも検索してみるか,という気分に自分もなったのだから。鑑賞中はスリルを楽しむことができるし,鑑賞後も知識を増やすきっかけを与えてくれた。
冷房の効いた映画館に座して鑑賞する我々はまさに,ラスベガスから送られてきた「ナメてる」女性FBI捜査官なのであり,彼女が雪山の装備を整え積雪を踏みしめていくにつれて,我々もまたワイオミングの土地柄とそこに暮らす人々の心の機微を少しずつ学んで行くのである。
激走スノーモービル
重く心にのしかかってくるテーマと描写だけど、テンポ良く案外スルッと入ってくるストーリーで観やすかった。
やるせなくて静かで、でも確かに激しく突き上げるものを感じる。
真っ白の雪景色に動物の死体が転がっているカットが印象的で、不意に人間の遺体が画面に入ってくるとドキッとする。
ナタリーの遺体を見つけた時、コリーはどんな感情になったのか…計り知れない。
ナタリーの両親のリストカットと扉の外の慟哭が一番ガツンと来た。
自分が傍観者であることを強く実感させられた。
一瞬で空気が緊張し張り詰める感じや、華を一切合切削ぎ落とした銃撃戦シーンの迫力とショックが強い。
僻地ならではのことなのか、銃社会ではよくあることなのか…
一応事件解決だろうけど、これどう報告するんだろう。
前半で、攻撃的な態度とはいえヤク中兄弟の一人を普通に殺していたことが気になった。
物語の終着点のほんの少しばかりの救いにホッとした。
直後表示される文章にはまた辛くなるけど。
正直理解できないことや気になる点はいくつかあるものの、そんな差し水に左右されない芯の通った面白さがあったと思う。
病室での不器用な優しさにクスッとなる。
雪景色と重なる淋しさ
きっちり遂行される復讐物なので、もやもやが残るということはない。
けど、大切な人を失った哀しみ、淋しさだけがずるずる尾を引くような感じがする。
取り敢えず、彼氏が悪い奴じゃなくて本当によかった。
絶望まみれのお父さんに、最後、ほんのすこしだけ光が見えてよかった。
ひと思いに撃ち殺すのではなく、娘さんと同じ苦しみを味わわせられてよかった。
よかったよかったと数え挙げられるとことは沢山あるけど、一言で纏めてしまうと「大切な人を失って悲しい」映画だった。
アメリカの社会情勢とかは不勉強でよく分からないけれど、事件を事件として取り上げず流してしまう閉鎖的空間は恐ろしい。
疑問
疑問① 採掘場て 閉鎖中じゃなかったけ? 少女の遺体現場で「あそこは いま 閉鎖中だよー」て言うシーンなかったけ? だったら 何故 あんなに犯人いっぱいいるの?
疑問② 少女て どうやって 採掘場まで来たの? なんで 裸足で 逃げたの?
私の記憶違い。見落としがあるかもしれませんが 分かる方いらっしゃいましたら 教えてください
雪上ジェットカーだけが爽快だった。
愛情の反対は憎しみではなく無関心だ。アメリカ合衆国はネーティブアメリカンたちを特定の居住区に隔離している。先住民に対するリスペクトはない。フロンティアは逆方向から見れば侵襲だ。中央から無関心に放置され閉ざされた住民たちの悲しみの連鎖が切り取られた秀作であると思う。白い雪の上の真っ赤な血のごとく浮かび上がった。吹雪が去ればまた、血潮も犯人の足跡も消し去ってしまう非常な土地で。
(ふと、沖縄に思いが入ってしまったのは私だけではないのではないか。)
希望に満ちたいたいけな少女が犠牲になる殺人事件は個人的な悲劇だが、住民たちの集合意識の一部でもある。コヨーテは、家畜や放置された死体には手をつける。しかし、本当の獣のような鬼畜は暖房の効いたインドアにしかいなかった。
隔離されていても武器と薬はやすやすと侵襲してくることも悲劇を増幅する。殺人事件と立件されない限りFBI捜査官はたった一人張り付くことすら難しいこととの対照も実に皮肉であった。
主人公二人の表情の豊かさと、映画ならではの臨場感あふれる雪上ジェットシーンの爽快さに救われた。
大傑作
大傑作でしょう
ネイティブアメリカンの歴史を前もって頭に入れてから見るべきか。
アクション的演出皆無(ちょいレザボアドッグス風)の終盤の銃撃戦、レイプに至るまでの描写、主演のレナーとヒロインのオルセンが恋仲にならないとこ等々超自然体の演出にも関わらずエンターテイメントとして飽きずに見れた。
アメリカの現状を他人事として映画で学ぶというより自分の胸に突き刺さるセリフ「現状ある全ては自分の選択だ。」「世界と闘うのでなく俺は自分の感情と闘っている」「あいつは俺たちのように忍耐強くないから気にかけてやれ」等々、演技に久しぶりに感動した作品。
アメリカ的な内容
2人のカップルが殺されたことに対する刑事の復習劇だが、そのために銃撃戦で双方10人以上死ぬと言う効率の悪い展開に、銃社会の恐ろしさを感じた。
ストーリーも終始暗く良い所を見出せなかった。
米国闇部を白い雪原で描いたクライム佳作
アメリカ中西部ワイオミング州、冬。
吹雪があり、雪に一面閉ざされたある日、ネイティブアメリカンの保留地ウインド・リバーでひとりの若い女性死体が発見される。
発見したのは、近隣の家畜がコヨーテに食い荒らされていることの通報を受け、駆除に出ていたハンターのコリー(ジェレミー・レナー)。
彼も四年前に娘を亡くしており、情況が似ている・・・
といったところからはじまる物語で、すぐにコリーはネイティブアメリカン女性と結婚しており、亡くした娘は彼女との間にできた子どもだったということがわかる。
映画はその後、FBIから派遣されてきたバナー女性捜査官(エリザベス・オルセン)が加わり、犯人究明に乗り出すが、常に行く先々は雪に覆われている・・・と展開する。
直前に観た『ノクターナル・アニマルズ』の劇中小説の冬版・保留地版という趣が強く、知られざる米国の一面をあぶりだす迫力は相当なもの。
興味深いのは、ネイティブアメリカンの保留地の扱いで、英語では「reservation」、かれらにとって用意された土地という意味で、歴史的なことを反故にしたような押しつけがましい響きがある(つまり「囲い込み」にもかかわらず、という意味である)。
で、その保留地の自治は、彼らネイティブたちにまかせっきりで、殺人事件と明白でないと、全米警察機構のFBIは関与できない。
(BIAという組織に捜査は委譲され、当地のBIAの警察組織は6人しかいない、つまり、解決はほとんどなされない)
発見された女性の死体は、レイプ痕跡はあるものの、犯人からの逃走中に、極寒の中で肺出血を起こし、結果、窒息死したことが判明する・・・
というあたりかなり興味深く、バナー捜査官が本来は捜査権がないコリーを相棒をして捜査を進めていくまで、近年まれにみる雪中行で、撮影のベン・リチャードソンも含め、テイラー・シェリダンの演出は迫力がある。
そして、事件の真相がわかり・・・
というあたり、さて、このタイミングで事件の真相を語るべきだったのかどうか、少し疑問が残る。
捜査する側は、真相については薄々でしかわからないなかでのクライマックス前の真相バラシ・・・
後の、クライマックスの銃撃戦からはショッキングな編集なのだけれど、ここでいいのかしらん、少々説明が長い、と感じました。
ここは、もう少し前段階で、怪しいと感じて合同捜査に出る前あたりが、観る側にはわかりやすく、ハラハラするような語りになったのではありますまいか(って、個人的は『めまい』のネタバレ的位置が最適と思うのだが)。
というのも、この映画では、事件の真相(だれが、どんな目的で、被害者女性に害を及ぼしたか)がカタルシスにつながるわけでもなく、かといって、ここを描かないと米国の闇(最後の字幕説明されるネイティブアメリカンの失踪事件についての説明)に焦点が当たらないので、なんとももどかしいのだけれど。
というわけだが、本作、米国の闇を扱った映画としては、かなり上位に属すると思います。
(安易に、コリーの娘の死に直結しないあたりが、その闇を深く描いていると思いました)
鑑賞1回目
娘を失った哀しみと怒りが強くにじみ出ていたが、それだけに父と娘のシーンがもう少し描かれていても良かったと思う。
また見所がイマイチ少なかったのとオチも驚きにかけていた。
印象的なシーン(というかセリフ)はワルとつるんでいた被害者の兄貴が妹の死を知って怒りで世界が敵にみえてくるとといったことに対し、ジェレミーが少しの理解を示すも「俺は感情と戦う。」といったシーンが娘を失った自分へも言い聞かせてる感じがして印象深い!
やるせない怒りや悲しみの風景
アメリカ原住民の保留地で起こった少女死亡事件を追うというサスペンスですが、原住民の置かれた厳しい環境や、子を失った親の心情も描かれ、社会派ドラマとしても人間ドラマとしても観ることが出来ました。
また、知的で冷静に的確に獲物を仕留める、主人公のハンター役のジェレミー・レナーが格好良い。
なおかつ、怒りや悲しみを内に秘めた表情など、演技も素晴らしかったと思います。
犯人を追うサスペンス展開の方も、クライマックスの構成など、とても緊迫感がありました。
事件の真相となる部分は意外性があるわけではないのですが、こういった構成で提示し、緊迫感のある容赦ない銃撃戦へ続く流れは圧倒されました。
真相は意外性はありませんが、やはり非情で残酷だと思います。
犯人に報いを与えても癒やされることのない子を失った親の心、把握されない原住民の女性の失踪者達、ラストはやるせなさが残ります。
荒涼とした雪原の風景も印象的で、やるせない怒りや悲しみの心象風景のように感じました。
すごかった
子どもを亡くした者どうしの共感がなんとも胸を打つ。インディアンのお父さんが「オレはもう戦う気力がない」と言っていたのが「がんばれ」とは口が裂けてもいえないようなただならぬ空気だった。奥さんは鬼のようにリストカットしていて地獄のようだった。
銃撃戦がアクション映画的な演出が全く無くて、かっこよくもなんともないリアルな殺し合いだった。突っ立ったまま撃ち合う。
最後の制裁も素晴らしかった。彼女が事件に巻き込まれる様子がひどくリアルでありえそうで恐ろしかった。
現状ある全ては自分の選択によるものだ、というメッセージが半端に語られたらうざいばかりなのだが、ここまでの作品で突きつけられると納得せざるを得ない。
映画館が混んでいて、前から二列目で、映画館の冷房が効きすぎて寒くて、ウィンドリバーに連れて行かれたような気分だった。見終わって体調が悪くなった。
カウボーイを●すのが俺たちのヒーロー
カンヌ映画祭〈ある視点部門〉監督賞受賞作のクライム・サスペンス(バディもの)。
今作品は、ラジオ番組の町山智浩の映画評で知ったのだが、その際の前段階の予習が非常に重要だということを再確認させられた内容である。広大なアメリカの土地ならではの、西部開拓時代から進歩が止まってしまっている場所での非人道的な振る舞いとそれを根付かせてしまっている経済的、歴史的背景を、逆に自然の雄大さとの比較で際立たせている。
それにしても今作はアメリカの国の成り立ちや法律、歴史をある程度勉強していないと、ストーリーの深みが読み取れないのではないだろうか。その辺りをスルーしてしまうと、サスペンスドラマとして大事な“理由付け”が薄まってしまい、正に“アメリカン”コーヒーな訳だ。そうなると日本のテレビでの『2時間ドラマ』の域を出ず、単純に故人の怨恨が起因という形で終わってしまう。
アメリカは州そのものが国であり、国達が集まった“合衆国”という成り立ちである。そしてその州を跨がる事象だけの法律を連邦法に定め、その他の法律は州毎に制定している。今作品の舞台はワイオミング州にあるウィンドリバーインディアン保留地であり、そこは連邦の管轄であるのだが、連邦法では強○罪は制定されていない。そして正に征服され虐げられた先住民達の強制移住区であり、そこでは広大だが、痩せた土地に、たった6人の警察官しかいない。辺境の土地には夢はなく、『生き延びるか、諦めるか』の二者択一しか道はない。失業率、貧困率でトップランクのこの場所では、全てが死んでいるのだ。そんな中での暴行殺人事件なのである。当の先住民達ももはや先祖の儀式や矜持もズタズタに切り裂かれ、伝承が施されず、誇りも棄てられたまま、しかし気持は留まってしまっている。顔にペイントをすることさえ、もはや正統な方法が受け継がれていないからデタラメである。
そしてそれはまた、白人とて、同じだ。“ホワイトトラッシュ”も又、その境遇に苦しみ喘ぎ、その孤独を酒やドラッグで誤魔化し、現実を直視できずにいる。『酔って、孤独で、そして暴行』という悪循環だ。
プロット展開として、ミスリードを設ける意味合いで、土地の鼻つまみを登場させ、しかし実はこの土地から資源を奪っているエネルギー省管轄の警備員という連中に視点を変えていくのだが、そこの展開はもっと二転三転が欲しかったし、今の映画ではそれをやっている作品は枚挙に暇がない。勿論、『事実に基づく』作品だから、100%フィクションにはできないのだけど、しかしもう少しドラマティックさをストーリーに盛り込んでも良かったのではと、一寸残念だ。例えば、もっと鬼畜でサイコパスな登場人物が出て、このアメリカの法律網の盲点を予め理解しているとか、死んだ女の子は暴行死ではなく、直接死因は冷気を肺に吸い込んだことによる、窒息死であることも、もう少しそこをトリックに使うとかは、織込んでも良かったのではと思うのだが、そうなると意味合いが変わってしまうのだろうな。推理モノではなく、あくまでもヒューマン、そして現在社会問題を投影したテーマなのだろうから。
FBI捜査官のTバック、そして、女の子のTバック、その辺りに、もう一つのテーマである男女間の意識の違い、世代間の意識の違い、そして女性の社会的参画のあり方みたいなものを対比させるギミックとして、細かい小ネタも散りばめられている点も興味深い作品に仕上がっていた。きちんとカタルシスで帰着したところは制作者の良心として、受容れやすいのではないだろうか。現実はこんな“必殺仕事人”はいないけどね・・・
人としての掟がある!
ジェレミーレナーが好きでと、新聞の評価で観ました。監督もボーダーラインの脚本家も興味ありましたね。
タイトルから、フローズンリバーをイメージしましたが別物。サスペンス調と、保留地の人間関係が、解らず前半は、やや退屈でした。ワイオミング州の雪の厳しさとハンターで大いなる勇者もイメージしてしまいました。
雪中を装備不十分で走ると肺の中の空気が凍り自分の血で窒素する。だから他殺ではない理屈が、腹立たしい。レナー役の娘さんも行方不明になっているんですね。
ラストの銃撃戦は、かなり迫力がありました。
ラストシーンは、法律では、違法ですが、生き物としての掟を破った人には、その罰が与えられたんですね。
ネィティブアメリカンの女性の行方不明は、とても多くアメリカ政府は、全く記録にも残していない事実に驚きます。西郷どんの奄美大島の方々を思い出しました。
重いテーマですが、ある視点でみる秀作でしたね。
おすすめします。
先住民族に対しての映画
ストーリーよりも助演女優のエリザベス・オルセンが
個人的見解だが元世界準ミスの知花くららに似ていて
それが気になってしかたなかったのが印象的でした。
ストーリーは地方の田舎町でよくある隠されてうもれて
しまうような事件なのだがそれを何故かFBIが
捜査に乗り出してくるというストーリー
その被害者が先住民だと言う事、死因も不可解な事
そしてそういう事件記事も先住民は
何故かニュースにも取り上げられないこの不文律の実態を
作者、脚本家は言いたいようです。
アカデミー賞候補だそうですが虚しさが残る映画ですので
評価は低いです。
追記 注) 後、この映画はレイプシーンが含まれているので
そのようなシーンが苦手な人は見ない方が良いです。
全59件中、41~59件目を表示