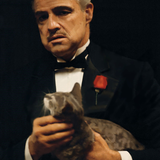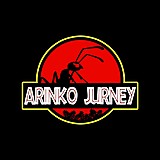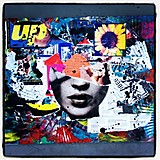ウインド・リバーのレビュー・感想・評価
全290件中、201~220件目を表示
考えさせられる、実話を元にしたクライムサスペンス
ネイティブアメリカン(インディアン)を追いやり強制的に住まわせた、居留地「ウィンドリバー」。
彼らは絶望感で苦しみ、悲しみの中で声を殺してひっそり暮らしている。そんな最中に起こるクライムサスペンス。
実話を元に、アメリカの今も続く奥深い歴史の闇を抉じ開けた、胸に刺さる作品。
エンドロールの言葉も脳裏に焼き付く。
ボーダーライン北限版
暗喩
色々と暗喩が多いのかとも思う。
物語の軸は、寒村で起こった殺人事件を解き明かすって事なのだけど…この話しが「ネィティブアメリカンの失踪」なんてものからインスパイアされてるからタチが悪い。
それらの失踪事件の統計は取られていないらしく…そんな事から考えると、この話自体が取られない統計の内情にも思え、後味が悪い。
この寒村は限界集落かの如く、閉塞感があり人の出入りが少ない。そんな中、主人公であるハンターはFBIに対し、刑の執行を匂わす。
そして、おそらくならこの刑事が反対するなら見殺しにするつもりでもあったろう。
それが出来る環境と覚悟はあるのだと思う。
物語の中「ハンター」は、執行人かの如く悪を断罪はする。
ところが失踪事件の内情とかを考慮に入れると、コイツが実に不鮮明な立ち位置を醸し出す。
このハンターは、自分の良識の範囲で執行してた。ラストなどはご丁寧に雪山迷彩をして、目立たぬように。
ちょっと、アレコレうがった見方をすれば、奥の深そうな脚本だった。
この寒村がアメリカの縮図とするなら…。
レイプや殺人などをピックアップしてる訳ではなく、それらを事件ごとなかったものにしている「ハンター」が、かなり際どい存在。
実際、事件が粗方片付いた時、彼を連行する組織などはなく、日常が帰ってこようとしてる。
違和感の正体はこれで…当事者が口を塞げば追求できない現状があるという事。
この「ハンター」がアメリカのネィティブアメリカンへの黙殺だったり隠蔽だったりって部分を担ってるのかもと思った時に、インスパイアされたって意味が、ぼんやりと浮かび上がるような気がした。
極寒の自然を舞台にした骨太のサスペンス
ネイティブアメリカンの居留地で起こった若い女性の殺人事件。
それを過去に同様な事件で娘を失ったハンターと若いFBI捜査官が追う。
特にネタバレ禁止のどんでん返しがあるわけでは無い。
ネイティブアメリカンの生活・人生の厳しさ、自然の厳しさを舞台に物語はハンターが獲物を追うように淡々と進んで行く。
そしてクライマックスの銃撃戦。
ラストの犯人への「処罰」。
これも主人公が淡々とすすめるがゆえに重厚感が増す。
FBI捜査官や署長、被害者の父親など、主人公の周りのキャラクターにもう少し深堀があっても良かったと思うが、余韻のある秀作。
『レヴェナント』の現代版
『ウィンド・リバー』は,『レヴェナント』の舞台を現代に置き換えたものだ。
主人公はネイティヴ・アメリカンの女性と結婚し、彼女との間に生まれた娘を氷点下の大地で失った白人男性だ。娘がどのように死んだのか、その経緯はよく分からないままだ。娘の死がきっかけかは分からないが,妻とは離婚したらしい。
その彼が解決しようとするのは,自分ではない人間の娘が被害者となった事件だ。なぜなら、そうすることによって少しでも償いになるという期待があるからだ。全うできなかった父親としての役割を果たすことができるという期待があるからだ。被害者もまた自分の娘同様にネイティブ・アメリカンの血を受け継いでいる。被害者となった少女の父親は主人公の知人である。娘を失った知人に自分を重ね合わせることによって、主人公は父親としての役割を全うしようとしているのだ。
アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督の『レヴェナント』は、『ウィンド・リバー』同様、ネイティヴ・アメリカンの女性との間に生まれた我が子を殺された父親の復讐劇だ。『レヴェナント』が、怒りや憎しみを原動力とする主人公を描く一方で、『ウィンド・リバー』は、より温かみのある父性が主人公を駆動しているように思う。
『ウィンド・リバー』と『レヴェナント』の共通点は、「我が子の弔い合戦の物語である」というだけではない。復讐が主人公が直接手を下すことによって完成するのではない点、法・公権力・モラル・マナーではなく、個人の物理的・肉体的な力がものをいう世界=自力で生きる世界を舞台にしているという点においても、2つの作品は共通している。
主人公は過酷な環境を自力で生き延びるが、主人公の目的である「弔い」を完成させるのは、主人公ではない。『ウィンド・リバー』においては過酷な自然であるし、『レヴェナント』においては作中で西洋人よりも自然に近い存在であるネイティヴ・アメリカンなのだ。
2つの作品が共にこのような結末を迎えることには、どのような意味があるのだろうか?
『ボーダーライン』同様に、広大な自然の中を突き進む乗り物が重低音と共に突き進む様が、空撮を用いつつ描かれた。『最後の追跡』でも同様に乗り物で広大な大地を駆け巡る主人公が描かれていたが、砂漠や雪山といった広大な環境で、乗り物は,無力な人間に心強さを与えてくれる。
州全体で50万人程度の人口しかないワイオミングの人口密度は2.26人/平方㌖であり,東京都の6,283人/平方㌖と比較すればもちろんのこと,47都道府県中最下位である北海道の68人/平方㌖と比較しても圧倒的な差がある。年間降水量は東京の1/5程度で農耕もできない。州の平均標高は2,000m程度,最低でも900mはある。東海岸までは最短でも2,000kmほどあるし,西海岸からはロッキー山脈を越えなければならない。冬は雪が積もり行動が制限される。人が定住し,現代都市的な生活を送るにはコストがかかりすぎるし,お金の使い道=娯楽も少ない。
このような枯れた土地柄と,ネイティヴ・アメリカン。2つの要素は物語の「背景」として描かれるのみで,具体的に事件にどう結びつくかは直接語られることはないが,物語に奥行きや深みを与えてくれる。実際,ワイオミングという土地について簡単にでも検索してみるか,という気分に自分もなったのだから。鑑賞中はスリルを楽しむことができるし,鑑賞後も知識を増やすきっかけを与えてくれた。
冷房の効いた映画館に座して鑑賞する我々はまさに,ラスベガスから送られてきた「ナメてる」女性FBI捜査官なのであり,彼女が雪山の装備を整え積雪を踏みしめていくにつれて,我々もまたワイオミングの土地柄とそこに暮らす人々の心の機微を少しずつ学んで行くのである。
激走スノーモービル
重く心にのしかかってくるテーマと描写だけど、テンポ良く案外スルッと入ってくるストーリーで観やすかった。
やるせなくて静かで、でも確かに激しく突き上げるものを感じる。
真っ白の雪景色に動物の死体が転がっているカットが印象的で、不意に人間の遺体が画面に入ってくるとドキッとする。
ナタリーの遺体を見つけた時、コリーはどんな感情になったのか…計り知れない。
ナタリーの両親のリストカットと扉の外の慟哭が一番ガツンと来た。
自分が傍観者であることを強く実感させられた。
一瞬で空気が緊張し張り詰める感じや、華を一切合切削ぎ落とした銃撃戦シーンの迫力とショックが強い。
僻地ならではのことなのか、銃社会ではよくあることなのか…
一応事件解決だろうけど、これどう報告するんだろう。
前半で、攻撃的な態度とはいえヤク中兄弟の一人を普通に殺していたことが気になった。
物語の終着点のほんの少しばかりの救いにホッとした。
直後表示される文章にはまた辛くなるけど。
正直理解できないことや気になる点はいくつかあるものの、そんな差し水に左右されない芯の通った面白さがあったと思う。
病室での不器用な優しさにクスッとなる。
第一級の社会派サスペンス
荘厳で苛酷な雪深い山の中で起こった少女殺害事件を、野生動物局の孤高のハンターと新米の女性FBI捜査官のにわかコンビが、幾多の苦難に見舞われながらも、いつしか心を通わせ、真相を暴いて行くクライム・サスペンス。そしてラストでネイティブアメリカンが強いられている悲惨で信じ難い現状への鋭い告発がなされる。ジェレミーは今回も「メッセージ」と同様、懐の深い、地に足の着いた真の男を好演したし、エリザベスも事件を解決するための情熱と力強い意思を持った女性を見事に演じている。2人とも人の痛みや悲しみを感じとることのできる正常な感覚の持ち主で、人間の善意の象徴だと思う。トレーラーハウスのドア1枚の開閉で、過去から現在に画面転換するショットは見事で、さすがテイラー・シェリダン。クライマックスでジェレミーが悪党を猟銃で次々と狙撃するシーンとピートが愚かにもたった数十メートル走っただけで息絶えるシーンには溜飲が下がった。ナタリーの父マーティンに平穏が訪れることを切に願う。
銀世界でアメリカの闇を描く
雪景色と重なる淋しさ
きっちり遂行される復讐物なので、もやもやが残るということはない。
けど、大切な人を失った哀しみ、淋しさだけがずるずる尾を引くような感じがする。
取り敢えず、彼氏が悪い奴じゃなくて本当によかった。
絶望まみれのお父さんに、最後、ほんのすこしだけ光が見えてよかった。
ひと思いに撃ち殺すのではなく、娘さんと同じ苦しみを味わわせられてよかった。
よかったよかったと数え挙げられるとことは沢山あるけど、一言で纏めてしまうと「大切な人を失って悲しい」映画だった。
アメリカの社会情勢とかは不勉強でよく分からないけれど、事件を事件として取り上げず流してしまう閉鎖的空間は恐ろしい。
疑問
疑問① 採掘場て 閉鎖中じゃなかったけ? 少女の遺体現場で「あそこは いま 閉鎖中だよー」て言うシーンなかったけ? だったら 何故 あんなに犯人いっぱいいるの?
疑問② 少女て どうやって 採掘場まで来たの? なんで 裸足で 逃げたの?
私の記憶違い。見落としがあるかもしれませんが 分かる方いらっしゃいましたら 教えてください
カウボーイが良いもんでインディアンが悪もん。
なかなか
雪上ジェットカーだけが爽快だった。
愛情の反対は憎しみではなく無関心だ。アメリカ合衆国はネーティブアメリカンたちを特定の居住区に隔離している。先住民に対するリスペクトはない。フロンティアは逆方向から見れば侵襲だ。中央から無関心に放置され閉ざされた住民たちの悲しみの連鎖が切り取られた秀作であると思う。白い雪の上の真っ赤な血のごとく浮かび上がった。吹雪が去ればまた、血潮も犯人の足跡も消し去ってしまう非常な土地で。
(ふと、沖縄に思いが入ってしまったのは私だけではないのではないか。)
希望に満ちたいたいけな少女が犠牲になる殺人事件は個人的な悲劇だが、住民たちの集合意識の一部でもある。コヨーテは、家畜や放置された死体には手をつける。しかし、本当の獣のような鬼畜は暖房の効いたインドアにしかいなかった。
隔離されていても武器と薬はやすやすと侵襲してくることも悲劇を増幅する。殺人事件と立件されない限りFBI捜査官はたった一人張り付くことすら難しいこととの対照も実に皮肉であった。
主人公二人の表情の豊かさと、映画ならではの臨場感あふれる雪上ジェットシーンの爽快さに救われた。
期待どおり
生きてく
バートンとワンダ
大傑作
大傑作でしょう
ネイティブアメリカンの歴史を前もって頭に入れてから見るべきか。
アクション的演出皆無(ちょいレザボアドッグス風)の終盤の銃撃戦、レイプに至るまでの描写、主演のレナーとヒロインのオルセンが恋仲にならないとこ等々超自然体の演出にも関わらずエンターテイメントとして飽きずに見れた。
アメリカの現状を他人事として映画で学ぶというより自分の胸に突き刺さるセリフ「現状ある全ては自分の選択だ。」「世界と闘うのでなく俺は自分の感情と闘っている」「あいつは俺たちのように忍耐強くないから気にかけてやれ」等々、演技に久しぶりに感動した作品。
全290件中、201~220件目を表示