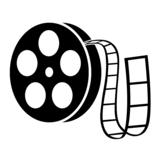BPM ビート・パー・ミニットのレビュー・感想・評価
全37件中、1~20件目を表示
社会運動にとって「社会」とは何か
社会運動につきものの、穏健路線かラディカル路線かの組織内対立がアクトアップ・パリでもあった。そこでは「中立」に意見を述べると体制寄りに見えるという指摘があった。過激な運動手法は社会の理解を得られないとも。
社会から遊離しては社会運動は閉鎖的になり、カルト化する危険が生じる。しかし穏健路線は、時に妥協しすぎて運動の意義を損なう。ショーンは死してなお「政治的葬儀」を望んだ。その理不尽への怒りと運動への熱狂が、惰性に流れがちな穏健派への回答だったのだろうし、社会へのメッセージだったのだ。
90年代、HIV患者のために戦った若者達の姿をヴィヴィッドに描いた名作
全く内容を知らないままに本作を観た。そして驚かされた。かつて『パリ20区、僕たちのクラス』で脚本と編集を担当したロバン・カンピヨによる監督作なのだが、かつて自身がメンバーの一人だったというACT UP(HIV感染者への差別や不当な扱いに抗議する団体)のミーティングは、まるで『パリ20区』で見られた学生達のやりとりのようにヴィヴィッドでテンポよく、その洗練された作りに一気に飲み込まれる。時に白熱する議論と、政府や製薬会社への息詰まるプロテスト場面とを織り交ぜ、その活動の波間で病状が悪化して亡くなっていく仲間への追慕も描かれる。
90年代のパリでHIVがいかに受け止められ、それに対し人々がどう団結したのか、その風を感じられることもさることながら、メンバー一人一人の横顔が実に印象深くて忘れがたい。とりわけ主人公ショーンの、徐々にやせ衰えていく身体、彼の生き様と心情を体現した俳優の演技が見事だ。
踏み絵的
男どうしの性愛シーンがすきじゃない。正直言ってブロークバック~でもゴッズオウンカントリーでも君の名前で~でもそれを感じた。
それらが名画であることに異存はない。
Aケシシュ監督のアデル~(2013)には、アデル・エグザルホプロスとレア・セドゥの濃厚な性愛シーンがある。が、ぜんぜんイヤではなかった。女どうしなら大丈夫なのだ。
でも男どうしのばあい、生理的嫌悪というほどのことじゃないが、なんとなく・・・。
──偏見だろうか。
本作BPMにも男どうしの性愛描写がある。見たことないほど露骨だった。局部は出ないが、けっこう長いあなるせっくすの描写がある。
ゲイをあつかうコンテンツが性愛と密着しているのはなぜだろう──。と思うことがある。
男女の愛と、男男の愛と、女女の愛は、同質のもの──と見るならば、男女の愛のように、性描写のあつかいは慎重でなければならないと思う。
言っていることが伝わるかわからないが、男女の愛をあつかった映画で、かならず性描写がでてくるわけではない。
ラブストーリーに性描写が出てくるのは、それを目的としているばあいとか、大人向けとか、性描写に必然性があるときとか、旧弊な日本映画で女優を脱皮させたい──とか、等々の狙いがあるときに限る。
しかしゲイの映画ではわりとふつうに性愛シーンがでてくる。
このギモンはハッテン場にも言える。男男間では恋愛が省かれていきなり性愛にいたる──それがじぶんが知っているハッテン場の構造である。ゲイ映画でも、似たような気配を感じてしまう。──のだ。
この映画はHIV活動家たちの熱さと青さと、陽性者の死の恐怖をとらえていて躍動的で見応えがある。
が、情交シーンもさることながら、性の気配がつきまとう。ここに出演している男たちは、つねに愛をささやきあい、つねに欲情している気配があった。その気配が個人的には困った。
ところで、さいきん(2022/05)の海外ニュースで、本作にも出演しているアデル・エネルの引退のインタビュー記事をみた。
引退といってもマイルドな感じで、演劇には関わり、映画もまた出るかもしれない──と言っていた。
記事によるとアデル・エネルが引退を決意したのは、(フランスの)映画業界が『資本主義的、家父長制的、人種差別的、性差別的な構造的不平等の世界を擁護している』から、であり『私は内側から変えようとしたが、もうその一部にはなりたくないのです』と一種の諦観を述べていた。
さいきん日本でも榊英雄や園子温や河瀬直美などのセク/パワハラ報道があった。
エネルのインタビューをみるかぎり、フランス映画界にもそのような縦構造があると感じられた。
しかし日本にはそれを告発して引退するエネルのような俳優はいないだろう。
『2020年2月28日(セザール賞授賞式にて)、かつて13歳のSamantha Geimerをレイプした罪で有罪判決を受けたロマン・ポランスキーが『An Officer and a Spy』で監督賞を受賞した後、エネルはCéline Sciamma、Noemie Merlant、Aïssa Maïgaとともに第45回セザール賞授賞式から立ち去りました。エネルは退場する際、拳を振りながら「恥だ!」と叫び「ブラボー、小児性愛!」と叫びながら、皮肉っぽく拍手する姿が撮影された。』
(Adèle Haenelのwikiより)
アデルエネルはそんな熱い人だった。
一方、天然な感じもあるひとだった。
わたしは昔、ダルデンヌ兄弟の「午後8時の訪問者」(2016)のレビューにこう書いた。
『youtubeに遍在している彼女のインタビュー動画を見たことがある。
演技上にない素のアデルエネルは、見たこともないほど天然な感じの人である。
対談や会見の最中、彼女は、絶え間なくキョロつく。
眼球と頭がつねに動いて、意識が散漫にほかへ移る。まるで動画にでてくる赤ん坊のように、たえずどこか/なにかを触り、忙しなく好奇心の方向が変わる。
その一方で熱く語ったりもする。
その、素のファンキーな感じがクリステンスチュワート以上なのであって、とうぜん、そんな人はおらず、まして女優ならなおさらである。
ゆえに、もしアデルエネルがこの天然のまま映画に収まったら──と思うほど魅力的な「素」だが、ただし、あまりに動きが止まらないので、トゥレットとか多動性とかの障害を思わせもする。』
アデル・エネルの天然はすごい。この天然を映画で見ることができればと思っていたから、引退報道はざんねんだった。(ひょっとしたらすぐ復帰するのかもしれないが・・・)
なんにもない日本映画界ほどではないが、仏映画界もトリュフォーがいた時代との比較でずっと低迷を言われている。
それゆえエネルのような人さえ代表作が限られてしまう。(だとしても「いい映画」がまったく一つもない日本の俳優よりずっとましだが)
エネルには午後8時の訪問者もPortrait of a Lady on Fire(2019)もあるが、もっと見たい人だった。
MeToo告発は今も世界の潮流である。今後も続くだろう。
ただし日本国内での告発は、海外のそれとポジションがぜんぜん違う。
海外のばあい実力者が告発されることが多い。
前述したポランスキーの件。ポランスキーはじっさい犯罪者だと思う。しかし、ポランスキーの映画はすごい。反撥/袋小路/ローズマリー~/チャイナタウン/テナント/テス/オリバーツイスト・・・。それとこれとは別だと言いたくなってしまうほどの天才だ。
養子にたいする何年も前のわいせつで告発されたウディアレンもかつてのような映画製作ができなくなっている。
さいきん(2022/05)の海外ニュースでは007のフクナガ監督にたいするセクハラ告発があった。
実力ある者だらけの海外の告発にくらべて、日本の告発は非才なクリエイターたいするもの──と個人的には感じている。
ようするに、とるにたりないクリエイターが告発される。
わたしは榊英雄や園子温や河瀬直美が告発されても「それとこれとは別だ」と言いたくならない。
さいきん別のパワハラニュースがあった。
『2022年、映画業界におけるハラスメント行為への告発が相次ぐ中、小林が監督、脚本、撮影、編集自ら行った作品である「ヘドローバ」のメイキング映像の中で、大人による少年への暴行が行われるシーンで、殴られる部分は演技ではなく、実際に、当時中学生であった子役の少年を、元プロ格闘家の大人が本気で繰り返し顔面を殴打していると報じられた。殴られた子役の少年は泣きながら嘔吐し「とにかくヤバかったです。いろいろ」「死にそうでした」と発言していたが、小林勇貴は「恐ろしいものが撮れてしまいましたが、そうですね、でもすごい良かったです。児童虐待、撮りました」と笑顔でコメントしていた。これらがネットを中心に多数の批判を呼び、問題になっていることを受け、小林が原案として参加している同年公開予定の「激怒」のプロデューサーは、小林の名前をクレジットから外したことを発表した。』
(ウィキペディア、小林勇貴より)
個人的に思うのは、どうでもいいクリエイターのパワハラをニュースにするなってこと。
この小林という人のやったことに問題があったなら刑事なり民事なりにすればいいのであって、凡人をニュースにしてはいけない。つまりどうでもいいようなアングラ映画をつくっている無能なクリエイターのやったことを全国ニュースにしてはいけない。と個人的には思っている。
日本は人の創造物を認めることを是とする。
だが日本映画がつまんないのは基本的にその寛容が元凶に他ならない。
日本のMeToo運動が海外と異なるのもその点。
セク/パワハラの告発とはいっぱんに権力や人望があり世間に才能を認められている者が裏でやったことを暴露することにある。
もとから人望がなかったり、誰も知らない作品をつくっていたり、非才なら、それは告発と言うより、たんに素地が露呈しただけのこと。
やっぱりね、──でお終いである。
話が逸れたが、本作BPMはシリアスな主題を背負っている。演出もいい。HIVでも終末のほうのステージを扱っている。つらい。が、前述のとおり性的で男どうしが愛をささやき合う。かなり扇情的。けっこう困った。
コロナ禍の今こそ見るべき・・・
差別や偏見。1990年代と言えば、ようやくHIVの知識が浸透し始めた頃。まだ医療は確立されていなく、感染したら確実に死ぬと言われてたのを思い出す。差別というのもほとんどゲイに対するもので、他にも注射針を使いまわす薬物常用者、娼婦、囚人といった人たち。特に性的マイノリティのLGBTがターゲットだ。普通に男女間でも伝染るんだよ!と訴える彼らは、政府や製薬会社に抗議したり、高校に乗り込んでコンドームを配ったりする活動がメイン。アクトアゲインスト・エイズなら知ってたのに、恥ずかしながらアクトアップの団体は知らなかった。
メインはショーンとナタンの恋物語になるのですが、彼らアクトアップの抗議活動の方に惹かれてしまいました。日本における新型コロナウイルス感染者数や医療現場の状況。さらにアビガン等特効薬の臨床データやワクチン開発状況など、国民には知らされてないことが多い。もっと声を上げなきゃ隠されたままになりそうで怖いのです。
BPMって音楽用語じゃね?などと思っていたのですが、原題では120がついていて、心拍数を表すらしいです。途中の音楽も120bpmだったのかもしれませんが、それよりも拍手の代わりに指パッチンを鳴らすルールがあったので、その拍子が120bpmだったのだと勝手に勘違いしています。
それにしても未知のウイルスの恐怖。これからも人類はウイルスと戦い続けなければならないのでしょう。今もなおHIV感染、エイズ患者は増えています。日本にも2万人以上の感染者がいます。90年代当時はネット環境も少なく、恐怖や不安は今以上だったことも想像できますが、情報時代だからこそデマにも注意して対策をしっかりとらねばと、なぜか映画の趣旨と違った感想を持ってしまいました。
「ACT UP Paris」
1990年代の初め、エイズは怖がられており、行政や製薬会社の動きは鈍かった。
パリではエイズ患者を中心に「ACT UP Paris」が組織され、命がかかっている自分たちの思いを伝えようと、かなり過激な運動を繰り広げていた。
主人公は男性エイズ感染者、この運動に参加してきた非感染者の男と恋におちる。
当時の自分自身の心の内を見透かされたようなセリフが痛い。
屈しない人々
愛と理解と訴えの鼓動
2017年度のカンヌ国際映画祭グランプリ受賞作品。
パルムドールの『ザ・スクエア』は独創的ではあるがシュール過ぎて自分には合わなかったが、訴えるメッセージ性などはこちらの方が良かったと思う。
1990年代初頭のパリ。
実在する同性愛や反HIVの活動団体“ACT UP”。
社会の差別や偏見と闘った若者たち。
今も同性愛やHIVへの差別・偏見は根強く残っているが、だいぶ理解は深まっている。
しかし、90年代初頭はまだまだそうではなかった。
同性愛同士で性交すればHIVに感染、同性愛=HIV、HIV陽性者の近くに居るだけで感染するという誤解すらあった。
何もHIVは空気感染や肌に触れたって感染はしないし、男女同士で予防ナシに性交して感染する時は感染するというのに…。
社会の理解や医学の研究が進んでなかったとは言え、一体何故こんな誤解が植え付けられたのか。
同性愛やHIVへの差別・偏見は、社会の問題を殊更浮き彫りにする。
同性愛に自由を。
HIVの正しき理解と予防を。
“ACT UP”の活動内容は社会への訴え。
時には過激な行動も辞さない。
作り物の血を投げ付ける。デモは頻繁に。治療薬の提供を渋る製薬会社に乗り込む。…
団体内でも常に白熱した議論が繰り広げられる。
法を犯した行動もあったかもしれない。
が、何かアクションを起こさないと、社会は関心すら持たない。
意識改革へのきっかけにもならない。
監督のロバン・カンピヨは実際にACT UPの一員だった事もあり、実体験を基に、当時の熱気や若者たちの姿をリアルに臨場感たっぷりに描写。
その演出力やキャストの熱演はとても劇映画とは思えず、まるでドキュメンタリーを見ているようだ。
テーマやメッセージは社会派だが、主軸は繊細な愛の物語。
新加入の青年と、カリスマ性溢れる団体の中心人物。
二人の出会い。
惹かれ合う。
ラブシーンは激しく、生々しくもある。
が、次第にHIVの症状が悪化していき…。
HIVによって愛する大切な人を失う悲しみの物語でもある。
生きたくても、生きられない。
だから、万一手遅れになる前に、そうならない為にも、知ってほしい。
理解を。
自由を。
愛を。
切実な訴えを。
観終わった後の余韻が凄まじい
個人的には2018年No.1の映画です。映画館で観終わっても席をなかなか立てませんでした。
HIV/エイズに対する活動を描いた映画なので、時折強い描写も見られますが、とても強い信念を持って作成された映画だと感じました。
ナタンとショーンの関係が中心で描かれていますが、この映画の醍醐味はACT UPの活動だと思っています。彼らの過激にも映る活動の背景にある根強い偏見と無知。
テーマ的に見るのをためらわれる方がいらっしゃるかと思いますが、彼らの活動の背景にあるものは、20年以上たった今でも大きく変化していないことを私たちに教えてくれます。
指鳴らせないけど賛成。拍手じゃダメ?
字幕翻訳・松浦美奈さん。すき。
ほかに字幕監修もいた。
ショーン役の子に似てる日本人絶対知ってるけど誰?思い出せん?と今も思ってます。
知らないことを知ることを目的とした鑑賞でして、思いのほかお勉強以上にエモーショナルでグッときた映画でした。
私は虐げられた状態で、破壊行為に出る人の気持ちがわかる。自分も赤インクまみれにすることを選ぶと思う。ダメだとわかっているけど、そうせざるを得ないって思う。
テロと変わらないとも思うけど。
楽しそうにパレードで踊り、恋だか性欲だかを弾けさせ、ミーティングで意見をぶつけ合って、泣いて、笑って戦うみんなに、賛成する。
でも私指ならないのよね、カスカスゆうだけ。
それでもいいかな?仲間に入れて。
予想を超えた感動
不治の病ではなくなったHIV。
素晴らしい作品
最後はロマンポルノ
思えば、まだLGBTという言葉もなかった頃、世界には同性愛者が数多く生きていて、それは売春宿や精神病棟にだけ存在する特殊な人々ではなく、我々の職場や学校にも少なからず生活をしていることを、ある種の驚きをもって知り始めたのはエイズの蔓延のニュースと共にではなかっただろうか。
同性愛者にエイズ患者が多い(誤解のないように補足するが、エイズ患者=同性愛者だと述べたいのではない。)のか、エイズ患者に同性愛者多いのか、そのあたりの情報もよく整理されないまま、HIVウィルスへの感染がひき起こす病気に関する情報は世界を震撼させた。
しかし、同時にこの病気は、同性愛や性愛について公の場で語ることをタブーとしない潮流を生み出したのではなかろうか。
HIVに感染し、命の尽きるのを日々感じながらも、HIV感染への対策を政府や社会に訴えることに駆り立てられている若者たちの姿は壮絶である。
映画は彼らに対して必要以上の感情移入をしない。見知った顔の俳優がスクリーンに登場していなければドキュメンタリーかと思うほどに、彼らの焦燥感が直接伝わる。
同時にこの直接的な描き方は、彼らが結局は性愛に対してオープンな人々であることを観客に見せつけてもいる。
ショーンが亡くなったあと、恋人のナタンは他の活動家とベッドをともにすることを自ら望む。行為の後、ショーンを想い慟哭するナタン。しかし、愛する人を失った悲しみを他の人との行為によって埋め合わせようとする短絡的な発想は、もはやピンク映画である。喪服の未亡人が、親戚のおやじに慰められるものとなんら変わらない。
本当のところは分からないが、どうも「簡単にヤレる」ことが同性愛者になった理由の一つでもあると、この映画は最後に彼らの業についても言及していたような気がする。
あまりにも重すぎる真実
「沈黙は死、行動は命」
「活動家」と聞くと、ついついあまりよくないイメージを思い浮かべてしまう。乱暴な行為で事を荒立てている人たちというイメージだったり、傍若無人に自分の主張を押しつけている人たちというイメージだったり。しかしながら、そういう人たちの活動によって社会が動くこともある。そしてそういう人たちが声を発してくれることによって、それまで知らずにいた叫びを知ることが出来たりもする。この映画は、エイズが社会問題として大きく取り上げられるようになり始めたころのフランスの物語。そして今、もう一度改めて彼らの叫びに耳を傾ける。病に関するあらゆる誤解が錯綜していた時代は過ぎたものの、あれから社会は何か変わっただろうか?いや、これは現在進行形の叫びである。
そしてこの映画は、"ACT-UP"と名付けられた活動団体のパリ支部のメンバーたちが、常に生と死と隣り合わせの状態で、それでもこの社会をどうにかして動かそうと過激な手段で声を上げていく様子を写実的に切り取りながら、その過程でエイズ患者がいかに不当な立場に置かれているかや、エイズ患者が一向に減らない(寧ろ増え続けている)理由などを問いかけていく。冒頭のミーティングシーンからして、とてもリアリティがある。活動家のイメージというとその過激な行動からして感情的な人たちをイメージしやすいが、その裏で行われている「M」と呼ばれるミーティングは非常に理性的で、感情的になることを極力抑えるようなシステムを用いて行われている。彼らの行動が決して感情論ではないことを裏付けるようでとても印象深かった。
そして彼らの活動と並行して、若い青年ショーンとナタンの間のロマンスが描かれて行くのだが、このラブストーリーの美しさが物語には力強い必然となる。とてもリアルで生々しく、観ているだけで思わず息が上がるようなセックスシーン。特に印象深いのは、数学教師との初体験でエイズに感染したことを語りながら交わすセックスと、すでに死期が迫って来ていた頃に病室で体が弱りゆく中、手淫でオーガズムに達するシーン。いずれも生々しいシーンであるのだけれど、人を愛し愛し合うということを究極までピュアに浄化した行為に感じ取れて、切ないんだか悲しいんだか理由はよく分からないまま涙が出てしまった。そしてショーンを演じたナウエル・ペレーズ・ビスカヤートの熱演がまた魂に響くもので、この作品だけでもうすっかりファンになってしまった。
どうしてエイズ患者が減らないか。その理由はとても簡単で、減らそうとしなかったから、である。そしてその理由はというと、エイズに感染する者として挙げられる、同性愛者・売春婦・薬物常用者などは、社会にとっていなくなって都合のいい者たちだと判断されたからだ。彼らを排除しようとする国の動き、差別と無知と無関心からくる切実な絶望、そして自らに残された時間に対する焦燥。現実と事実を織り交ぜながら、次々にスクリーンへと突き付けられていく。何より、彼らが闘う姿勢を一切偽らなかったこの映画をとても正直な映画だと思った。
「沈黙は死、行動は命」だと彼らは謳った。そして21世紀に時代が変わった今も、まだまだ声を上げ続けなければ、無知と無関心は終わることがない。でも本当は、沈黙と死がイコールしないことこそが一番望ましいことのはず。そう思った。
全37件中、1~20件目を表示