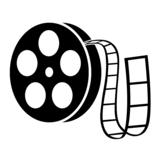夜明けの祈りのレビュー・感想・評価
全38件中、1~20件目を表示
静寂と映像美で綴る歴史の狭間の悲劇と希望
撮影監督のカロリーヌ・シャンプティエの映像がとにかく美しい。サイレント映画と思えるような静寂が印象的で、それも映像の美しさを際立たせている。
第2次大戦直後のポーランドの修道女に起きた悲劇を描いたこの作品は、ナチスに占領され、ソ連によって解放されたポーランドの戦後の悲劇を体現する存在として、解放軍であるソ連兵に望まぬ妊娠させられた修道女が描かれる。
物語は、敬虔なカトリック信者ゆえに妊娠の事実を隠そうとする修道女たちと、彼女たちを救おうと奮闘する主人公の医者との交流を中心としている。
厳粛な雰囲気の中、歴史の狭間で苦しめられた人々の鎮魂歌となるような、そんな映画だ。史実とは異なるエンディングを描いているが、未来への希望を持たせていて良い。
聖女から人へ
実話をもとにしているということで
いろんなところで狼藉を働きまくったロシア兵に怒り心頭
おまえらの頭はちんこなのかと!
派閥は異なっていても同じキリスト教の尼さんではないか。
信じられん、考えられん、野獣か。
そんな憤りが激しく湧き上がる。
さて。突然の悲劇が彼女たちを襲って、さらにその後も
神の試練というにはあまりにも辛すぎる事態が。
信仰と人道のはざまに揺れ動く、
そこに立ち会うことになった医師もどうしていいか
混乱するだろう。
国は違えど同じ宗教だし、
同じ女性だ。
医師の道にのっとっての選択を貫くのだが
その途中で自身も襲われかけたり職を危うくしたりと
医師自身も様々な苦難に襲われる。
力を尽くしたのに救えなかった苦悩はいかばかりか。
悲劇が新たに生んだ悲劇もある反面
それを機に生き方を転換するものもいたりと
選択はそれぞれだ。
神の御心を主体にしていた生活から
自分の選択で動くようになったのは、
幸か不幸かはわからないけれども、
聖なる何かから人への変化だった、とも見えた。
神の救いは得られるかわからないけれど
子供たちの笑顔が救いになること願う。
【第二次世界大戦末期、ポーランド修道院で起きた悲劇を、一人のフランス人女性医師の崇高な行為が浄化させる様を描いた作品。傑作である。】
希望
タイトルなし
1945年ポーランドの修道院で起きた悲劇
ナチスドイツから開放されたと思ったら今度は規律の低いソ連軍に凌辱されるなんて。
宗教とは
信仰とは
修道女の肌が映らないよう授乳シーン等に配慮がみられる
祝詞のようなやつが美しく響く
雪景色
赤ちゃんがたくさん
ハッピーエンドでまだ救われたがそれまではずっと悲しみの連続
フランス赤十字はええもんに描かれる
美人の女医さんは実在の人なのか
良い方に裏切られた。これは…な映画。
宗教的正しさとは?
映画はソ連の兵士に陵辱されて妊娠させられてしまった修道女達の物語。...
立場と信仰の葛藤劇
1945年、時は戦後ポーランド。
信仰を破ってまで助けを求めに行くシスター。
立場上の都合により最初助けてあげる事が出来ないフランス赤十字女性医師。
2人の出会いから物語が始まる。
自分の置かれている立場と信仰との葛藤によって最初は上手く話は運びませんが、お互いの歩み寄りによって物語が良い方向に進んで行きます。
歩み寄りと言う点ではパーフェクトな内容です。
物語展開的に、戦後の混乱が混乱だけに目を背けたくなる内容ですが、新たなる生命の誕生や生まれつき備えられている母性本能開花など、希望が持てる描写も共感出来る所です。
満点でオススメしたくはなりますが、私的に不満点もややあります。
それは成人男性の描き方。
殆ど絶対悪の様なロシア男性陣の描き方や、バーにて彼女が悩んでいても目の前でふらっと他の女と踊ってしまう彼氏医師など、描き方が少し雑に思えました。
監督女性なんですね。少し偏りが観られます。
女性主体の映画なので分からなくもないですが、異性もこの映画を観るんですよね。
その辺り意識して作って欲しかったです。
信仰は命よりも重いのか
重厚
1分の希望から立ち向かう勇気を
映画を見て思いがよぎった事です。
批評でない点をご容赦下さい。
私が主人公のマチルドだったら彼女達を助けるだろうか。自分の属する組織に報告せずに、果敢にやりきれるだろうか。
マチルドには使命があったのだと思う。彼女達を助けに行くと選択をした時から、彼女達を受け止め、支えになる使命があった。もしくは、彼女達を近くに感じるにつれ、使命に変わっていったのかもしれない。
価値観が違う人達をどのように捉えるか。『そうだよね』と言って表面的にやり過ごすのか。無理矢理にでも従わせるのか。それとも、それを受け止めてその人達と向き合うのか。
私は医師ではないので想像もつきませんが、もしかしたら、命を助けるために医療を施すことより、その人達の問題に向き合うことの方が勇気が必要なのではないかと思うのです。
めんどくさい問題は逃げればいいし、人道的にと言うならただ医療を施せばいい。嫌でも薬を使って従わせる事も出来るかもしれない。
しかし、マチルダは非常に勇敢な女性だったと思う。
この物語が実話に基づくフィクションであっても、戦争下にあった時代、こんな事が起きるのだから、一体何のために戦うんだろうと普通に感じるのだけど、
本質は、戦うことより、お互いに持つ問題にしっかりと向き合う勇気を持つことの方が難しいのではないかと思うのです。
今、不安定な状況だから余計に思うのだけど、勇気は必要だと思う。武力で解決するのではなく、表面的に取り繕うのではなく、本当に解決するべき問題に向き合う勇気を持たなくてはならないと思う。
彼女達が最後にそう決意したのと同じように、勇気を持たなくてはならない。
心は無辜のまま
キリスト教は子孫にキリスト教を強制する宗教である。かつてのキリスト教は子孫だけでなく他人に対しても信仰を強要していた。教会は権威を生み出し、人々は神ではなく権威に対して跪くようになった。権威は政治に利用され、キリスト教は坂を転がり落ちるように堕落していった。
しかし民主主義が世界中に広まりはじめると、キリスト教は他宗教の排斥をやめ、信教の自由を尊重するようになった。いまでは他人の宗教についてとやかく言うキリスト教徒はほとんどいないだろう。だがそれはあくまで他人に対してである。
自分の子供に対しては当然のように信仰を強要する。自由の国であるはずのアメリカ合州国でさえそうである。いまだに大統領就任式で聖書が使われる。他宗教のアメリカ人にとっては決して愉快な儀式ではないだろう。宗教の権威はまだなくなっていないのだ。
キリスト教だけではなく、仏教徒にも同じような傾向がある。母親が仏教徒だったら子供も仏教徒だと、あるスリランカ人から主張されたことがある。
ほぼ無宗教の国である日本にいると、宗教の話はなかなかピンとこないが、熱心なキリスト教国やイスラム教国では、宗教は政治から日常生活まで、あらゆる場面で指導層の権威が猛威を振るう。
本作品は、修道院長があくまで守ろうとするキリスト教の権威と、シスターマリアが告白する、残酷な現実に揺らぎ続ける信仰との対比を描いている。信仰は権威を必要としないが、修道院という組織は、組織維持のために権威のある指導者を必要とする。シスターマリアのもうひとつの悩みがそれだ。
第三者であり無宗教である医師からみると理解できない話だが、命を救うという主人公の行動が、シスターたちに目覚めた母性の共感を得ることになる。残忍なソ連兵、戦争の傷跡、信仰と権威など、背負う重荷が多い女たちは、それでも知恵を出し、勇気を出して生きていく。そのありように深い感動がある。
原題のLes innocentesは英語のイノセントと同じで無実の、無辜のといった意味で、Lesがついているから、無辜の人々という意味になる。女たちは身体を穢されても、心は無辜のままなのだ。
全38件中、1~20件目を表示