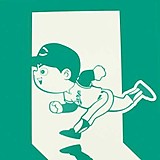サバイバルファミリーのレビュー・感想・評価
全285件中、181~200件目を表示
知恵と備蓄と行動力。
設定自体が興味津々で公開前から楽しみにしていた作品。
もし日常から電気が無くなったら…という不安は、すでに
3.11の時に多少味わった関東圏の人間なので想像ができる。
あの頃は節電!消電!と謳っていたのに、のど元過ぎれば
当たり前の如く電気を使いまくっている日常生活になって
つくづくサバイバル能力に劣る自分を思い知る作品だった。
原因不明、復旧不能、いつ使えるか分からない電気を待つ
くらいなら皆で大阪へ!っていう根拠のない希望のデマが
流れ、大勢の人が行列して高速道路を歩く様子など滑稽に
見せながらも、常にどこかで(アンタならどうするの?)と
尋ねられてる不安が続く。食料も水も果て、ついに川の水
そして豚の捕獲にまで乗り出す家族の困窮。いや、生きる
ことは食べること。ブランド物や金銭では立ち向かえない
サバイバル本能とどこまで行動できるかが生死の境となる。
こんな時やはり凄いと思うのは、電気がないのがなんだ?
と云わんばかりに生活苦に陥らない農家のおっさんありき
で、彼から様々なノウハウを家族は教わる。そこにない物
に代わる知恵と普段の備蓄などこちらまで大変勉強になる。
そういや藤原紀香も雑草はビタミン!を連呼していたっけ。
小日向ファミリーの右往左往ぶりと要所要所で助けられる
幸運を背景に物語は突っ込みどころ満載でサクサクと進む。
個人的にはお母さん(深津絵里)の飄々とした呑気が魅力で、
「お父さんはそういう人なんだから!」って言いながら夫
を心から愛し敬っている姿と、そんな妻を父親に逢わせる
ことを目標に必死で鹿児島へと向かう夫の姿は子供達から
見ても励みにはなるはずだ。こんな時だからこそ家族団結!
と叫ばずにいられない身につまされるサバイバル劇だった。
(突然の蒸気機関車にはビックリしたけど、あれなら走る?)
設定に無理がありすぎて楽しむにはかなり厳しい。
和製パニックモノはどんなかな?と見に行きました。ツッコミどころ満載なので、よくこんな脚本とか設定を通したなと逆に関心しました。
科学的な「嘘」については許容するとします。発電所からの電気が止まる以上に「電気そのものが無い、発電・通電ができない」という設定なので、それは良しとします。そこにツッコむと生命活動がすべて止まらなきゃいけませんので。(=全生物即死。)
でも、政府機能の止まった中での人間の心理に関しては嘘ついちゃダメでしょ。漫画・ゲーム・小説などでリアル志向のパニックモノがあふれんばかりに量産されてる昨今で、略奪・レ〇プ・殺人などの負の側面がちっとも出てこない。そういうシーンの描写が無くても、置かれた状況に対して主人公一家だけじゃなく登場するすべての人があまりにもノー天気過ぎる。
家族ドラマを描きたいなら、警察機能が生きてるなどのギミックを設定すべきだったと思う。
1日50km~100kmを何日も移動する時の碌に運動していなかった人間の体にどのようなダメージがあるかとか、気の効いたサバイバル術とか、ほとんどありませんのでパニックのシミュレートとしても何の価値もない映画です。それ目当てにしてはいけません。
で、ハードルをさらに超下げて、家族ドラマ部分だけ見るならまぁいいかな。0.5星あるのはそのドラマ部分を評価しての加点です。
「生きる」ということに気付かされる
全てを失った家族が手に入れたもので賞
家族で笑える幸せ
小日向文世と深津絵里が夫婦役を演じるというだけで、ある種のアンバランスが想像される。アンバランスは静止エネルギーと同義であり、何かのきっかけでダイナミックに動きはじめる。両俳優とも、期待にそぐわぬ見事な演技だった。
ファミリーはいかにも現代的な家族で、最初のうちは、当然ながらまったく感情移入できない。仕事最優先で家族を顧みない夫、我儘勝手な息子と娘に、性格は悪くないが能天気な妻。
ストーリーは予告編や公式サイトにある通りのサバイバルだが、特殊な能力の持ち主が現れることも、思わぬ幸運が舞い込むこともなく、等身大の人間が体当たりで状況に挑む、ある意味で振り切った演出だ。ところどころに伏線や思わぬゲスト出演があって、楽しめる。
電池や発電装置をふくむ、あらゆる電気が突然なくなる生活は、特に若い世代を直撃する。スマホが使えなければ友達でなくなるのは、つまり友達はスマホの中にいたということだ。
サバイバルの中で家族の絆は強まるが、逆に家族以外に対しては微妙に排他的な心理状態になる。それでも礼儀を忘れないのは日本人らしいし、助け合える状況では進んで助け合う。まっとうな家族が極限状況に陥ってなおまっとうであり続ける、稀有なサバイバル生活を過ごす物語で、自分でもきっとそうするに違いないという共感があり、ストーリーの途中からは完全に家族に感情移入している。
蒸気機関車がトンネルをくぐった後の車内のシーンがこの映画の白眉ではなかろうか。どんな状況でも家族で笑えるのはいいことだなと、しみじみ思わせる幸せなシーンだ。
「家」の「族」だ。
大切なことに気付かされた。
この映画を見て大きく二つのことに気付かされた。
一つは、身の回りのものを当たり前のように思い感謝していなかった自分
二つは、生きるために、家族を守るためにプライドを捨て命をかけるハングリー精神
一つ目に関しては、作中で電気が無くなったときに、当たり前のように使っていたものが使えなくなり不自由を感じるしかなかった家族を自分と照らし合わせた時に、自分自身が今ある環境を当たり前のように思い、今の環境に対しても不平不満をもらしていることに気がついた。
無くなったときに価値を感じるのだなと思い、今ある環境に感謝しなければならないと感じた。
また、二つ目のハングリー精神に関しては、仕事のことばかりで家族のことに本気で責任を持つことができなかった父親が、極限の状況で家族のために土下座をしたり命を懸ける姿である。
この作品を見た人は是非、生きるためプライドを捨て、家族の命に責任を持つことを自分ができるか問うて見ていただきたい。
自分自身が今の生き方を考えたときに、もっとやるべきことがあると強く実感したからである。
新手のホームドラマだ
電気がない!
コメディーだけど、ある面「シン・ゴジラ」と似たシュミレーション映画。コメディーだからシュミレーションの突っ込みはソコソコだけどもしこんな状況になったら私はとても映画の家族のように鹿児島までたどり着く自信はない。水は手に入れられないだろうし、火は起こせない。豚を丸一匹さばくなんて、とても出来ない。
映画は極限のロードムービーで家族の成長ドラマ。小日向文世のおとっつぁんはイメージ通りのハマり役。家族に対して威張るばかりで何も出来ない。深津絵里のおかあちゃんの方が頼りになる。子供ふたりも最悪のクソガキ。それが旅の過程で成長していく。
映画的な楽しさは蒸気機関車の登場シーン。危機に瀕した小日向家族を2度も助ける。「シン・ゴジラ」の機関車の活躍よりずっと爽快。特におかあちゃんが危なくなったときの最初の登場シーンはいいなぁ〜。もうひとつの楽しさは大地康雄の農家の爺さん。西部劇に出てくるガンコな故郷の爺さんみたいで、こういう爺さんがいたらしばらくは生き残れそう。
電気が無くなった理由が示されないのもいい。危機は理由なくやってくる。この映画の家族みたいに成長してメデタシ、メデタシには絶対にならんだろうが。
全285件中、181~200件目を表示